日本の城はあまりにかわいそうだ…短期的な富のために歴史的遺構を奪われた天守から見える残念な景色
プレジデントオンライン / 2025年1月6日 9時15分
※本稿は、香原斗志『お城の値打ち』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■日本でいちばん美しい城
高松城、今治城、宇和島城の三城は、一般に日本の三大海城とされている。それぞれについて、かつての海城としての姿と現況を確認してみたい。
生駒親正が天正16年(1588)に築城し、徳川光圀の兄である松平頼重が整備した高松城は、日本最大の海城だったといわれる。そればかりか、日本でいちばん美しい城だったかもしれない。
北面は瀬戸内海に接し、海岸からそびえ、その裾を波が洗う石垣上には二重や三重の櫓が並び、それらは白い土塀で結ばれていた。また、海水を引き入れた広い水堀が城内をくまなくめぐっていた。
明治になってからのものだが、「讃州讃岐は高松様の城が見えます波の上」という民謡のくだりもある。事実、海上から眺めれば、波の向こうに建ち並ぶ櫓と、その奥にそびえる三重四階の天守が望まれたはずで、ヴェネツィアのサン・マルコ広場を海上から眺めた光景とくらべたくなる。
現在も水堀には海水が引き入れられ、鯛が泳いでいる。だが、周囲は埋め立てが進み、城の中心部こそ海と近いが、石垣と海をへだてて水城通りと呼ばれる車道がとおされ、フェリー乗り場がもうけられている。
北の丸の最北端には三重の月見櫓と水手御門が現存する。月見櫓は本来、船の出入りを監視する「着見櫓」だったといわれ、それに連続する水手御門は海に向かって開かれ、参勤交代の際などには、藩主は沖合に停泊する御座船まで、ここから小舟で移動したという。
しかし、いま門の外にあるのは、水も涸れそうな狭い堀である。月見櫓も水手御門も持ち場を失ってしまい、博物館の展示物のようになっているのが惜しまれる。
■ギリギリ海城の名残をとどめている
藤堂高虎が慶長7年(1602)から、三角州の砂地に築城工事を開始した今治城は、内堀、中堀、外堀と三重の堀で囲まれた輪郭式の城郭で、北側は瀬戸内海に面していた。いまも残されているのは、幅が50~70メートルにおよぶ広い内堀と、それに囲まれた本丸と二の丸だけである。水堀にはいまも海水が引き込まれているため、鯉ではなく鯛が泳いではいるが、海は少し遠くなってしまった。

今治城と同じ伊予に位置する宇和島城も、藤堂高虎の手になる。リアス式海岸である宇和海に突き出た標高77メートルの丘上に、慶長元年(1596)から6年かけて築かれた。
丘陵先端の二方が海に面し、後方三方は海水を引き込んだ水堀に囲まれ、城域が不等辺三角形をした城郭だった。周知のとおり、この丘上には現存12天守のうちのひとつが建つ。だが、堀はすべて埋められ、丘陵の裾を波が洗っていた海もすっかり埋め立てられ、かなり遠ざかってしまった。
それでもこの三城は海までの距離が近く、海城の名残はとどめている。というのも、かつての海城で、その面影をすっかり失っている城が多いのである。
■高層ビルや住宅で風情が台無しに
大分県大分市の府内城は、水上に浮かぶ姿が格別であることから「白雉城」の別名があった。城の北側と東側の、遠浅の潟に近いところに本丸があり、その外側には城の中心部を守るために、約600メートルにわたって細い帯曲輪が防波堤のようにめぐらされていた。もちろん、帯曲輪の外は海だった。しかし、いまでは海岸線ははるか彼方に遠のいている。

帯曲輪の外側にある狭い水路が海の名残で、その向こうには一面、ビルや住宅が建っている。しかも、埋立地には歴史的景観への配慮がまったくないまま、高層建築が次々と建てられ、城跡を威圧するように睥睨している。
同じ大分県の臼杵城(臼杵市)は、三方が海に囲まれた断崖絶壁の「島城」だった。しかし、その面影がすっかり失われている。
この城は臼杵湾に浮かぶ東西約420メートル、南北約100メートルの丹生島上に築かれ、北、東、南の三方が海に囲まれていた。キリシタン大名としても知られた大友義鎮(宗麟)が築城した当時は、干潮時にだけ西側の砂州が現れて陸地とつながる純然たる島だったが、大友氏の滅亡後、文禄2年(1593)に入城した豊臣系大名の太田一吉が、土づくりだった城を石垣で固めると同時に、西側の砂州を埋め立てて三の丸を整備し、以後は半島に近くなった。しかし、海に突き出した島城であることは、明治を迎えるまで変わらなかった。
■欧州との決定的な違い
いまは丹生島を歩いても、海が遠いうえに、眼下には断崖の直下から住宅がぎっしりと建っている。周囲の海は昭和42年(1967)までに、すっかり埋め立てられてしまったという。だが、いまも海に浮かぶ島のままだったら、どれほど壮観だったことだろう。内外から観光客が引きも切らず押し寄せ、みなその美しさに感嘆の声を上げたにちがいない。
臼杵城も城内の整備が進み、埋められていた堀が復元されたりもしている。また、保存状態のよい城下町の景観整備も進んでいる。むろん、それは評価できるが、島の周囲を整備して、かつてのような海に戻すことは永久にできない。
ヨーロッパでは、フランス西海岸のサン・マロ湾上に浮かぶ著名なモン・サン=ミシェルはいうまでもなく、海城や海に面した城塞都市は、周囲もふくめて往時の環境が伝えられている例が多い。一方、日本ではいまも石垣が波に洗われている城は、萩城や唐津城など、ごく一部の例外にすぎない。尼崎城のように、海が遠くなっただけでなく、城の遺構がなにひとつ残っていない海城の例さえある。
■歴史遺産を犠牲にする愚行
日本ではバブル期までの土地神話、すなわち地価は必ず上がるという思い込みが象徴しているが、海であれ、湖沼であれ、堀であれ、埋められるかぎりは埋め立てて、あらたな土地を創出することに価値が見出されてきた。土地の創出は富の増大に直結し、ひいては地域や国土の発展につながると信じられてきた。
欧米に追いつき、追い越すことを意識しながら、歴史遺産のおかげで地域が豊かになり、国土の魅力が増す、という発想が欧米にあることには気づかず、短期的な富の増大のために歴史遺産を犠牲にするという愚行を繰り返してきた。日本のこうした姿勢は明治時代にはじまり、戦後の復興期、そして高度経済成長期に拍車がかかった。
本書『お城の値打ち』の最後に海城を取り上げたが、それは海城がとくに問題だからではない。城の周囲の環境が守られていないことを伝えるのに、海が埋め立てられたという事例が好適だったからにすぎない。残念ながら、問題が多い点は海城にかぎらない。
堀を埋め、石垣や土塁を崩して市街化された区域がない城など、世界遺産の姫路城をふくめて日本にはほとんど存在しない。そして、いったん市街化された区域には、高いビルが無節操に建ち、歴史的景観を愛でようにも、そうした建物が暴力的に視界の邪魔をする。あるいは、わざわざ歴史遺産を破壊して生み出した土地が、空き家や空き地だらけという場合も少なくない。
■小倉城を見ると悲しくなる
たとえば小倉城は、かつては紫川の河口近くに五重の堀が囲み、総構の周囲は約7キロにおよぶ壮大な城だった。現在、公園として残されているのは、本丸および南方の松の丸、北方の北の丸、それらを囲む堀など、かつての城域の一部にすぎない。それだけなら多くの日本の城郭とくらべて、特別にひどい状況とはいえないが、訪れて驚かされるのは、周囲から受ける圧迫感である。

北九州市役所から望む小倉城とリヴァーウォーク北九州(右)(写真=Keramahani/CC-BY-SA-4.0/Wikimedia Commons)
本丸北側の二の丸跡には、リヴァーウォーク北九州など派手な色彩の奇抜な建築が壁のように建ち並び、残された城内のどこにいても視覚に飛び込んできて、歴史的景観を強烈に威圧する。
しかも、それらのビルに入居しているのが、放送局や新聞社、劇場など、文化に携わり、かつ公共性が高いはずの組織だから驚かされる。そのうえ、市庁舎や警察署までもが歴史的景観を妨害しており、日本という国の文化度を象徴しているようで悲しくなる。
■整備されるべき面は城だけではない
史実に忠実な建造物の復元や、城域全体の復元整備。それらが重視されるようになったことは評価できる。しかし、そこにとどまって、歴史遺産が周囲の環境から浮き上がっているようでは、城は博物館の展示物と変わらなくなってしまう。
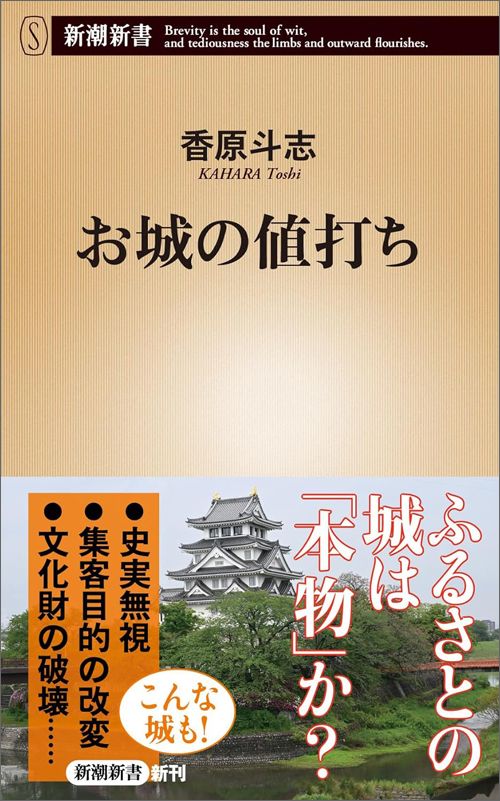
天守や櫓、門など点の整備だけでなく、点と点を結んだ線、線で囲んだ面の整備にも意識が向くようになってきた、とすでに記した。それはいい。しかし、整備されるべき面は城外にまで広がるのが理想である。
埋立地をもとの海に戻すのは難しい。しかし、熊本城の復旧で石垣を積み直す際の、もとの姿を忠実に復元するための徹底したこだわり。復旧するだけでなく、以前より強度を高めようという姿勢と、それを可能にする技術。そうした意識と取り組みが、城郭を取り囲む環境にまで向くようになれば、悲劇的であった日本の城の歴史に、少しは光明が差すことにもなるだろう。
そのときには刹那的な利を追わずに、100年先まで見据えて取り組んでほしい。それは地域だけでなく、日本全体の誇りになる。日本の魅力を本質的に高めながら海外にも発信すれば、為替の動向に左右されることなくインバウンドを呼び込める力にもつながるだろう。
----------
歴史評論家、音楽評論家
神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』(新潮新書)、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。
----------
(歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
3位は安土城(滋賀県)、2位は岡城(大分県)、1位は…歴史評論家が選ぶ「あえて寒い冬に訪れるべきお城」ランキング
プレジデントオンライン / 2025年1月2日 16時15分
-
このままでは小田原城や小倉城の二の舞になるだけ…メディアが報じない「名古屋城天守再建問題」の本質
プレジデントオンライン / 2024年12月29日 16時15分
-
あなたの地元にあるお城は「ホンモノ」か…歴史と伝統を完全に無視した「ニセモノ天守」に騙されてはいけない
プレジデントオンライン / 2024年12月24日 16時15分
-
「現存12天守だけが名城」は大いに間違っている…年末年始に訪れたい「復元天守のお城」ランキングベスト7
プレジデントオンライン / 2024年12月21日 9時15分
-
夜の特別貸切!世界文化遺産・国宝『姫路城』でスペシャルな体験を 第3回 姫路城プレミアムナイトツアーを開催!
Digital PR Platform / 2024年12月20日 11時0分
ランキング
-
1「完璧」「みんなが食べたい味」プロも完食の美味しさ...。餃子の王将で頼むべき、最強中華6選とは。
東京バーゲンマニア / 2025年1月7日 17時5分
-
2「想像の100倍寒かった」関東から「盛岡」に移住した30代男性の後悔。「娯楽がパチンコか飲み屋しかないのも辛い」
日刊SPA! / 2025年1月7日 8時51分
-
3マジで危険…。 信号待ちで「バイクのすり抜け」違反じゃない? 「マジで危ない」「クルマの後ろで待て」との声も 何がダメな行為なのか
くるまのニュース / 2025年1月7日 16時40分
-
4「いつまで待たせるんだ!」若い女性店員に文句を言う迷惑客は“まさかの人物”だった…こっそり店長に“会社と名前”を教えた結果
日刊SPA! / 2025年1月7日 15時51分
-
5"優しい気遣いさん"すぐキレる人に対処するコツ 相手に「キレることによるメリット」を与えない
東洋経済オンライン / 2025年1月7日 14時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










