「平日はバリバリ働き、休日は寝溜め」は二流…「気品が漂う一流」が感性を磨くために休日にやっていること
プレジデントオンライン / 2025年1月30日 16時15分
※本稿は、梅澤さやか『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
■感性を磨きたければ「手」を使おう
現代社会には、かつて当たり前だった香りを焚き、和歌を詠む文化的空間はもはや存在しません。たとえ形式的に似た場をつくり出したとしても、当時と同じ集いの場を再現することは不可能です。現代において同じようなことを再現したとしても、その感性を真に再現することはできないからです。
しかし、私たちの日常生活の中にも、自然への感性を磨く機会は残されています。その重要な手がかりとなるのが、「手を使うこと」なのです。日々の些細な動作の中に、昔の人々が培ってきた感性を取り戻すヒントが隠れているのかもしれません。
自然を深く理解し、その微妙な変化を感じ取るには、特別な実践があります。昔から伝わる決まった動きや手順(これを「所作」と呼びます)を行うのです。これらの所作を通じて、五感だけでなく、体全体の感覚を駆使して情報を受容し、理解を深めていくことができます。この過程において、「手」は極めて重要な役割を担っています。
■手を使うことで、認知機能が向上する
手を使うことには、科学的に裏付けられた多くの利点があります。
手には、数百本の末梢神経が集中しています。たとえば、目を閉じていても、ポケットのなかの小銭の形や大きさを触っただけで、その額を判別できることがあります。これは、手にある沢山の神経のおかげなのです。
手や指先を使うと、脳に多くの信号が送られ、神経活動が活性化します。料理の際にさまざまな食材を触り、その質感や新鮮さを判断するとき、私たちは無意識のうちに手の感覚を使って脳を刺激しています。
このような日常的な行為から、「むすんでひらいて」のような単純な手遊び、さらにはピアノなどの楽器演奏といった複雑な指の動きまで、手を使うあらゆる活動が認知機能を向上させることは、科学的にも広く認められています。
だからこそ、手は単なる身体の一部ではなく、脳と直接つながる重要な「情報センター」なのです。
手を意識的に使うことで、まず脳の健康が維持されます。健康な脳は、より効率的に情報を処理し、学習能力を高めます。これが認知機能の向上につながります。認知機能が向上すると、私たちは周囲の環境をより鋭敏に捉え、微細な変化やニュアンスにも気づきやすくなります。
茶碗を手に取るとき、その温かさや質感、重さなどを、より繊細に感じ取れるようになるかもしれません。あるいは、庭の植物に触れる際、葉の微妙な質感の違いや湿り気まで感じ取れるようになるかもしれません。このように、脳の健康維持と認知機能の向上が、私たちの感覚をより豊かにし、世界をより深く、多面的に体験することを可能にするのです。つまり、手を使うことから始まる一連の過程は、感覚の豊かさを大きく増進させることにつながります。
■品がある人は「手の動かし方」が違う
手は外界の情報を感じ取り、それを脳に伝達すると同時に、脳からの指令を受けて適切に反応します。この特性により、手は周囲の環境からの様々な刺激を敏感に捉え、処理し、それに応じた行動を生み出す能力を持っています。
さらに重要なのは、手が単に情報を受け取るだけでなく、その情報を脳に送り、同時に脳からの指令を受けて動きを生み出すという双方向の機能を持っていることです。この受容と表現の両面性が、手を通じた学びと感覚の洗練を可能にしています。
たとえば、温度の微妙な変化や物の質感の違いなどを、手を通じて直接的に感じ取り、その情報を脳に送ります。同時に、脳からの指示を受けて、適切な力加減や動きを生み出すことができます。
この双方向の情報のやり取りが、手を単なるセンサーではなく、情報の集約と発信の中心、つまり「情報センター」たらしめているのです。この受容と表現の両面性が、手を通じた学びと感覚の洗練を可能にしています。
このような手の特性を活かすことで、私たちはより深い学びと豊かな表現を実現できるのです。手を通じた情報の取得、処理、そしてそれに対する反応は、単なる機械的な過程ではなく、感性や創造性を育む重要な要素となっているのです。
■三味線から考える、手の使い方と感覚
三味線の演奏を例に挙げてみましょう。演奏者は、異なる曲を弾く際に、単に指の動きを変えるだけではありません。撥(ばち)で弦を弾く力加減や速さ、触れ方なども変化させることで、雰囲気や感情以上の奥深い表現を表現しています。
具体的に三味線で長唄の「勧進帳(かんじんちょう)」の一節を奏でるのと、「秋色種(あきのいろくさ)」を奏でる場合を比較してみましょう。「勧進帳」は、緊迫感のある場面を表現するため、強く力強い撥さばきが特徴的です。演奏者は撥で弦を力強く弾き、曲の劇的で緊張感のある雰囲気を表現します。
一方、「秋色種」は、秋の風情を描写するしっとりとした曲調が特徴です。撥さばきは繊細で、弦に触れる感覚は柔らかく、余韻を大切にします。この曲では、秋の静けさや情感を表現するため、撥と弦の接し方に細心の注意を払い、微妙な音の強弱や間の取り方を重視します。このように、同じ三味線でも曲によって手の使い方や感覚が大きく異なります。三味線奏者は手の感覚を通じて、それぞれの曲の特性に合わせた演奏を実現しているのです。力強さと繊細さ、緊張感と静けさ、これらの対照的な表現を同一の楽器で表現できることが、三味線の奥深さを物語っています。

■感性を鍛えるとアウトプットが変わる
私の経験をひとつご紹介いたします。メインのパソコンとして使用しているMacBook Proにおいて、唯一不満だったのがキーボードでした。ノートパソコン特有の薄いキーストロークは、タイプミスを増加させるだけでなく、思考と手の動きのリズムが合わず、作業の効率を低下させることがしばしばありました。
あるとき、思い切って某メーカーのプロフェッショナル向けキーボードを購入しました。最も印象的だったのは、その打鍵感です。テクノロジー系のジャーナリストやYouTuberが熱心に語る、キーを押したときの指が沈みこむ「スコスコ」という感覚の重要性を、初めて実感しました。
この打鍵感は、タイピング速度の向上や長時間の入力作業における疲労軽減といった利点をもたらすのですが、私が特に注目したのは、キーボードのタッチに反応して、入力する内容に関する発想が変化するという気づきでした。
この体験を経て、日常的に頻繁に触れたり使用したりする道具や洋服に関しては、自分の手で実際に触れ、その物と自分とのあいだにどのような相互作用が生じるかを意識的に観察するようになりました。私たちは手を使うことで脳の働きを整えながら、膨大な量の情報を学び取ることができます。手を通じて感性を鍛えることで、アウトプットが質的に変わるのです。
■手を使った所作が中心の「茶の点前」
手を使った感性の鍛え方は、日本文化の様々な場面で見られます。
その代表的な例として、茶の湯の点前があります。茶の湯では、手を使った所作が中心となり、それらの動作を通じて感性の洗練が行われるのです。
裏千家のウェブサイトには、亭主からお茶を出されたときの客人の作法について記述があります(「薄茶のいただき方」)。
こちらをまとめるとこのような手順になります。
(2)茶碗を右手で2度回して茶碗の正面を避けて、静かに味わう。
(3)飲み終わったあと、指で飲み口を清め、茶碗の正面を自分に向ける。
(4)茶碗を拝見する。
茶の湯における所作は、初心者にとっては型通りの作法を覚えることから始まります。一見機械的に見えるこれらの動作には、実は深い意味が込められています。
たとえば、茶碗の扱い方には細やかな配慮が表れています。亭主は茶碗の正面を自分に向けてお点前を行い、客に正面を向けて差し出します。茶碗の正面は必ず客に向いています。客は受け取ったあと、時計回りに2回まわすだけです。飲み終わったあと、客は正面を自分に向けて待ち、半東が取りに来る際に再び時計回りにまわして、正面を半東に向けます。
これらの動作には理由があります。茶碗の正面は最も格が高いとされ、亭主がおもてなしの心でその正面を客に向けることで敬意を表し、客も同様に正面を返すことで亭主への敬意を示すのだと教えられます。
■茶道を通して、他者への配慮・自己内省が学べる
しかし、茶の湯の真髄はこうした作法を単に暗記することではありません。実際の体験を重ねることで、手から得られる情報を基に適切な所作を体得していくプロセスにあります。
経験を積むにつれ、茶碗の重さや触感から視覚以上の情報を受け取れるようになります。また、茶碗の正面は亭主が決めるため、どこが正面かの正解はありません。それは、このようなやり取りをする経験のうちに、どこを正面としたいかが自ずと見えてくるようになるからでしょう。
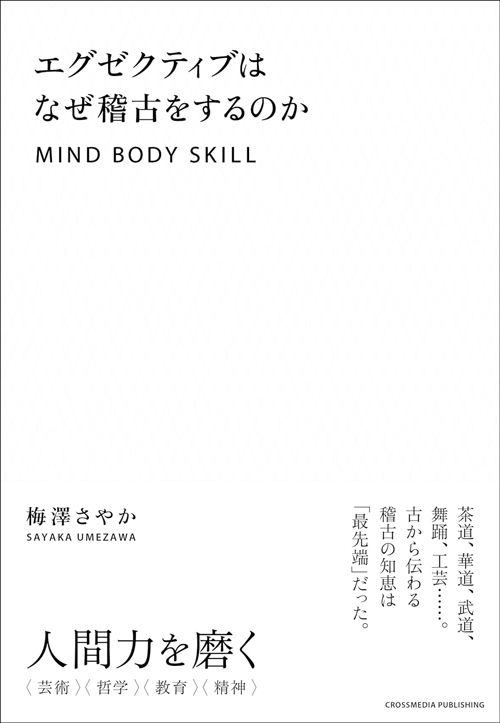
この手の動作と感覚から得た情報は体全体にフィードバックされ、茶碗と体が相互に影響し合いながらその場の雰囲気を醸成します。これは日本文化特有の「物と人との対話」と言えるでしょう。この対話を通じて、参加者は自然との調和、他者への配慮、そして自己の内省を学びます。
つまり、茶の湯における所作は単なる形式的な動作の連続ではなく、手を通じて情報を収集し、それに基づいて判断する力を養う過程なのです。各場面で最適な振る舞いを自然に選択できるようになることが、茶の湯の真の習得と言えます。
このように、手の感覚を通じた学びは日本文化の美を理解し感性を磨くには重要な手がかりとなります。形式の裏にある本質的な意味を自らの身体感覚を通じて理解することにつながるからです。
----------
ブランドプロデューサー
カルチャーマーケティング・コンサルタント。KAFUN代表。慶應義塾大学文学部哲学科美学美術史学卒。19歳から世界的な写真家・荒木経惟の専属モデルを務め、芸術的な環境に身を置く。凸版印刷株式会社マーケティング本部 消費行動研究所を経て独立し、国際広告賞などを受賞。30年近くにわたり、芸術・デザイン・ファッションを通じたブランド戦略に多数関わる。知識とリアルな体験を融合してたどり着いた「カルチャーマーケティング」の手法を用いて、ブランドの背景や特徴を分析。人々のライフスタイルや価値観との関わりを読み解き、ブランドの過去・現在・未来を貫く価値を見出し、最適なポジショニングを導き出す戦略からブランド・プロデュースを行っている。現在はジャパンブランドや伝統文化の海外展開を視野に入れたリブランディングやラーニング企画に力を入れている。
----------
(ブランドプロデューサー 梅澤 さやか)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
野球でもサッカーでも音楽活動でもない…意外にも20~30代男性社員が夢中になる「社内部活動」の名前
プレジデントオンライン / 2025年1月31日 16時15分
-
茶道や武道、瞑想で「心が整う」とはどういう事か 科学的に裏付けられた健康効果が存在している
東洋経済オンライン / 2025年1月28日 15時0分
-
できる人ほど「仕事の道具選び」に妥協しない理由 「よい道具」は使い続けることで進化していく
東洋経済オンライン / 2025年1月21日 18時0分
-
習い事で成長する人がやっている"視点"の持ち方 「なぜ?」「どうして?」と疑問を持つことがカギ
東洋経済オンライン / 2025年1月14日 18時0分
-
小学生の投球動作は「正解を求めすぎ」 脱・手投げへ…脳と体を刺激する“大きい球”
Full-Count / 2025年1月14日 7時5分
ランキング
-
1寝る前に飲むと太る!? ぜったい避けたいNGドリンク3つ
つやプラ / 2025年2月2日 12時1分
-
2コンビニ「カフェラテ」飲み比べ!セブン・ローソン・ファミマ3社の苦み・甘みに違いはある?お得感のあるコンビニは...。
東京バーゲンマニア / 2025年2月2日 11時0分
-
3入居金4億円も…超高級老人ホームの衝撃実態、セレブ居住者たちの“マウント合戦”と“色恋沙汰”
週刊女性PRIME / 2025年2月2日 10時0分
-
4このサイズ感が最高に“わかってる”…!!無印で発見したコットンの正解アイテムとは
女子SPA! / 2025年2月2日 15時46分
-
5健康のカギは「朝食」…1日の総カロリーの20~30%を取るべし
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月2日 9時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










