「遺体解剖写真を見ても大丈夫か」と念押しされ殺人事件の裁判員に…塾講師の女性が目撃した血なまぐさい世界
プレジデントオンライン / 2025年2月10日 9時15分
※本稿は『裁判員17人の声 ある日突然「人を裁け」と言われたら?』(旬報社)の一部を再編集したものです。
■「解剖写真を見ても大丈夫ですか」と聞かれ、辞退した人も多かった
塾講師。裁判員をつとめた当時は50歳代。塾では小中学生には5科目、高校生には英語を教えている。
――はじめにあなたが担当された事件についてお聞かせください。
【N】裁判は2018年に担当しました。被告人が殺人、逮捕監禁致死などで起訴されていた事件でした。
――呼出状が届き、裁判員に選ばれるまでの段階でも、印象的な出来事がいくつかあったとお聞きしました。
【N】地裁の裁判所から届いた「裁判員選任手続き期日のお知らせ」の中の資料のひとつにカレンダーがあり、裁判所に出向く必要のある日には色がついていました。同封の「裁判員制度のナビゲーション」には、裁判は平均で5日前後と記載されていましたから、カレンダーは色づけされた日程のなかでいつ招集されてもいいように、という予定を示すものだと思い込んでいました。
もちろん書類の一部には、今回は長期間にわたる裁判である旨が記されていたのですが、書類が多かったもので読み飛ばしていたようです。選任の日に周りの人たちと話したとき、同じように思っていた方も何人かいたので、誤解していた人も多かったかもしれません。実際に裁判官が「カレンダー通りに出席しなければならない」と話したときには少しどよめきがありました。
――かなり長期に及ぶ裁判だったんですね。罪名も殺人罪と、非常に重たいものですが……。
【N】「解剖写真を見ても大丈夫ですか」という裁判官の言葉に驚いた人も多く、この理由で辞退した方も多かったように思います。
■ボコボコにされた被害者の写真を見てショックを受けた人も
――選任手続きのときの話でしょうか。
【N】はい。これについては無理と回答した人は個別に呼ばれて面接しました。「大丈夫だと思う」と答えた私たちは、5人ずつくらいのグループで裁判官、検察官、弁護人の方々の前で面接をしました。私が「大丈夫だと思います」と述べたら弁護人から、「思います」ではなくはっきり答えてほしいと言われました。それ以上明言もできないで黙ってしまったのですが、そのまま手続きは進みました。
のちに裁判員になってからのことで、解剖写真については明日見せます、と予告してくれたので心の準備もできたのですが、予告なしにボコボコにされた被害者の写真や、その後の車のなかの遺体の写真が見せられたときの方がショックが大きく、3日間夜も眠れなかったという裁判員もいました。ただその方は最後まで裁判員でいましたね。私はそこまでのショックはありませんでした。
■母親から「殺人事件に関わるのはやめて」と言われたが…
――あなた自身は選任に関して、どのように考えておられたのでしょうか。
【N】たくさんの候補者がいたので、まず私が選ばれることはないだろうと気楽に構えていましたが、私をふくめた裁判員が6人、補充裁判員が6人選任されました。当日に辞退した人が多かったとあとで知りました。
高齢の母親からは、殺人事件に関わるのはやめてほしい、でも断ることができないのならこれを身につけておくように、とお清めの塩とお守りを持たされました。選任手続きのときにアンケートがあったのですが、「選任されたらやってみますか」という問いには選ばれないだろうと思い、「次回選ばれたらやってもいいです」と回答したくらいです。選ばれたので慌ててその日の仕事をキャンセルする連絡をして、大変でした。
――裁判員制度の知識のほどはいかがでしたか。
【N】「裁判員は20歳以上の有権者から選任される」(現在は18歳以上)という程度の知識しかありませんでした。書面と一緒に送られてきたパンフレットも読みましたが、専門用語が多く、すべてを理解することはむずかしかったです。
■被告人は地元の有名人、初日から法廷で証言を聞くことに
――審理のようすを教えてください。
【N】実は裁判が始まってから被告人がかなりの有名人であり、私の周囲でも多くの人が彼を個人的に知っていると知り、驚きました。
また、裁判員に選ばれたら、裁判が始まる前にもっと詳しい内容、心構えや審理の流れについてなど説明されるものだと思っていたのですが、いきなり初日から法廷に出席し、証人の話を聞くことになるとは思いもよりませんでした。最初は自分がなにをすればよいのかわからなかったのですが、裁判官が証言などを筆記されているのを見て、私もひたすら書くことに徹しました。裁判官からは、気になる証言があればまたビデオで見られますよ、と言われたのですが、証人が多すぎて、自分で整理する必要があると判断して続けました。おかげで指が腱鞘炎になりました。腱鞘炎は未だに治っていません。

――ていねいにメモをとられていたんですね。長い審理のあいだで、他に印象に残ったことはありましたか。
【N】検察側の陳述書はとても見やすく、証人の顔写真や事件の関与への記載、また事件の流れが詳しく描いてありました。弁護側は書面がなくすべて口頭と液晶画面上での陳述、弁護人は書面を見ずに語り口調で発言されていたので、まるで外国のドラマの裁判のようでした。どちらも裁判員に配慮してとても歯切れよく、わかりやすい言葉を選んで話されているのが印象的でした。また解剖写真にも配慮されていたようで、思ったより生なましくなく、拍子抜けするほどでした。
■凶悪犯罪であり、通常の期間では終わらない長期公判に
――評議はいかがでしたか。
【N】まず事件を時系列に並べていくことから始まりました。いくつもの事件が同時進行しており、登場人物も多く、丁寧に整理・確認する作業が必要だったためです。
そうして事件ごとに全員が意見を出し、評議を進めていきました。公判が長かった分、事件についてそれぞれの立場で考える時間は十分にあり、また裁判長がどの意見も否定せず、疑問があれば全員でそれについて考える、という姿勢をとっていらしたこともよかったと思います。
ただ、量刑をこの場で決めなければならない、との言葉には、裁判員側から驚きの声と大きなため息が聞こえました。量刑は裁判官たちで決めるもの、と思っていた人が何人かいたようです。評議について、私たちはわかっているようでもはじめてのこと。始める前に最終ゴールについてあらためて説明があればよかったと思います。
――審理が始まる前に普通は裁判官から、「裁判員はこれから有罪か無罪かの判断と、有罪の場合には量刑判断もする」ということについて説明があると思うのですが……。
【N】あったのかもしれませんが、事件の審理と証人尋問が沢山始まったので、メモをとったり審理の理解で手一杯でした。
ですが審理していくうちに、とても重大な犯罪事実なので、刑を決めるとしたら重罰になる、と予想がついてきたため、自分たちが任されると知って衝撃を受けました。
評議の結果を受けて裁判官が判決文を作成しましたが、裁判長が全文を読み上げるのにも時間がかかりました。

■裁判員6人のうち3人が知人、1人は同級生だった
――裁判員裁判の長期化は問題視されていますが、あなたのように長いあいだ拘束された例もめずらしいと思います。その点からみて感じたことなどはおありですか。
【N】長い裁判になると通常では考えられないこともたくさんあると思います。まず裁判所から遠い地域に住んでいる人は、長期間通うことが困難です。そのため裁判員は近隣に住んでいる人から選任されました。つまり非常に狭い地域から選ばれたということで、私の場合は6人のうち、3人が私と何らかのつながりのある人たち、加えてもうひとりは中学・高校の同級生でした。被害者側の家族の弁護士も私の知り合いで、驚きの連続でした。この点の負担については配慮を望んでいます。
裁判は暴力団も絡んでいるということで、傍聴席の前にはアクリル板がありました。どんな立場の方かはわかりませんが、ほぼ毎回法廷に来られる方が何人もいます。アクリル板を通してでもお互いに顔はわかってしまいます。あるとき、その日の公判を終えたあとに家族と待ち合わせした喫茶店で、いつも傍聴席で顔を見かけていた方が前の席に座りました。思わず目をそらし、その方は私に黙礼して店を出られましたが、期間が長いと知らない人に顔を覚えられる怖さもある、ということを実感した出来事です。
■裁判が終わり、血なまぐさい話から気持ちをリセットした
――裁判が終わったときの感想を教えてください。
【N】裁判員といえども裁判に関しては素人ですし、期間が長くなれば気持ちの負担も大きくなります。終了後には友人とともに新幹線でディズニーランドに行きました。やり切った感よりも、現実の血なまぐさい話からまったく違う世界に行って、気持ちをリセットしたかったからです。意識していなくても、ずっと事件や被告のことを考えて過ごしていたように思います。
それから、裁判の途中で辞退された3人のうちひとりは、親族のお葬式に参列するためでした。裁判を辞退したときの気持ちはとても言葉には言い表せない、とあとでその方から聞いています。この裁判が終わるまで、家族や親族に何も起こらないことを裁判員全員が願っていたと思います。
――裁判のあと、経験談等を話す機会はありましたか。
【N】家族や友人が裁判の傍聴に来てくれていたんです。百聞は一見に如かずということで、裁判についてどんな言葉で説明するより有効でした。終了後は、まず私の周りから裁判について話すことを止められました。理由は被告の親族が身内の友人であったこと、暴力団絡みの事件であったことなどです。守秘義務で話してはいけないのでは、と言われたこともよくありました。
■経験を講演で話すも「一般人が裁判員になるベきではない」
――事件の内容もあり、周囲には話し辛い雰囲気だったのでしょうか。講演をされたこともあるとうかがっています。
【N】私が講座をもっていた公民館から、裁判員に選任されるまでの話をしてほしいと依頼を受けました。実際に30人ほどの前で話をしたときに、一番多かった質問は「どうすれば裁判員を辞退できるか」というものでした。「一般人が裁判員になるベきではない」と話されるかたもいました。裁判員のイメージはとてもマイナスで、制度が本当に広く認知されているのか疑問です。裁判所はもっと積極的に正しい情報を伝えるべきではないかと思います。
――他にも制度について、不満に思ったことなどはおありですか。
【N】被告人が控訴した場合、高裁の判断が気になって傍聴に行く裁判員も多いと思います。一審で裁判員をつとめた人が優先的に傍聴できるようにするシステムがほしいですね。
――経験者団体にアクセスされたのはいつごろでしょうか。
【N】自分の経験を話せる場がないかと思い、ネットで検索して裁判員経験者ネットワークという経験者団体の存在を見つけ、連絡をとりました。そこではじめて自分の経験を語ることのできる場所があると知り、同じような経験者にも会うことができました。裁判が終わって半年後のことでしたが、とてもうれしかったです。同じような裁判員体験をしている経験者の前で関心を持って聞いてもらえて、弁護士や臨床心理士の方からも疑問点について教えてもらい、安心してそれまでの思いの丈を話せたので、帰りのエレベーターの中でうれしくて涙が出たのを覚えています。
このように裁判員制度の意義や課題について真面目に取り組み、経験者の交流の場を設定している団体があることに驚きましたが、裁判所も裁判員の参加を推進したいのなら、このような民間交流団体のことを本気で社会に知らせる努力をするべきだとつくづく思いました。とくに裁判終了後には、経験者団体の存在を裁判員に伝えるようにしてほしいと思っています。
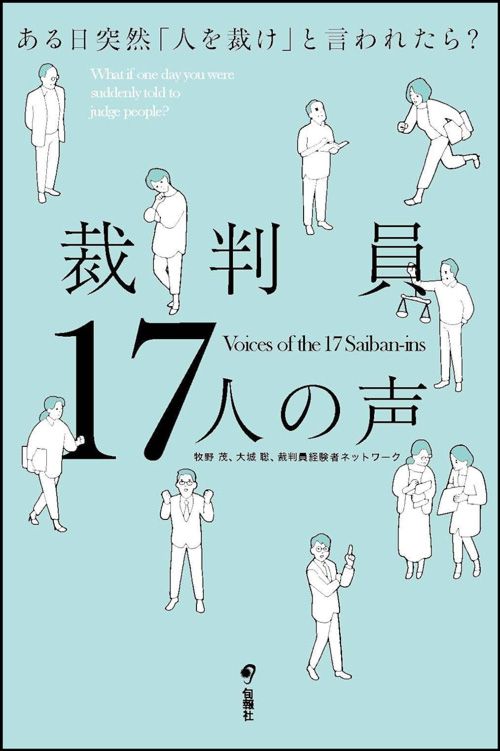
――裁判員を経験したことで、何か変化はありましたか。
【N】裁判員裁判が報道されると、その裁判員の方たちの心情を考えるようになりました。どんな裁判でも素人が関わるというのは大変なことです。ましてや裁判員裁判になる事件は世間的にも注目が集まることが多いと思います。そこに向き合っている方々の気持ちはどう、と考えるようになりました。
――もし、もう一度裁判員に選任されるとしたら、引き受けたいと考えますか。
【N】短い期間であればぜひ。
――次に裁判員になる人にメッセージをお願いします。
【N】ためらっている人がいれば、やってみて損はないよ、と背中を押します。遠い世界にあった司法が身近に感じられる経験は、日常生活ではなかなか得られません。おそらく裁判員経験者の皆さんが同じことを思われているのではないでしょうか。
----------
弁護士
慶応義塾大学法学部卒業。日弁連刑事弁護センター幹事。2010年に「裁判員経験者ネットワーク」を立ち上げ、共同代表に。裁判員制度の推進、改善を目指している。著書に『裁判員制度の10年』(日本評論社)、共著・監修に『高校生も法廷に!10代のための裁判員裁判』(旬報社)がある。
----------
----------
弁護士
弁護士。中央大学法学部卒業。「裁判員経験者ネットワーク」共同代表。市民の視点から裁判員制度への提言を続けている。「福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)」事務局長なども務める。共著に『増補改訂版 あなたが変える裁判員制度―市民からみた司法参加の現在』(同時代社)、共著・監修に『高校生も法廷に!10代のための裁判員裁判』(旬報社)。
----------
----------
----------
(弁護士 牧野 茂、弁護士 大城 聡、裁判員経験者ネットワーク)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
食パンを万引きした男が見つかって暴行…貧困ゆえのせつない事件を裁判員として裁いた商社マンの体験
プレジデントオンライン / 2025年2月9日 9時15分
-
「被害者女性が自分から男の家に入ったことは落ち度か」性加害事件の裁判員になった30代男性が苦悩したワケ
プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分
-
「被害者は同意していたと認識」男は改めて起訴内容を一部否認 女性教諭殺害差し戻し審 北海道
STVニュース北海道 / 2025年2月3日 18時36分
-
母・浩子被告「できないことは断った」父・修被告裁判で証言…法廷で様々エピソード語る狙いとは
STVニュース北海道 / 2025年1月29日 18時30分
-
「違う点がいくつかあります」父親の裁判員裁判始まる 父親は無罪を主張 すすきのホテル頭部切断事件
HTB北海道ニュース / 2025年1月14日 17時17分
ランキング
-
1「めっちゃうま!」セブンで買える、SNSで話題のスイーツ3選。贅沢気分に浸れる美味しさ。
東京バーゲンマニア / 2025年2月10日 18時3分
-
2義理チョコは「人間関係の潤滑油」? 義理でもうれしい…“義理チョコ文化”に対する男性の“本音”
オトナンサー / 2025年2月10日 20時10分
-
3「ドラマの衣装合わせで下着を脱がされ…」芸能界にあふれるひどすぎるハラスメント被害の実態
プレジデントオンライン / 2025年2月10日 7時15分
-
4西成「家賃2万7千円」ほぼ廃墟ハウスに住んだ結果 住人はほぼベトナム人、そこで見た驚きの光景
東洋経済オンライン / 2025年2月10日 8時30分
-
5「8年前より今のほうが断然美肌」“肌老け”を脱出した48歳が、肌のために「やめて良かった食習慣」8つ
女子SPA! / 2025年2月10日 15時46分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










