"減税派"の織田信長とは全然違う…戦国最強の武将・武田信玄が"天下統一"を果たせなかったワケ
プレジデントオンライン / 2025年2月11日 16時15分
※本稿は、宇野仙『日本史と地理は同時に学べ!』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■地理を学べば、歴史がもっと理解できる
「歴史の勉強をする際に、歴史の教科書だけで勉強してはいけない」と言われたら、みなさんはどう思うでしょうか? 多くの人は「何を馬鹿なことを」と思うかもしれませんが、しかしこれは実際に日本史や世界史を深く勉強している人であれば誰もが頷いてくれることです。
歴史の勉強には、地理的な要因が深く関わっていることがあります。世界地図をしっかり理解していなければ、いくら世界史の勉強をしても頭に入ってくるわけがありません。江戸や大阪が地理的にどのような優位性があったのかを理解していなければ、江戸時代の勉強をしていても理解できない部分が多いです。
江戸時代の人口規模がわからない状態で江戸時代の勉強をしても、半分くらいしか理解し切れないのです。もし日本史の勉強や世界史の勉強で躓いてしまったとしたら、それは歴史がわかっていないのではなく、地理を理解していないからかもしれないのです。
重要なのは、日本史と地理を融合した形で学んでいくことだと言えます。今回はいくつかの例を挙げて、日本史の疑問は、地理の知識があれば解消でき、理解が深まることをみなさんに共有したいと思います。
■“最強の戦国武将”には、土地が不足していた
例えば戦国時代の勉強をしていると、「戦国最強の武将は誰か?」という問いを考えることがあるのではないでしょうか。
この問いに対して、上杉謙信や武田信玄の名前を挙げる人は多いかもしれません。武田信玄は、甲斐の国・現在の山梨県の戦国大名で、「甲斐の虎」と呼ばれました。信玄の率いる武田の騎馬隊は、戦国時代において最強と謳われていました。
しかし、信玄は天下を取ることができず、最終的に織田信長・豊臣秀吉が天下統一を果たします。なぜ、軍事的に強かったにもかかわらず、武田信玄は天下統一を果たせなかったのでしょうか?
もちろん、さまざまな要因が複雑に絡み合った結果ではあると思いますが、実はこれに関しては、地理的な視点で見ると1つの重要な事実が浮かび上がります。それは、「土地の問題」です。
まず、甲斐の国は農地が弱く、水害の多い地域でした。そのうえ、内陸にあったため、水運を使った交易ができず、商業があまり栄えませんでした。織田信長の領地の農業生産性はかなり高かったと言われており、かつ、水運で経済的にも成功していたことを考えると、かなり対照的です。
■「土木工事」にも莫大な金が費やされた
実際、甲斐・信濃の石高は一説によると60万石程度で、最盛期でも100万石程度だったと言われています。これは、尾張・美濃・伊勢を合わせて150万石程度を手中に収めていた織田信長と比べても少ない数字と言わざるを得ません。
武田信玄といえば、信玄堤が有名です。信玄堤とは、武田信玄が甲府盆地につくった大規模な堤防です。連続した堤防ではなく、複数の堤防を重ね合わせるなど、当時としては斬新な設計でした。この信玄堤をはじめとして、武田信玄は土木工事にとても力を入れていたと言われていますが、なぜ武田信玄が土木工事を推進していたのかというと、やはり、農地が弱いため経済的な困窮を余儀なくされていたからだと思われます。

土木工事を行うことで、武田信玄は農業生産性をなんとか上げようとしていた、という説が濃厚です。土木工事のために、武田信玄は何度か増税を行っています。大規模な増税も何度か行われたと言われ、土木工事の予算に回されていました。
当然、戦いにも莫大なお金がかかります。そのため、武田信玄は増税を行って土木工事にたくさんの予算を回しながら、戦いの準備もしなければならなかったのです。減税を行って経済を回そうとしていた織田信長と対照的ですが、土地を考えれば仕方がないことでした。
しかも、武田信玄による増税は、領民の逃亡を招いてしまったとも言われています。このように、武田信玄は、自身の領地に大きなハンディキャップを抱えていたことがわかります。「武田信玄は強かったのになぜ天下を取れなかったのか」を考えると、このように地理的な要因が考えられるわけです。
■“税=米”が続いたのは、世界的にも稀だった
また、もう一つ面白い例を挙げましょう。日本史の勉強をしていてよく登場する言葉に、「石高」というものがあります。奈良時代から江戸時代の終わりまで、日本では貨幣経済が進展した後でも、基本的には米を年貢として徴収する税制が採用されていました。
この体制が終わったのは、1873年(明治6年)に導入された地租改正のタイミングです。従来の年貢制度が廃止され、農民は土地の所有者として地価に基づいた税(地租)を貨幣でおさめることになりました。つまり、150年前まで、日本の税は米だったということですが、これは世界的に見てもかなり稀な事例です。
もちろん、貨幣経済が進展するまでは穀物で税を徴収するのが普通でした。古代ローマや古代エジプトでは小麦や大麦などの穀物が税として徴収されていたそうですが、貨幣経済の進展とともに廃止されました。
日本に一番近い例として、中国では16世紀中頃まで米麦や生糸などの現物で税をおさめていたのですが、一条鞭法という税制に改められて銀が税としておさめられるようになりました。これも1580年代には全国に普及したと言いますから、日本とは300年もの断絶があります。
■なぜ「貨幣」ではなく、「米」だったのか
でも、ここで一つ疑問が生じます。なぜこれだけ長い間「米」による税制が採用されたのでしょうか? その理由の1つに、「石高」と呼ばれるシステムの存在があります。
「石高」では、その地域の経済力を「石」という指標を用いて米の生産量で測るものです。このシステムは、明治時代が始まるまで続きました。1石は100升で、約180リットルあります。重さで表すと、約150キロに相当します。
前田利家が基礎を築いた加賀藩は、戦国時代から江戸時代にかけて、米の生産が多い藩でした。石高は100万を超え、全国1位です。それを讃えて「加賀百万石」という言葉までできたほどです。

このように、石高はその地位の生産性や勢力を示す言葉として扱われるようになりました。この石高に応じて税も設定されており、このシステムの存在が税を米で徴収する体制を支えていたと言えます。
なぜ、日本では石高という指標が採用されていたのでしょうか? 地理の視点で見ると、このことについてより深く理解できるようになります。
稲作は日本の風土に適しており、米は昔から現在に至るまで日本の主食としてずっと愛されています。しかも、日本の国土の広い範囲で稲作を営むことが可能でした。この点は日本が他の国と違う点です。「国土の大部分で同じ穀物が収穫できる国」はアジアの中でも比較的珍しいのです。
■史実には地理的要因がある
インドも中国も、国土の一部では米の生産が難しい地域も存在しています。中国は東西南北に大きく、稲作が可能な地域もあれば稲作が難しくて小麦を主食とする地域もあります。世界的には、気候条件によって栽培する穀物が変化するのが普通なのです。しかし日本だけは、国土の大部分で米が生産可能だったわけです。
しかも、米は長期保存が可能なため、流通や取引の基本単位としても適しています。日本では貨幣経済の進展が他の国に比べて遅かったと言われていますが、それだけ米が流通や取引の基本単位として適していたために貨幣を導入する必要性にそこまで迫られなかったということかもしれません。
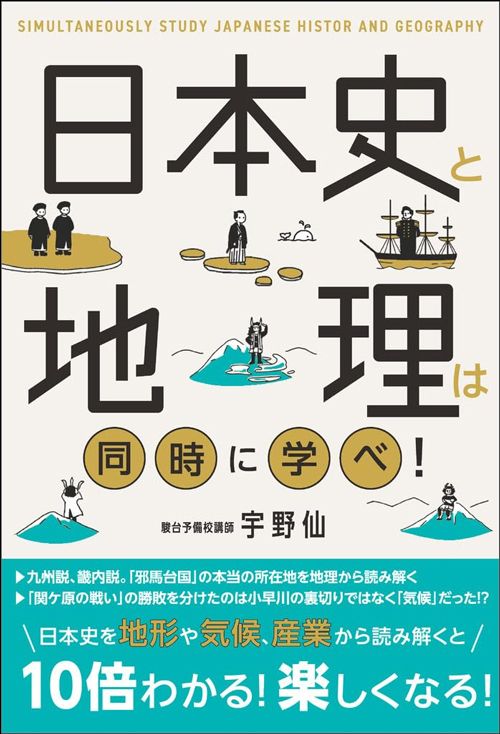
そんな日本において、石高制は非常に理に適ったシステムだったと言えます。人口や領地の広さでは、生産性の高さは測れません。でも、石高制は実際に得られる米の生産量を評価するものですから、かなり実に迫った評価指標となり得たわけです。幕府も石高制を積極的に利用し、石高制を「大名を効率的に管理するための重要なシステム」として扱っていたと言います。「米」=「日本社会における基本的な経済・生活基盤」だったから、日本は長い間、税制を米に頼っていたのだと考えられます。
このように、日本史の事象の背景には密接に地理的な要因が隠されています。工業や農業・主食や食料の生産など、さまざまな地理的要因があって歴史が形作られている以上、歴史の勉強には地理の勉強が前提となっていると言えます。もし歴史を勉強していて行き詰まったら、地理の勉強から始めてみてはいかがでしょうか。
----------
駿台予備校地理科講師
1978年、北海道旭川市生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、キーエンスに入社し、営業職に従事。キーエンスを退職後、予備校業界に入り、Z会東大進学教室講師や河合塾地理科講師を経て現職。著書に『大学JUKEN新書 共通テスト 地理B 最速攻略法 改訂版』(旺文社)『大学入試 地理B論述問題が面白いほど解ける本』『地理B 早わかり要点整理』(ともにKADOKAWA)、『ぐんぐんわかるセンター地理B』(駿台文庫)などがある。
----------
(駿台予備校地理科講師 宇野 仙)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
結局のところ「信長」は革命児だったのか、否か 時代により揺れ動く評価と家臣たちの不遇
東洋経済オンライン / 2025年2月7日 12時30分
-
来年大河『豊臣兄弟!』第3次キャスト7人発表 小栗旬、宮崎あおいら“主演級”ズラリ
ORICON NEWS / 2025年2月3日 12時31分
-
戦国最強「武田信玄」天下取れなかった地理的要因 地理的視点でみると、ある事情が浮かび上がる
東洋経済オンライン / 2025年1月23日 16時0分
-
【6000人以上に調査】好きな歴史上の人物ランキング! 「坂本龍馬」を抑えた1位は?
オールアバウト / 2025年1月18日 8時5分
-
だから豊臣秀吉は天下をとれた…主君・信長が遺した「織田体制」に対して秀吉が行った掟破りの行動
プレジデントオンライン / 2025年1月14日 16時15分
ランキング
-
1豆腐「きぬごし」「もめん」よく食べるのはどっち? 調査で明らかに
マイナビニュース / 2025年2月11日 15時1分
-
2出版不況に「超豪華な無料雑誌」京都で爆誕のワケ 紙にこだわる大垣書店が勝算見込んだ本屋の未来
東洋経済オンライン / 2025年2月11日 14時30分
-
3ママ友に“利用され続けた”30代女性。会計時に店員が言った「スッキリする一言」で縁を切ることができたワケ
日刊SPA! / 2025年2月11日 8時53分
-
4トヨタ最新「ルーミー」に反響集まる! 「一気に昔の高級車っぽくなる」「レトロ感がたまらない」の声も! “高級感&渋さ”アップの「昭和感サイコー」な専用パーツとは?
くるまのニュース / 2025年2月11日 6時10分
-
540代女性に多い「やってはいけない“老け見え眉メイク”」5パターン。「今っぽ眉毛」との大きな違いは
女子SPA! / 2025年2月11日 15時46分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










