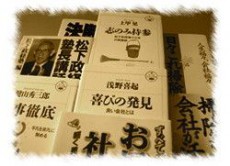なぜ「掃除・片づけ」が人生に関わるのか-2-
プレジデントオンライン / 2013年5月8日 11時15分
■TOPIC-2 掃除とビジネスが出合った年
掃除・片づけと自己啓発の結びつきを探ろうとすると、たとえば原始仏教の時代における周利槃特(しゅりはんどく、掃除で悟りを開いたとされる人物)、掃除を重視する禅宗の修行生活、世界の各宗教に共通する「けがれ(穢)」の観念、「みそぎ(禊)・はらい(祓)」を重んじる神道といった宗教の世界にまで行き着いてしまいます。これらは非常に重要な背景だとは思うのですが、あまりに果てのない話になるので、ここでは書籍上の言論動向に絞って、掃除・片づけと自己啓発の結びつきを追っていくことにします。
掃除・片づけが自己啓発と結びつけられるようになった潮流には、大きな流れが二つあります。一つは企業経営者による掃除論で、もう一つは女性向けの家事に関する書籍です。今回はまず経営者の方からみていくことにしましょう。
珍しいパターンだと思うのですが、掃除と自己啓発が結びついた時点は、特定することが可能だと思われます。それは、致知出版社から出た3冊の著作が、互いに参照し合いながら掃除の効用を説き始めた1994年です。
刊行された順で並べると、9月に日本経営システム相談役(当時)の浅野喜起さんによる『喜びの発見』と松下政経塾常務理事・副塾長の上甲晃さんによる『志のみ持参』が、次いで11月にローヤル社長(当時。現イエローハット)の鍵山秀三郎さんによる『凡事徹底』が刊行されています。
論じられていることは大きく2点で、一つは、未来の政治的リーダーを育てる松下政経塾において、掃除が奨励されていたことについて。もう一つは、掃除を企業文化として根づかせ、松下政経塾での掃除実践にも大きく影響を与えた鍵山さんの人生とその考え方についてです。
■1994年から語られ始めたこと
松下幸之助さんには次のようなエピソードがあります。1923(大正12)年、工場の大掃除を見て回った際、松下さんは便所が掃除されていないことに気づきます。松下さんは自ら率先して便所掃除に取り組みますが、一人を除いて工員は手伝おうとしません。松下さんはこれをみて、「こういうような精神の持ち方なり態度では、仕事の面でもいい仕事はできない」、「たとえ仕事には直接関係はなくても、人間としてのあり方というか礼儀とか作法を知らないようでは、この松下工場に勤務した意義もうすい」と考え、今後は「人間としていかにあるべきか」を教えていこうと決意したというエピソードです(『決断の経営』184-186p)。『決断の経営』は1979年の刊行でした。
松下政経塾の設立間もない1980年の講話には、「掃除を完全にするということは、一大事業です。百貨店に行っても、掃除のゆきとどいた百貨店と、掃除のゆきとどいていない百貨店とは違う。掃除がどことなしにおそまつなところは、やっぱりはやりませんね」という言及もあります(松下政経塾編『松下政経塾塾長講話録』145p)。ただ、同書ではこうした発言のみがあるだけで、その意図についての解説は何もありません。
松下さんは掃除をしっかり行うことが人間としてのあり方、礼儀作法の教育に有用であり、ひいてはそれが企業の成功につながると考えていたようなのですが、今引用した以上に詳細に説明されることはありませんでした。また、みてきたように1979年の『決断の経営』、1981年の『松下政経塾塾長講話録』において掃除に関するエピソードが既に紹介されていたわけですが、ここから掃除の効用に注目しようという人は長い間現われませんでした。もちろん、企業の生産管理における5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)は1980年代には既に普及していたのですが、それを人間形成と合わせて論じようとする著作はありませんでした。
1994年、掃除は人間形成に役立ちを、また掃除を徹底する組織は成功するということが語られ始めるようになります。刊行の順に追っていくと、まず浅野さんが鍵山さんのエピソードを紹介します。それは次のようなものです。
近年、雑事をおろそかにする人や企業が増えている。しかしそうした、手足を使うことをおろそかにしては頭も働かなくなる。鍵山さんは1961年のローヤル創業時以来、早朝に最寄駅から会社までの通勤路を掃き清めることを始めたが、手伝おうとする社員が現れるまでに10年、ほぼ全員に行きわたるまでに20年かかった。掃除という雑事を自ら行うことで、目の前の問題から逃げない態度を育み、細かいところまで気がつくようになり、またそれによって人とのかかわりが深くなり、喜んでもらえることも増えることになる。また、皆で一緒に取り組むことで社内の人間関係も良くなり、やる気も起こり、ミスが減り、商品の価値が高まるとともに人材も育つ。このような考えの偉大なる実践者として鍵山さんがいるのだ、と(『喜びの発見』49-53、104、165-168p)。
上甲さんは1981年に松下政経塾に入職して以降、松下さんの考えが塾生になかなか伝わらないことに頭を悩ませます。その一つの例が掃除です。人間としてのあり方、礼儀作法を体で覚える、実地で習得するという松下さんの考え方と、掃除の「意義と効用」「理論的根拠」を求める塾生のすれ違いが埋まらないというのです(『志のみ持参』75-78p)。
そのようなとき、上甲さんは鍵山さんに出会い、政経塾の掃除は「やらされてやっている掃除」であり、「これはだめですな」と率直にいわれてしまうことになります(『志のみ持参』101-102p)。上甲さんは鍵山さんが長年かけて掃除を社風とした経緯を知り、また周利槃特のエピソードを知って、次のような見解にたどりつくことになります。
「実は掃除というのは、ただ単に環境美化というだけではなくて、我が心の塵を払わん、我が心の垢を拭わんという、いわば自分自身を変えていく一つの大きなポイントがあるのではないか」(132p)
「塾生を育てる、塾生を変える前に、私の人生の中において、いちばん変わらなければならないのはおのれ自身だったのです」(133p)
「私の掃除の先生」(135p)と呼ぶ鍵山さんとの出会いを経て、上甲さんは次のような考えを打ち出します。これまで、特にバブルの時期、顕著に行われていたのは、「お金の力に頼って仕事をする」経営、いわば「金力経営」だった。しかしバブルが崩壊した今日、そのような経営は立ち行かなくなる。今後重要なのは、「働いている一人ひとりの人が自分の心の力で仕事をする」ことを基本に据えた経営、つまり「心力経営」ではないか。「心は無限」であり、「使えば使うほど豊かにな」る。そのような「心力経営」に向かうための一つの典型が、「一人ひとりの心の中に、自分がきれいに掃除をしておけばどんなにみんなが気持ちがいいだろうという心」を育む、掃除なのではないか、と(139-141p)。上甲さんは、鍵山さんの考え方を知って、「松下幸之助さんが願ったのはこういうことではないか」(142p)とまで考えるようになります。
さて、浅野さんにしても、上甲さんにしても、鍵山さんが「掃除哲学」(『喜びの発見』106p)の重要人物であることが分かると思います。では鍵山さん自身の見解を次に見ていくことにしましょう。
■不景気の時代の「二分法」
鍵山さんの著作『凡事徹底』は1994年11月に刊行されていますが、同様の内容は1992年以来講演で幾度も話しているとのことで、掃除とビジネスとの出合いはより正確にはもう少し前だというべきかもしれません(『凡事徹底』のもとになった講演は、1993年5月と1994年2月に行われたものでした)。そもそも、松下さんの大正時代のエピソードや、3S(整理・整頓・清掃)や5S(3Sに清潔・躾が加わる)という言葉が当時既にあったことを考えると、日本企業の文化として掃除と修養とを結びつけようとする姿勢はもともとあったと考えるべきでしょう。ただ、それが活字になって大々的に主張されるようになるのは、1990年代前半まで待たねばならないのです。
ところで、なぜ1990年代前半だったのでしょうか。それは、既に浅野さん、上甲さんの著作でも一部紹介されていたことですが、鍵山さんの次のような主張から考えることができるのではないでしょうか。
不景気になると商品を安くしなければならない、新しい商品を売らなければならないと思う人が多いが、そうした商品を今までと同じ売り方、並べ方で売ろうとしても大した魅力は出ない。むしろ「いままであった商品を新しい売り方で」というほうが無駄がない。無駄をなくし、成果を上げるためには、手元にある商品の魅力や、どうしたら人に喜んでもらえるかに「気づく」ようになるというところにある。「微差、あるいは僅差」に気づき、それをおろそかにせず改善し、「徹底して平凡なことをきちっとやっていく」ことが、やがて「大差となって現れて」くるのだ(『凡事徹底』15-27p)。
不景気に関しては、次のような言及もあります。不景気になると合理化しようという考えが出てくる。これ自体は素晴らしいことだが、「自分の会社にとって不都合なことを他人や他者に転嫁することが合理化だと思っている経営者が非常に多く」いる。これは他人に対する思いやりが欠けたものであり、このような会社の社員は間違いなくすさんでいく。「思いやりのない集団になって、だんだん心がすさんでいく」。「会社で何が大事かというと、利益より社風をよくすることだと思います。社風が悪い会社で未来永劫よくなった会社はありません」(43-53p)。
自己啓発書には、しばしば「二分法」が登場するということを、これまでの連載で幾度か述べてきました。浅野さん、上甲さん、鍵山さんは、近年の啓発書ほどに明確な二分を行っているわけではありませんが、彼らは概して、次のような二分法で企業や人を切り分けているように思います。
つまり、一方には、凡事・雑事をおろそかにし、他人への思いやりに欠けた、金さえあれば何でもできると思っている者がいる。もう一方には、凡事をおろそかにせず、他人を喜ばせようとつねに考え、また他人に感謝する気持ちをつねに持ち、自分自身を高めようと思っている者がいる。上甲さんの著作ではバブル(崩壊)、鍵山さんの場合は不景気という表現が用いられていますが、これらはいずれも二分法を補強する背景論だといえます。バブルのときは前者でもよかったかもしれないが、それがはじけ不景気となった今、前者ではもうダメだぞ、これからは心を大事にしていかねばならないぞ、というわけです。
このような考え方は、この時期のベストセラーの内容にも通じるところがあると私は考えています。端的には1992年に刊行され、翌年のベストセラーに名を連ねた作家・中野孝次さんの『清貧の思想』に近しいと考えます。同書には次のようにあります。「一九八〇年代のいわゆるバブル経済の繁栄の中でそういう欲望(富貴への願望と所有への欲望:引用者注)の奴隷になった連中を多く見たばかりです」(141p)。このような観点から、鴨長明・西行・吉田兼好などの「心の世界を重んじる文化の伝統」(2p)を見つめなおそうとする著作が『清貧の思想』でした。空前の好景気とその終焉を経て、「お金ではなく、心なのだ」という考え方が多くの人に現実味のある考えとして受け止められるようになったこと。『清貧の思想』がベストセラーになったことと、鍵山さんの考えに注目が集まり、書籍として刊行されるようになったことは、このような共通の背景があるように思われます。
さて、鍵山さんの著作から、もう一つ言及を拾っておきたいと思います。1995年の『日々これ掃除』では、次のような言及があります。
「人間は誰でも理想と現実に大きな差がございますね。理想と現実が一致しているという人はいないわけで、必ず現実に対して理想は遥か高いところにあるわけですが、この理想に至るためにどうしたらいいかということがわからない方が大変多いわけです。掃除をしておりますと、理想にどうしたら近づくことができるかという方法が、じつに具体的に、よーく見えてくるような気がいたします。ですから、掃除は理想と現実を近づける大きな力を持っているんではないかと思います」(24p)
ここには「夢」という言葉こそ使われてはいませんが、理想を実現するための力が掃除にはあると述べられています。ここだけ読むと近年の著作と同様である気もするのですが、ここでは「頭だけで物事を考えて」いると、「頭の中の堂々めぐり」で終わりがちなので、「手を使って」掃除をしたほうが、「今まで思いもつかなかったこと」が浮かぶという説明が後に足されています(24-25p)。つまり、舛田光洋さんのように、掃除をすることで夢がかなう、という直線的な関係にはなっていないのです。掃除という無心に行う作業をすることで、理想を実現するためのアイデアが浮かぶかもしれないよ、という話なのです。つまりまだ、舛田さんの着想にまではたどり着いていないということができます。
■「掃除と経営」の限界点
鍵山さんの『凡事徹底』が刊行された1994年以後、掃除と企業経営に関する著作が多く刊行されるようになります。1995年、ライターの山本健治さんによる『掃除が変える 会社が活きる』では、「いま、掃除がひそかに注目されている」(「はじめに」)として始まり、この時点での注目すべき人物、掃除の効用等について整理がなされています。
まず、掃除が今日重要とされる背景についての言及は、鍵山さんらの主張と同様のものです。つまり、掃除には根気、誠実さ、「あらゆることを馬鹿にしないという気持ち」が必要だが、「ついこの間までの私たち日本人は、そういう『基本』をおろそかにしていたのではないか」。「努力、根性、質実、勤勉などといった言葉はもう古臭い」もので、「いかに楽をして、手軽に、大きくもうけるか」と考えてきたのではないか。しかし「こういう安易な考え方では、決して長続きはしない。そのことはバブル経済の繁栄とその崩壊を通じて、誰の目にも明らかになった」。そこで基本から教育をやり直そうという話も出てきたが、「それを担う『人』の部分にこそ、もっと本質的な問題があるのではないか」(「はじめに」)。このように、バブル経済はいまや崩壊し、人間のあり方や心こそが重要であることがわかった、そこで掃除に注目してみようというストーリーがここでも語られています。
山本さんが紹介するのは、まず鍵山さん、次いで浅野さんと上甲さん、松下さんはその後に1章分を割いています(上甲さんの著作よりもさらに踏み込んで、松下さんの掃除哲学の検討がなされています)。ついで、楽しく、かつ重要な仕事として掃除を位置づけるディズニーランドにも1章が割かれ、そして掃除で業績を伸ばした企業数社がまとめてとりあげられています。
私が特に注目したいのは、『掃除セミナー』を開催している中央会経営教育センター代表(当時)の谷口正治さんに「掃除の効用」を聞いている箇所です。山本さんの整理によればそれは、「無心になれる」「気分が爽快になる」「よい行ない(善行をして満ち足りた気分になることができる:引用者注)」「自ら掃除をすることによって、謙虚に誠実に生きることの大切さを教えられる」「社長のいすに座ることで、見ていなかった、見えなかったことが見えるようになること」「現場をじっくり見直す機会になること」だといいます(29-40p)。
これらは包括的に言及されていると思うのですが、いずれも経営者にとって、という視点からの整理でした。山本さんの著作の表紙には、掃除には「あらゆる仕事のエッセンスが含まれている」、「経営活性化策としての掃除の大切さを説く」とあるように、あくまでも掃除は経営者(ここまでに紹介した著作における登場人物の多くは男性でした)にとって重要なもの、また仕事に関係するために重要なものだと認識されています。つまりまだ、掃除によってどんな人でも夢がかなう、片づけによってどんな人でも人生がときめく、というところまではたどりついていないわけです。
とはいえ、バブルが崩壊した今、心のあり方が重要であるという状況認識を背景として、掃除は自分を見つめ直し心を磨く有効な手段なのだという言論が現われたことは、掃除と片づけの歴史からみれば、画期的な出来事でした(省略しますが、以後ますますこうした著作数は増えていきます。鍵山さんだけ見ても、『凡事徹底』から数えて既に32冊もの著作を刊行されています)。しかし、掃除と会社経営というテーマの書籍が切り拓いたのはここまでです。この後は、橋本奎一郎『お掃除社内革命』などによって、ここまでに示した論点のハウ・トゥ化が進んでいくことになります。
近年の掃除・片づけ本の内容にたどりつくには、別ジャンルの書籍に目を転じて追っていく必要があります。それが次週の素材、女性向けの整理・収納本です。
----------
『決断の経営』
松下幸之助/PHP研究所/1979年
『松下政経塾 塾長講話録』
松下政経塾編/PHP研究所/1981年
『志のみ持参』
上甲 晃/致知出版社/1994年
『喜びの発見』
浅野 喜起/致知出版社/1994年
『凡事徹底』
鍵山 秀三郎/致知出版社/1994年
『掃除が変える 会社が活きる』
山本 健治/日本実業出版社/1995年
『日々これ掃除』
鍵山 秀三郎/学習研究社/1995年
『お掃除社内革命』
橋本 奎一郎/中経出版/1996年
『清貧の思想』
中野 孝次/草思社/1992年
----------
(牧野 智和)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【衆院選】岡山1区で自民・逢沢一郎氏が当選確実 13回目の当選
日テレNEWS NNN / 2024年10月28日 0時39分
-
【衆院選】佐賀1区で立憲・原口一博氏が当選確実 民主党政権で総務相
日テレNEWS NNN / 2024年10月27日 23時30分
-
小学校の生徒会長選挙はみじめな最下位…無口でシャイな男の子が「論客」で知られる総理大臣になったワケ
プレジデントオンライン / 2024年10月24日 16時15分
-
相手を「論破」してスッキリ!? 若者世代を魅了する「ひろゆき氏的な思想」の危うさに迫る『「それってあなたの感想ですよね」論破の功罪』が10月17日、新潮新書より発売!
PR TIMES / 2024年10月17日 14時45分
-
「経営者が政治家になれない?」日本の大問題 経営者出身は学者や芸能人より少ない傾向に
東洋経済オンライン / 2024年10月5日 11時0分
ランキング
-
1連続強盗「家族が生き残る家」の特徴と"10の武器" 防犯対策をしても強盗犯が突破してきたら…
東洋経済オンライン / 2024年10月29日 9時0分
-
2上司に「ムチャな仕事量を減らして!」と伝えるには…「時間が足りません」はNG。ひろゆきの仕事で使える“ズルい”言いまわし
日刊SPA! / 2024年10月29日 8時46分
-
3中小企業「冬のボーナス額」はいくら?
マイナビニュース / 2024年10月28日 11時10分
-
4「妻と浮気相手の間に生まれた子」を見捨てられなかった夫の悲哀。養育費を支払う“条件”は離婚翌日に破られ…
日刊SPA! / 2024年10月28日 15時54分
-
5【肉の日】2024年10月の飲食店キャンペーン・割引情報まとめ
イエモネ / 2024年10月27日 10時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください