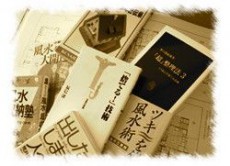なぜ「掃除・片づけ」が人生に関わるのか-4-
プレジデントオンライン / 2013年5月22日 11時15分
■TOPIC-4 「片づけ(られない)」への注目
ここまで、掃除・片づけ・整理・収納に関する書籍を一緒くたに論じてきましたが、これらのテーマには一つだけごく最近になって登場したものがあります。それは「片づけ」についての著作です。順番としては、主婦向けの掃除に関する書籍は1960年代以降、整理・収納に関する著作は1970年代以降連綿と刊行され続けているのですが、「片づけ」という言葉がタイトルに冠された書籍は1990年代、より具体的には前回紹介した飯田久恵さんの『生き方が変わる女の整理収納の法則 住まい&オフィスで片づけ上手になる極意』が刊行される1995年まで待たねばなりません。
片づけと整理は一見、ほぼ同じようにみえますが、近年の片づけ本のなかではそれらは異なるもので、整理よりもまず片づけこそが行われるべきことだと語られます。そして、この差異化が片づけ本の重要ポイントなのです。では、その差異はいかにして生まれていったのでしょうか。今週はこの点から考えてみたいと思います。
今述べた差異について簡単に解説しておくと、近年の片づけ本でいわれるのは、整理や収納、掃除は自分がコントロールできる程度までモノが減った状態になって初めて意味があるのであって、まずモノを減らす、より端的には「捨てる」ことが行われるべきだという話です。そこから、自分にとっての必要なモノを厳選し、そこから自分が分かり、といった話に展開していくわけです。
この「捨てる」ことから始まる片づけという考え方のルーツは、近藤麻理恵さん自身が影響を受けたと述べていることですが、2000年のマーケティング・プランナー辰巳渚さんによる『「捨てる!」技術』にあると考えられます。ただ、捨てることへの注目はその1年前から始まっているので、そこからみていくこととします。
■「捨てる」という発見
管見の限りでは、捨てることに注目した書籍の事始めは、1999年の経済学者・野口悠紀雄さんによる『「超」整理法3 とりあえず捨てる技術』ではないかと考えられます。とはいえ、同書で書かれていることは、情報の整理を目的とした、仕事関係の書類を捨てる技術でした。世に情報整理に関する著作は溢れており、同様のことは既に語られていたと考えられますが、それを「捨てる」という言葉で表現したところが新しい試みでした。
翌年、辰巳さんの著作が刊行されますが、辰巳さんは野口さんが「衣服や家具などの整理と廃棄」についての「要・不要の判定は容易だから、『捨てるためのノウハウ』は、格別必要ない」(『「超」整理法3』19p)として情報整理に焦点を絞ったことに疑問を呈しています。そんなに容易であるのなら、「家庭のなかはこれほどモノで溢れるはずはない」、と。辰巳さんは、「仕事を神聖視」する野口さんを批判的にみて、「モノを捨てる技術は、どこかのジャンルに限ったものではない。生き方、とまでいえる姿勢なのだ」と述べます(『「捨てる!」技術』76-77p)。
辰巳さんが説く捨てる技術とは、どのようなものでしょうか。まず示されるのは、捨てるということへの発想の転換です。モノを捨てるということには、「もったいない」という「後ろめたいような気分」が伴うものだった。一方で、次々と新商品が登場し続ける世の中に背を向けるというのも「あまりにさみしい」。そうであれば、「“捨てる”ことを肯定」し、そのなかで「モノの価値を検討」することで、「暮らしそのものを管理していく」のはどうだろうか、と(3-7p)。これを辰巳さんは「新しい美徳」の創造だとまで述べています(26p)。このような「もったいない」という美徳からの離脱は、小松易さん、近藤麻理恵さん、やましたひでこさんのいずれもが語っていることでもありました。
このように、近年の片づけ本のルーツといえる発想が辰巳さんにはあるのですが、捨てることで自分が変わる、人生が変わるといったことが大々的に主張されるわけではありません。同書の基本的な性格は、タイトルが示すとおり技術論でした。具体的には、とりあえずとっておこう、いつか使うから、誰かが使うかも、思い出や記念のモノだからといった、捨てることの妨げになる考えを取り払うための技術と、一定期間使わなければ捨てる、一定量を超えたら捨てるといった、積極的に捨てていくための技術が示されているという著作でした。
辰巳さんの著作の刊行は2000年4月でしたが、同書のヒットを受けてか、2000年後半には「捨てる」ことをテーマとした著作が次々と刊行されます。阿部絢子『「捨てる!」コツのコツ』、捨て方技術研究会『今すぐできる「捨て方」速攻テクニック』、スクラップレス21『「収納」するより「捨て」なさい』、等々。前回紹介した飯田久恵さんも、2001年に『「捨てる!」快適生活』という著作を刊行しています。これらの著作の内容はほぼ辰巳さんと同様のものですが、いずれにせよ、掃除でも収納でもなく捨てる(片づける)ことを重視する発想は、この時期から広がっていったのだと考えられます。
■「片づけられない」ことの問題化
2000年代における捨てること(片づけ)への注目は、ここまでに述べた文脈とは別のところでも起こっていました。それは2000年にアメリカの心理療法士サリ・ソルデンさんの『片づけられない女たち』の翻訳刊行以降に起こった、「片づけられない」ことの問題化です。
同書および、2001年刊行のアメリカの心理療法士リン・ワイスさんの『片づかない!見つからない!間に合わない』(両書とも、ニキ・リンコさんの翻訳によって、WAVE出版から刊行されていました)は、ADDという診断名を切り口にしていました。つまり、片づけられない女性たちのなかには、「ADD(注意欠陥障害)という神経系の障害が原因で苦労している人たちがいる」(『片づけられない女たち』3p)というわけです。
しかしこれは、片づけられないのはADDだからだ、と「障害のせい」にする書籍では決してありません。むしろ同書は、「ADDであるかどうかにかかわらず、部屋を片づけられない、こまやかな気配りの苦手な女性たち」を、「片づけられないからといって、夢をあきらめないでください」、「散らかった部屋の中でも、人生はもう始まっているのです」と応援する書籍であり、また「ADDという切り口から、社会のダブルスタンダードを照らしだす」書籍でもあるといいます(8-9p)。ここでいう社会のダブルスタンダードとは、女性ばかりが片づけること、ひいては家事とくに掃除を行うよう求められ、それができないばかりに結婚に踏み切れない、人間関係に支障をきたす——男性よりも女性にそうしたトラブルは顕著に現われる——ということを意味しています。このように、「片づけられない」ことは、一種の問題提起としてまず現われたのでした。
しかしこの「片づけられない」という言葉はやがて、ADDあるいはADHD(注意欠陥・多動性障害)とは切り離されて用いられるようになります。たとえば雑誌メディアでは、2001年8月の『MINE』で「片づけられない女たちの、収納解決塾」という特集が組まれていますが、ここには何らかの障害に関する言及はありません。
書籍タイトルでも2003年から2004年にかけて、サニー・シュレンジャーら『いつも時間がないA君と片づけられないBさんへ』、マリリン・ポール『だから片づかない。なのに時間がない。「だらしない自分」を変える7つのステップ』、荒井有里『出したらしまえない人へ しまおうとするから片づかない』といった書籍が刊行されていますが(翻訳書の原題には、片づけられないということに関する文言はありません)、ここにも障害に関する言及はありません。ポールさんの著作では、タイトルにもあるように整理整頓ができないのは「だらしない」ためだとされています。また、荒井さんの著作では『片づけられない女たち』を引きつつ、「ADD自体あやふやな病気」で、実際に何らかの障害が原因で片づけができない人は「ほんのひと握り」であり、「『出したらしまえない』のは病気ではありません」と述べられています(『出したらしまえない人へ』54-55p)。
荒井さんはかなり注意深く書かれてはいますが、いずれにせよどの著作も、片づけられないのは病気ではないと述べています。これらのプロセスは社会学の概念では「医療化」と「脱医療化」という観点から捉えることができます。このテーマに関する社会学の基本文献であるP.コンラッド/J.W.シュナイダー『逸脱と医療化——悪から病へ』によれば、医療化とは「ある問題を医学用語で記述するということ、ある問題を理解するに際して医療的な枠組みを採用すること」(1p)といった定義がなされています。医療化の一つの機能は、同書の副題にもあるように「悪から病へ」、つまり「病気」というレッテルを与えることで、ある現象を道徳上の問題ではなく治療上の問題へと書き換えてしまうことにあります(11p)。脱医療化は概していえばその逆です。
同書では「医療化が周期的な次元を持つ」、つまりある対象は、専門的な認定、公的位置づけ、人々の意識といったさまざまな水準において「悪しきものと病めるものとの認定の間を行ったり来たり」するとも述べられています(512p)。「片づけられない」ことはまさにそのような展開をたどりました。当初、医療的な枠組みとワンセットで問題提起され、話題となる。しかし間もなくそれは病気ではないと差し戻され、書籍、雑誌、ワイドショーや情報番組等で「片づけられない」ことは、病気ではないけれども「困った人たち」というような扱いで報じられ続けるようになる。この問題を医療的な枠組みから捉えるべきか否かは私の能力を超えるものですが、いずれにせよ、「片づけ(られない)」ことへの注目がこうして集まったことも、近年の片づけ本ブームを理解する補助線になると私は考えています。
■「風水」はどのように入り込んだか
最後に補助線をもう一つ引きたいと考えています。舛田光洋さんの『夢をかなえる「そうじ力」』では大々的に、やましたひでこさんの『新・片づけ術 断捨離』ではごく簡単に、人智を超えた存在と掃除・片づけの関係が言及されていました。舛田さんに関しては『脳内革命』や船井幸雄さんとの関連を推測することができるのですが、やましたひでこさんという女性の手になる片づけ論と、人智を超えた、つまり「スピリチュアル」なものとの関係には、別の文脈があるようにどうしても思います。
私が考えているのは「風水」です。テレビや雑誌で、しばしば風水に関するコーナーや記事をみることがありますよね。それらのコーナー・記事では「風水とは…」といった注釈が特になされることもなく、風水的にはこのインテリア配置は云々、と語られているように思います。つまり風水はもはや注釈の必要がないという程度には、私たちの生活の一風景となっているわけです。この風水のなかに、掃除や収納に関する言及が徐々に入り込んでくるようになるプロセスを以下ではみていきます。
さて、風水というものは、いつからこの日本で定着したと思われるでしょうか。これは意外にかなり最近のことです。もちろん、風水は大陸にルーツがあるもので、その歴史は非常に長いものがありますが、それが日本で、読者が自分で利用できるようなかたちで紹介されるようになったのは1993年から1994年のことです。
1993年、風水という言葉を冠する(「風水害」は除く)、国内初の書籍が刊行されます。仙術、奇門遁甲、占術、般若心経、法華経、前世等についての著作を1970年代以来手がけてきた田口真堂さんによる、『願いがかなう気学風水入門——愛、財産、健康が自由自在・中国4000年の奥儀を初公開!』です。翌1994年には、小林祥晃さんの『風水パワーで大開運——食事からインテリアまで何でも使ってツキを呼ぶ』が続きます。このうち田口さんのものは、「気学風水とは?」という章から始まり、自分の本命星を知る、方位盤の読み方を知る等の解説が半分ほどをしめる、まさに風水を学ぶための入門書という性格の著作でした。これに対して小林さんの著作は、タイトルにもあるように、インテリアの配置についてあれはよくないこれはよくないと、微に入り細にわたって実用的な話を重ねていくというものです。どうやら後者、小林さんのほうに、風水と掃除・片づけを結びつける系脈がありそうです。
小林さんはドクター・コパという愛称の方がおそらく有名でしょう。彼はテレビの風水に関するコーナー、雑誌の風水に関する記事でも必ずといってもいいほど出てくる、「風水タレント」の第一人者であり、また実際に非常に精力的に風水に関する言論を発しています。彼のホームページの「書籍一覧」には、彼がこれまで刊行してきた、実に572冊もの著作がリスト化されています(2013年4月5日時点)。この小林さんの言論を追っていくことで、風水と掃除・片づけが結びつくプロセスの一端を推し量ることができると私は考えます。
小林さんは当初、家相学を自らの「売り」としていました。家相学には風水と同様、非常に長い歴史がありますが、基本的には家の間取りと方位を考えようとするものです。1970年代、北竜子『あなたに幸せをもたらす絵で見る家相』(1970)、多田花外『幸福を呼ぶ家相』(1976)といった、家相と幸福に関する著作が刊行されていましたが、これは間取りと運勢の関係を述べるもので、そこに何を置くか、どう住まうかということは問題にされていませんでした。小林さんも処女作である1986年の『楽しく自分を活かす住まいの東西南北——中国3000年の歴史が証明した家相運』以来、しばらくはこの家相学を使える一級建築士、という立場で著作を刊行していました。
1991年、『驚異のインテリア・パワ——こんな家具・インテリアがあなたのツキを奪う』という著作が刊行され、小林さんはインテリアの置き方に言及し始めます。しかし掃除や収納についてはまだ何も言及がありません。そしてまだ風水の話もしていません。1993年、『小林祥晃の家相わが家の秘伝集——住まいのパワーで運をつかむ』では、掃除に関する言及が以下のように出てくるのですが、ほこりは喘息の原因となるためよくないのだ、という非常に単純な観点から語られていました。
「棚はよほどこまめに掃除をしないかぎり、ほこりのたまり場になってしまいます。その部屋で生活していると、ほこりが風に舞って落ちてきて、呼吸するうち体内に入ってしまいます。ほこりは体に悪く、気管支などを傷める悪玉です。ダニなどの発生源にも、喘息の原因にもなります。棚をつけると病人が出て、家が栄えないというのは、こうした理由からなのです」(52-53p)
ただ、その一方で同書では「鬼門をとにかくきれいにすることです。(中略)明るく清潔にすることで、その凶作用はある程度防げます」(79p)ともあり、掃除と運勢の関係が論じられ始めてもいます。しかし先の引用における単純さを考えると、小林さんのなかでは掃除にまだ特段の意味を持たせていないことが伺えます。
1994年の『風水パワーで大開運』、つまり小林さんが風水という言葉を使い始めてから、掃除に関する言及が一貫性をもってなされ始めます。同書では「風通しが悪く、部屋が汚いと運気は下降します。まずは、部屋を掃除し照明を明るくしてください」(100p)として、掃除と運気との関係が述べられています。1994年の『ツキを鍛える風水術』では、「風水では、汚れたものには運がドロップする」(52p)として、特段これ以上の説明はされないのですが、風水の考え方からすると汚れはよくないという説明がなされるようになります。
1996年の『Dr.コパの風水「超」収納塾——陰宅パワーで幸せをつかめ』ではついに収納に手が伸ばされ、収納の仕方によって幸運になるという見方が示されるようになります。そして同書でも「そもそも、風水とは汚れを嫌うもの」(44p)という立場がとられ、具体的には次のように収納・掃除と幸運の関係が論じられます。
「ラッキーゾーンが汚れていたり、ゴミが落ちていたりすると家の運気が落ちる」(21p)
「キチンと片づいていて、ラッキーパワーを高めるようなアイテムがしまわれていれば、確実に住まいのパワーがアップします」(23p)
「仮に、部屋の北方位に押入れがあるとします。この場合、ホコリや汚れがなく、きれいに片づいていれば精神的に落ち着ける“気"が得られるはずです」(28p)
また同書では「ツキを呼ぶためにモノを捨てる、運を開くためにモノを残す」(144p)という主張もなされています。小林さんの著作すべてを紐解くのは不可能に近いのでここまでとしますが、掃除や収納に、気(舛田さんでいえばエネルギー)という観点からの解釈がかぶせられ、また開運・幸せと掃除・収納が結びつけられるようになるという変化が1990年代中頃には既に観察できるのです。こうした世界観をもつ風水が、注釈なしにテレビや雑誌で扱われるようになった状況を考えれば、掃除や片づけによってエネルギーが云々、という物言いが出てくるのはそう驚くことではないと思いませんか。そして、それがベストセラーとなるということも。
さて、長い探求を続けてきましたが、近年の掃除・片づけ本の構成要素について、その先行する系譜を色々とみてきました。次週はこれらを踏まえて、近年のベストセラーの何が新しいのかとともに、そこから見えてくる現代社会とは何かを考えてみたいと思います。
----------
『「捨てる!」技術』
辰巳 渚/宝島社/2000年
『「超」整理法 3』
野口 悠紀雄/中公新書/1999年
『出したらしまえない人へ』
荒井 有里/主婦の友インフォス情報社/2004年
『小林祥晃の家相わが家の秘伝集』
小林 祥晃/廣済堂出版/1993年
『風水パワーで大開運』
小林 祥晃/廣済堂出版/1993年
『ツキを鍛える風水術』
小林 祥晃/マガジンハウス/1994年
『Dr.コパの風水「超」収納塾』
小林 祥晃/経済界/1996年
『だから片づかない。なのに時間がない。』
マリリン・ポール/ダイヤモンド社/2004年
『絵で見る家相』
北 竜子/国際興産株式会社出版局/1970年
『幸福を呼ぶ家相』
多田 花外/住宅新報社/1974年
『楽しく自分を活かす住まいの東西南北』
小林 祥晃/ハート出版/1987年
『驚異のインテリア・パワー』
小林 祥晃/廣済堂出版/1991年
『願いがかなう気学風水入門』
田口 真堂/永岡書店/1993年
『今すぐできる「捨て方」速攻テクニック』
捨て方技術研究会/ワニブックス/2000年
『「捨てる!」コツのコツ』
阿部 絢子/ワニ文庫/2000年
『「収納」するより「捨て」なさい』
スクラップレス21/ぶんか社/2000年
『「捨てる!」快適生活』
飯田 久恵/三笠書房/2001年
『片づけられない女たち』
サリ・ソルデン/WAVE出版/2000年
『片づかない!見つからない!間に合わない!』
リン・ワイス/WAVE出版/2001年
『いつも時間がないA君と片づけられないBさんへ』
サニー・シュレンジャー、ロバータ・ロッシュ/幻冬舎/2003年
『逸脱と医療化―悪から病へ』
P. コンラッド、J.W. シュナイダー/ミネルヴァ書房/2003年
----------
(牧野 智和)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
気付かぬうちに…年間数万〜十数万円のムダづかいをしている?「60歳以上の単身世帯」の平均生活費からチェック
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 11時30分
-
自分の家を好きになることから始めよう。家相に詳しい一級建築士が語る「お金の貯まる家づくり」
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2024年6月20日 10時0分
-
お金も時間も無駄に…“ふるまい”で分かる「家が散らかっている人」の特徴【生前整理・遺品整理のプロが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 8時15分
-
電気代の節約に?…部屋の「ものを減らす」ことで得られる“意外な効果”【生前整理・遺品整理のプロが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月12日 11時20分
-
物置部屋に毎月数万円…?納戸は「空の状態にして開かないようにするのがベスト」な理由【生前整理・遺品整理のプロが解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 11時20分
ランキング
-
1ミラノ風ドリア「480円→290円」で売上数3倍…創業者が「サイゼリヤの料理は、まずくて高い」と語る深い理由
プレジデントオンライン / 2024年7月4日 8時15分
-
2寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分
-
3Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
4なぜ免許証とマイナカード「24年度末」までに一体化? 紛失したら運転できない? 国民にメリットあるのか
くるまのニュース / 2024年7月4日 9時10分
-
5定年後に、見落とすと厄介な出費「3選」とは?
オールアバウト / 2024年7月3日 21時40分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください