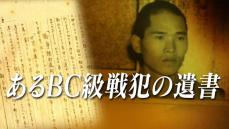「命令に従った」は通用しない 問われる個人としての戦犯~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#44
RKB毎日放送 / 2024年5月31日 22時15分
米軍機搭乗員3人の殺害に対して、41人に死刑が宣告された石垣島事件。戦犯裁判にかけられた元日本兵たちは、米軍の調査官らから「共同謀議」が成立するように「命令なく自主的にやった」という内容を強要、誘導された調書を取られ、その後弁護人に「命令があった」と訴えた。しかし、「命令に従った」としても死刑から免れることができなかったのが藤中松雄ら実行者たちだ。「命令だった」は通用しないのだろうかー。
◆軍隊では「命令に対する服従は絶対」
戦勝国が敗戦国を裁く戦犯裁判。日本が受諾したポツダム宣言には「戦争犯罪人の処罰」が含まれていた。「通常の戦争犯罪」にあたる捕虜虐待で、BC戦犯として横浜軍事法廷にかけられた石垣島警備隊の炭床静男兵曹長。処刑の現場を仕切っていた榎本中尉の命令によって、炭床兵曹長は杭に縛られていた米軍機搭乗員のロイド兵曹を銃剣で1回刺した。その前にすでに20人程が刺突していたという。すでに沖縄戦が始まり、連合軍の石垣島への空襲も激しくなっていた。職業軍人ではない職人など市井の人たちが多く集められていた石垣島警備隊の士気をあげようと、ロイド兵曹は刺突訓練の的にされたのだ。榎本中尉は、「次、次」と命令し、多くの兵に突かせた。
国立公文書館が所蔵する石垣島事件のファイルの中に「横浜石垣島弁護団松井調査官よりの照会文回答案」というものがあった。海軍の用紙に記されている。弁護団が海軍での命令についての説明を裁判に提出したのだろう。それによると、
「命令とは、指揮権を有する上官が、部下に行為又は不行為を命ずるもので、その条件としては命令者及受命者の職務権限内の事項に関し、且つ適法なるものでなければならない」とある。そしてどの程度、命令に従わねばならなかったかというと、「命令に対する服従は絶対的」であり、一旦命令を受けた後は、それが難しいだとか、実行を怠る、また、それをするかしないかについて意見を述べ合うなどは断じて許されないと書いてあった。
◆命令されたら、やらざるを得なかった
炭床静男兵曹長の次男・健二さんと三男・さんは、裁判記録から父が事件に関わった当時の状況を知って、次のように感想を述べた。
次男・健二さん「そのときに私も同じ状態になったら、命令されたら仕方ないですよね、ひとりだけ独特な行動をして逃げるわけにいかないでしょう。逃げたら卑怯者というふうになるわけですから、おやじの気持ちもわかりますよ。戦争という大きな国の中で動いているわけだから、命令されたらやらざるを得ないというのが本音じゃないですかね。それが戦争という状況でしょうからね」
三男・浩さん「父が酔っ払った時に、上官の命令は絶対だという時代があったんだというようなことを、時々言っていました。いま思えば、事件のことも含めてそう言っていたんだと思いますが、その当時は子供だったから、意味は分からなかった」
静男にしてみれば、軍人として命令を忠実に守ったということだったのだろう。元警察官の健二さんは、
次男・健二さん「だからわかりますよ、おやじのやったことは理解できる。今はやっちゃいけないことですけど、当時としてはやるでしょうね、やっぱり。私も命令されたら逃げられんですから」
◆今も戦争犯罪は起きている
石垣島事件は過去の戦争犯罪だが、いまも地球上では戦争犯罪が絶えない。日本の戦犯裁判は現在、どのような影響を及ぼしているのか。日本大学生産工学部の高澤弘明准教授に解説してもらった。
高澤准教授「例えばウクライナで今、ロシアがやっていること、ウクライナもやっているかもしれませんが、捕虜の扱いだとか、あるいは一般市民を巻き込んでの戦闘は、戦争犯罪になります。日本の場合は、幸いにしてこの80年間、戦争がなかったので忘れられていますが、戦争犯罪は今も発生しています。そして、今の戦争犯罪の考え方の源流は、第二次世界大戦後のドイツと日本の戦犯裁判が大きく影響しています」
◆第一次大戦以前はなかった「個人の責任追及」
高澤准教授「戦争が終わった後、個人が責任追及されるのは、第一次世界大戦以前はなかったんですね。例えば日清戦争や日露戦争の場合、終わったら講和条約を結んで、戦争犯罪人を出したり処罰したりというのはなくて、賠償金を払ってそれで許してくださいねという流れですが、第二次世界大戦以降に関しては、戦争が終わって、国家も動いたかもしれないけれども、個人としてもちゃんと責任を取りなさいということです。個人が責任追及された最初のケースがドイツと日本ですので、それが現在の国際司法裁判システムにも大きく作用しています」
◆個人の責任問われ”驚き”
高澤准教授によると、捕虜の扱いを定めたジュネーブ条約違反の場合は、当然その実行者も条約違反になるが、第一次世界大戦まではその責任を誰が負うかというと、個人ではなく国家が負ったという。国家が肩代わりして賠償金を払うなり、国家責任という形をとり、個人が裁かれるということはなかったが、第二次世界大戦以降、特にポツダム宣言やドイツの場合は、個人が処罰された。
高澤准教授「今は犯罪だから個人として裁かれて当然だろうっていうふうに一般的には認識されていますが、横浜裁判の当時、被告の人たちからすると、個人個人の責任追及というのはされないのが前提の世代だったわけですよね。たまたま日本が負けて、ポツダム宣言で戦犯裁判が開かれて、その裁判で初めて、その現場にいた実動部隊も裁かれるのかということで、びっくりしたような状態だった。なんでというような不満は、当事者からするとあったのではないでしょうか」
「命令に従っただけなのに、何故戦犯に問われないといけないのか」という戸惑いは、多くの被告たちが弁護人に訴えた文書からも伝わる。日本はジュネーブ条約を批准はしていないが準用していたので、捕虜虐待は不法行為にあたる。それを知らされることもなく、戦闘行為の延長という感覚で捕らえた米兵を処刑してしまった兵士たち。命令が適法でなければ海軍の命令の規定からもはずれる。個々人がした事の責任を追求された時、「命令に従った」は免罪符にはならなかったのかー。(エピソード45に続く)
*本エピソードは第44話です。
ほかのエピソードは次のリンクからご覧頂けます。
◆連載:【あるBC級戦犯の遺書】28歳の青年・藤中松雄はなぜ戦争犯罪人となったのか
1950年4月7日に執行されたスガモプリズン最後の死刑。福岡県出身の藤中松雄はBC級戦犯として28歳で命を奪われた。なぜ松雄は戦犯となったのか。松雄が関わった米兵の捕虜殺害事件、「石垣島事件」や横浜裁判の経過、スガモプリズンの日々を、日本とアメリカに残る公文書や松雄自身が記した遺書、手紙などの資料から読み解いていく。
筆者:大村由紀子
RKB毎日放送 ディレクター 1989年入社
司法、戦争等をテーマにしたドキュメンタリーを制作。2021年「永遠の平和を あるBC級戦犯の遺書」(テレビ・ラジオ)で石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞奨励賞、平和・協同ジャーナリスト基金賞審査委員特別賞、放送文化基金賞優秀賞、独・ワールドメディアフェスティバル銀賞などを受賞。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
下士官ですら死刑執行 米軍の怒りはどこに 石垣島事件厳罰の背景は~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#48
RKB毎日放送 / 2024年6月28日 22時6分
-
なぜ下士官までが極刑に 41人が死刑 石垣島事件の特殊要因は~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#47
RKB毎日放送 / 2024年6月21日 22時4分
-
「命令の実行者が絞首刑」石垣島事件の過酷な判決 ほかのBC級戦犯裁判はどうだった~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#46
RKB毎日放送 / 2024年6月14日 22時2分
-
間違った命令に従った場合は・・・戦犯裁判で抗弁にならなかった日本の認識~28歳の青年はなぜ戦争犯罪人となったのか【連載:あるBC級戦犯の遺書】#45
RKB毎日放送 / 2024年6月7日 22時6分
-
BC級戦犯 出所したはずの父は妻子の元へ帰ってこなかった
RKB毎日放送 / 2024年6月7日 16時54分
ランキング
-
1河野太郎氏、やから発言釈明 「言葉の選び方は慎重に」
共同通信 / 2024年7月3日 20時0分
-
2潜水艦修理契約で不正か=川崎重工、海自に金品提供疑い―防衛省
時事通信 / 2024年7月3日 19時51分
-
3横浜患者連続死、無期確定へ=東京高検が上告断念
時事通信 / 2024年7月3日 16時28分
-
4知床沖観光船沈没事故で乗客家族らが損害賠償を求め運航会社と桂田精一社長を提訴「亡くなられた家族と残された家族の尊厳の問題」
北海道放送 / 2024年7月3日 18時5分
-
5旧優生保護法違憲判決 「思い伝わり夢のよう」 原告団に歓喜の輪
毎日新聞 / 2024年7月3日 16時52分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください