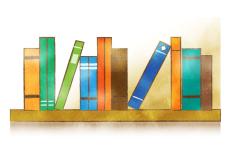<ビブリオエッセー>「ふるまい」が喚起するもの 「建築と言葉-日常を設計するまなざし」小池昌代/塚本由晴(河出ブックス)
産経ニュース / 2024年6月19日 12時7分
「『実は、この床の下に死体が埋まっているんだよね』ということになったら」と建築家の塚本さんが言えば詩人の小池さんは「死体と建築。言葉ひとつが空間の肌合いを決めてしまう」と応える。ドキッとしたがシャリとネタ、言葉を重ねた高級なすしをいただくような対談だ。
本書のきっかけは2008年、サンパウロで開かれたシンポジウムだ。塚本さんの柔軟で鋭いレクチャーに小池さんが心を動かされ、企画ができたそうだ。話を聞くうちに小池さんは、塚本さんの建築が「『建造物』でなく、まさに『棲家』と呼ぶにふさわしいもの」に見え、塚本さんがしばしば使う「ふるまい」という言葉に心の中であっと声をあげたという。
それは「磁石」のように「日常を覆っている様々な要素」を集め、「ついには一軒の家のような、ある『形』を取り始める」と書く。対して塚本さんは「今、建築は言葉に期待する」と応えた。二人の話は感性が豊かで、化学反応のように新しい発想につながっていく。
「建築は言葉で動き出す」や「人間は風景に支えられる」など印象的な話がいくつもあるが「個人主義の壁」という表現が目に留まった。他者との関係性を語り合うのだが私は学生時代の記憶がよみがえった。二人部屋の学生寮に入ったとき同室者との壁がなかったのだ。一人になれる壁が欲しかった。そこでアパート探しをしたが、隣り合う部屋の境に共同トイレがある部屋へ案内された。音が妄想をかきたて、壁という存在の不可思議さを思ったものだ。
古い建物や都市計画の話から二人は「都市と家の『ふるまい』」を語り、「風景の再生」を考える。そこには建築と時とのふるまいを言い表した言葉があり、対談の妙味を堪能した。
山形県天童市 古間恵一(66)
◇
投稿はペンネーム可。650字程度で住所、氏名、年齢と電話番号を明記し、〒556-8661 産経新聞「ビブリオエッセー」事務局まで。メールはbiblio@sankei.co.jp。題材となる本は流通している書籍に限り、絵本や漫画も含みます。採用の方のみ連絡、原稿は返却しません。二重投稿はお断りします。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
旅行中、白洲さんは風景を食べていた―盟友の脳裡によみがえる人間・白洲正子
文春オンライン / 2024年6月21日 17時0分
-
<ビブリオエッセー>描き出された希望と絶望 「ゴールデンボーイ-恐怖の四季 春夏編」スティーヴン・キング著 浅倉久志訳(新潮文庫)
産経ニュース / 2024年6月17日 13時22分
-
ゆっきゅん「私に与えられたポエジーは、天井から」 詩人・小野絵里華と“ポエジー”を語る
ananweb / 2024年6月12日 20時0分
-
<ビブリオエッセー>まるで心のストレッチ 「メンタル脳」アンデシュ・ハンセン/マッツ・ヴェンブラード 久山葉子訳(新潮新書)
産経ニュース / 2024年6月10日 12時39分
-
なぜ大学病院の病室からの景色はイマイチなのか…多くの大学病院が刑務所と同じ構造になっている大問題
プレジデントオンライン / 2024年5月27日 15時15分
ランキング
-
1食欲なし、足のむくみは心臓がやられている可能性…「大病の予兆」見分け方のコツは遠い場所に出る危険サイン
プレジデントオンライン / 2024年6月23日 6時15分
-
2インバウンドに沸く「お台場フードコート」の現在 外国人目線の「ザ・日本食」が集まる施設だ
東洋経済オンライン / 2024年6月23日 12時30分
-
3〈月収43万円〉の定年サラリーマン〈退職金1,500万円〉を元金に、長年の夢だった「カフェ」をオープン!感無量もわずか8ヵ月で閉店、500万円の借金を負った「残念な理由」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月22日 10時15分
-
4「イオンや業スーの激安そうめんはマズい」が覆る!驚くほどおいしくなる3つのコツ
女子SPA! / 2024年6月23日 8時46分
-
56歳未満の女児を脳死判定、心臓や腎臓を提供へ…松戸市立総合医療センター
読売新聞 / 2024年6月23日 19時2分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください