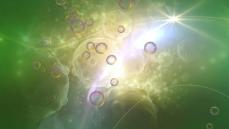がん細胞がぷちぷち壊れていく…人類の希望「光免疫療法」発見の瞬間「がんを光らせる実験のはずがまさかの結末に」
集英社オンライン / 2023年9月27日 11時1分
2020年9月、厚生労働省から正式に承認を受け、楽天メディカルが普及に尽力中の光免疫療法。およそ9割のがんに効く治療法であると期待されている。がんという複雑怪奇な病に立ち向かう、この治療法はいったいどうやって生まれたのだろうか。『がんの消滅:天才医師が挑む光免疫療法』 (芹澤健介[著]/小林久隆[医療監修]、新潮新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。
始まりは、がんを「治療する」ための研究ではなかった?
2009年5月、米国メリーランド州ベセスダ。ワシントンD.C.のすぐ北西に隣接するその町に、アメリカ最大の医学研究機関、米国国立衛生研究所(NIH:National Institutes of Health)はある。そのNIHの主任研究員、小林久隆の実験室で奇妙な現象が起きていた。
――がん細胞がぷちぷち壊れていく。
当時、小林が取り組んでいたのは「がんの分子イメージング」である。
医学における〈イメージング〉とは人体内部の構造などを解析、診断するために画像化すること。「がんの分子イメージング」とは、つまりがんを可視化する研究だ。がんを「治療する」ための研究ではない。ましてやがん細胞を破壊するなどということが目的ではない。
がん細胞の表面には他の正常細胞にはないタンパク質が多数、分布している。がん細胞を移植されたマウスの体組織内に、このタンパク質とだけ(特異的に)結合する物質を送り込んでやれば、がん細胞にだけその物質がくっつくことになる。
この物質に蛍光物質をつけてやればどうなるか。がん細胞だけを光らせることができる。外科手術の際は、その光っている部分、がん細胞だけを取り除くことが可能になるし、取り残しも防げる。簡単に言えば、当時の小林が取り組んでいた研究のひとつはそうしたものだった。

その日、朝から試していたのは〈IR700〉という光感受性物質だった。光に当たると化学反応を起こして発光する物質である。IRはInfrared=赤外線の略だ。700nm(ナノメートル)付近の波長の光に反応するからIR700と名づけられた。
700nmの光とは、テレビの赤外線リモコンでも使われるような無害安全な種類の光である。紫外線のような波長の短い光だと細胞を傷つけてしまう恐れがある。そのために選ばれた可視光に近い近赤外線である。
その光を何度がん細胞に当ててもうまく光らない。
マウスのがん細胞と試薬はちゃんと結合しているはずだった。だが、きれいに光らない。がん細胞が仄かに発光はするのだが、際立った反応を見せることもなく、そのまま暗くなってしまう。明らかにほかの試薬とは違う反応だった。実験は失敗に見えた。
「またダメだ……」
「どうしてなんだろう」続く、実験現場の奇妙な現象
実験に当たっていた小川美香子(現北海道大学大学院薬学研究院教授)は、蛍光顕微鏡のモニターを見つめていたその時のことをよく覚えていた。小川は京都大学薬学部出身。浜松医大の助教職から2年間という期限で小林のもとに留学していた。
小川の研究テーマもまた「がんの分子イメージング」だ。自他ともに認める〝化学屋〟で、実験の精度や手順には定評がある。実際、NIHでも優秀な博士研究員(フェロー)に与えられる賞を受賞していた。
「どうしてなんだろう」
がん細胞と結合させる試薬によって、がんの光り方や明るさも変わる。リストアップした試薬を片っ端から実験し、その差異をデータとしてまとめるのが小川の仕事だった。
東京慈恵会医科大学の大学院からNIHに来たばかりの光永眞人(現慈恵医大医学部講師)も戸惑いながらモニターを見つめていた。

帰国を控えた小川から実験を引き継いでいる光永の役割は記録用に撮影データを残すことだった。当時を振り返って光永は言う。
「パッと光を当てれば、ほかの色素はだいたいこちらの予想通りに光ってくれました。近赤外線の強さや露光時間を計算してやると、がん細胞がどのくらい光って、何秒後には消えていくというパターンがある程度は分かっていたんです。ですが、IR700の場合はがん細胞の光り方も違っていて、近赤外線を当てた後、顕微鏡の視野が急激に暗くなっていきました」
この2年で小川はすでに200近くの蛍光物質を試している。近赤外線を当てたとたん、その光エネルギーに反応してモニター内でがん細胞が鮮やかな緑色に光ればそれは「よい試薬」だ。
しかし、リストの最後の方にあったこのIR700は、何度実験を繰り返してもきれいに光らせることができなかった。ぼんやりと光るには光っても、その淡い光はすぐ消え、顕微鏡の視野が暗くなる。その繰り返しだった。
IR700の大元は、道路標識や東海道・山陽新幹線の車体のあの青色の塗料
そもそも、このIR700の実験を小川が後回しにしていたのにはわけがある。
「小林先生には前々からやってみてと言われていたんですけどね」と小川は言う。
「〝化学屋〟の私としては、IR700の化学式があまり素敵な形じゃないなあと思っていたんです」
理系の研究者はしばしば自分の専門分野を伝える際にこうした言い回しをする。〝物理屋〟〝化学屋〟〝数学屋〟などだ。それはともかく、小川のような薬学の専門家の目からはIR700という物質はそう見えたらしい。
「化学式を見るとわかるんですが、この試薬はもともとは水に溶けにくいフタロシアニンという色素を水溶性にするために、スルホ基を上下につけているんです」
スルホ基とはスルホン酸の陰イオン部分で、水によく溶ける。スルホン酸自体は硫酸に匹敵する強い酸なのだが、このスルホ基の性質を利用して、染料や界面活性剤など水に溶けていないと使えない有機化合物を合成する際に使われる。
「実験の素材としては非常に扱いにくそうな化合物だったんですね。なので、正直なところ、ほったらかしにしていたんです。でも、そろそろ留学期間も残りわずかだし、小林先生にもお尻を叩かれていたので、ちょっとやってみようかと」
フタロシアニンは光や熱に強い性質を持つ色素である。道路標識や東海道・山陽新幹線の車体のあの青色の塗料に使われている。これを水溶性にしたIR700は小林が以前から懇意にしていた小さな化学メーカーが売り込んできた。この物質が気になった小林はメーカーと調整を重ね、実験や治療に使えるよう仕立てていたのだ。

そのIR700の実験がうまくいかない。
それどころか、がん細胞は死んでしまっているようだった。死んだがん細胞を特定できたところで画像診断としては意味がない。生きたがん細胞を光らせてこそ、治療に役立つのだから。
ぷちぷち割れる…光免疫療法の「発見」
急いで倍率を上げてよくよく観察してみると、がん細胞がどんどん壊れているように見えた。まるで水風船が割れるように、あるいは焼いた餅が膨らむように、がん細胞が次々と膨張して破裂していくのだ。その様子を小川は「ぷちぷち割れる」と表現した。
「そんなふうにがん細胞が割れるのはそれまで見たこともありませんでした。それに、がん細胞を光らせる実験中にがん細胞が死んじゃうっていうのは、少なくとも担当者の私は求めていない結果でしたし、どこで実験の手順を間違えたんだろうって、そればっかり考えていましたね」
実験のエキスパートである小川が「それまで見たこともなかった」と首をひねるような現象だった。
光永も困った顔でモニターを見つめるばかりだった。光永にとってもがん細胞が割れて死んでいくのは想定外だった。普通に考えれば、近赤外線を当てるだけでがん細胞が壊れるはずがない。光の出力は正常値。高出力でがん細胞を焼き殺しているわけではないのだ。

そもそも実験に使う光として近赤外線が選ばれているのも、「細胞には影響を与えない安全な光」だったからだ。だが、何度繰り返しても結果は同じ。
「やっぱりコイツの形が悪いんじゃないかなあ。このスルホ基が何かを邪魔してるんじゃないかと思うんですけど」
小川が言ったのはIR700のことだ。
「なんだか光り方も変ですよね……」
このIR700には光永も朝から撮影のタイミングや露出の調整で苦労させられていた。
すでに午後一番のラボ・ミーティングの時間が迫っていた。小川はミーティング直前、実験の様子を上司である小林に伝えた。
「今朝からIR700を試しているんですけど、うまくいかなくて……」
「うまくいかない?」
「何度やっても死んじゃうんですよ」
「……死ぬって、何が」
「がん細胞が、です」
「がん細胞が死ぬって……小川さん、それってどういうことや」
小林は時折、生まれ故郷の西宮の話し言葉が出る。
そそくさとミーティングを終え、小川が顕微鏡室でその現象を小林に見せた時だった。小林が大きな声でこう言った。
「これはおもろいなあ!」
食い入るようにモニターに見入っていた。
「すごい、すごいで! これは治療に使えるんちゃうか!」
光免疫療法が〝発見〟された瞬間だった。
「がん細胞だけを殺す治療法が開発されつつある」と大統領が漏らした!?
その後、小川美香子から助手を引き継いだ光永眞人が実験を重ね、光永を第一著者、浜松医大に戻った小川を第二著者、小林久隆を最終著者とした論文「特定の膜分子を標的とするがん細胞を選択的に近赤外線によって破壊する治療法(Cancer Cell -Selective In Vivo Near Infrared Photoimmunotherapy Targeting Specific Membrane Molecules)」(2011年11月、『ネイチャー・メディシン』)が発表された。後に「光免疫療法(PIT:Photoimmuno-therapy)」、あるいは「近赤外線光免疫療法(NIR-PIT:Near Infrared Photoimmunotherapy)」とも呼ばれることになる治療法の最初の論文だ。
当時のバラク・オバマ大統領が年頭の一般教書演説でこの治療法を「米国の研究成果」として取り上げたのは、論文発表からたった2ヶ月後のことだ。

〈近赤外線でがん細胞を選択的に破壊する〉という前代未聞の治療法が、いかに医学界を超えたインパクトを与えたかがよくわかる。
オバマは「技術革新(イノベーション)を起こすには基礎研究が必要だ」と述べた後、こう言った。
「今日、連邦政府が支援する研究所や大学において、数々の発見がなされている。健康な細胞を傷つけることなく、がん細胞だけを殺す治療法が開発されつつあるのだ」
おそらくは「注目すべき研究がないか」と大統領府からNIHに問い合わせがあるなり、「注目すべき研究があります」とNIHから報告がなされるなりしたのだろう。
演説内で取り上げられることを事前に知らされていなかった小林は、その翌日、隣の研究室の同僚から知らされ、ホワイトハウスの公式サイトに行ってみると動画があった。
「ほんの一瞬だったので〝あ、言ったな〟という感想以上のものは抱きませんでしたが、あの演説がひとつの契機になったのは事実ですね」
「がん細胞だけを狙い、物理的に殺す」シンプルなメカニズム
実際、小林の研究生活はここから大きな変化を遂げていくことになる。光免疫療法は「第五のがん治療法」として注目を浴びる中、2020年9月に承認、12月に保険適用を果たすわけだが、まずは光免疫療法のざっくりとした仕組みはこうだ。
小川が出会った「奇妙な現象」のメカニズムは実にシンプルである。光免疫療法はがん細胞だけを狙い、物理的に、「壊す」のだ。がん細胞と特異的に結合したIR700が、近赤外線を当てられると化学反応を起こし、がん細胞を破壊する。これだけだ。
後の研究で詳しくわかったことでは、IR700は近赤外線を照射されると化学変化を起こして結合している抗体の形状を物理的に変化させる。その際、がん細胞に無数の穴を空け、穴から侵入した水ががん細胞を内部から破裂させるのだ。

この「がん細胞だけを狙い、物理的に殺す」という点が光免疫療法の重要な特徴だ。この仕組みはのちに詳しく見ていくことにする。
原理はシンプルだが、もちろんここには最先端の科学技術が詰まっている。
どうやってがん細胞にだけIR700をくっつけるのか?
なぜ近赤外線を使うのか?
特定のがんにしか効かないのではないのか?
そもそも、画像診断の研究をしていたはずの小林が、なぜ治療へと研究の舵を切ったのか?
その根底には、小林のサイエンティストとしての、そして医師としての、深い知見と哲学が宿っているのだが、詳細を見る前に、なぜこのシンプルな光免疫療法が「ノーベル賞級」と言われ、がん治療の「第五の治療法」と呼ばれるほどに注目されたのかを見ておこう。
「第五の」と言うくらいであるから、これまでに「第四」までが治療法として認められてきた。長らく「三大療法」とされてきたのが「外科療法(外科手術)」「放射線療法(放射線治療)」「化学療法(抗がん剤治療)」である。
「第四の治療法」と呼ばれるのが本庶佑京都大学特別教授が開発に携わり、2018年にノーベル医学・生理学賞を受賞したことで知られる「がん免疫療法」だ。
文/芹澤健介 写真/shutterstock
『がんの消滅:天才医師が挑む光免疫療法』 (新潮新書)
芹澤 健介 (著)、小林 久隆 (監修)

2023/8/18
¥924
256ページ
978-4106110061
なぜ「天才」なのか
どこが「ノーベル賞級」なのか
原理はシンプル――だがその画期的機構から「第5のがん治療法」と言われ、世界に先駆け日本で初承認された「光免疫療法」。がん細胞だけを狙い撃ちし、理論上、「9割のがんに効く」とされる。数々の研究者たちが「エレガント」と賞賛し、楽天創業者・三木谷浩史を「おもしろくねえほど簡単だな」と唸らせた「ノーベル賞級」発見はなぜ、どのように生まれたのか。「情熱大陸」も「ガイアの夜明け」も取り上げた天才医師に5年間密着、数十時間のインタビューから浮かび上がる挫折と苦闘、医学と人間のドラマ。
「はじめに」より
がんをもはや「怖くない」と言う人もいる。国立がん研究センターによれば、日本人の2人に1人ががんになる。東京都をはじめ、各自治体は「早期発見すれば、90%以上が治ります」とがん検診を勧める。「全身にがんが広がっていなければ、約50%の人が治りますと言う医師もいる。(中略)だがそれでも、日本人の死因1位は1981年から変わらずがん(悪性新生物)だ。2021年の厚生労働省の統計によると、がんの26・5%は2位の「高血圧性を除く心疾患」の14・9%を大きく引き離す。年間170万人ががんになり、そのうち70万人が治療法がないなどの理由で「がん難民」になると言われる。結局のところ、日本人は2人に1人ががんになり、4人に1人はがんで死ぬ。この数字が示すのはむしろ、身内や親しい友人をがんで失ったことがない人など、どのくらいいるのだろうということだ。「9割のがんに効く」治療法があれば、どのくらいの人たちと私たちはまだ一緒に過ごせていただろうかということだ。光免疫療法はまだ途上である。現状は、限られた病院で、限られた患者の、限られたがんに施されるに過ぎない。「夢の治療法」が現実化するためには、越えなければならない壁がいくつもある。本書では足かけ6年にわたる小林久隆医師への直接取材を基に、光免疫療法のメカニズムとその現在、過去、未来を描くとともに、私たちが直面する「壁」とは何なのか、この治療法が生まれた背景に何があったのかを報告したい。
「目次」より
はじめに
第一章 光免疫療法の誕生
実験現場の奇妙な現象/光免疫療法の「発見」/光免疫療法の原理/標準治療/三大療法/「がんの消滅」/NIH──米国国立衛生研究所/39歳でのリスタート/〈ナノ・ダイナマイト〉/爆薬IR700/起爆スイッチ/スイッチのオン・オフ/〈魔法の弾丸〉/分子標的薬/ミサイル療法/9割のがんをカバーする/光免疫療法の真価/免疫はがんを殺せるか/制御性T細胞/〈免疫システムの守護者〉/「全身のがんが消えた」/偶然か戦略か/イメージングがもたらしたもの/“見る”ことと“治す”こと/光免疫療法への道/完璧な理論武装
第二章 開発の壁
資金の壁/誰と組むか/西へ東へ/三木谷浩史と父のがん/「おもしろくねえほど簡単だな」/1週間で3度の会合/RM -1929/治験の壁/施術条件の壁/ある同僚の死/効きすぎてしまった?/奏効率の壁/政治の壁/「ひとりの天才がいるだけではダメ」/辿り着いた国内承認/現場の医師より/光免疫療法ではない治療/「人生最後の山」
第三章 小林久隆という人
ノーベル賞はありうるか/「同世代のヒーロー」/医師で化学者で免疫学者/「まっすぐではなかった」道/謳歌した大学院時代/渡米ショック/学位論文/苦い教訓/どん底の研究生活/“医者”か研究者か/まともなことをしてるんやろか/年1500件の内視鏡検査/「がんこ」で「しつこい」/少年時代/灘の“化学の鬼”/京都大学へ/何かを見つけるための6年間/震災の記憶/日本のキャパシティ/骨ぐらいは拾ってやる/「無駄な実験なんてひとつもない」
終章 がんとはなにか
がんは難しい/セントラル・ドグマ/自己の分身/光免疫療法の未来
おわりに
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
国内承認から10年、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)を用いたがん免疫療法の現状
PR TIMES / 2024年7月24日 17時45分
-
アッヴィ、ベネトクラクスについて、再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫(MCL)に対する適応追加承認申請
共同通信PRワイヤー / 2024年7月12日 14時0分
-
CUBICStars「オルガノイド・スフェロイドに特化した研究用試薬を発売」
PR TIMES / 2024年7月7日 23時40分
-
CD4-CD8-ダブルネガティブT細胞が大腸がんを攻撃する免疫を抑えている?
PR TIMES / 2024年7月5日 11時45分
-
【日本BD】イメージング機能を搭載した次世代フローサイトメーターに新たな選択肢、「BD FACSDiscover(TM) S8セルソーター」 3および4レーザータイプを発売
PR TIMES / 2024年7月1日 18時45分
ランキング
-
1「コロナと夏かぜ流行中」何が起きているのか ワクチンを打っている人、打ってない人の違い
東洋経済オンライン / 2024年7月26日 8時10分
-
2イトーヨーカドー春日部店が閉店へ 「クレヨンしんちゃん」に登場するスーパーのモデル 「残念」「寂しい」惜しむ声
ねとらぼ / 2024年7月26日 16時5分
-
3テレビ離れの小中高生にバカ受け…「27時間テレビ」で視聴率急伸した"5つの時間帯"の芸人とタレントの名前
プレジデントオンライン / 2024年7月26日 10時15分
-
4日本人に多い「近視」 子どもは特に要注意、放置すると及ぶ“危険性” 眼科医が解説
オトナンサー / 2024年7月26日 7時10分
-
5マヨネーズにつけて食べると消化酵素が3倍増…キャベツの栄養を爆上げするのは「千切りorかじる」どちらか
プレジデントオンライン / 2024年7月26日 9時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください