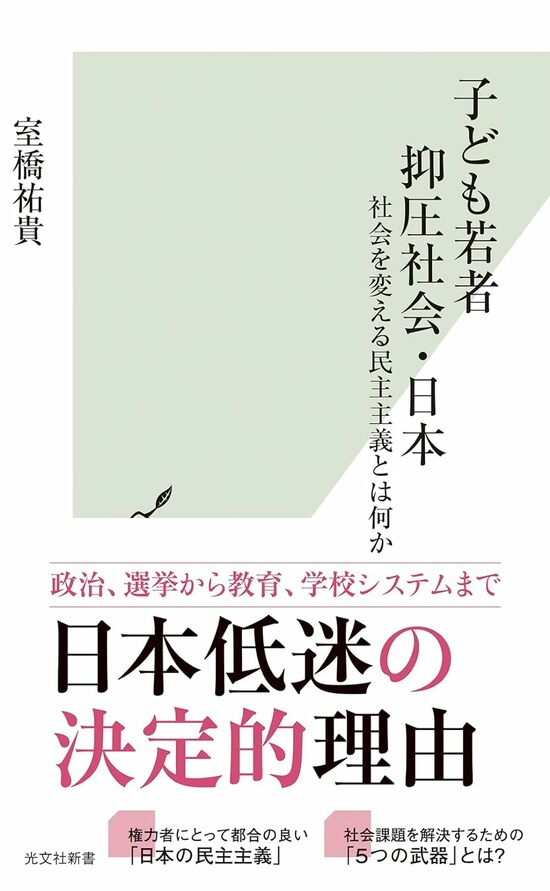なぜ日本からブラック校則はなくならないのか…校則は憲法より上位の存在、その校則の権限は校長に絶対的に委ねられている現状
集英社オンライン / 2024年5月26日 19時0分
なぜ日本でブラック校則がなくならないのか? 若者の声を政治に反映させる「日本若者協議会」代表理事・室橋祐貴氏によると、戦後70年間を経て、むしろ学校側が生徒を管理しようとする風潮は強まっているという。
【写真】なぜか校則違反に設定されている髪型といえば…
著書である『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』より一部を抜粋・再構成し、日本の教育の変遷について解説する。
ブラック校則がなくならない理由
2017年の大阪黒染め強要裁判を大きなきっかけに、「ブラック校則」と呼ばれる理不尽な校則が注目されるようになった。民間団体や弁護士などによる実態調査が進められ、2019年、2020年頃から徐々に先進的な学校や教育委員会で具体的な見直し方法の検討や実施が行われてきた。
2021年には、筆者が代表理事を務める日本若者協議会が校則見直しを進める際には、生徒も議論に参加するよう求める提言を文部科学省に提出し、生徒を交えた校則見直しの議論が加速するようになった。
そして2021年6月に、文部科学省が「校則の見直し」に関する通知を各教育委員会などに発出し、東京都教育委員会では下着の色の指定やツーブロックの禁止などのブラック校則が全廃された。このように着実に改善は進んでいる一方、現場ではまだまだ多くの細かい校則が存在し、明確にルールとして書かれていなくても、指導上、厳しい校則が強いられているケースも多く存在する。
また、2022年12月には、教師用の生徒指導に関するガイドブックである「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂され、子どもの権利を尊重すること、校則見直しを進める際には生徒の意見を尊重することなどが記載された。こちらも改善が見られる学校もあれば、私立学校を中心に、生徒が声を上げても、ほとんど聞き入れてもらえないケースもいまだ多く存在する。
このように行ったり来たりをしている校則問題だが、生徒を交えた校則議論が広がるのも今回が初めてではない。過去を振り返ってみると、戦後3回、校則見直しの議論は盛り上がっている。
1回目が、戦後すぐから1950年代。戦後、GHQが日本を民主国家にするため、生徒会(生徒自治会)やPTAを導入し、その時、文部省が作成した「新しい中学校の手引」においても、学校を民主化することが記載された。
生徒会の目的は「生徒をして、民主社会における生活様式に習熟せしめることである」とし、学校の活動は「民主的でなくてはならない。そのためには、学校は、生徒の活動に関する生徒との協議会をいろいろ持つことが必要である。
……いろいろな協議会の中には、校則や、学級のきまりや、学級文庫・学校図書館の規則を推薦するための協議会」と記述している。
これを受けて、各学校で民主的な取り組みが広がった。例えば、都立第一高校(現在の日比谷高校)の生徒会は1949年に「星陵生徒会自治憲章」を制定し、第4条では「(生徒会)会員代表、PTA代表、校長で三者協議会をおき、相互の意思疎通をはかる」とされた。
子どもの権利条約を世界で158番目に批准
しかし、1950年には憲章を改正して校長の保留権が入り、生徒自治から「特別教育活動としての生徒会活動」に転換した。
それでも、千葉県立東葛飾高校では、1969年に生徒会と職員会の二者で「教育制度検討委員会」を設置して話し合い、選択授業・自由研究導入、服装条項以外の生徒心得全廃(1972年に制服廃止)、職員生徒連絡協議会の制度化などの改革を実現し、二者協議会は他の学校にも広がっていった。
だが、進学校で受験シフトが強化されたのに加え、1970年代以降、学生運動に対する反発として、抑圧的、管理教育的なアプローチが取られ、民主的な取り組みは萎んでいった。後述する部活動の強制加入も含め、戦後目指してきた日本の民主化教育から、今へと続く管理教育への転換を考えるにあたって「1969年」は非常に重要な年になる。
戦後2回目に学校の民主化が盛り上がったのは、1990年代。1989年に、国連で子どもの権利条約が採択され、日本は1994年に批准した。これを受けて、子どもの権利条約の意見表明権に基づいた生徒参加論が研究者や日本弁護士連合会(日弁連)などから提起された。
その代表例である、長野県辰野高校では、1997年に学校に関する事柄を、生徒・教職員・保護者の代表者らが話す「三者協議会」を設置。アルバイトや服装の校則、授業が改善されるなど、生徒、教職員、保護者が、学校運営の主体として意思決定に関わっている。しかし、政府の対応が消極的で、自主的な取り組みだったため広がりには欠けた。
日本は1994年に子どもの権利条約を世界で158番目と遅く批准したが、批准した直後の1994年5月20日、文部省は「児童の権利に関する条約」について通知を発出した。
その中で、「本条約第12条1の意見を表明する権利については、表明された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理念を一般的に定めたものであり、必ず反映されるということまでをも求めているものではないこと」と記載し、暗に子どもの権利条約を批准しても、大きな変化がないことを示した。
これにより、先生が決めて児童生徒は従う、というパターナリズムの構造が変わらないままとなった。前述の通り、パターナリズムとは、強い立場にある人が、弱い立場にある人のためを思って、代わりに意思決定することである。しかし、本人の意思は確認しないため、本当に本人のためになっているかはわからない。さらに、数ある選択肢から自分で意思決定(自己決定)する力も育たないなど弊害は多い。
こうした政府の消極的な態度もあり、積極的に子どもの権利条約の中身について周知はされず、子ども本人も、教員も子どもの権利の内容について十分に知らない状態となっている。
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2019年に全国の15歳から80歳代までの3万人を対象に実施した子どもの権利に関するアンケート調査結果(「子どもの権利条約採択30年日本批准25年3万人アンケートから見る子どもの権利に関する意識」)によると、子どもの権利条約に関して、子ども8.9%、大人2.2%だけが「内容までよく知っている」と回答し、子ども31.5%、大人42.9%が「聞いたことがない」と回答した。
「ゼロ・トレランス」と「スタンダード」
さらに、同団体が2022年3月に実施したインターネット調査「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査」によると、子どもの権利について「内容までよく知っている」教員は、約5人に1人(21.6%)のみ。「全く知らない」「名前だけ知っている」教員は、合わせて3割にのぼる(30.0%)ことが明らかになった。
ちなみに、若者の政治参加が世界で最も進んでいるスウェーデンでは、12歳(小学校6年生)時点で、88%の子どもが「子どもの権利条約」について知っているという。
この1994年の文部省の通知は、今も有効なため、改めて見直し、積極的に子どもの意見表明権を認め、学校や教職員に子どもの意見を尊重するよう求める必要がある。
こうして自主的な取り組みが広がった1990年代だが、2000年代に入ると、トップダウンで物事を決め、生徒の行動も縛る管理教育が強化され、子どもの意見尊重だけではなく、教員同士の話し合いも弱まった。
2000年、学校教育法が改正され、それまで実質的に意思決定機関となっていた職員会議の位置付けを見直し、職員会議は「校長の補助機関」となり、校長の権限が強化された。
さらにあたかも職員会議で議論するなと言うように、2006年には東京都教育委員会が職員会議で、「挙手」「採決」などの方法で教職員の意思を確認する運営を行ってはならないとする通知を都立学校長に出した。
2014年には文科省が東京都教育委員会と同様の内容の通知を出し、翌年にはそれが守られているかどうかの全国調査を実施して、守っていない学校には是正させた。こうして教員同士の合議制が失われ、生徒に対しても、言われたことを守る態度が求められるようになっていく。
2006年、教育基本法が改正され、そこでは、「国を愛する態度を養う」とともに「規律を重んずる」教育(第六条)が定められ、自分の頭で考えて、批判的に物事を見る子どもより、規律を重んじ遵守する子どもが「良い子」とされた。そして、翌年には文科省が「問題行動を起こす児童生徒」には毅然とした指導を行うよう通知し、「ゼロ・トレランス」と「スタンダード」が広がることとなった。
「ゼロ・トレランス」とは、1990年代にアメリカで広がった生徒指導で、学校側があらかじめ規律と懲戒規定を明示して、それに違反した生徒を例外なく処分するという方法である。トレランスとは、寛容さという意味で、無寛容に対応していくということである。
「スタンダード」は、「授業中は姿勢よく座る」「掃除は黙って行う」「廊下は静かに右側を歩く」といった、持ち物の規定や授業を受ける時の望ましい姿勢などを示したルールである。これが小学校から始まっており、細かく〝正しい〟行動が求められている。こうして、「期待通り」、「上」が決めたルールに自分を合わせる子どもが増えている。
写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
公立高校の校長「現場と自治体の間」で揺れる苦悩 人手不足の中、問題行為起こした先生の対応も
東洋経済オンライン / 2024年7月11日 8時30分
-
コエルワがNPOカタリバ主催「みんなのルールメイキング」の令和6年度 北海道・東北エリア地域パートナーに就任
PR TIMES / 2024年7月9日 10時45分
-
【アーカイブ動画公開】学校改革に必要な管理職の人財育成力
PR TIMES / 2024年7月8日 10時45分
-
今なら言える「挑戦を」投稿で応援も アイドル歴5年、大阪の予備校講師
共同通信 / 2024年6月30日 18時2分
-
「子どもの権利」、児童・生徒と教員の意識に差-小中学校81校、13,573人のアンケート結果【プレスリリース】
PR TIMES / 2024年6月30日 10時15分
ランキング
-
1日本のにんにくは中国産が9割。「国産にんにく」と「中国産にんにく」の違いとは? 3つの産地で比較
オールアバウト / 2024年7月26日 21時5分
-
2マヨネーズにつけて食べると消化酵素が3倍増…キャベツの栄養を爆上げするのは「千切りorかじる」どちらか
プレジデントオンライン / 2024年7月26日 9時15分
-
3イトーヨーカドー春日部店が閉店へ 「クレヨンしんちゃん」に登場するスーパーのモデル 「残念」「寂しい」惜しむ声
ねとらぼ / 2024年7月26日 16時5分
-
4日本人に多い「近視」 子どもは特に要注意、放置すると及ぶ“危険性” 眼科医が解説
オトナンサー / 2024年7月26日 7時10分
-
5「コロナと夏かぜ流行中」何が起きているのか ワクチンを打っている人、打ってない人の違い
東洋経済オンライン / 2024年7月26日 8時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください