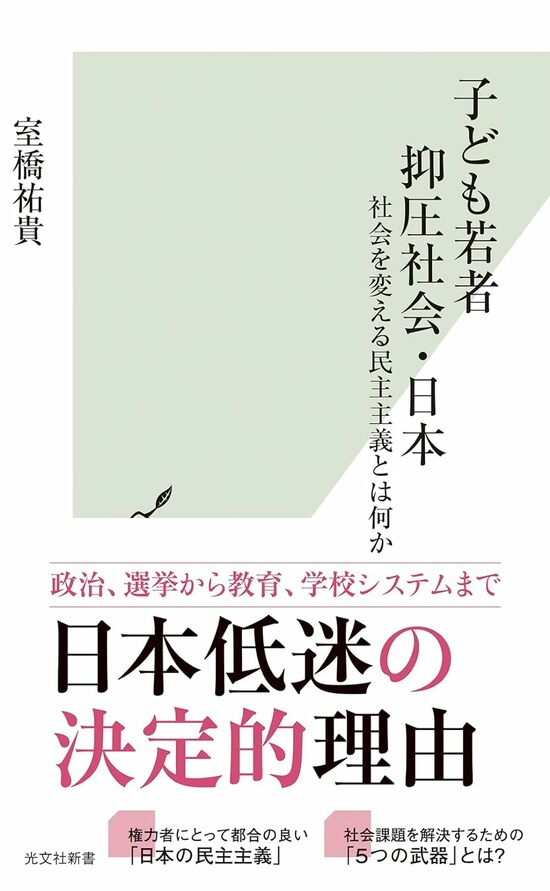部活動の強制加入、高校野球の強制応援が続く日本の教育現場…岩手県の中学校は、2020年度で6割の学校が「強制加入」
集英社オンライン / 2024年5月28日 8時0分
〈子どもの自殺が2022、2023年ともに500人を超えるも学校は硬直的。生徒の自己肯定感は低く、学力、運動能力、年齢でラベリングされ、序列化される現実〉から続く
世界的にも異質とされている日本の学校の部活動。もちろん自ら進んで取り組んでいるなら問題はないだろう。だが入りたくないのに入らされているとしたら…?
書籍『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』より一部を抜粋・再構成し、日本の部活動の問題を教師と生徒、ふたつの両方の視点から考察する。
部活動の強制加入
ルールで児童生徒の行動をがんじがらめにしているのは、校則だけではない。その一つが、部活動である。2017年度にスポーツ庁が実施した運動部活動等に関する実態調査によると、公立中学校の30.4%、公立高校の15%が部活動は「全員が所属し、活動も原則参加する」、実質的に強制加入の状態となっている。
しかし本来、学習指導要領によれば、部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」とされており、制度上は「参加は任意」となっている。また2018年3月にスポーツ庁、12月に文化庁がそれぞれ運動部・文化部の「活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し、部活動への参加を強制しないよう留意しなければならないことを、本文、Q&Aで明記している。
にもかかわらず、いまだに部活動強制加入が続いている。岩手県内の中学校では、2020年度、任意加入は150校中60校で、6割の学校が「強制加入」となっている。
では政府がガイドラインを作っているにもかかわらず、なぜ部活動の強制加入は続いているのか。その理由としては、大きく7つ挙げられる。教員へのアンケートサイトである「フキダシ」で、部活動の必須加入に関するアンケートも実施したため、その回答結果も参考にしながら、背景を整理していきたい。
① 歴史的背景
今では、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」とされる部活動だが、20年ほど前まではクラブ活動が全員必修であった。
平成元年(1989年)の学習指導要領改訂までは、特別活動として週1回行う「クラブ活動」が必修で位置付けられており、同年の改訂で、中学・高校ともに、教育課程外活動の部活動をもって代替できることになった(「部活動代替措置」)。結果的に、全員が部活動に参加する流れになっていったが、その後、中学校では平成10年(1998年)、高校では平成11年(1999年)改訂の学習指導要領で必修のクラブ活動は廃止され、部活動は任意参加の、課外活動の一環として行われるようになった。
しかし、これまで全員参加になっていたため、そのまま依然として残っている。また、1980年代頃までは、今より学校が荒れていたため、放課後自由にさせない、部活を通して指導する、という成功体験を、まさに今の校長世代が経験していることも大きい。
さらに、名古屋大学・内田良教授らの調査によると、部活動が教育課程外であると正しく認識できている現役教員は56%程度しかいないという結果になっており、そもそもあくまで「任意参加」のものであると認識されていない。
② 教育的意義があると思われているから
前述の生徒の「荒れ」への対応策としての側面もあるが、部活動によって規律や自己肯定感を高めるなどの教育的意義が挙げられる。筆者も学生時代はずっと(好きで)サッカー部に所属しており、その意義は否定しない。ただ、部活動を通してしかそういった規律や努力の方法などを学べないかというと、全くそんなことはない。
全然やる気もない部活動を強制的にやらされても、むしろ嫌いになる可能性の方が高いのではないだろうか。また同じ学校内だけの部活だと、非常に狭い、閉じた関係性になるが、学校外のコミュニティに参加することができれば、その分様々な人と知り合うこともでき、種類が限られた部活動よりも、趣味の範囲が広がる可能性も高い。
よく「生徒数の減少で部活動の数を維持できなくなっているから」という声も聞くが、そもそも同じ学校内で様々な部活動をやってきたこと自体、異常だったのではないだろうか。実際、他の国々では部活動はあまりなく、地域コミュニティの一環でクラブが存在する。
生徒の部活動強制加入や、教師の全員顧問就任、無報酬によるタダ働き、そうした「犠牲」の上に成り立っていただけである。
そして子どもの減少や、教員の多忙化によってこれまで以上に無理が生じており、見直すべき時期に差し掛かってきている。
「部活動をやっていないことで、関わる先生が減るため、色々な見方からの指導ができなくなる。地域によっては、部活動をやって子どもを疲れさせてから帰らせたり、休日も学校に行く必要を作り出すことによって、地域の治安を維持していたりすることもあるから。また、受験時に部活動で頑張ったことを聞かれたり、資格や成績によっては推薦の条件にあてはまることがあるから」(学校現場の声を見える化するWEBアンケートサイト「フキダシ」)
「部活動は教育課程外の活動なので、それを必須にして生徒の意思を無視した状態で行うのはおかしいと思います。放課後の時間は個人のものであり、自由選択で自分らしく生きられる時間として位置づけてあげたいです。
また生徒を必須加入させることは、教師も必須担当(指導)せねばならぬ状況につながります。勤務時間内ももちろんですが、勤務終了後や土日のボランティア参加等、こちらも本人の意思に反して半強制的に行われます。必須加入かそうでないかに関わらず、この法外な働き方は大きな問題をはらんでいます。
世界各国を見渡しても、かなり異質な教育活動。同質性を押し付け、それぞれが個性豊かに生きることへの不安を植え付けます。多様な生き方を尊重する意味でも、部活動は自由選択であるべきだと思います」(同アンケート結果)
③ 部費を生徒会費として全員分徴収しているから
意外と知られていないのが、部活動に関するお金のやり取りだ。部活動をやる場合には、もちろんその部活に関連した費用はかかるが、「学校諸費」として、生徒全員から徴収されている。その名目は必ずしも「部活動後援会費」のような「部活動」に限定されず、生徒会費として徴収されたお金が部活動に回っている場合もある。
学校側からすれば、全員からお金を徴収しているため、全員に部活動に入ってもらわないと困る、という理屈である。
④ 中体連等への加盟費を全校生徒の人数分、支払っているから
こちらも費用に関係しているが、中体連等、大会を運営している組織にお金を払っているために、全員部活動に参加すべきであるとなりやすい。
逆に言うと、中体連としては、大会等の維持運営のために全員からお金を徴収しなければ成り立たない、という論理もある。
⑤ 内申&入試に影響するから
部活に入るべきという圧力は、必ずしも学校(教員)からだけではない。高校入試に影響するため、保護者が入るのを勧めるというのもある。実際、地域によっては、部活動の成績が内申点に加点されており、部長をやっていれば、入試に有利に働きやすいというのもある(噂も含め)。
⑥ 同調圧力
学校入学の最初の1学期だけ加入という学校も珍しくない。その後は、任意で辞めて良いというものである。しかし実際は、中学生が学校の先生に「辞めたい」というのはハードルが高く、学校によっては、顧問だけでなく、3人の教員のサインが必要としているケースもある。これでは暗に「辞めるな」と言っているようなものである。
ある国立の中学校では、こうした事態を防ぐために、毎年入部届を出す仕組みにしており、辞めるハードルを下げる工夫を行っている。
⑦ 生徒を学校に囲う論理
これまで述べてきた内容と大きく関連するが、放課後まで生徒を管理したい、管理してもらいたい、という双方のニーズが、学校、保護者、地域住民に根強く残っている。
その根底にあるのは、放課後自由にしたら、何をするかわからない、という生徒への信頼のなさ(過度な子ども扱い)や、生徒が放課後に何か問題を起こしたら学校の責任にする保護者や地域住民の意識、社会全体の問題である。
「私の学校は全員加入である。外部のスポーツクラブに通っている生徒も、何かしらの部活動に所属しなければならない。なぜ、全員加入なのかと職員会議で質問したところ、『放課後の活動を把握できない』『放課後に問題が起こる可能性がある』『家にいる時間が増えれば、ゲーム・スマホ依存につながる』などと管理職から言われた。
『放課後の活動を把握できない』『放課後に問題が起こる可能性がある』……
この2つについては、生徒を管理するという学校の、教師の姿勢が丸出しだと感じた。なぜ、把握しなければいけないのか。放課後は、家庭に子どもをかえすべきである。自由な時間がなさすぎる。今の子どもたちは、窮屈な生活だと感じる。
『家にいる時間が増えれば、ゲーム・スマホ依存につながる』……
家庭の指導力の問題だ。家で1人になると、好き勝手やらないか心配だから学校で面倒みなければというボランティア精神なのだろうが、学校は託児所ではない。我々教員にも、家族がいるはずだ。他人の子どもの面倒を見て、どうして自分の子どもを、家族を犠牲にしなければならないのだろうか」(学校現場の声を見える化するWEBアンケートサイト「フキダシ」)
このように、管理教育の象徴となっている部活動の強制加入だが、学生はどう思っているのだろうか。
日本若者協議会が2022年3月に、学生(中学生・高校生、近年卒業の大学生)向けにアンケートを実施したところ、「どちらかと言えば賛成」も含め、96%が部活動の強制加入の撤廃に賛成と回答し、その理由としては、「他にやりたいことがあるから」「学業への支障」「教員の労働環境が過酷だから」「ストレス、休日まで拘束してほしくない」「子どもの自由を尊重すべき」といった点が挙げられた。いくつか回答内容を抜粋しよう。
「やりたい生徒とやりたくない生徒が同じ熱量で部活に打ち込めるとは思わないし、生徒間のトラブルの原因になるから。また、部活の時間が先生の勤務時間を圧迫するのはおかしいと思うため」
部活を真剣にやりたい生徒にとっても、本当は他のことをやりたい生徒にとっても、デメリットの大きい部活動の強制加入。制度上、任意加入となっているからという理由だけでなく、生徒の自主性、主体性を尊重するのであれば、当然任意加入であるべきだ。
そのためには、生徒会活動と同様に、部活動も、教育活動の一環ではなく、健康や生涯スポーツ、趣味を見つけるといった、人生を豊かにするための学校外活動へと見直していく必要があるのだろう。
これに対し、日本若者協議会では、部活動の任意加入の徹底や、入試における部活動欄の廃止などを求めて、スポーツ庁に要望書を提出。
その後、2022年6月、スポーツ庁の「運動部活動の地域移行に関する検討会議」の提言において、「部活動強制加入は不適当」であること、「退部が高校入試で不利にならないように」といった内容が記載された。
また部活動の強制参加は、自分の部活だけにとどまらない。中には、野球部の応援に強制参加させる学校も存在する。実際そうした声が日本若者協議会のもとに届いており、過去には、吹奏楽部がコンテストの大会出場を諦め、甲子園の応援を優先した事例もある。
ただでさえ、炎天下で熱中症のリスクの高い、野球の試合観戦。こちらも同様に見直していく必要がある。
写真/shutterstock
外部リンク
- 人口のおよそ14%「境界知能」は知的障害と何が違うのか…複雑な内容の文書を扱う活動などでは強いストレスを感じることも
- 〈「ギフテッド」と呼ばれる人たち〉3歳で機械式時計の仕組みを熟読、小4で英検準1級…IQ154の少年が学校に行けなくなった理由とは
- 30年後、野球部員は1校3.5人に…部活動を維持できないケース多発! それでも改革を拒む教育ムラの人々は「部活は大事な学校教育」と言う
- 下着は白かベージュ…外国出身児童が不登校になるほど強要した「ブラック校則」の実態と教員の言い分「地域からクレームが毎週くる」
- 「私たちはすごく非現実的な、夢の中にいるような時代を生きている」…見なかったW杯、安倍氏の国葬、岸田政権の今後、小室圭さん…芥川賞候補作家・鈴木涼美が噛み砕く2022-2023年の世相
この記事に関連するニュース
-
公立名将の決断「教員辞めました」 嫌だった土日練習も…放課後“閑散”「ちょっと寂しい」
Full-Count / 2024年7月5日 7時50分
-
報酬5万円、ビール販売…手本となる“地域文化” 部活動改革の悩み解く「発想転換」
Full-Count / 2024年6月14日 7時5分
-
社説:全中大会の縮小 少子化踏まえた改革を
京都新聞 / 2024年6月13日 16時0分
-
中学軟式の消滅は「最大の懸念」 “成長途中”の受け皿へ…教員一体で示す模範例
Full-Count / 2024年6月11日 7時5分
-
中体連 全国大会から水泳・体操などを除外へ ウインタースポーツは全て取り止め 道産子への影響は?
HTB北海道ニュース / 2024年6月10日 19時41分
ランキング
-
1「ぐっすり眠れない人」今すぐ摂るべき5つの食材 「眠りを誘うホルモン」が睡眠の質を高める
東洋経済オンライン / 2024年7月6日 21時0分
-
2日産新型「セレナ“ミニ”」登場は? シエンタ&フリード対抗の「小型ミニバン」は? 実はあった「小さな3列車」 ユーザーの声いかに
くるまのニュース / 2024年7月6日 7時40分
-
3「二重あご」になっちゃう理由 実は肥満だけじゃない 原因&改善法を美容外科医が解説
オトナンサー / 2024年7月7日 7時10分
-
4浴室リフォームを決意、どんな補助金が使える? 「省エネリフォーム」に関する補助金は多い
東洋経済オンライン / 2024年7月7日 8時50分
-
5何もしてないのに「バッテリー上がり」した! 真夏の「突然のトラブル」どう防ぐ? いつか起こり得る「エンジンかからない」どう対処するのがOKか
くるまのニュース / 2024年7月6日 18時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください