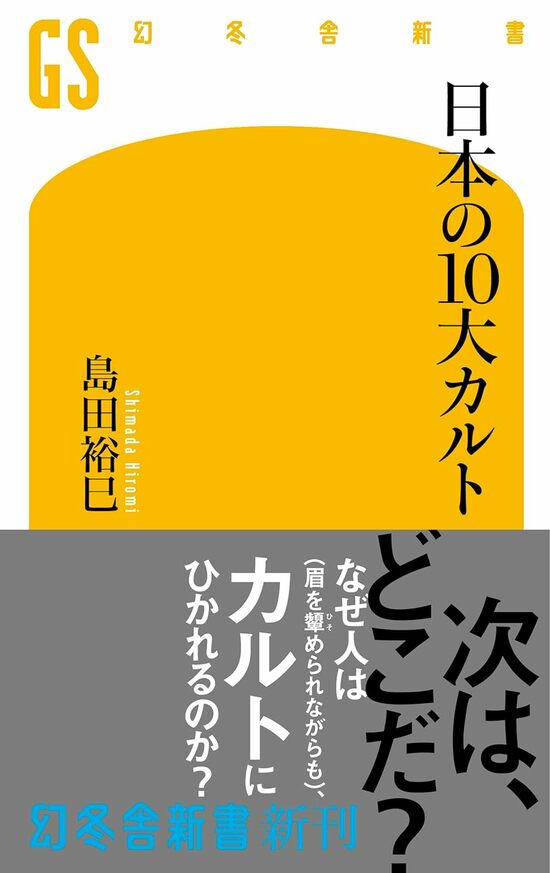旧統一教会、エホバ…なぜ世間にこれだけ叩かれてもなお、惹かれる信者がいるのか……そのヒントは“カレーライス”にあった
集英社オンライン / 2024年6月6日 19時0分
〈なぜフランスでは「創価、幸福の科学、統一教会」がカルト扱いされているのか…フランスがカルトを規制する上で注視する「10の基準」とは〉から続く
人は誰しも孤独な存在で、ときにはメンタルが弱ってしまうことがあるだろう。カルトは弱った心の隙間につけ込むことで、信者を増やしてきたのだ。
【写真】旧統一教会が信者を増やすためにふるまっていた定番料理
戦後日本で拡大していたった宗教の布教戦略を、書籍『日本の10大カルト』より抜粋・再構成し解説する。
世間はカルトに厳しいが、それでも人はカルトにひかれる
旧統一教会は、ソ連の崩壊によって共産主義の勢力が力を失ったこともあり、反共(勝共)を以前ほど強く打ち出さなくなっている。そこには、メンバーの世代交代もかかわっている。旧統一教会に1960年代から1970年代にかけて入信した信者は、反共ということに関心を持っていたわけだが、二世信者にはそうした意識は乏しい。
顕正会でも、最近では強引な折伏で逮捕者を出すということがなくなってきている。おそらくそこには、会員の世代交代が関係しているであろう。街頭で『顕正新聞』を配っているのは年配者がほとんどで、若者たちの姿を見かけることはない。顕正会も二世会員になると、組織の拡大にはさほど熱心ではなくなっている。
しかも、カルトに注がれる社会の目は相当に厳しいものになってきている。
そこにはオウム真理教の事件の影響が大きい。宗教団体は権力が介入できない聖域ではなくなり、問題となる行動を起こせば、社会から強い批判を浴びるだけではなく、警察による厳しい取り締まりも受けるようになってきた。ライフスペースの教祖に殺人罪が適用されたり、法の華三法行の教祖に詐欺罪が適用されたのも、それが関係する。
エホバの証人については、社会が親による虐待を問題視し、それを犯罪行為として扱うようになったことで、子どもの輸血拒否や鞭打ちによるしつけが難しくなった。教団もそうしたことを奨励しているわけではないと、弁明せざるを得なくなってきた。
社会がいかに圧力をかけていくか、いわゆる「カルト問題」解決の鍵はそこにある。
ではなぜ、人はカルトと指摘されるような集団にひかれるのだろうか。
その理由について、騙されて入信していくのだと説明されることがある。実際、教団のなかには、正体を隠して勧誘するところがある。
なぜ、なおひかれる人々がいるのか
だが、騙されたとしても、どこかでそれに気づくわけで、それでも入信していくにあたっては、入信する側に何らかの理由があるはずである。
その理由を考えるには、二つの事柄に着目する必要がある。
一つは、その人間のおかれた状況である。
もう一つは、出会いである。
この二つの事柄が重なることで、人は、その集団にはまっていく。
まずは状況である。
人はいつも幸福な状態にあるとは限らない。不運に見舞われることもあり、不幸のどん底に突き落とされることだってある。
しかし、それほどの不幸ではなくても、孤独に襲われることがある。この孤独が、人を宗教へと導く決定的な要素になりやすい。
戦後に拡大した新宗教の場合、創価学会や立正佼成会ということになるが、まさに孤独が入会のきっかけになった。こうした教団が伸びたのは1950年代半ばからの高度経済成長の時代で、地方から都市に労働力として出てきた人間たちが、そのターゲットになった。
彼らは小卒や中卒で、大企業に勤められないのはもちろん、中小企業でさえ就職できず、零細企業や町工場あるいは商店に勤めるしかなかった。そうした職場には労働組合もなかった。
仕事は厳しいわりに賃金は安く、倒産や解雇も珍しくなかった。彼らは、地方にいたときには、地域共同体のなかにしっかりと組み込まれていたが、都市に出てきたばかりの段階では、そこからは切り離されてしまい、孤独な状況にあった。新宗教は、そうした境遇にある人々に手を差し伸べることで信者を増やしたのである。
私が旧統一教会のホームを訪れたその日、帰りがけに、ホームのメンバーからカレーライスをご馳走になった。カレーライスというのは、旧統一教会において新しい仲間を増やすための手段の定番らしいのだが、日頃、一人暮らしで仲間もいない人間であれば、それだけで旧統一教会にひかれていく。後日また訪れたりするのだ。
カルトと言うと、恐ろしい集団のイメージが強い。けれども、現実に存在する集団は、新しく入ってくる人間に対してはとくに優しく接してくる。それで孤独を癒される人間はいくらでもいる。孤独に子育てをしている女性も、そうなりやすい。
カルトの恐ろしさばかりが強調されると、言われていたのとは違う集団の姿に接して、世間の見方は間違っているとさえ思うようになる。強調がかえって逆効果にもなってしまう。
カルトの側も、それを想定し、積極的に出会いの機会を用意する。それが勧誘であり、布教である。いくら孤独を感じていても、そうした人間は積極的に出会いの場を求めたりはしない。けれども、誘われると、優しくしてくれる分、それに乗ってしまうのだ。
出会った当初は、その集団の教えや活動の方法など知らない。説明を受けても違和感しか持たない場合もある。だが、誘う側は熱心で、集団に入ったことのメリットを熱を込めて語る。そうなると、それにほだされ、集団から離れられなくなる。
信者になっても、誰もが全面的に信仰を受け入れているとは限らない。さまざまな疑問を感じているだけではなく、集団の嫌な面を見せつけられることだってある。それでも、どこか一点でも魅力を感じていると、集団との関係をなかなか切ることができないのだ。
いったん集団のメンバーになってしまえば、そこでさまざまな人間と出会い、人間関係が結ばれる。集団をやめてしまえば、そうした人間関係をすべて失うことになる。
その人間がまだ若ければ、別の所で新しい人間関係を結ぶこともできるが、年齢を重ねていれば、それは難しくなる。そうなると、たとえ教えや組織のあり方に疑問を感じるようになっていたとしても、容易には離れられなくなるのである。
カルトがまったく存在しない社会はない
そもそも、カルトとされるような集団に加わった人間を幸福とするのか、それとも不幸とするのかは、かなり難しい問題である。
本人がそれをどうとらえるかということもあるし、周囲の、とくにその人間と密接な関係にある人間のとらえ方もそれぞれだからである。同じ人間でも、あるとき重大な疑問を抱き、脱会して集団にいた過去を不幸だと考えるようになることもある。一方で、最後まで幸福を感じ続けるような人間もいる。
困難を感じる人間がいるとすれば、それは、いったん集団のメンバーになりながら、途中でそこを抜けた人間だろう。
集団にいたあいだは、その活動にすべてを捧げていた。ところが、信仰の内容に不信感を抱いたり、組織の方針に疑問を感じたりして葛藤し、そこを抜けたとき、過去の自分の人生が無駄だったのではないかという思いに駆られる。自分が間違ったことをしていたのではないかと感じるかもしれない。
そうした人間はどうなるのか。
当初の段階では、自分が所属していた集団の悪をあばき、それを徹底して批判する行動に出やすい。周囲に同じ体験をした元信者がいれば、思いを共有することもできる。そうなれば批判にも勢いがつく。
だが、それが本人にとっての幸福に結びつくわけではない。元いた集団から逆に批判されたり、誹謗、中傷されることもある。それで傷つくことも多い。それにいくら自分が厳しい批判を展開しても、集団が簡単に崩壊するわけではない。やり場のない怒りにどう折り合いをつけてよいのか、かえって問題が難しくなっていく。
過去はなかったことにはできないという根本的な事柄がある。
だったら、そうした過去にも何らかの意味を持たせなければならない。どういう意味を持たせるのか。脱会した人間のその後の人生は、そこにかかっているとも言える。
カルトなど存在して欲しくない。そう考える人は少なくないだろう。だからこそ、旧統一教会に対する解散命令請求に多くの支持が集まった。
しかし、人間はどこかに精神のよりどころを求めようとする。その重要な対象が宗教である。しかも宗教はおしなべてカルトとしてはじまるのだ。
カルトとしてはじまった宗教は、次第にカルト性を薄めていき、社会に定着していくわけだが、そうなると、当初その集団が持っていた魅力も失われていく可能性がある。そうなれば、新しいカルト=宗教が誕生し、同じような歴史がくり返されていく。
カルトがまったく存在しない社会はない。私たちは、それを踏まえた上で、そうした集団がどういうものかについて知識を増やし、それが存在する意味について考察を深めていく必要がある。対処の仕方はそれしかないとも言えるのである。
写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
旧統一教会の敗訴が確定 TBS番組で名誉毀損主張
共同通信 / 2024年11月29日 17時48分
-
旧統一教会が北九州市に名誉毀損と宗教ヘイトなどで損害賠償求めた裁判 請求棄却
RKB毎日放送 / 2024年11月21日 0時2分
-
断絶決議、旧統一教会が敗訴 福岡地裁「信教の自由制限せず」
共同通信 / 2024年11月20日 18時42分
-
候補者の取材拒否、識者は警鐘「民主主義が崩壊する」 旧統一教会問題で異例の選挙戦を振り返る
カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年11月10日 15時0分
-
トランプ氏の支援に邦人信者 旧統一教会の分派、信頼を演出
共同通信 / 2024年11月1日 15時28分
ランキング
-
1AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?
オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分
-
2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分
-
3Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人
まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分
-
4ついに日本政府からゴーサイン出た! 豪州の将来軍艦プロジェクト、日本から輸出「問題ありません!」 気になる提案内容も明らかに
乗りものニュース / 2024年11月29日 6時12分
-
5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた
Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください