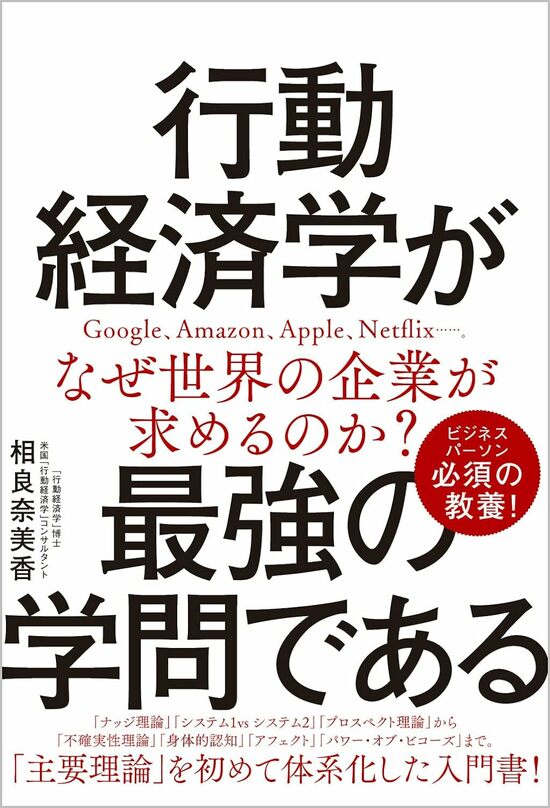「人は落ち込んだとき散財してしまう?」「なぜ〝$20.00〞より〝20.00〞のほうが売れる?」日常に潜む行動経済学
集英社オンライン / 2024年6月20日 11時0分
特に理由もないのに「なんとなく高いほうを買ってしまった」という経験はないだろうか? 感情によって不合理な行動をとってしまう人間と経済との関係を研究した学問が、行動経済学だ。
世界中でニーズが高まっている行動経済学をわかりやすく解説した書籍『行動経済学が最強の学問である』より一部を抜粋・再構成し、日常に潜む散財のリスクを明らかにする。
感情が「お金の使い方」にも影響を与える
人間の非合理な意思決定に大きく影響を与えるアフェクトは、人のさまざまな「非合理な行動」を作り出しますが、その中でも「お金の使い方」について特徴的な行動を引き起こすことがあります。
あなたも経験があるでしょう。例えば、「気分が落ち込んだときに、ついお金を使いすぎてしまった」。もし人間が合理的な存在であれば、感情に任せてこのような散財をするようなことはしません。しかし、私たちはそのときの感情によって、「非合理なお金の使い方」をします。
そして、そんな「非合理なお金の使い方」をする人間の集まりが経済(ビジネス)ですから、当然、経済も感情によって動かされる非合理な存在なのです。
ここでは、感情がどのように人の「お金の使い方」に影響を与えるか、見ていきましょう。
アマゾンは「キャッシュレス効果」であなたを麻痺させる
先ほど、ネットショッピングではタッチパネルで買うほうがより商品を魅力的に思ってしまう「保有効果」を紹介しました。感情が「お金の使い方」に与える影響の例でもあります。
つまり、買う前の商品に対しては、「自分のもの」というアフェクトを持たないほうがいいわけですが、「お金そのもの」に対しては、「自分のもの」というアフェクトを持ったほうが無駄遣いはなくなります。また関連して、現金で決算するかキャッシュレスかという違いもお金の使い方に影響を与えます。
日本でも急激にキャッシュレス化が進み、消費者庁の発表によれば、普及率は2019年12月の54.2%から2022年2月には64.0%に増加しています。日本でもこれほど進んでいますが、アメリカはもはやほとんどの人が現金を使わない社会で、カードかスマホアプリで支払う習慣がすっかり定着しています。
しかし、行動経済学では、キャッシュレスの人のほうがお金を使いすぎてしまうことがわかっています。
「お金を使ってしまった」という心理的痛み
なぜなら、キャッシュレスだとお金の決済の際の「透明性が低い」ということで、「お金を使ってしまった」という心理的痛み(Pain of Paying)を感じにくいからです。また、いくら使ったという感覚も低く、「いっぱいお金を使ってしまった」ということに対するネガティブ・アフェクトも生まれにくくなってしまい、結果、簡単に使ってしまうのです。
逆に、現金の決済のほうが透明性が高い、つまり、リアルで目の前の商品に対する現金を手渡しすることにより、「どれだけどのように使ったか」という感覚が強くなるので、ネガティブ・アフェクトが生まれやすく、無駄遣いをしなくなります。
アマゾンなどのネットショッピングは、まさにカード決済で、しかも、ワンクリックで購入が完結する。買いたい商品に対するポジティブ・アフェクトに導かれるまま、麻痺したような経済感覚での買い物となりがちです。
またお金を使った感覚が薄いので、「無駄遣いしてしまった」というネガティブ・アフェクトも感じることが少なく、ついつい続けて無駄遣いしてしまいがちです。
もちろん、カードやアプリは安全性、利便性に優れていますから、使い分けるのも一案です。例えば健康や教育など、「自己投資として使ったほうがいいお金」はカードで支払う。
なぜなら手渡しする現金では、「払うことの痛み」をもっと身近に経験し、使うのを惜しんでしまうからです。あなたが「ここにはお金をかけるべき」と考えているものには、(もちろん予算内で)あえてカードを使うのも一つの選択です。
逆にスターバックスのラテのような「ちょっとした楽しみ・贅沢」は、現金で支払う。コーヒーの香りに対するポジティブ・アフェクトに釣られてついつい気がつかずに無駄遣いするのではなく、現金を数え、手渡しすることで、「お金を使った」という感覚を高められることになります。
また、より意識的に購入することによって、「それだけの大切なお金をはたいている」ということから、その楽しみや贅沢の幸せをより強く実感することができます。
なぜ〝$20.00〞より〝20.00〞のほうが売れるのか?
お金との心理的距離について、さらに面白い実験を紹介しましょう。レストランで2通りのメニューを用意しました。
・Aには「○○○ $20.00」と各料理に「$+金額」を表示
・Bには「○○○ 20.00」と各料理に「金額のみ」を表示
違うのは「$」の表示があるかないかだけ。メニューのデザインや、料理の種類など、その他の条件はすべて同じです。
結果、Bのメニューを受け取ったお客さんのほうが大幅に消費額が増大しました。
「$」という表示がないことで、頭では金額とわかっていますが、「お金を払う」という行動が心理的に響かず、簡単にお金を使ってしまったのです。
日本でも外資系ホテルや高級レストランでは、「2000円」とせず「2000」というように、算用数字のみのメニューを置いているところがあります。
自分が売り手側で売上を伸ばしたいなら「2000」と数字のみの表示にし、買い手側で節約をしたいとき、もし「2000」という表示になっているメニューを見たら、慎重になったほうがいいでしょう。
また、アプリ決済やeコマースではポイント制度も盛んですが、ここにも透明性を下げる「キャッシュレス・エフェクト」という企業側の戦略があります。
例えば「いつでも返品OK」というサイトは、お金ではなくポイントで返金され、「ポイント=お金」という感覚が薄らぐので、貯まったポイントを気軽に使いがちです。
カジノやゲームセンターでは現金をコインに替えて遊ぶのも同じ理由で、お金を溶かす仕組みがあちこちに潜んでいるのです。
写真/shutterstock
外部リンク
- 数万人登録のマッチングアプリにも「いい相手がいない」と嘆く未婚者たち…アプリが未婚率の改善になっていない3つの理由
- 「日本に国家破綻はない」は本当か? 「今回は違います」と言われながらも、国家破綻が繰り返しやってくる理由
- 未婚者が既婚者より幸福度が低いと感じる傾向はなぜおきるのか。「結婚したらしあわせになれる」と思っている人は結婚できない
- アムウェイ「取引停止令」が教えてくれる、なくならないマルチ商法の甘い罠と騙されないための3つのポイント
- 「面倒なお願いには付箋に手書きでひと言添える」「すぐに行動にしてほしいときは盛り上がったタイミングがチャンス」…世界中の大学の研究から明らかになった相手に届く伝え方とは
この記事に関連するニュース
-
【行動経済学】高級時計の見せ方は、垂直とナナメ、どちらが正解?人間の無意識に働きかける「概念メタファー」とは?
集英社オンライン / 2024年6月22日 11時0分
-
2012年オバマ大統領を再選に導いた「3つの質問」とは? ネットフリックスで2話目が自動再生されることで働くバイアス…最強で最恐の学問「行動経済学」
集英社オンライン / 2024年6月21日 11時0分
-
風水師が解決策をアドバイス!金欠を呼ぶ「悪い習慣」5つ
オールアバウト / 2024年6月17日 21時20分
-
結婚しないほうがいい男性の特徴5つ|見分け方とは?
KOIGAKU / 2024年6月7日 18時3分
-
相手はどう動く?経済学者・安田洋祐さん『安田洋祐の戦略思考入門|第5話. 非協力ゲーム:囚人のジレンマゲーム』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!
PR TIMES / 2024年6月3日 22時40分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
-
4運動習慣による“天然のコルセット”で施術後は順調に回復【ひどい腰痛も8割治る】
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月3日 9時26分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください