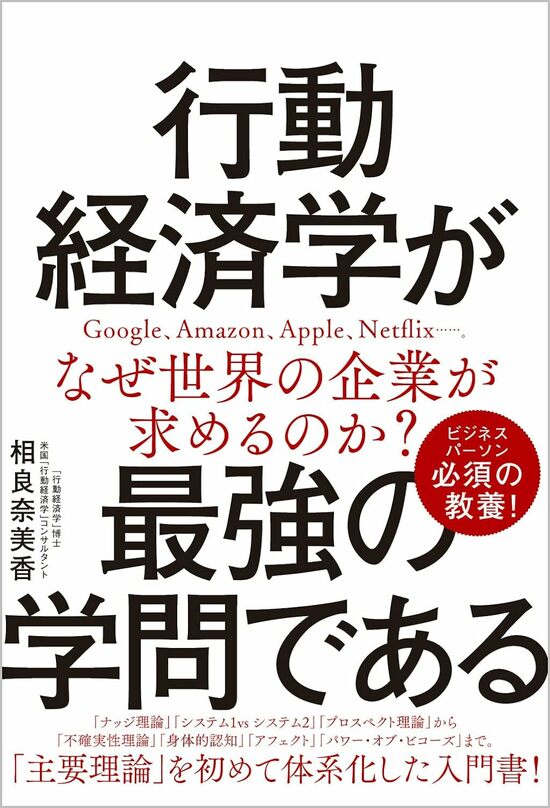【行動経済学】高級時計の見せ方は、垂直とナナメ、どちらが正解?人間の無意識に働きかける「概念メタファー」とは?
集英社オンライン / 2024年6月22日 11時0分
〈2012年オバマ大統領を再選に導いた「3つの質問」とは? ネットフリックスで2話目が自動再生されることで働くバイアス…最強で最恐の学問「行動経済学」〉から続く
まったく同じ時計の広告でも、垂直に写っているかナナメに写っているかで、まったく印象が異なるという。無意識の中で人が情報をどのように受け取っているかがわかれば、より効果的な広告を打つことができるだろう。
『行動経済学が最強の学問である』より一部抜粋・再構成し、そのロジックを解説する。
「概念メタファー」―高級時計の見せ方は、垂直かナナメか?
この2つの時計の広告は、とある論文で実験された広告の写真です。同論文では、この2つの広告のうち、どちらがより効果的かが実験されました。
ここで結論に入る前に、あなたも考えてみてください。どちらがより消費者に魅力的に映るでしょうか。もちろん同じ時計、同じモデル、ポーズもポケットに手を入れるという同じポーズで、唯一違うのは「時計の向き」だけです。
同論文によると、左の広告のほうが権威性を示す、つまりは高級時計には効果的な広告になると結論づけています。なぜでしょうか。
左右の広告を比べると、左の広告は時計の向きが「垂直」で、右の広告は「ナナメ」になっています。このとき、人は左の広告からは、「権威性」や「贅沢」な印象を感じます。
人は垂直のものを見ると、無意識のうちに「人の上に立つ」「出世する」「優位性」といった感覚を抱くのです。その感覚によって「この時計は高級品に違いない」と解釈します。
垂直性は「重力に逆らって上昇・忍耐力・強さ」を無意識に示唆するとの調査結果も出ており、左の写真を広告に使うことで、「高級で長く使える最高の時計」というイメージを喚起します。
このとき、「人の上に立つ」「出世する」「優位性」といった抽象的な概念を「垂直(な配置)」という「具体的なもの」に喩える(比喩)ということが起こっています。
このように、抽象的な概念を具体的なもので比喩することで、人が理解しやすくなる認知の枠組みを「概念メタファー(Conceptual Metaphor)」と言い、比喩が単に修辞技法や言葉の綾ではないことを証明しています。
あなたももし「高級な印象」を与えたいのなら、それを垂直に配置するといいでしょう。逆に、もっと躍動感を演出したいときには、あえて右の広告のようにナナメに配置するということも検討してもよいでしょう。
他にも概念メタファーによる認知のクセを利用すれば、より効果的なビジュアルを決定できます。
上の2つの水のボトルの写真を見てください。もしあなたが「高級感」を演出したい場合、どちらを選ぶべきでしょうか。
答えは、左です。
背が高く細長いほうが高級な印象になります。一方で、親しみやすい安心感を演出できるのは右です。
人は無意識のうちに「細長いもの=高級」「低くて幅があるもの=気楽」と感じるためです。人は直感的に、背の高いものを見ると「力・権威・高級感がある」と感じ、低いものを見ると「安心、親しみやすさ」を感じるのです。
これも「高級」という抽象的な概念を「背が高く細長い」という具体的なもので比喩して理解しやすくしている、「概念メタファー」です。
「認知の流暢さ」のためにアップルのロゴは上部に載せるべき
商品のパッケージのデザインの際には、ロゴの配置も重要な決定事項でしょう。そのときのロゴの配置についても、商品の知名度によって場所を変えたほうがよいでしょう。載せる位置によって印象が変わります。
アパルナ・サンダーらの実験によると、アップルのような訴求力の高いブランドの商品だと、ロゴが下部よりも上部にあったほうが好まれました。反対に、あまり人気のないマイナーなブランドだとロゴが下にあったほうが好まれ、購買意欲も高まったのです。
これはテクノロジーの商品だけではありません。アメリカでも大人気のスターバックスも、ロゴが下部よりも上部にあったほうが好まれした。
これも、「訴求力が高い」イコール「優れている」という抽象的な概念を「ロゴの位置」という具体的なもので比喩して理解しやすくしている、概念メタファー理論です。
このように、商品や広告のビジュアルを考える際には「認知の流暢さ(Cognitive Fluency)」を意識することも非常に重要です。先ほども「非流暢性」で説明しましたが、「流暢」とは「ひっかかりがない」、つまり「わかりやすい(瞬時に認知できる)」ということです。
その意味で概念メタファー理論は、認知の流暢さを作り出す手法の一つです。「高い=パワフル」「低い=気楽」という概念メタファー理論を利用し、「認知の流暢さ(わかりやすさ)」があるデザインを作り出せば、それぞれ消費者に受け入れられやすくなります。
「AのデザインとBのデザイン、どちらが好きですか?」
この質問はマーケティングリサーチの定番ですが、このときにただの好き嫌いではなく、身体的認知のクセを踏まえて検証することが大事です。
そうすれば、わかりやすく、自然に感じるデザインを選ぶことができます。またこうした行動経済学の知識を、プレゼンテーションの際に学術的なエビデンスとして示してもいいでしょう。
写真/shutterstoc
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
グローバル企業が「人材をかき集めている」...最強の学問「行動経済学」が、ここまで注目されているワケ
ニューズウィーク日本版 / 2024年11月15日 18時19分
-
借金が増えると「ブランドもの」が欲しくなる!? ラグジュアリーブランドと購入者の内なる〈ナルシシズム〉の意外な関係性【心理学者が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月15日 7時15分
-
最高哲学責任者(CPO)で会社はどう変わるか? エシックス(倫理)と資本主義を考える(4)
東洋経済オンライン / 2024年11月5日 13時0分
-
好感度ワースト1位なのに!? アンチが多いはずのタレントがテレビや広告から消えないワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月31日 8時15分
-
2024年度日本経済学会賞授与
PR TIMES / 2024年10月26日 14時40分
ランキング
-
1書店に行くとなぜか急にトイレに行きたくなる「青木まりこ現象」とは?
マイナビニュース / 2024年11月21日 16時2分
-
2【風呂キャンセル界隈】医師「心身が疲れた時こそ入浴を」 - 安全で健康的な方法とは
マイナビニュース / 2024年11月21日 11時0分
-
3【冬の乾燥対策に】ドラッグストアで手軽に買える! ハンドクリーム5選
マイナビニュース / 2024年11月21日 17時0分
-
4とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分
-
5生産性を上げ、まわりと差がつく5つの栄養素 ライバルを出し抜くために必要なのは「食事」
東洋経済オンライン / 2024年11月21日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください