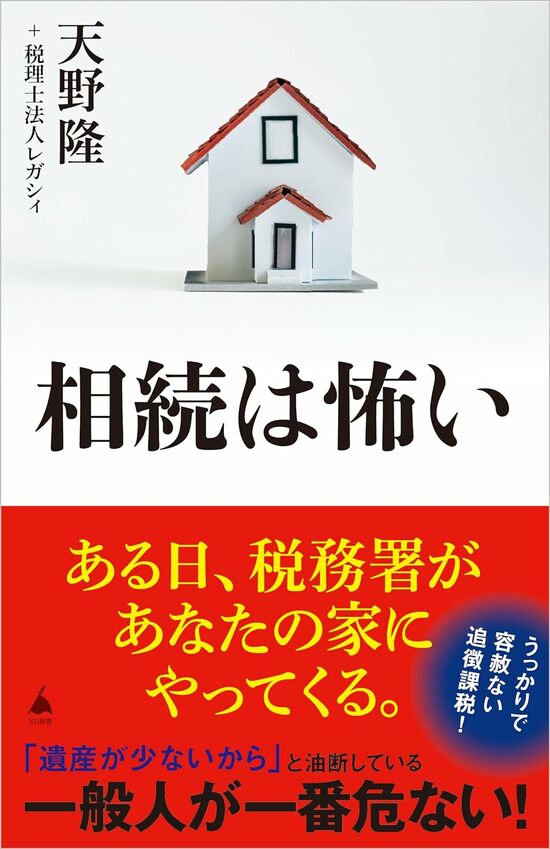相続税において税務署が一番見つけたいのは「名義預金」。「郵便貯金はスルーされる」はウソ…気をつけるべき税務調査のポイント
集英社オンライン / 2024年6月13日 11時0分
現在、日本の税制ではいわゆる「お金持ち」ではない人が亡くなった場合でも、相続税が課税されるようになっていることをご存知だろうか? 果たしてその条件とは? 自分には財産などないと油断していると急に税務調査が来るかもしれない…。
【画像】定年、ローンの払い終わった持ち家、貯蓄ありは相続税の課税対象に⁉︎
『相続は怖い』 (SB新書)から一部抜粋・再構成してお届けする。
富裕層でなくても税務署はしっかり見ている
2015年の相続税法改正前は今よりも基礎控除額が多かったことから、「相続税の課税対象=お金持ち」のイメージを持ち続けている人が少なくありません。
しかし改正後の基礎控除額は、従前の6割に縮小されています。たとえば、改正前であれば相続人が3人いる場合、基礎控除の額は8000万円でしたが、現行では4800万円となっているのです。
税制が変わって以来、相続税の課税対象者が拡大しました。
国税庁によると2021年(令和3年)中に亡くなった人143万9856人のうち、相続税の課税対象となった人の数は13万4275人で、課税割合は9.3%でした。
改正前の2014年(平成26年)に亡くなった人約127万人のうち相続税の課税対象となったのが約5万6000人、課税割合4.4%であったのと比べると、倍以上になっています。
もう相続税の課税対象となるのは「お金持ち」だけとは限りません。
関東地方でいえば、北は浦和、東は千葉、南は横須賀、西は高尾までの間でローンの払い終わった持ち家があり、定年まで勤め上げて退職金をもらい、2000万円くらいの貯蓄のある人であれば、課税対象になる可能性が高いです。
課税されるタイミングは「二次相続」のときです。
二次相続とは?
二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続したあと、その配偶者が亡くなったことで発生する二度目の相続のことです。
平均寿命からすると夫が先に死亡することから、残された妻が経済的に困窮することのないよう、相続税法では、配偶者の税額軽減の枠が多かったり、一定の大きさの土地を評価減する「小規模宅地等の特例」があったりと、さまざまな制度があります。
Aさんの家の例で説明すると、Aさん亡きあと、妻がこれらの制度を利用できるため、結果として相続税の課税対象となりません(ただし申告は必要です)。
しかし妻が亡くなったときには、これらの制度が利用できないため、相続税の課税対象となる確率が高いのです。
実際、父親がサラリーマンで母親は専業主婦、東京近郊に持ち家と2000万円以上の預貯金・有価証券があり、二次相続で課税対象となったという方は少なくありません。
納税額は40万円から200万円とさほど大きくはないのですが、課税されている以上、相続税の税務調査の対象にならないとも限りません。
申告はきちんとしておくようにしましょう。
税務署は名義預金を見つけたい
税務の世界では、申告書に書かれていない財産(故意であるか過失であるかを問わず申告書に「表現されていない」財産)を「不表現資産」という呼び方をします。
不表現資産のうち最も見つかりやすいのが名義預金です。
名義預金とは、口座名義人がお金を出していない預金のことをいいます。
相続が発生したとき、亡くなった人が配偶者や子供などの口座を作っていて、亡くなった人が管理していた場合に名義預金と見なされ、相続財産に戻すことになるので相続税の対象となります。
税務署は市町村役場から死亡の連絡が入ると、「相続税の対象となるくらいの財産がありそうだな」と思えば、まず亡くなった方の自宅数キロ四方にあるすべての銀行にその人自身やその人の家族の銀行預金について問い合わせをします。
税務署から「誰にいくらの預金がありますか?」と尋ねられると、銀行は誠実に答えます。ここで名義預金のあたりをつけるわけですね。
たとえば夫婦のうち夫が亡くなったとき、妻名義の預金が見つかったとしましょう。果たしてこれは本当に妻自身の財産なのか?と税務署は考えます。
妻自身に収入があったり、妻の親から引き継いだ財産があったりした場合は別として、専業主婦なのに何百万、千万単位の預貯金を持っていることがわかると、税務署としては「このお金の出どころはどこなんだ?」と考えます。
「これは妻の名義を借りてお金を移動させただけで、本来は亡き夫の財産なのではないか」との推測が成立します。
このように名義は他の人の名義であっても、お金の出どころが亡くなった人である預金を「名義預金」といいます。
相続税の税務調査でいちばん見つかりやすく、見つかったら納税者はほぼ言い逃れができないので、税務署としても見つけたいのが名義預金なのです。
無記名の割引債とは?
かつて、無記名の割引債という金融商品が存在しました。
無記名の割引債とは債券の一種で、額面から利子相当分を差し引いた金額で購入し、償還時に額面金額が払われる債券です。
たとえば、900万円で無記名の割引債を買っておくと、満期時には100万円がプラスされ1000万円になって償還されるというものです。つまり額面金額と発行価額の差が実質上の利子となります。
具体的にはかつての東京銀行から「ワリトー」、みずほ銀行から「ワリコー、リッキー」、商工中金から「ワリショー」などの名前で発行されていました。
現在はマネーロンダリング防止のため、無記名のものは新しくは発行されていませんが、かつては非常に人気の高い商品でした。
今から20年近く前になりますが、相続財産隠しに巨額の割引金融債が使われていたのが発覚したことがあります。財界の大物の財産約40億円のうち16億円あまりを隠し、相続税約10億円を脱税したとして相続人である長男が相続税法違反の罪で在宅起訴されたのです。
それに使われたのが割引債でした。
もう所持している人は少ないと思いますが、今でも税務調査で割引債が見つかることはあります。税務署は被相続人の死亡前の預金の動きをチェックします。預金が引き出されていて行き先が不明なものは割引債になっていると推定します。とはいえ、無記名なのでお金の出どころははっきりしません。
そこで税務署は銀行からお金が引き出された日と同じ日に割引債を購入した痕跡を発行元に求め、徹底的に調査します。
たとえばある日、銀行から2億円が引き出され、それと同じ日に無記名なので誰なのかわからないけれども、2億円の割引債が購入されていた、となると「これだ!」となるわけです。
このあたりの税務署の調査力にはいつも感服させられます。
ちなみに無記名とはいえ割引債の発行元には本人を特定するのに便利なヒントもあるようです。
また、被相続人が生前銀行から借金をしたときに、割引債を担保に入れていることもあります。担保は記録に残っているので、割引債を買ったことが判明するというわけです。
「郵便貯金はスルーされる」はウソ
「郵便貯金は申告しなくても大丈夫」と考えている人がいます。
郵便局には税務調査は入らないという噂がありますが、それはウソです。
今は昔の物語となってしまいますが、かつて郵政省対大蔵省の戦いの時代がありました。そのころは大蔵省が郵政省に配慮していたこともあります。縦割り行政の弊害ともいえますが、今はそんなことはありません。
そんな都市伝説にだまされないようにしてください。
名義預金発見のため、経歴を詳細に調べ上げる
手っ取り早く隠された預貯金を見つけるため、税務署は被相続人の経歴を徹底的に調べます。
どんな学歴でどんな仕事に就いていたか、会社の規模、出世コースに乗ったか乗れなかったか、どんなスピードで昇進したか、転勤があった人の場合、それぞれの場所に何年いたのか……それを知るだけで生涯所得がどれくらいだったのか推測でき、そこから割り出して「これくらいの預貯金があってもおかしくない」と考えます。
「それにしては申告書に上がってきた預貯金の額が少ない」という場合、もう一段ギアを上げてさらなる調査へと進んでいきます。
たいていの場合、人はお金を隠したいとき、自分が今いる場所から物理的に遠い場所に隠そうとします。私たちは「遠隔地預金」などと呼んでいるのですが、福岡に赴任した人が、そのあとも各地を転々としたけれども、福岡に残した銀行口座にボーナスの一部を入金していた、などということがあるのです。
だから税務署は赴任先のすべての銀行の調査をします。そのためにまず経歴を押さえることが最重要課題となるわけです。
文/天野隆、税理士法人レガシィ 写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
親の遺品から、私名義の「通帳」が見つかりました。毎年50万円で「500万円」貯めてくれていたようですが、受け取って大丈夫ですか? 初めて預金の存在を知ったのですが、贈与が完了しているなら“申告不要”でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月15日 2時30分
-
苦労をかけた母に“恩返し”のはずが…離れて暮らす母親に〈月5万円〉の仕送りを30年間続けた53歳女性にまさかの税務調査。「多額の追徴税」を課され、二度涙したワケ【税理士の助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月12日 11時15分
-
夫婦で貯めてきた「500万円貯まる貯金箱」をついに満杯にしました!このような場合でも「税務署」からの調査は入るでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月12日 3時40分
-
年金「夫婦で28万円」の70代夫婦、激愛する孫に「年100万円・20年分」の贈与も、税務署「これは贈与になりません」と撃沈するワケ「何かの間違いでは?」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月7日 9時15分
-
税務調査? 嘘だろ?…年収400万円の53歳“普通のサラリーマン”にまさかの税務調査。何事もなく終わったはずが…思わず二度見した「驚愕の追徴課税額」【税理士が助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月3日 11時0分
ランキング
-
1AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?
オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分
-
2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分
-
3“風呂キャンセル”は冬でもNG、界隈の人々に皮膚科医が忠告、「乾燥で体臭は拡がりやすくなる」
ORICON NEWS / 2024年11月29日 11時30分
-
4Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人
まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分
-
5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた
Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください