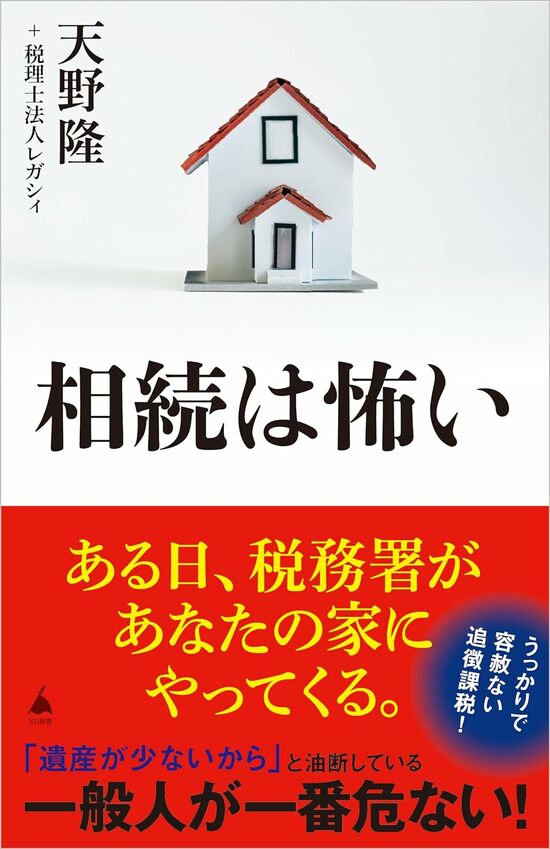現代の相続問題で一番気をつけるべきは「デジタル資産」。申告忘れには加算税や延滞税が上乗せされる…相続専門税理士が指摘する3つの問題点とは
集英社オンライン / 2024年6月15日 10時0分
〈土地の相続でモメてる家は詐欺にあう可能性あり…かつては55億円の被害も発生、地面師たちが狙う相続財産のスキ〉から続く
相続で「遺産」と聞くと、土地や家、預貯金などをイメージする人が多いはず。しかし、デジタル化が進む現代においては、故人がデジタル形式で保管していた財産も遺産に含まれる。そんなデジタル資産の注意点とは?
『相続は怖い』 (SB新書)から一部抜粋・再構成してお届けする。
デジタル資産が増えてくる
これまで資産といえば預貯金や有価証券、不動産など目に見えるものばかりでした(教育や親からの教えなどは除きます)。
ところがインターネットが普及してインターネットバンクやネット証券会社などが登場してからは、本人以外知り得ない資産が生まれるようになりました。
2023(令和5)年5月に総務省が発表した「令和4年通信利用動向調査の結果」によると、スマートフォンを保有している世帯の割合が90.1%と9割を超え、個人の保有割合でも77.3%と堅調に伸びています。
年齢階層別で見ると、インターネット利用状況は13~59歳の年齢階層が95%以上と多く、60~69歳は86.8%、70~79歳は65.5%、80歳以上は33.2%となっています。
インターネットの利用目的・用途の調査結果も発表されており、「金融取引」を選んだ人の割合は24.3%と、前年の21.6%に対して2.7ポイントアップしました。
現在、被相続人となっているのは80代、90代の高齢の方々です。この年代で、インターネットを利用している人はまだ3割。あくまで推測に過ぎませんが、この3割の人たちが利用するのはネットショッピングやSNSが目的で、ネットバンキングやネット証券での取引、さらにはサブスクの利用を目的としているケースはそう多くないと思われます。
問題はこれからです。
調査結果が示すように、70代になると、その上の世代の倍にあたる約66%の人がインターネットを利用しています。その中には金融取引をしている人たちが少なからずいることでしょう。
生前にそうしたデジタル資産について家族に「こういうことをやっているよ」と話しておいてくれればいいのですが、そうでないと誰も知らないデジタル資産がそのまま放置されるという事態になってしまいます。
デジタル資産の問題点
相続財産にデジタル資産が含まれている場合、次のような問題があります。
1 デジタル資産の存在自体を見つけることが困難
基本的にデジタル資産について、郵便物で知らせが届くことはありません。実はこれが存在を見えにくくしています。
亡くなった人が生前利用していたパソコンやスマホなどのアプリやメールの受信箱を見ない限り、探し出すことができません。
2 本人にしかわからないパスワード等で管理されている
デジタル資産を探すには、亡くなった人が使っていたデジタル端末をチェックしなければなりませんが、そもそも端末に入るのにパスワードが必要です。
生前に知らされていれば入ることができますが、相続人の誰もが知らなかった場合には、手がかりになりそうなメモを探したり、場合によっては業者に頼んだりしなければならないこともあり得ます。
また、インターネットバンクにしろネット証券にしろ、今はセキュリティチェックが厳しくなっていて、二段階認証が設定されていたり、顔認証が求められたりするケースが多いようです。
簡単に第三者がアクセスすることができない仕組みになっているため、その中身を知るのにも困難を極めることになります。
3 相続の手続きが煩雑になる
どうにかデジタル資産にたどり着き、その中身まで把握できたとしても、そこから先がまた大変です。
すべての情報を整理して、一つひとつ相続財産に該当するかどうかをチェックし、相続財産の評価額を再計算しなければなりません。
また相続人自身が日ごろからインターネットバンクやネット証券を使いなれているならいざ知らず、なじみのない人にとっては解約するのも容易でないことが予想されます。
というのも、デジタル資産の場合、手続きのほとんどがオンライン化されており、「電話連絡して書類を送ってもらって……」などといったアナログな手法が使えないからです。
もしも、すでに相続税の申告を行い納税も済ませたあとにデジタル資産が見つかった場合、期限後申告や修正申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10カ月です。その期間が過ぎてしまっていると、加算税や延滞税が加算されてしまいます。
マイナンバーカードの普及が「見えない資産」を可視化する
私が期待を寄せているのが、マイナンバーカードの普及です。
マイナンバーカードとオンライン上のすべての金融取引を紐づけすることで、相続人も知らなかった「見えない資産」の存在をあぶり出すというわけです。
具体的にいえば、将来、マイナンバーカードにはすべての金融機関が登録されており、ネット上の手続きで相続手続きが完了するようになるのです。
文/天野隆、税理士法人レガシィ 写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
調査対象の8割以上が追徴課税!実施時期や時効、よく聞かれる質問…「相続税の税務調査」を税理士が全解説
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 9時15分
-
相続税を払った5人に1人が税務調査を受けている…税理士に依頼しても追徴課税が発生してしまうワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分
-
土地の相続でモメてる家は詐欺にあう可能性あり…かつては55億円の被害も発生、地面師たちが狙う相続財産のスキ
集英社オンライン / 2024年6月14日 8時0分
-
相続税において税務署が一番見つけたいのは「名義預金」。「郵便貯金はスルーされる」はウソ…気をつけるべき税務調査のポイント
集英社オンライン / 2024年6月13日 11時0分
-
税務署はすべてお見通し!? 「8割が追徴税」となる税務調査、「狙われやすい人」の共通点【税理士監修】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時0分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください