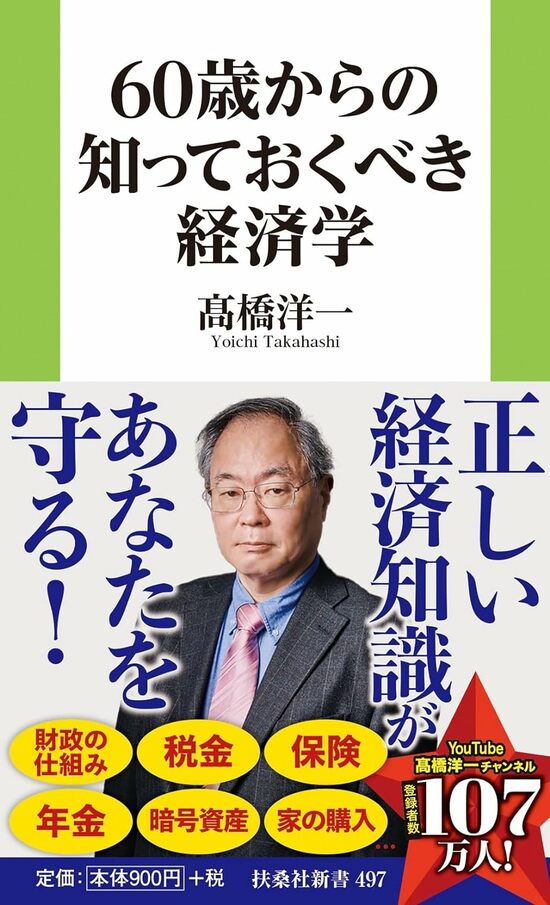〈国債は国の借金だからなくなればいいという間違い〉「無知からくる暴論」と髙橋洋一が徹底反論するワケ
集英社オンライン / 2024年6月11日 11時0分
〈円高より「円安」のほうがいいと髙橋洋一が断言する理由 「国内で円安を批判するのは国益に反する行為といえる」〉から続く
国債=国の借金のイメージが先立つが、実際には金融商品や災害時の資金集めとして機能する面もあるという。
【画像】災害時には、国債を発行して必要な資金を集めるという機能も果たす
高齢者にとって役立つ「経済学」について基礎から解説した『60歳からの知っておくべき経済学』より一部抜粋、再編集してお届けする。
この世から「国債がなくなる」と…
政府の借金が増えすぎているため、借金が増えれば国民負担も増え、将来世代にツケを回す。そういう論調は根強く残っているが、国債は決して悪ではない。実際に景気を底上げする効果があるのに、そのことを理解していない人が多い。
そもそも、国債がこの世から消えたらどうなるのだろうか。借金がゼロになっても、国民負担がゼロになるわけではない。むしろ大問題が生じる。
その意味を知るには、国債のもう一つの側面を理解することが重要だ。それは「金融市場における国債」という顔である。
国債は政府の「借金」であると同時に、金融市場において必要不可欠な「商品」でもある。金融市場では、株式や社債と同じように取引されている。
基本的なことを先に確認しておくと、金融市場では国債と株式、国債と社債を交換する取引が行われている。
例えば、A社の株式を持っている人が、その株式をB社の社債と交換したいと思っても、B社側に「A社の株式は受け取らない」と断られたら交換はできない。しかし、国債との交換なら簡単にできるため、まずA社の株式と国債を交換し、その後に国債をB社の社債と交換するという取引が行われる。
つまり、国債がなくなると、株式や社債の取引が減少してしまうのだ。
企業は銀行からの融資だけでなく、株式や社債でも資金調達をしている。そのため、国債がなくなれば資金繰りがたちまち悪化する。金融市場における国債は、他の商品と簡単に交換できる使い勝手のいい金融商品という役割を果たしているのだ。
なぜ企業が、株式や社債取引の中継としてわざわざ国債を保有するのか、疑問に思う人もいるだろう。その理由は、現金をそのまま保有しているだけでは、利益は生まれないからだ。一方、国債は政府の借金であるがゆえに利子がつくため、企業は国債を保有しているだけで利益が生まれる。金融市場では利払いのやり取りを通じて、経済が活性化する。
銀行がいい例だ。銀行は、国民の預金がいくらあっても利益は生まれず、融資をしたり、国債でわずかの利払いでも得たりしていかなければ、商売を続けられないだろう。国債がなくなると、金融関係者の仕事が失われる可能性もある。
ドイツで起きたハイパーインフレのトラウマ
国債の発行が必要な理由は、金融機関のビジネスを支え、ひいては資本主義社会の発展を促進するためだ。米国ニューヨーク市場や、英国ロンドン市場などでは、国債を介した取引が最も多い。
国により国債発行額は異なるものの、世界中の金融市場で国債の取引が行われており、金融の専門家も国債の必要性を認識している。
もっとも、ドイツは先進国で唯一、国債の発行額が少ない国だ。第1次世界大戦後、ドイツは生産力が大きく低下して物資が不足し、結果的にお金があり余るようになった。それで急速にお金の価値が下がり、物価が急上昇した。いわゆるハイパーインフレが起きてしまったのだ。
このトラウマから、ドイツはインフレを抑制する政策を採用している。国債を発行すると、市場に余分なお金が流入してインフレが引き起こされる可能性があるから、国債の発行を控えめにしている。
ドイツのような例外は除いても、国債は金融市場で重要な役割を担っている。国債が借金だからといって、全て消えてなくなればいいというのは、無知からくる暴論だ。
国債は未来への投資
2011年、東日本大震災が起きた。その後、復興には多額の費用が必要だということで、2012年に「復興特別税」なる新たな税が導入された。
この復興特別税は、「復興特別法人税」と「復興特別所得税」から成り、所得税、住民税、法人税に上乗せされた。法人税の復興特別税は2014年に終了したが、所得税の復興特別税は2037年まで続く予定だ。
実は、災害復興に必要な資金を調達するには、国債を発行するのが効果的だ。災害時に増税することは経済に悪影響を及ぼす愚策である。災害で大打撃を受けた地域は消費が低迷する。被災地の経済を支えるためには、幸いにも被害を受けなかった地域の経済力が必要だが、増税はその力を大きく削いでしまうのだ。
災害時における国債の役割
経済を活性化させるには、むしろ減税が適切だ。災害時に増税するという愚策を、筆者はかつてきいたことがない。
災害時には政府の税収が一時的に減少するかもしれないが、だからこそ財源確保のために国債を発行することが重要なのだ。それも100年債、500年債といった超長期国債が適している。
国を揺るがすような大災害は稀で、100年に一度、500年に一度というレベルだ。そのため、今から100年、500年をかけて大規模な災害に備えるため、世代間で復興財源を提供し合い、100年、500年をかけて返済していけばいい。
国債は国の借金だから悪である、将来世代に借金を押しつけることになる、というイメージで批判する人もいる。しかし、税収だけで国を運営するのは不可能であり、国債を発行して必要な資金を集めるべきだ。
税金は国民が支払う義務を負うが、国債は欲しい人だけが購入すればいい。税金を未納にすると脱税という違法行為になるが、国債を買わなくても誰からも文句を言われない。国にお金を貸したい人だけが貸し、その見返りに利息収入を得る。こうして国は運営されている。
それに、災害が起こった世代だけで復興財源を出すのは不公平だ。こうした考え方は、経済理論である「課税の平準化理論」に基づいたものであり、一般的な見解である。
本来、景気のいい時期は税率を上げて、景気の悪い時期には税率を下げることによって、経済の安定化を図るのだ。国債には災害復興だけでなく、未来への投資という目的もある。現在の国債発行額では投資額が不足しており、例えば「教育国債」といったかたちで投資すべきだ。
一般的に、教育水準の高い人ほど所得が多くなる。高所得者は納税額も増え、国への貢献度が高まる。いわば出世払いで、将来世代が成長し、投資効果が表れれば、その人たちに貢献してもらえる。そのほうが、よほど税収アップにつながるというものだ。
もっとも、市場では、赤字国債と建設国債が区別されていないように、教育国債として発行されるわけではない。単に国債の利率と償還期限で購入の判断はなされる。
あえて教育国債を設ける理由は、国債を売却したお金を、より多く教育に割くようにするためだ。教育の無償化も国債で賄えばいい。
国の投資対象には、公共投資としての図書館や体育館などの建物、いわゆるハコモノがある。それも多少の雇用創出にはなるが、教育への投資が有形資産への投資よりもはるかに大きな効果があることはすでにわかっている。
不動産という有形資産だけでなく、人材という無形資産にもっと投資をしてみてはどうだろうか。そのほうが、社会的により大きなリターンが期待できる。
文/髙橋洋一
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「日本国債大崩壊」の先にある、まさかの光景…<富の持ち主>が入れ替わる、戦後日本の“再来”時に、笑うのは誰か【経済のプロが予測】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 8時15分
-
少額でも始めることが可能!投資初心者にとって実は株式投資が最も向いている理由
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 11時0分
-
お金は知っている 日本再生を阻む「プライマリーバランス黒字化」 財務官僚は毎年異様に執着 現代の資本主義は政府が借金すればこそ成長できる
zakzak by夕刊フジ / 2024年6月21日 11時0分
-
「個人向け国債」と「地方債」は何が違うの?
オールアバウト / 2024年6月18日 12時20分
-
「円安も有利に働く」爆速で100万円貯めるプロの投資テクと、主婦におすすめの副業
週刊女性PRIME / 2024年6月16日 7時0分
ランキング
-
1小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
2ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分
-
3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた
東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分
-
420年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
5「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください