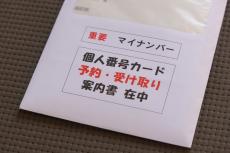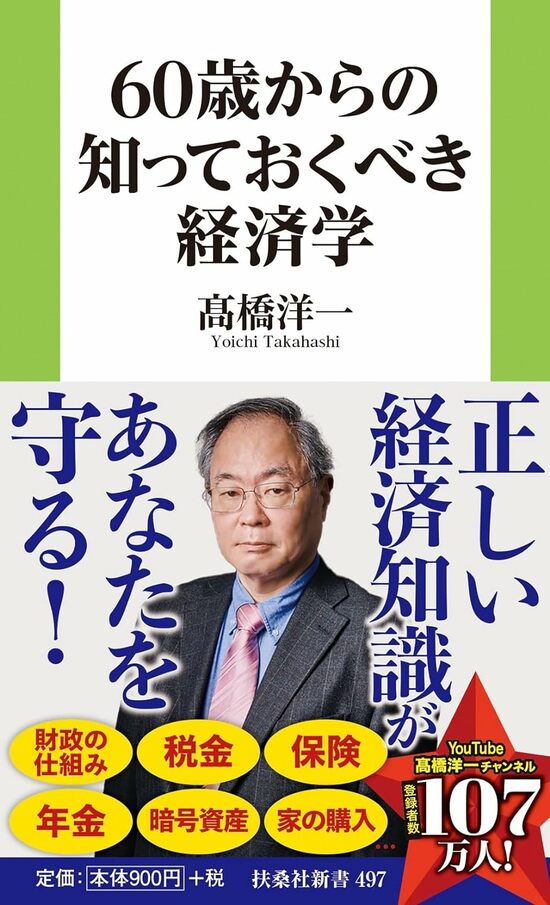半年後に迫ったマイナンバーカードと健康保険証の一本化が経済合理的に正しい背景とは「年間約1000億円のコストが解決する可能性も」
集英社オンライン / 2024年6月12日 11時0分
〈〈国債は国の借金だからなくなればいいという間違い〉「無知からくる暴論」と髙橋洋一が徹底反論するワケ〉から続く
セキュリティ面への不安から、苦戦を強いられている「マイナンバーカード一体型 保険証」。しかし、年金制度の問題点と解決策という視点でみると一本化されることが望ましいという。
なぜ経済合理的に正しいのか分析した『60歳からの知っておくべき経済学』より一部抜粋、再編集してお届けする。
年金制度の問題点と解決策
現在の年金制度には問題もある。ここでは二つの事例を紹介しよう。
一つめは、2016年に問題となった「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)だ。GPIFは、国民年金と厚生年金の年金積立金を運用する組織である。かつて問題とされた理由は、5兆円を超える運用損失を出したからだ。
もっとも、株式の運用には、上昇もあれば下落もある。民主党政権下では、経済不況により運用利回りが低くなったが、安倍政権が発足した後は回復した。2016年は、その利回りが一時的に下がっただけで、その後に株価は上昇して再び収支が好転した。
トータルでみれば、市場運用開始以降の2001年度から2023年度第2四半期までの収益率は年率プラス3.91%、累積収益額はプラス126兆6826億円(うち利子・配当収入は49兆2195億円)と着実に資産を積み上げており、運用資産額は219兆3177億円となっている。
とはいっても、GPIF自体は根本的な欠陥を抱えており、筆者としては不要な組織だと考えている。その欠陥とは、GPIFによって運用されている積立金の原資が、本来は存在しないはずの公的年金の積立金である点だ。公的年金は賦課方式なので、積立金があること自体がそもそもおかしい。
もし年金を積立方式にした場合、インフレによるお金の目減りに備えて、積立金を株式などで運用する必要がある。しかし、現在の公的年金は賦課方式で、物価スライドの仕組みを取り入れており、インフレヘッジをしているので問題はない。
百歩譲って、どうしても公的年金を市場で運用するのなら、株式ではなく、インフレ対策として「物価連動国債」での運用が適している。ただし、GPIFの運用が全体に占める割合は小さいため、問題が生じても年金制度が破綻する心配はほとんどない。
二つめの問題は「徴収漏れ」だが、これが最も厄介で、早い話が「脱税」だ。
そもそも、日本の年金は全国民が加入する「皆保険」制度であり、その意味では社会保険料は税金と同じ性格のものだ。
年金保険料は本来、全ての滞納者に対して強制徴収されるべきだが、これまでは年金保険料を納めていなくても、強制徴収されることはほとんどなかった。そのため、「年金保険料は払わなくていい」と思っている人も少なくないが、それは大きな間違いだ。
そもそも「未納」という表現が正しくない。「滞納」こそが正しい表現で、意図的に滞納しているのなら、それはもはや脱税だ。
保険原理からいえば、年金財政が厳しくなった際には、税の投入ではなく保険料の引き上げが適している。だから、まずは歳入庁を創設して、税と社会保険料を一体的に徴収し、社会保険料の取りっぱぐれを減らす必要がある。
運営が難しい「健康保険」はマイナ一体型が理想
「健康保険制度」は、年金制度以上に運営が難しいし、多くの課題がある。
年金は人口減少など予測可能な要因が多く、大きな戦争や巨大な自然災害でもない限り、年金数理をもとに将来の年金支給額を計算しやすい。
しかし、健康保険は10年後、20年後の医療費の総額がいくらになるか、という予測がしづらい。将来、また新型コロナウイルスのようなパンデミックがまん延するかもしれないため、先読みがしづらく、治療費の不透明さがあるからだ。
医療の進歩により、新しい治療法や薬が開発される一方で、治療費の高額化も懸念される。すでに数百万円かかる高度な治療も存在している。
こうしたことから、年金よりも医療費のほうが予測しづらいのだ。
医療費の一部は公的健康保険でカバーされ、それを超える高度な医療は民間医療保険でサポートされる仕組みが構築されつつある。今後は、公的健康保険と民間医療保険を使い分ける人が、目立ってくるだろう。
高齢化が進むなかで医療ニーズが増加する一方、国民が負担できる保険料には限界がある。そのため、いずれは保険対象となる医療費の総額が設定されていくだろう。医師が患者の症状を選別し、症状の重い人から優先的に、総額の範囲内で配分されるような方法が検討されていくと予想される。
健康保険制度の運営が難しいもう一つの要因は、本人確認が容易でなかったことだ。従来の保険証には顔写真がなく、他人のなりすましや不正利用、本人確認のミスがかなり発生していた。厚労省のデータによれば、年間約500万件もの再確認が必要とされ、そのコストは約1000億円に上っていたという。
健康保険証が本人確認の一環となっていた社会システムでは、人間の性善説を前提としていたため、マイナンバー保険証への移行が急がれていた。そこで、一体型の「マイナ保険証」になれば、他人によるなりすましや不正使用の問題は解決できる。
すでに紙の保険証は廃止して、マイナンバーカードに一本化する作業が進められている。岸田首相は最近、国民の不安解消を最優先に考え、現行の保険証は1年間の猶予期間を設けて引き続き利用可能とし、その間に不安を解消する方針を掲げた。
マイナカードが浸透しない背景
ここで読者の中には、2023年にマイナンバーカードに別人の情報が7000件以上登録されていた件を思い出す人がいるかもしれない。この問題があったせいで、世論調査でもマイナ保険証への移行の延期や、撤回を求める声も出ている。
だが、こうしたケースでは、事例数だけでなく、その比率を考慮することが重要だ。7000件という事例は、国民全体の0.0056%にすぎない。約1.8万人に一人という確率のため、年末ジャンボ宝くじ4等5万円の当選確率である1万人に一人よりも低く、その半分程度にすぎない。
このように確率の観点から考えると、筆者なら1.8万人から選ばれるとはあまり考えない。だが、世論調査の結果をみると、こういう場合は「自分が該当するかも」と不安を覚える人も多いようだ。
こうした心理的な反応は避けられないが、一方で報道ではあまり批判を煽らないほうがいい。新しい制度へ移行する際には、一時的なミスが発生する可能性はあるが、まったく移行しない場合、永続的なデメリットが生じるからだ。一時的なミスと永続的なデメリット、この双方をしっかり比較検討することが、国民の不安解消のためには必要だ。
筆者は20年ほど前の官僚時代、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の構築に携わった経験がある。これは、国民の確定申告など納税に関する作業を簡単にできるようにするシステムであり、一部を改良すれば国民にお金を配布することも可能だった。
それなのに、お金を徴収するシステムはいち早くつくり、配布する準備には20年もかかった。これが、新しいシステムに移行しないことで生じるデメリットの一例だ。
マイナンバーカードの健康保険証利用は2021年10月から始まり、2023年9月からは全ての医療機関・薬局で利用可能になった。現在も急ピッチで環境整備が進んでおり、いずれは本人の再確認がほとんど不要となり、医療機関・薬局でも事務コストの低減が実感されていくだろう。
文/髙橋洋一
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「マイナンバーカード保険証」を利用すると医療費が安くなるって本当? 利用するにはどうしたらよい?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 10時20分
-
携帯電話の契約時のマイナンバーカード読み取り義務化に専門家「いずれは国民全員に強制的に発行する仕組みを作らないと…」
北海道放送 / 2024年6月20日 19時56分
-
夫婦で年金「月20万円」で安心してたのに、まさかの「手取り額」に仰天!? 定年前に知っておくべき「年金から引かれる金額」とは?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 3時0分
-
悔やんでいます…最愛のパートナーを亡くした50歳女性が「月10万円の遺族年金」を受け取れない理由【FPの助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月14日 11時15分
-
結局「マイナンバーカード」ってなんだったんですか? 一度も使っていないのですが…。
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 11時10分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください