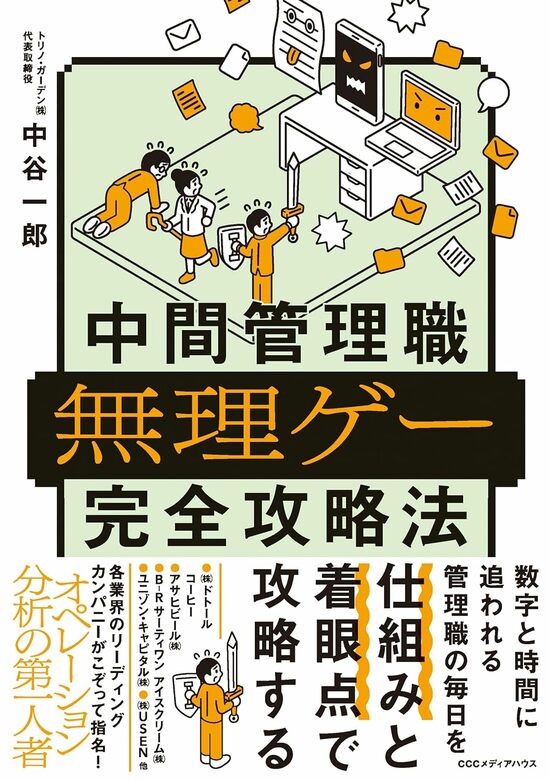「フリーアドレスだから会話が弾む」は間違い。上司と部下のコミュニケーションが活発化する最もシンプルな方法とは?
集英社オンライン / 2024年6月19日 8時0分
〈小さな成功体験、会社への信頼…新人が職場に定着するまでの5つの心理的ステップとは。すべての中間管理職が知っておくべき新人スタッフのメンタル段階〉から続く
「部下から話しかけられることがほとんどない」。“報連相”が大事な職場で部下が上司に話しかけにくいというのは問題だろう。だが、それはどこの職場でも起こりうる事案だ。
『中間管理職無理ゲー完全攻略法』より一部抜粋・再構成し、ほんの少しの工夫で部下の心理的なハードルを大きく下げる方法を解説する。
〈問題〉報連相を求めても、部下から積極的に話しかけてこない。結局毎回自分から尋ねる羽目に
もう少し積極的にコミュニケーションをとって、情報共有してほしいのに、部下から話しかけてくることがほとんどない。部下のステータスやプロジェクトの進捗情報が共有されず、自分から尋ねると危機的状況があらわになることも。
〈解決法〉目線の高さを物理的に変えることでコミュニケーションのしやすさをコントロール
自分の目線の高さによって、相手の、コミュニケーションに対する心理的ハードルの高低が変化します。それを逆手にとり、自分の座る場所や姿勢を変えることで、部下からのコミュニケーション頻度をコントロールしてみるのはいかがでしょうか。
〈解説〉
部下やチームメンバーから、あまりに頻繁に話しかけられると、自分の仕事に支障が出てしまう。かといって、まったくコミュニケーションがなければ、それはそれで困るものです。
部下からのコミュニケーションがなければ、仕事ぶりを評価することも、問題を把握することもできませんし、戦略を立てる上でも、業務の無駄やミスを防ぐ上でも、報連相は必要不可欠です。
進行上、ミスや誤解が生じていないか、適切な方法で業務を進められているのか、上司のほうから頻繁に尋ねてしまうと、まるで部下を信用していないように見えてしまうでしょう。
もちろん、尋ねれば話してくれるのでしょうが、いつでも部下自らコミュニケーションをとれる状況が、組織としては健全なはずです。
では、どのようにすれば、部下から自然と話しかけてくれるようになるのでしょうか。
実は、上司がどんな席で仕事をしているかによって、会話の発生頻度が変わる、ということが我々の実験から明らかになっています。
近年、フリーアドレス制を導入しているオフィスが増えました。フリーアドレスのオフィスでは、テーブル席、デスク席、ソファ席、ハイテーブル席など、さまざまな形の席が用意されていることが多々あります。
フリーアドレスを採用している企業の狙いの一つには、上司・部下間、あるいは部署を横断する形で、コミュニケーションをより円滑にとりやすくし、アイデアや情報の交換を活発化したい、というものがあるようです。
実際に我々も、固定席制からフリーアドレス制へオフィスレイアウトの変更をした際に、どのように社員同士のコミュニケーションが変化するかをある企業で調査したことがあります。
そして、この調査では意外なことが判明しました。
フリーアドレスにしてもコミュニケーション量は増えない
それは、フリーアドレスにしたからといって、一概にコミュニケーション量が増えるとは言い切れないということです。
対象となるオフィスにカメラを設置して、録画した映像から発話内容や回数、会話時の距離や人数、会話の発生した場所や状況といったデータを取得。このデータをフリーアドレスにする前後で比較するという方法で、分析を実施しました。
分析の結果、必ずしも、フリーアドレス制にしたことでコミュニケーション量が増えるとは言えない、ということが明らかになりました。
同時にわかったのが、「上司の目線の高さ」と「部下からのコミュニケーション発生数」に相関があること。
どういうことかと言うと、上司がローソファに座っている時には、部下から話しかけられる回数が減り、上司が立っていたり、ハイスツールに座ったりしている時には、部下からのコミュニケーションが増えたのです。
人には、それ以上他人に近づかれると不快に感じてしまう範囲、「パーソナルスペース」があります。計測実験により、このパーソナルスペースが、目線の高さによって変化することがわかりました。
通常、仕事や地域などの社会的な関係にある相手とのパーソナルスペースは、1.2~1.3mだと言われています。
しかし、上司がハイスツールに腰かけている状態だと、部下は90cmという距離まで近づいて、話しかけてきたのです。
さらに、上司がスタンディングデスクで仕事をしていた時には、部下はすぐ隣にやってきて、45cmという至近距離で上司に業務の相談を始めました。
この計測実験は、複数の企業で実施したのですが、どこも同じような結果となっています。また、飲食店やホテルのロビーなどで空いている席に腰かける際、隣席からどの程度距離を空けるかを椅子の高さごとに計測した実験でも、同様の結果が得られています。
目線の高さでコミュニケーションをコントロール
これらのことから、パーソナルスペースの範囲は、目線の高さによって、広がったり狭まったりするということがおわかりいただけるかと思います。
これを利用して、作業に集中するために話しかけてほしくない時は低い席で仕事をして、部下とコミュニケーションを積極的に取りたい時には立ちながら仕事をするなど、目線の高さを変えることで、コミュニケーションの量や頻度をコントロールできるようになります。
円滑なコミュニケーションは、円滑な業務遂行を促すだけでなく、問題の早期発見や、チームのモチベーション維持、職場の雰囲気作りにも重要な役割を果たしています。
目線の高さとコミュニケーションの関係を知っておくことで、「話しかけないで」「話しかけて」と言葉や態度で表さなくても、ごく自然にコミュニケーションのしやすさを調節できるようになります。これは、あらゆるオフィスで応用しやすいテクニックです。
図/書籍『中間管理職無理ゲー完全攻略法』より
写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
会社で孤立しやすい人の特徴と対処法3選
KOIGAKU / 2024年7月7日 18時53分
-
"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
-
「この資料じゃ使えない!」「仕事の優先順位がわかってない!」 心ない上司の言葉に新入社員が失意の末に
J-CASTニュース / 2024年6月29日 12時0分
-
プライベートで仕事を引きずる人の特徴とは…境界コントロールできる人が人生満足度や仕事のやる気が高い訳
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 17時15分
-
「隣は嫌だ!」「入口に陣取る」...理想的な「管理職の席」配置とオフィスレイアウト
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月24日 17時40分
ランキング
-
1円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?
トウシル / 2024年7月22日 8時0分
-
2なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え
プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分
-
3イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで
東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分
-
4システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超
時事通信 / 2024年7月21日 22時45分
-
5コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」
産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください