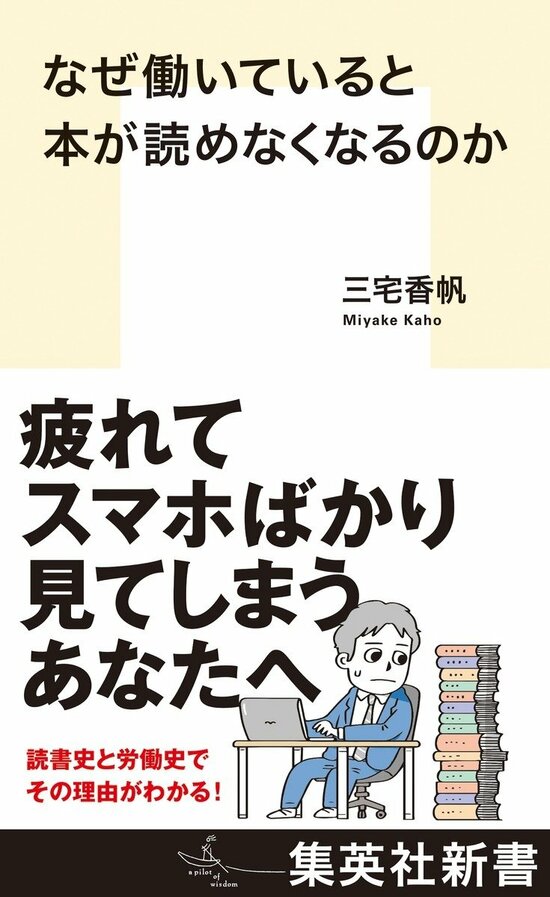「意志を持て」「ブラック企業に搾取されるな」「投資しろ」「老後資金は自分で」働き方改革と引き換えに労働者が受け取ったシビアなメッセージ
集英社オンライン / 2024年8月7日 8時0分
〈〈なぜ働いていると本が読めなくなるのか〉「自分が決めたことだから、失敗しても自分の責任だ」社会のルールに疑問を持つことができない新自由主義の本質とは〉から続く
高度経済成長期から始まったとされる日本の長時間労働問題。2019年に施行された「働き方改革関連法案」はその問題に対してのアプローチではあったが、単純に余暇を楽しめというメッセージではなかった。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』より一部抜粋・再構成し、働き方改革について考察する。
働き方改革と時代の変わり目
時代の波に乗りに乗ったかのように見えるビジネス書『人生の勝算』。読んでいると、2017年(平成29年)に発売された同書がすでに「今の時代にはそぐわない」ことを幾度も説いている点が、妙に印象に残る。
たとえば著者の前田裕二が「自分の人生のコンパスを自分で決める」例として、「自分は仕事に熱狂したが、兄はそんな仕事一本ではなく家族を大切にして幸せそうだ」というエピソードを挙げる。
ここには「仕事ばかり頑張るだけが正義ではないけれど」とでも言いたげな、そこはかとない時代へのフォローが見え隠れしている。さらに「他者のことを考えて行動せよ」と説いている際、「でも昔と今とではルールが違いますので」と注釈をつけているあたり、やはり自分が時代にそぐわないことへのフォローを入れているなと感じてしまう。
飲みの席でバカをやり切れるようになって以来、営業の電話を取ってもらえる確率が飛躍的に向上しました。こんなことで、と最初は悔しかったのですが、前田は振りきって何でもやれるヤツだと評判も広がって、飲みのお誘いや、営業での指名が増えました(注:もちろん、これが通用するお客さんは一部でしたし、今の証券業界は接待ルールが厳格になっており、ゲームのルールが変わっているかと思います)。
『人生の勝算』の編集者である箕輪厚介は、自己啓発書『死ぬこと以外かすり傷』(マガジンハウス)を2018年に出版した。この本もまた「行動重視」のビジネス本であり、死なないならどんな行動をとってもいいと綴られている。が、2023年(令和5年)に彼は『かすり傷も痛かった』(幻冬舎)というエッセイを出版している。
そりゃそうだ。いくら死ななきゃいいと思っていても、現実は、かすり傷ですら痛い。
─そのことに皆が気づき始めたのが2010年代後半だった。
2015年(平成27年)に電通過労自殺事件が起こり「働き方改革」という言葉が叫ばれ始めた。2019年に施行された働き方改革関連法は時間外労働の上限規制の導入、年次有給休暇取得の一部義務化など、長時間労働にメスを入れる形になった。高度経済成長期からはじまった、この国の長い長い長時間労働の歴史がやっと変わろうとしていたのである。
ノマド、副業、個で生きる
大企業の長時間労働是正がなされる一方、2000年代からはじまっていた日本社会の「やりたいことを仕事にする」幻想は、2010年代にさらに広まることになる。
働き方改革がはじまる少し前─2014年(平成26年)からはじまったYouTubeのCMキャンペーンのキャッチコピー「好きなことで、生きていく」を覚えている人もいるだろう。
そう、会社に頼る代わりに、一方で「副業」や「フリーランス」といった働き方がもてはやされたのだ。会社や組織に頼らず、個で稼げ、と説かれる。
「ノマド」という言葉も浸透し、立花岳志の『ノマドワーカーという生き方―場所を選ばず雇われないで働く人の戦略と習慣』(東洋経済新報社)が出版されたのは2012年(平成24年)のことだった。
この傾向は、働き方改革を経てますます強くなる。つまり会社で終身雇用に頼るのではなく、好きなことや自己実現を果たせることで、個として市場価値のある人間になるべきだ、というメッセージが日本社会に発信されたのだ。
自分の意志を持て。グローバル化社会のなかでうまく市場の波を乗りこなせ。ブラック企業に搾取されるな。投資をしろ。自分の老後資金は自分で稼げ。集団に頼るな。─それこそが働き方改革と引き換えに私たちが受け取ったメッセージだった。
労働小説の勃興
働き方改革の時代性は、読書の世界にも影響を及ぼす。
実はリーマンショックを経た2000年代末から2010年代、労働というテーマが小説の世界で脚光を浴びていた。
たとえば非正規雇用の女性が主人公である津村記久子の小説『ポトスライムの舟』(講談社)が芥川賞を受賞したのは2009年(平成21年)。企業を舞台にした池井戸潤の小説『下町ロケット』(小学館)が直木賞を受賞したのは2011年(平成23年)。就職活動をテーマとした朝井リョウの小説『何者』(新潮社)が同じく直木賞を受賞したのは2013年(平成25年)。
どれも「働き方」や「働くこと」の是非を表現した小説だった。
さらに2016年(平成28年)に発売され芥川賞を受賞した村田沙耶香『コンビニ人間』(文藝春秋)はベストセラーとなった。本書はコンビニで働く女性の物語なのだが、コンビニで働くことで自分を「普通」に適合させるのだと主人公は感じている。
つまり労働が主人公の女性にとって、実存そのものの問題となっている。
ほかにも、『舟を編む』(三浦しをん、光文社、2011年)、『銀翼のイカロス』(池井戸潤、ダイヤモンド社、2014年)など、仕事をテーマにしたベストセラーも登場し、ドラマも労働の風景を描いた『半沢直樹』(TBS、2013年)、『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS、2016年)が高視聴率を獲得した。
2000年代半ばには「純愛」ブームがあったが、2010年代は、「労働」ブームだったと言えるだろう。
ちなみに、2010年代の労働の捉え方については、拙著『女の子の謎を解く』(笠間書院、2021年)で解説したので、興味のある方はそちらで読んでみてほしい。
写真/Shutterstock
外部リンク
- 「全身全霊で働くっておかしくないですか?」会社員が読書できるゆとりを持つためには――大事なのは、真面目に働く「フリをする」技術【三宅香帆×佐川恭一対談 後編】
- 「就活の仕組みが適当すぎはしないか?」「就活はうまくいったけど、肝心の仕事はさっぱりダメ」受験、就活、出世競争……京大文学部の二人が激化する競争社会にツッコミ「これ、なにやらされてるんやろ?」【三宅香帆×佐川恭一対談 前編】
- 「ちくしょう、労働のせいで本が読めない!」「いや、本を読む時間はあるのにスマホを見てしまう」 社会人1年目の文学少女が受けた“仕事と読書の両立のできなさ”のショックとは?
- 「本を読まない人」に読書の楽しさを伝えるためには?文芸評論家・三宅香帆が「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴と考える
- 日本社会は「全身全霊」を信仰しすぎている?「兼業」を経験した文芸評論家・三宅香帆と「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴が語る働き方
この記事に関連するニュース
-
「まどか26歳」9時5時勤務の研修医が見た"葛藤" 「労働時間が短い=良い」は思い込みなのか
東洋経済オンライン / 2025年1月31日 8時50分
-
みんなが語った本ランキング2024
PR TIMES / 2025年1月30日 12時45分
-
「男が育児うつになるなんておかしい」東京から妻の実家の沖縄に里帰り移住、大きな環境の変化で「育児うつ」となった男性の“唯一の逃げ道”となったものとは…
集英社オンライン / 2025年1月25日 10時0分
-
【ネガティブ読書案内】仕事を辞めたくなった時に読みたい本(案内人:外山薫さん)
集英社オンライン / 2025年1月18日 13時0分
-
「入社してはいけない悪質企業」はネットで公表されている…「日本からブラック企業が絶滅」の実現可能性【2024下半期BEST5】
プレジデントオンライン / 2025年1月14日 7時15分
ランキング
-
1義理チョコは「人間関係の潤滑油」? 義理でもうれしい…“義理チョコ文化”に対する男性の“本音”
オトナンサー / 2025年2月10日 20時10分
-
2「油」で生理痛やPMS解消、栄養士が教える上手な“選び方”と“とり方” 注目は「カメリナオイル」
週刊女性PRIME / 2025年2月11日 6時0分
-
3「めっちゃうま!」セブンで買える、SNSで話題のスイーツ3選。贅沢気分に浸れる美味しさ。
東京バーゲンマニア / 2025年2月10日 18時3分
-
4「コンビニおにぎり」各社の人気ランキング、1位は? - おにぎり協会調査
マイナビニュース / 2025年2月10日 13時53分
-
5疲れるのは夏だけじゃない!? - 冬の疲れの原因、乗り切るための対策とは
マイナビニュース / 2025年2月10日 12時33分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください