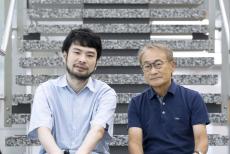「単純な物語」を捨て、小説世界を構築する 奥泉 光×小川 哲『虚史のリズム』刊行記念対談
集英社オンライン / 2024年9月14日 9時0分
二〇二〇年六月号より、『すばる』誌上で三年半にわたって連載された奥泉光氏の大作『虚史のリズム』が、このたび満を持して刊行されました。
二〇二〇年六月号より、『すばる』誌上で三年半にわたって連載された奥泉光氏の大作『虚史のリズム』が、このたび満を持して刊行されました。
背幅cm、重さkg超え、圧倒的な存在感を携えた本書ですが、見た目のインパクトをはるかに上回る濃い物語が読み手を待ち構えています。舞台は第二次世界大戦後の一九四七年、GHQ占領下の東京。山形で起こった一つの殺人事件をきっかけに、「K文書」なる国家機密の謎が動き出し……。
歴史の混迷を背景に、様々な登場人物が交錯し、語り、多層的な物語が紡ぎ出されてゆく様は、『地図と拳』をはじめとした小川哲氏の著作とも重なる部分がありそうです。壮大な物語世界を、お二人はどのように言葉で立ち上げているのでしょうか。大森望さんを司会に迎え、じっくり語っていただきました。
司会・構成/大森望 撮影/山本佳代子
――奥泉さんの大作『虚史のリズム』がついに刊行されたということで、今日は大いに語っていただきたいと思います。お二人とも、近現代史の、特に戦争を背景にした大作を複数書かれています。小川さんに関して言えば、満州を舞台にした『地図と拳』はもちろんですが、その前の『ゲームの王国』もカンボジアの内戦が背景で、どちらもSF的要素が入っています。そう思うと、お二人の作品には共通点が多い気がしますが、まずは小川さんに『虚史のリズム』の感想から伺いましょうか。
小川 校了前のゲラで読んだのですが、段ボール箱で届いたのは驚きました(笑)。でもすごく読みやすくて、思ったほど時間はかかりませんでした。奥泉さんの書き方が非常に親切で、読者が迷子にならないようにできていると感じます。
あと、これは僕がそう読んだという話ですが、本書は基本的に二つの謎を軸にしたミステリーの形式をとっています。「棟巍(とうぎ)正孝を殺したのは誰か」という謎と、それに関連して出てくる「『K文書』とは何か」という謎。当然、容疑者が何人か出てくるのですが、それぞれの容疑者に注目すると恋愛小説に見えてきたり、政治小説に見えてきたり、SFに見えてきたり、というように、いろんなジャンル小説をミステリーが包含するような構造で書かれてもいる。そもそも「この小説はミステリーなのか?」という問い自体がミステリーの謎になるような構成がすごいと思いながら読みました。
奥泉 ありがとうございます。実はこの『虚史のリズム』、連載がスタートする段階で担当編集者には、「今回は失敗してもいいや」と言っていたんですよ。あえて失敗を辞さずにいく、と。当然ながら意図的に失敗するわけにいきません。でも、風呂敷を広げて世界を大きくしていって、語りのバランスも考えずに、その結果収拾がつかなくなったとしても、今回はいいとしよう、そういうやり方で書こう、と。
同じ近現代史を材にして少し前に書いた『雪の階(きざはし)』という小説は、端正に世界を構築して、文体も緻密に考えて作りました。今回は、思想小説の色彩もあるので、端正は捨てて、破綻してもよいという考えだったんだけど、やっぱり性格なんでしょうね、なかなか本格的な失敗には至れなかったのが、不満と言えば不満です(笑)。でも、これは自分の長所でもあり短所なので、仕方がないなというふうに思いました。
「ミステリー」を採用する理由
――『虚史のリズム』ですが、奥泉さんの過去作である『グランド・ミステリー』と『神器―軍艦「橿原」殺人事件』の主要登場人物が出てきて、両者の続編と呼んでもいいようなかたちになっています。
奥泉 そうですね。ただもちろん、『虚史のリズム』単体でも問題なく読めるようになっているとは思います。『グランド・ミステリー』『神器』の流れで、今回もミステリーの枠組みを使っています。今までの作品もそうなのですが、提示した謎はいちおう合理的に解かれている。ジャンルに敬意を表して、ミステリーとしての最低限のモラルは守っている。ただ問題なのは、過去作もほぼそうなんだけど、謎が解かれたときには、もはやその謎はどうでもいいものになっているという……(笑)。これが僕の小説の基本的なパターンなんですが、今回もまあそうかな。
小川 たしかに、誰が犯人かという意味では、その点はあまり重要ではなくなりますね(笑)。
奥泉 謎解きに小説が収斂して行かない。昔、笠井潔さんに「君はミステリーを書いてない、ミステリーで書いている」と言われました。でも、小川さんもたぶん一緒なんじゃないかなという気がしますね。
小川 それはそうですね。
奥泉 SFについても同じことが言えるはずで、どうも小川哲という作家はSFを書く作家じゃないなという匂いを強く感じたんですよね。SFで書く人、むしろ他のことが書きたい人だろうと。たとえば『地図と拳』なら、建築というものの持つ意味とか、満州の歴史的意義とか、小説世界を広げていくことに関心があって、ミステリーやSF的なアイデアに収斂させていくことには、そんなにこだわりがないと見たんですけど、どうですか。
小川 僕も、ジャンル小説を書きたくて書いているわけではないですね。作品ごとに、その作品を通じて考えたいことがあって、一番ふさわしい形式を選んでいる感じです。
あと、奥泉さんがどうかはわからないのですが、自分がただ考えたいことを書き連ねても、商品として需要がないんじゃないかという心配が強くあって……。読者にどうやって興味を持ってもらうかという部分で、ジャンル小説、特にミステリーの力を借りる。SFはどちらかというとプロットの型ではなく、設定やガジェットの型なので、自分が考えたいことを考えやすくするために、哲学者が思考実験をするようなイメージで力を借りることが多いですね。だから僕の場合も、ジャンルありきということはあまりなくて、考えたいことが先にある。
奥泉 それは僕もそうですね。極端なことを言えば、今回もミステリーにする必要はないと言えばなかった。けれども小説を支える骨格は欲しい。骨格に支えられて物語や言葉ははじめて自由に展開できる。建築に喩えると足場ですかね。ある程度小説ができてくると、それは自立して、足場はいらなくなるわけですが、物語のとっかかりとして、読者が入りやすいというメリットも含めてミステリーを採用することが多いわけです。
――奥泉さんの場合、毎回不可解な事件がとっかかりになりますが、今回は『神器』に登場する石目鋭二という人物が“探偵”役に起用されていますね。もともとミステリーおたくのキャラクターとして設定されていた石目が、戦後の東京で「名探偵に俺はなる」と勝手に決意して事件に突っ込んでいく。本人は一所懸命、本格ミステリーの名探偵になろうとするんだけど、なかなかうまくいかない。途中で三回ぐらい「もう探偵はやめよう」と決意するシーンがあります(笑)。
小川 結局、石目はモテたくて探偵をやっているというのがいいですよね。物語中盤以降、探偵そのものへの興味を失ってもなお、ひとめぼれした相手・卑弥呼さんにモテたいという理由だけでなんとか探偵を続けていく。あまりいなかった探偵像ですね、情けなくて(笑)。
奥泉 かわいらしい人物ですよね。読者が上からの視線で優しく見てあげられるような主人公。広い意味でフモール、ユーモアということだと思うんだけど、そういう設定の主人公はやっぱり書いていて楽しいですね。今回、戦後という時代を書くにあたって、どうやって小説をスタートさせるかが難しくて、あれこれ試行錯誤したのですが、石目の語りの力を借りることで、ようやく物語をはじめられた。
――頭の中で主役オーディションみたいなことをされたわけですか? 今度は誰でいこう、というような。
奥泉 そうですね。人物というよりは文体ですね。語りのスタイルをどうするか。
小川 でもこの『虚史のリズム』、前半は石目と、もう一人の主人公・神島健作の視点が多いんですけど、後半になるにつれて美術学校生の水谷澄江がどんどん活躍していくんですよね。あの変化、奥泉さんは書く前から想定していましたか?
奥泉 全然していなかったです。それはそういうものじゃないですか? 書いてるうちに、「お、澄江、なかなか面白いな」とどんどん思えてきて。ちょっと理想化しすぎたかもしれないけど。
小川 最終的に、一女子学生に過ぎない澄江が民主主義を背負うんですよね。
奥泉 なかなかすごい人になっちゃう(笑)。澄江の魅力を引き出そうとするうちに、彼女の存在がどんどん膨らんでいきました。しかしそういうところが長編の醍醐味じゃないですか。
小川 そうですね。役割だけ用意してちょっと出した人物なのに、「あれ、この人、何かもっと隠し持っているぞ」と書いているうちに見えてきて、どんどん重要になっていく。
奥泉 そうですよね。
小川 この作品の後半の近代史をめぐる政治小説的なパートで、澄江が「自由」を語り重要な役割を果たした場面は、読んでいてびっくりしました。むしろ序盤では、素性の知れぬ「大将家(い)の倫子(みちこ)さん」のほうが重要そうだったのに、まさか澄江がこんなに活躍するとは……。実は石目もそうで、意外にも探偵以外の面で才能があるんですよね。
――すごく有能ですよね。商売がことごとくうまくいく。
奥泉 もともとそういうキャラ設定だったんだよね。人の懐に入るのがものすごくうまくて、圧倒的なコミュニケーション能力を持つ男。それをそのまま商売に生かしているわけです。
小川 あと、石目は生命力がものすごいですね。昔、漫画で見たラッキーマンを思い出しました。すごく運が悪いんだけど、絶対に死なない(笑)。
奥泉 たしかにそうですね(笑)。タイトルに入っている“リズム”という言葉は、石目の語りのリズムのことでもあるんです。ああ、戦後を描くのに、このリズムでないと自分はやはり書けなかったんだなと、後になって思いました。
dadadaのリズム
小川 実は『ゲームの王国』のときは小説の書き方がよくわかっていなくて、自分の中では破綻したというか、散らかしたものを全て片付けて終えることができなかったという感覚が残っています。だから『地図と拳』では、作品の柄が多少お行儀よくなっても、散らかしっ放しで終わらないようにしよう、破綻しないようにしようという気持ちで書き始めました。奥泉さんが『虚史のリズム』を書き始めたときとは正反対ですね(笑)。
とはいえこの作品も、終盤になるにつれ、奥泉さんの癖か美学かはわかりませんが、きちんと回収するパートが増えていきます。何といっても、dadadadadaの仕組みがあることで、はち切れそうになった小説を音楽的に収めることができてしまっているというか……。この小説のリズムは石目の語りのリズムでもあるとおっしゃっていましたが、後半になるにつれて、dadadaのリズムが前面に出てきますよね。
奥泉 後半で暴れているdadadaは、実はもともと出てくる予定はなかったんです。主人公の一人である神島が、下宿で横になっているとき、襖絵に描かれた人物が「あ」のかたちに口を開けているのに気がついて、ドイツ語の「da」と言っているのだと思った――そういうちょっとしたシーンを序盤で書いた。それだけのはずだったんです。ところが、そうか、「da」は死者が口から漏らす響きかもしれないなと、イメージがどんどん膨らんでいって……。戦争体験をどう捉えるかの問題をめぐるあれこれをこの本では繰り返し書いているわけですが、体験の全体を表象する響きとして、dadadaというダダイズムの詩句のようなフレーズが出てきた。その意味では、はち切れそうになった小説を音楽的に収めたというのはその通りで、この部分は小説テクストとしては破綻していると言えるかもしれません。
本を見てもらうと、装丁をしてくださった川名潤さんの版組が後半のほうですごいことになっているでしょう(笑)。前の方にも何度かdadadaが入っているんですが、ぶっちゃけていうと、実はそのあたりは、テクスト的に少し弱いので、なんとかdadadaで補強してくれませんかと、川名さんに頼んだんです(笑)。その意味では、失敗を辞さずというのは、ここでわずかながら実現しているのかもしれない。どちらにしても、小説というのは、公にしうる範囲内でなら何をしてもいいわけで、とりわけそういう遊びが許されるジャンルだとも思うわけで。
――dadadaのタイポグラフィで言えば、ルビにdadadaが入ってくるのは斬新だなと思いました。
奥泉 そう、そこは川名さんのアイデアですね。僕は後半でdadadaが蛇のようにうねるようにしてほしいと頼んだ(笑)。今はいくらでも奇抜なレイアウトに対応することができるじゃないですか。でも川名さんは、戦後すぐの組版でもできる範囲内でやりたい、と。そこは川名さん流のこだわりですね。
単一の物語に他者を閉じ込めない
――現実の歴史を背景に小説を書くことについて、お二人それぞれこだわりはありますか?
小川 僕が小説を書く上での一番のモチベーションになっているのは、他者について考えたいという感情なんです。もともとSFでデビューしたのも、他者のことを一番考えられるジャンルだと思ったからで……。自分とはまったく違う価値観や倫理体系を持つ人について考えたいという思いは、小説を書く上で大事にしていますね。
歴史に行き着いたのは、単純に、それまで未来に向いていた矢印が過去に向いただけです。戦前・戦中・戦後すぐ、いずれも今とはまったく違う価値観や倫理観、科学技術や社会システムのもとで生きていた人たちがいたわけで。仮に自分がその場にいたら何ができたか、どうすれば七十年以上前の戦争を自分に関係するものとして見られるか、ということを考えるのが、『地図と拳』を書く上での大きなテーマでした。
そのためにはまず、当時の人がこういう価値観のもとでこういうことを考えて生きていたという部分を描こう、と。現代の視点から眺めると、昔の人は野蛮で愚かだったという結論になってしまいがちですが、それでは近代史について考えることはできませんから。『虚史のリズム』でも、戦後の時代の価値観が示されていて、そこはすごく共感しました。
奥泉 そうですね。基本的に他者のことはわからないわけです。他人のことは究極的にはわからない。しかし人間には想像力がある。想像力を通じて他者のことを考えることができる。想像力を使って過去の人たちのことを考えられること、彼らがどのように考え行動したかを言わば共感的に描けることが、小説の最大の強みなんですよね。
ただ同時にそこには、自分が持つ単純な物語に他者を閉じ込めてしまう危険性がたえず存在しています。特攻隊が一番わかりやすい例だけど、パターンの中で「泣ける物語」を書くことはいくらでもできてしまう。でも、特攻隊をめぐる人々の思いや行動は、単純な物語では捉えられない。一方で我々はどうやっても物語的にしか世界を認識できず、他者もまた捉えることができないという難問がある。とすれば、物語そのものへの批評的な目を持つことを含め、いかなる物語でもって他者を描くべきなのか、たえず考えなくてはならない。
これには簡単な答えがあるわけではない。しかし、少なくとも言えるのは、単一の視点で他者や事象を捉えてはならないということだと思います。複数の物語をたえず用意する。いくつもの可能な物語のせめぎ合いの中で世界を構築していく作業しかないと思うんです。よく使われる言葉だと、「多層性」ということになるんだけれども。単純と言えば単純なことですが、それは何度でも言いたい。戦争にまつわる出来事は単一の物語に閉じ込められてしまう危険性が高いし、これからきっとどんどんそうなっていくんだと予感します。
小川 そうなると危険ですよね。特攻隊の感動的な話や、たとえば忠臣蔵もそうかもしれませんが、僕らの中に入ってきやすい物語化がなされています。なぜ入ってきやすいかというと、その時代に決断を下した人々の考え方や価値観を現代の僕らの視点で捉えているからだと思うんですよね。だからそうならないように、自分の物語に閉じ込めないように注意しないといけない。
奥泉 まったくそうですね。あと小川さんの小説で、方法として注目したのは、史実と虚構との関係性ですね。『地図と拳』で登場する李家鎮(リージャジェン)というのは架空の街です。加えて主要登場人物は全員フィクショナルな人物。これはひとつの方法ですよね。遠景では実在の人物も出てくるんだけど、台詞があったり内面が描かれたりする人物は、徹底してフィクショナル。僕の小説も基本的にそうなんです。今までの小説すべてそうだと言っていい。そのへんはどうですか、意識していますか。
小川 もちろん、すごく意識しています。歴史小説にはいろんな役割があって、実在の人物の再解釈もそのひとつですよね。史料にはその人の内面が描かれていないので、内面を組み立てるという仕事も小説家にはある。なぜこういう決断をしたのか、なぜこういう行動をとったのか。ただ、今のところ僕は、歴史上の人物の再解釈ではなく、近代史そのもの――もっと抽象的な、戦争って何だったんだろう、近代って何だろう、天皇って何だろうとか、そういうところ――のほうに興味があるので、再解釈ゲームには参加していません。
――『ゲームの王国』のポル・ポトは再解釈しているんじゃないですか?
小川 ポル・ポトについては、彼を扱ったフィクションがそもそも存在しないので、再解釈も何もないというか(笑)。当時、カンボジアがポル・ポトについての小説を書ける状況になくて、実際に書かれていなかったということもあるし、日本人にとってポル・ポトがすごく遠い人物だということもあります。まあ、『ゲームの王国』の中でポル・ポトはそんなに主要登場人物じゃないんですけどね。要するに、僕は別に日本の史料研究とか歴史学を前進させようとはしてないと、そういう話です。だからむしろ、実在の人物については、自分の想像力を守るために意図して出していません。出したほうが面白くなるかなと思うときもありますけど。奥泉さんはどうですか?
奥泉 いわゆる歴史小説については、書くだけの時間が今後に残されているかどうかわからないんだけれども、ひとつの課題と捉えています。日本の近代小説にその流れはあって、鴎外とか、大岡昇平とか、多くの作家が晩年に歴史小説にチャレンジしている。吉村昭さんもやっていますね。評伝というのはジャンルとして確立されていますが、それを含めて、歴史小説をどう書くのか、書けるのか、まだ掴めていなくて、やりたいんだけど、うーん、でもなあ……(笑)。「このとき甘粕はこう思った」とかって、やっぱり書きづらいじゃない。
小川 これまでフィクションにおいて、たくさんの甘粕像が描かれてきているわけですよね。半端にやると、みんなが描く甘粕とちょっとイメージが違うとか、そういうことにもなりかねないし……。
奥泉 方法論をずっと模索中なんです。
小川 「この人ってきっとこうだったんだろうな」と思える、二次創作的な妄想力がないと楽しく書けない気がします。近現代史上の人物って、「何月何日にどこにいた」「何年に昇進した」という記録がすべて残っているわけです。小説でその人物を描くとしたら、絶対に通らなければならないチェックポイントをクリアしながら、その間でひとつの人格を作っていく、解釈する、という試みになると思うんですけど、今のところ僕にはちょっと難しそうですね。できるならやってみたいですけど。
奥泉 近代史への関心と言えば、小川さんの関心の中心はどのあたりになるのかな。ポル・ポトを書いたり、満州を書いたりするのは、トータルな近代史への関心とはちょっと異なるのかなと。
小川 たぶん、もともとはユートピアに関心があるのだと思います。だから、共産党にも興味があって。うちの祖父が元共産党員でバリバリ活動していて、治安維持法か何かで逮捕されているんです。それとはあんまり関係ないのかもしれないけど、頭のいい人が集まって、「こうすれば理想の国ができるんじゃないか」と考えたことがなぜ必ず失敗するのかということは、昔から考えていますね。その問いが、満州やカンボジアを書くことにつながっているのかな。
奥泉 なるほど。僕は、とにかく太平洋戦争への関心がずっと中心にあるんです。わかりやすく言うと、どうしてああいう悲惨な戦争をしてしまったのか、そこに尽きる。でもこの関心は、小説家であることとは直接関係なくて――というのも変ですが、太平洋戦争のことを小説で書かねばならないと思っているわけではない、少なくともそれを書くために小説を書いているわけではないんです。しかしやっぱり自分の関心事だから、書くとそれが出てきてしまう。僕は太平洋戦争を中心に据えて、近代史を考えることをやってきたんですが、今回はそこから戦後のことを考えてみました。
僕の世代から見ると、戦後の占領期は謎に満ちています。むしろ戦前、戦中のほうが理解しやすい感じがある。占領期というのは、よくわからない不思議な時代なんですよね。その不思議さを小説中で表現したいという思いも、今回は特にあったんだけれども。でも繰り返しになるけれど、それは変な言い方ですが、小説の内側から出てきた関心ではなくて、もっと違うことを書いてもいいはずなんです。しかし結局は自分の関心事なので、それを書くしかないということになっちゃう(笑)。
小川 僕は一九八六年生まれなんですが、冷戦とか高度経済成長とか、自分が生まれてくる十年ぐらい前、親が学生だった頃に体験した時代が自分にとっては謎で、興味がありますね。それとちょっと似ているのかもしれません。僕の場合はむしろ、戦中や戦後のほうが理解しやすい気がします。
――奥泉さんは一九五六年生まれなので、占領期(一九四五~一九五二年)との距離感は同じくらいですね。
歴史は変えられるか?
小川 そういえば『虚史のリズム』には、国家機密である「K文書」とからんで、「第一の書物」「第二の書物」という、未来予知に通じるモチーフが出てきますよね。これは一九九八年に出た奥泉さんの『グランド・ミステリー』のメインモチーフですが、実は僕の『地図と拳』にも、未来予知みたいなものが出てくるんです。
――たしか『地図と拳』を書いた時点では、小川さんは『グランド・ミステリー』を読んでなかったんですよね。
小川 読んでいませんでした。大森さんに『地図と拳』の構想を話したとき、『グランド・ミステリー』を読んだほうがいいよと二回ぐらい言われて(笑)。でも、読んだら逆に書きづらくなりそうだなと……。
――『地図と拳』にも、未来を知っているかのような人物が出てきて、研究所が創設されて戦争を回避しようと努力するんだけど、結局歴史のコースは変えられない。あたかも『グランド・ミステリー』にオマージュを捧げたかのようにも見えました。
小川 奥泉さんの作品は以前からかなり読んでいて、特に『ノヴァーリスの引用』が大好きで、何度も僕なりに『ノヴァーリスの引用』をやろうと思って失敗しているんですよ(笑)。その経験があったので、これは読まないほうがいいなと思って。
――さすが、クリストファー・プリーストの『奇術師』を読まずに「魔術師」を書いた小川哲だけのことはあるなと思いました(笑)。
奥泉 読んでなかったんだ。
小川 理屈でつくっていくと同じ答えになるということですね(笑)。
――プリーストにも、『双生児』という第二次世界大戦を題材にした長編があります。これは双子のどちらが生きているかで歴史が二重化するというアイデアで、『グランド・ミステリー』と同じようなことをイギリスでやっている。二〇〇二年の小説なので、『双生児』のほうがあとですが。
小川 僕、いまだにプリーストは一冊も読んでいません。もう怖くて(笑)。絶対面白いのはわかっているんだけど、今後、自分が書くときにプリーストがちらつくのが嫌だなと。
奥泉 影響はむしろ受けたほうがいいと思うけどね(笑)。でもSFだったら、同じアイデアになっちゃうことはありうるか。そうするとたしかにやりづらいですね。
小川 SFの場合は同じアイデアで書かれていて、どっちも名作という例もいっぱいあるので、全く同じ作品には絶対ならないとは思うんですけど……。奥泉さんの「第一の書物」「第二の書物」というSF的な装置は、どんなかたちで生まれて、どんな意図で使われているものなんですか。
奥泉 『グランド・ミステリー』の出発点は、「戦時中という大量死の時代に、ひとりの人間の死の意味があるのか」という問いでした。そこからミステリーを構想していった。「第一の書物」「第二の書物」の二つの現実のモチーフは、書いている途中で出てきたもので、SFのアイデアとしてはとくに目新しいものではないけれど、これを導入することで、小説に膨らみと推進力が生じて、それに導かれるまま進んでいったという感じですね。そこから「個人は歴史を変え得るか」という主題も必然的に生じましたが、小説世界を多層化、重層化するための装置の面がむしろ強かったと思います。
今回の『虚史のリズム』は、その続編でもあるわけです。さっきの破綻の話で言うと、『グランド・ミステリー』の一番の破綻――というほどではないけれど、問題が残ったのは、志津子という女性なんですね。彼女は非常に大きい役割を小説中で持っているんだけど、しかし、『グランド・ミステリー』ではその後あまり出てこなくなって、彼女はいったいどうしたんだという疑問があったわけ。だから志津子に決着をつけることが、今回の小説を書く動機のひとつでした。
そうして書きはじめたら、志津子は少なくとも思想的には「歴史は変え得る」という立場に立つ強烈なキャラクターになっていった。それが書きたかったのかもしれませんね。歴史は改変できる。より良き世界の構築は可能である。そうした肯定的理念に己を賭ける人物として、彼女を描くことになった。だから極端なことを言うと、『虚史のリズム』は、彼女のために書かれた小説なんです。さらに、その思想を受け継ぐかもしれない澄江という人物も出てくる。『グランド・ミステリー』では、『虚史のリズム』で「K文書」を遺した人として登場する貴藤大佐が歴史の改変に挑戦して失敗する。今回は、非常にかすかで淡い線なんだけど、歴史の流れに抗していく可能性の芽が未来に残された。その点が『グランド・ミステリー』と『虚史のリズム』の大きな違いかもしれませんね。
小川 歴史小説の一番の弱点って――そう言っていいのかどうかわかりませんけど――オチがわかっていることじゃないですか。第二次世界大戦の話を僕がどれだけサスペンス味たっぷりに書いたところで、最後に日本が負けることはみんな知っているわけです。だから、読者からすると一定のストレスがあるかもしれない。つまり、出てくるやつは全員負けに向かって一直線に動いているという。
奥泉 満州国の建設も失敗に終わると。
小川 そう、失敗するのにいろいろ頑張っているわけで、「無駄だからやめろよ」と思いながら読む人もいるかな、と想像しました。『地図と拳』に予知のモチーフを出したのは、読者と同じような視点を持った人物を入れたかったからです。つまり、近代史を扱うに当たって、読者のツッコミを作中で代弁してくれる人物ですね。「そんなことしてると戦争に負けるよ」と言ってくれる人がいたほうが、負けるというオチがわかっている小説を読む上でストレスが幾分か軽減されるかなと。実際問題として、戦争に負けることを知っていた人物は、戦時中においてもそれなりの数でいたわけじゃないですか。だから、そういう人物を中心キャラクターとして動かしたいという欲求が、僕の場合はありましたね。
近代史を扱う小説の中に、予知や繰り返される人生という要素を入れるとき、それが作品のテーマを深める部分と、単純に読者の視点として機能する部分と、両方を持ち得るのかなと思っています。だから『虚史のリズム』にもそういうモチーフが出てくるのかなと想像していました。
奥泉 なるほどね。しかし、そうした仕組みは単純に面白いよね(笑)。僕は、SFでは時間ものが一番好きですね。
小川 たしかに戦後が舞台の『虚史のリズム』でも、現代からやってきたと思しき久良々が終盤で登場したりもしましたね。
奥泉 そうそう。ここまで書き進めてきたら、現代を生きている人間が出てくるのも全然ありだなと(笑)。なんせ主人公が鼠になっちゃった世界ですからね。これは『神器』でも同じことをやっています。今回の久良々(くらら)ははるかに頭がいいんですが(笑)。
小川 夢か現実かもわからないわけです。はたまた一方で「第一の書物」「第二の書物」の未来予知も、催眠術で説明できてしまうかもしれない。
奥泉 その可能性はどうしても残したくなる。リアリズムのラインもぎりぎり残したい。志津子も最後まで「第一の書物」のことを、二つの現実の存在を認めない。少なくとも認めるとは言わない。
小川 僕の小説はよくインテリの登場人物が多過ぎると言われますけど、たぶん奥泉さんの作品のほうがインテリが多いですよね(笑)。
――でも、愛敬あるバカも出てきて、バランスがとれている。
小川 いや、とはいえ石目もけっこう鋭いんですよ、戦争について語らせると。
小説のカルマ
奥泉 『地図と拳』は最初から義和団事件で始まって終戦までを書こうという構想だったんですか?
小川 そうです。『ゲームの王国』できれいな着地ができなかった一番の理由が、どこで終わるか決めていなかったことだったので、『地図と拳』は義和団で始めて終戦で終わろうと。始まりと終わりさえ決めておけば、だらだらすることはないだろうという感じでした。
――それで言うと、『虚史のリズム』のフィナーレは最初から決めていたんですか?
奥泉 いや、全然(笑)。殺人事件を起こすぐらいまでは考えていたけど、それだけですね。今までの長編はどれもそうだけど、ほとんどは書きながら構想も進めていく。
――今回は、これまでの作品の集大成っぽいところもあるじゃないですか。『グランド・ミステリー』と『神器』の両方の続編でもあり、さらに『雪の階』『東京自叙伝』はじめいろいろな過去作の要素が入ってきて、ラストは某作へのリンクを匂わせるという、まるでマーベル映画における『アベンジャーズ』のような(笑)。自作を全部つなげたいという欲望はあるんですか?
奥泉 たぶんあるんでしょうね(笑)。だって単純に面白いじゃない? どういう欲望なのかよくわからないけど、つい「ああ、あいつも出しておくかな」と。ちょっとした遊びみたいなものなんですけどね。特にラストなんかは、別にああいうふうじゃなくてもよかったんだけど、まあ、ああいうかたちで終わるのも面白いかなと。あと今回は、光る猫を二回出した。全部じゃないんだけど、僕の小説には光る猫がだいたい出てくるんです(笑)。ストーリーには関係ないんだけど、画家が絵の端っこにサインするみたいな感じで、光る猫を出しています。
小川 隠れミッキーみたいな。
――ミッキーと言えば、今回も鼠が大活躍しますね。
奥泉 そう。だから『東京自叙伝』にもつながっているんですよ。最後に出てくるオロチ、あれは要するに、『東京自叙伝』の地霊なんだよね、恐らく。
――それがあんなところまで出張している(笑)。
奥泉 はい(笑)。もう一度『地図と拳』の話に戻りますが、すごく大胆にひとつの架空都市、フィクショナルな街を登場させて、そこに関わる人間たちを描いていますよね。しかも、五十年ぐらいにわたる時間軸で。一種の大河小説的なテイストを狙っているんだなと思いました。
小川 そうですね。
奥泉 世代も交代していくじゃないですか。最初に読んだとき、冒頭に出て来た人物があっという間に退場して、「えっ、もう死んじゃうんだ」とびっくりしました。自分の小説だったら、あの人は最後まで生き延びますからね(笑)。そういう大河小説的な時間の流れの中で世界を構築していく書き方に、なるほど面白いなと刺激を受けました。自分もやろうかなと。僕の場合、作中の出来事のスパンがだいたい短いんですよ。
――『虚史のリズム』もこの厚さなのに、作中ではあまり時間は経っていない。
奥泉 小説内時間は四か月くらいですね。
小川 『地図と拳』で僕がイメージしていたのは、完全に『百年の孤独』なんです。
奥泉 なるほど。だから、やっぱり李家鎮という街が主役なんだ。
小川 五十年のスパンで満州を普通に書くと散漫になることはわかっていたので、ひとつの街だけに焦点を絞って、満州国をミニチュア化、カリカチュア化したものをつくるしかないなと。書いてるときは、こんなことをしていいのかとずっと心配だったんですけれども、書き終わってみたら意外と怒られませんでした(笑)。
奥泉 架空都市をつくってそれを満州の縮図とするというのは、まさしく小説ならではの技法で、面白い。べつに怒られるようなことじゃない。
――でも、近現代史の悲惨な史実を、小説ごときが恣意的に利用していいのかという議論もありますよね。
奥泉 たしかに、それはそうなんですよ。戦争をエンターテイメントにしていいのか。わかりやすい言い方をすればそういうことですよね。小説とはそういうジャンルなんだと開き直ることもできるけれども、やっぱりそこは気にすべきで、戦争の死者たちを搾取しない書き方を常に意識しますね。でも、その一方で、一種のエンターテイメント性も書き手としては考えざるを得ないわけで。それが小説というジャンルの、ある意味では怪しいところですし、逆にそこに魅力があるとも言える。
小川 背負わなきゃいけないカルマというか……。僕も搾取ということにはすごく気をつけているつもりではいますが、そういう見方で読まれてしまうことは避けられない。ただ、それでも忘却よりはましだろうと思います。つまり、誰も書かなくなって誰も論じなくなるよりは、たとえ金儲けのためだったとしても書き続けることのほうが健全じゃないか、というのが、僕の中での究極的な折り合いのつけ方ですね。傷つく人がいるから書けないという考え方ももちろんあるんだけれど、自分の中でそれと折り合いをつけながら、申し訳ないなと思いながら、でも書かないよりは書こう、と。
奥泉 そのためには結局、さっきも言った、単一の物語に人々を閉じ込めないということに尽きる。単一の視点で書いたとしても、別の物語、別の視点があり得るんだと、たえず意識して書くことが最低限のモラルだと思います。多層性こそが小説だと。ずっと同じことしか言ってないんだけどさ。
小川 あと、自分のイデオロギーのために利用しない、も大事ですかね。登場人物のイデオロギーは大切だけど、作家自身のイデオロギーのために小説を利用しない。それは作家の良心として考えていることではありますね。
“虚史”の理由
――タイトルの話に戻りますが、そもそもどうして「虚史」なんですか? 偽史でも稗史でも野史でもなく。
奥泉 正直、自分でもうまくは説明できないですね。虚史という言葉のイメージは最初からありました。「虚」というのは「フィクション(虚構)」という意味もあるけれど、「虚ろ」という意味もある。戦後という時代が虚ろなのではないかというイメージが僕の中にずっとあったんでしょうね。真面目に言えば、日本国民は太平洋戦争の死者たちをしっかり弔い得てない。その原因は、戦争体験をいまだ十分に経験化できていないということに尽きるんだけど、その結果、戦後という時代が、今僕たちが生きている時代を含めて、虚ろになっているんじゃないか、と。
――作中でもとある人物が、そもそも神国日本は負けるはずがなかった、ゆえに敗戦は現実ではない、偽の日本が負けただけだ、と主張しますね。
奥泉 そうそう、そういう思想はあり得たと思うんですよ。だから、戦争で亡くなった人たちは、いまもまだ戦場を行軍し続けているのだという強いイメージが僕にはある。彼らを無事日本に連れ戻し、しかるべき場所に落ち着いていただいたとき初めて、歴史が虚ろじゃなくなるという感覚。それは小説を書きはじめた頃からずっと一貫しているテーマですね。テーマというか、何度も言うようだけど、それを書こうと思って小説家になったわけじゃないんだけどね。そこにこだわっているのは間違いない。
――小川さんはそういうこだわりはありますか? 先ほどユートピアという話が出ましたが。
小川 そうですね。ユートピア思想の話は、何を書いていても出てくることが多いです。そもそもユートピア思想って、人類の歴史において、どの時代にもずっとあり続けているものですよね。それもあって、どの舞台で何を書いていてもそれを拾ってしまうというか……。理想の世界をつくろうとするんだけど、理屈上はうまくいくはずのものが、人間の愚かさ、人間が持つ動物的限界によって、むしろ悲惨なものになっていく。
奥泉 反転してしまう。
小川 そう、反転してしまう。それは根底にあるかもしれないですね。僕もそれが書きたくて小説を書いているわけじゃないんだけど、何を書いていてもそれが出てきてしまう。
――大東亜戦争にも、失敗したユートピア思想みたいな側面がありますね。
小川 戦争や思想って、根っこにはやはりユートピアとまでいかなくても、世界をよりよくしようという思いがあるはずです。でも、それがどこかで反転してしまうことの虚しさか、諦観か、あるいはそうじゃない可能性もあるという期待なのかわからないですけど、そこには興味を持ってしまいますね。
――『虚史のリズム』では、戦後、占領期の日本が描かれたわけですが、その先の構想はあるんですか? 『グランド・ミステリー』、『神器』、『虚史のリズム』と読んでくると、ぜひその先も読みたいという気もしますが。
奥泉 その先の戦後ね……。ちょっと、今はまだないですね。
小川 でも、書く可能性はある?
奥泉 はい。可能性は当然あります。
――では、いつかこの先が読める日が来るのを、首を長くして待ちたいと思います。今日はありがとうございました。
(2024.7.31 神保町にて)
「すばる」2024年10月号転載
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「お笑い芸人で史上初」“日本推理作家協会”会員になったカモシダせぶん。「ピン芸のネタを基に小説を書きました」
日刊SPA! / 2025年1月15日 8時51分
-
秘仏の扉を開いたのは破天荒すぎる男たちだった!? 新・直木賞作家が近代日本文化の黎明期に迫った感動作!
文春オンライン / 2025年1月8日 6時0分
-
【小説家・奥泉光×政治学者・原武史!】戦後80年・昭和100年の年に改めて天皇制を考える。二つの知性による白熱対話、『天皇問答』が河出新書より2025年1月7日発売。
PR TIMES / 2025年1月7日 12時45分
-
「つながる人、思い、物語」『いつかの朔日』 村木 嵐インタビュー
集英社オンライン / 2024年12月22日 10時0分
-
名優・村上弘明が独立 「僕の魅力?『田舎者』である事です(笑)」「現在はシナリオを書いているんです」
TABLO / 2024年12月18日 4時0分
ランキング
-
1高齢者は「体重」が重要…標準を下回ると死亡リスクが急上昇
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分
-
2芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか
東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分
-
3天正遣欧使節・千々石ミゲルの墓、長崎県諫早市の文化財に…ミカン畑での墓石発見から20年
読売新聞 / 2025年1月15日 17時0分
-
4「室内寒暖差がつらい…」その要因と対策が明らかに! - 三菱電機が紹介
マイナビニュース / 2025年1月14日 16時10分
-
5スニーカーのインソールを変えるだけで「靴の機能は劇的にアップ」する。“初心者が買うべき”一足とは
日刊SPA! / 2025年1月15日 15時51分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください