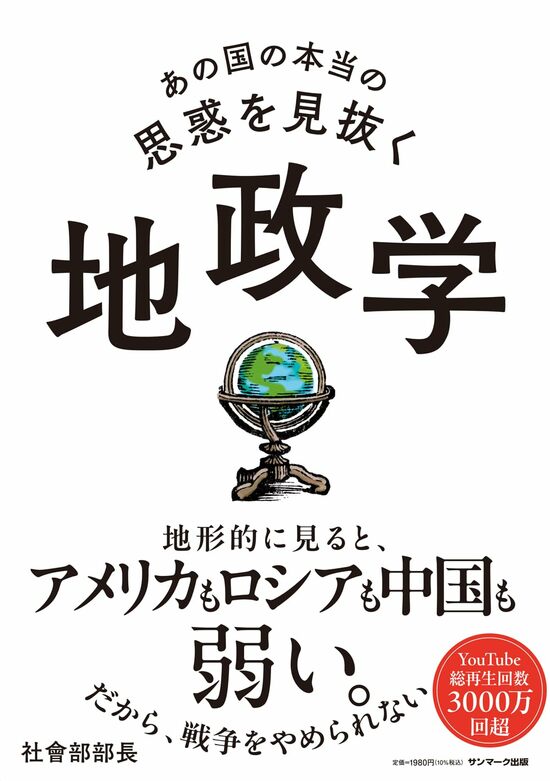アメリカは“世界最強の国”なのに「対米包囲網」が敷かれないのはなぜか…じつは中国やロシアほどは他国に恐れられていない本当の理由
集英社オンライン / 2025年2月10日 7時0分
世界最強の国アメリカ。しかし不思議なことに、世界の国々は中国やロシアを警戒するほどには、アメリカを恐れていない。実際「対中包囲網」という言葉はよく聞くが、「対米包囲網」という言葉はあまり聞かない。この「謎」を解く鍵は、国際政治における「安全保障のジレンマ」という考え方にある。地政学動画で平均150万回再生を記録する社會部部長が、不変の地政学の法則を解説した『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
【画像】アメリカでは殺人が起きやすく、スイスでは起きにくい理由
勢力均衡論最大の謎、アメリカ
勢力均衡論は、国際政治を説明する上で説得力のある理論です。実際に、16世紀以降スペイン、フランス、ドイツ、ロシア(ソ連)などが圧倒的な勢力を持って台頭したものの、周辺国が対抗連合を組んで覇権の阻止にすべて成功しました。
ところが、現代の世界ではこれに矛盾するように見える現象が発生しています。それは、アメリカに立ち向かう対抗連合が存在しないことです。冷戦が終わってから、アメリカは「唯一の超大国」として絶大な勢力を誇っています。それにもかかわらず、世界には複数の国が協力してアメリカを抑えようとする動きが見られません。
もちろん、アメリカに反抗する国々は存在します。イラン、北朝鮮、ロシア、そして中国はその最たる例でしょう。しかし、それでも「連合」は欠如しています。つまり、どの国も部分的な協力はしつつも、基本的には個別に行動しており、対抗連合と呼べるほどの団結はしていないのです。
これに加えて不思議なことがあります。それは、中国やロシアへの対抗連合は形成されていることです。「対米包囲網」という言葉はあまり聞きませんが、「対中包囲網」という言葉はよく聞きます。
勢力均衡論に基づけば、潜在覇権国(将来的にすべての国を支配する勢力を持つ覇権国になるかもしれないほど強い国)の定義に当てはまるのはアメリカであるはずです。アメリカをこのまま放置していれば、やがて覇権国になって世界を征服してしまいます。本来であれば、世界中の国がこれを恐れるはずです。しかし、多くの国はアメリカを抑え込もうとするどころか、むしろ協力しています。
一見これは、勢力均衡論に矛盾しているように思えます。ただ、依然として勢力均衡論は間違っていません。なぜなら、間違っているのは「アメリカが潜在覇権国である」という前提だからです。要するにアメリカは「潜在覇権国」と呼べるほど強い国ではないということです。
戦争を「起こさなければならない」とき
むしろ、多くの国がロシアや中国への対抗連合を組織している事実は、ロシアや中国こそが潜在覇権国であることを示しています。だからこそ、ヨーロッパの国々はNATOを形成してロシアに対抗、東アジアでも日本、韓国、台湾、フィリピンなどが緩い協力体制を築いて中国に対抗しているのです。
そして、どちらの対抗連合にもアメリカは加わっています。
なぜ、最強の国であるはずのアメリカは恐れられないのか?
なぜ、アメリカより弱いはずのロシアと中国は最も恐れられるのか?
この疑問に答えるには、まず勢力が経済力や軍事力だけでは決まらないこと、加えて地理が国の勢力に多大な影響を与えることに注目する必要があります。
アメリカは太平洋と大西洋という2つの大洋に囲まれているため、他国に攻め込むのが地理的に難しい状態です。実際、第二次世界大戦後の戦争での勝率は約6割です。このため、中国やロシアのような大国は、アメリカから直接攻められる心配をそれほど深刻に考える必要がなく、結果として「対米包囲網」を作る切迫した理由がないのです。
特に、隣接する国同士の関係においては、地理的な近さゆえに互いの軍事力の増強が直接的な脅威として認識されやすくなります。
ここで国家をより身近な隣人との関係になぞらえて考えてみましょう。
あなたと隣人がお互いに相手よりも強くなろうとして、競争が発生する状況を想像してください。あなたと隣人は共に、相手が武器を増強することを警戒し、自らを守るために強くなろうとします。
ここで大事なのは、あなたと隣人のどちらも、相手を攻撃するつもりはないことです。あくまで両者は自分を守りたいだけであって、相手を攻撃しようとはしていません。それでもお互いに「攻撃されるかもしれない」という不安を元に、武器を強化せざるを得ません。
この状況を「安全保障のジレンマ」といいます。これは、ある国が自国の安全を高めることを目的として軍備増強をすると、不安を感じた別の国が同様に軍備増強をする結果、双方に攻撃をする意図がないにもかかわらず、戦争の可能性が高まってしまう現象です。
国家は本来、自らを守ることにしか関心がありません。戦争を起こす国が決まって「これは防衛戦争である」と宣言するのも、その国は本当に自国の防衛にしか関心がないからです。
どんな国でも、隣の国が急速に軍備拡大をすれば多かれ少なかれ恐れるものです。今日の中国と日本の関係は、この典型例です。中国は自らを守るために軍拡を行っているはずですが、日本は「中国に攻撃されるかもしれない」と考え、防衛力を強化しています。
ただし、安全保障のジレンマには「起きやすい場合」と「起きにくい場合」があります。つまり、規模的には同じ軍拡を行ったとしても、状況や性質によって、他国がそれを恐れる場合と恐れない場合があるのです。
これは、アメリカの世界における立ち位置を理解する上で重要です。なぜなら、ロシアや中国は安全保障のジレンマを他国と抱えやすい環境にいる一方、アメリカは最強の勢力を持つにもかかわらず、安全保障のジレンマを抱えにくい環境にいるからです。
攻撃が簡単なほど戦争は起きやすい
では、何が安全保障のジレンマの起きやすさを決めるのか? 要因には、主に次の2つがあります。それが、①攻撃・防御有利性と②攻撃・防御判別性です。
①攻撃・防御有利性 攻撃が簡単なほど、戦争は起きやすい
「攻撃・防御有利性」とは、ある国が自国の安全を確保するために、攻撃する方が有利なのか、防御する方が有利なのかを表す指標です。それぞれ、次のように定義されます。
攻撃有利
相手を攻撃する方が自らを効果的に守れる場合。
防御有利
相手の攻撃を受け止め、防御に徹する方が自らを効果的に守れる場合。
少々複雑なので、アメリカ社会と日本社会における銃の有無を例にして単純化してみましょう。
アメリカでは、一般人でも多くの人が銃を持っています。このような社会は攻撃有利といえます。なぜなら、銃撃をする側は攻撃を成功させやすく、銃撃をされる側はそれを防ぐことが困難だからです。
従って、アメリカ社会において最も有効な身を守る方法は、相手が撃つ前にこちらから先に攻撃する、つまり先制攻撃を行うことになります。
言い換えれば、自分を「守る」ための最善の方法が、相手を攻撃することなのです。よって、アメリカ人が銃を所持する目的は、「他人を攻撃するため」というより、「他人を攻撃することで自らを守るため」なのです。
一方、日本では一般人は銃を持つことが禁止されています。このような社会は、防御有利といえます。日本社会における効果的な攻撃手段は刃物です。しかし、もし誰かが刃物で襲ってきたとしても、走って逃げたり、棒や盾になるものなどを使って防御したりする余地があります(あくまで銃に比べれば、です)。
このように、銃がない社会では防御が有利になり、殺人が起きにくくなります。少なくとも、「自分を守るために相手を攻撃しよう」という考えには至りません。よって、日本での最善の自己防衛手段は、家の鍵をしっかり閉める程度になります。
銃がある社会では殺人が起きやすく、銃がない社会では起きにくい。アメリカ人も日本人も同じ人間であり、防衛本能に根本的な違いがあるわけではありません。しかし、そこに銃があるかないかだけで、合理的な自己防衛手段は変わるのです。
防御有利の世界では戦争が起きにくくなる
銃社会と同じで、国際社会も攻撃有利の場合には戦争が起きやすくなります。なぜなら、防御を強化しても相手の攻撃を完全に防ぐことが難しいため、国々は「自分たちが先に攻撃した方が効果的」と考えるからです。
この世界では「先手必勝」「攻撃が最大の防御」といった考えが重んじられます。このような状況では、戦争は「予防戦争」として始まりやすくなります。予防戦争とは、相手が強くなる前に自分から攻撃することで安全を確保しようとする戦争のことです。
また、攻撃有利の状況では国際協力が難しくなります。相手を騙して油断させたり、約束を破って相手の隙をついたりする方が、攻撃が成功する可能性を高められるからです。このような行動が当たり前になると、国々はお互いを信じられなくなり、約束を結ぶことが不可能になります。
さらに、国々は他国が隠し持っている攻撃力も心配するようになり、余分に武器を増やします。これが「軍拡競争」という状態です。軍拡競争では、どの国も「念のために相手よりも強い軍事力を持っておこう」と考えて攻撃力を高めていくため、戦争の可能性が高まるだけでなく、その規模も大きくなります。
一方で、防御有利の世界では戦争が起きにくくなります。防御力さえしっかりしていれば、相手の攻撃を防げるからです。また、相手も「攻撃は成功しないだろう」と判断して攻撃を諦めます。
例えば、相手が100発の攻撃用ミサイルをこちらに向けていたとしても、こちらが迎撃ミサイルを100発用意していれば、自らを十分守れますし、相手もそれを理解するので攻撃用ミサイルを撃とうとは思わなくなります。
また、攻撃が成功しにくいため、わざわざ相手を欺いてまで攻撃しようとしなくなります。これにより、国際協力も容易になり、平和を維持しやすくなります。
防御が有利だと、武器をお互いに減らす「軍備縮小」が進みやすくなります。特に攻撃用兵器(弾道ミサイル、爆撃機など)に意味がなくなるため、積極的に捨てようとする機運が高まるのです。
アメリカで銃犯罪が多いのは「銃があるから」ではない
②攻撃・防御判別性 「曖昧さ」は「強さ」よりも恐ろしい
攻撃・防御判別性とは、相手の行動が攻撃を意図しているのか、防御を意図しているのかをどれだけ明確に見分けられるのかを表す指標です。要するに、相手の意図がどれだけはっきりと認識できるかどうかです。基本的に、相手の意図がはっきりわかるほど戦争は起きにくく、曖昧なほど起きやすくなります。
今度は、アメリカ社会とスイス社会を使って簡略化してみましょう。どちらの社会でも一般人が銃を持てる点は同じですが、違うのは、薬物の蔓延度です。アメリカでは薬物依存症者が多いため、相手の意図の判別が困難ですが、スイスでは容易です。これがアメリカを危険に、スイスを安全にしています。
アメリカでは薬物依存症者が多く、他人が何を考えているのかがわかりにくくなります。これによって、誰かが銃を持っていたら、その人が攻撃するつもりなのか、ただ防御のために持っているのかがわかりにくく、人々が不安になりやすいのです。この不安から、さらに多くの人が銃を持たなければ安心できなくなり、連鎖的に銃所持が広がります。
アメリカの警察官が容疑者をその場で射殺しがちなのも、容疑者の意図がわかりにくい中で自らを確実に守るためです。アメリカの警察官は、容疑者に近づくときによくポケットの拳銃を握ります。
容疑者にいつ銃で撃たれるかがわからないので、銃を向けられたら即座に射殺するためです。昼よりも夜の射殺率が高いのも、視認性が低く、相手の挙動がわかりづらいからです。
一方でスイスでは、アメリカと同じくらい銃所持が一般的ですが、薬物依存症者がほとんどいない上に、銃所持には非常に厳しい取り決めがあり、その人に判断能力や犯罪歴があるかどうかが徹底的に管理されています。そのため、たとえある人が銃を持っていたとしても、その人が何を目的にそうしているのかが比較的わかりやすいのです。
スイスではアメリカと違い、銃乱射事件は皆無ですし、他人に銃で撃たれる不安もありません。アメリカで銃犯罪が多い理由は、単に「銃があるから」ではありません。真の理由は、「他人に銃撃されるかもしれない」と不安を抱かざるを得ないその社会状況にあるのです。
写真/shutterstock
外部リンク
- 〈トランプWHO脱退〉日本への影響は? 骨抜きの国際機関化で世界規模の格差拡大か「このままでは大きな混乱が生まれる」専門家が指摘
- 養老孟司が「自衛隊のいる後ろめたさ」がなくなるのは危険だと警鐘するワケ…中国に見る、規範を重視する伝統の重要さ
- イスラエル人とパレスチナ人がドキュメンタリー映画を共同制作した理由「パレスチナの問題は世界のニュースから消えていく。だからこそ…」
- ヒッピーがペンタゴンを包囲し、向けられた銃口に花を差した日…新宿まで広がったアメリカの反戦デモ「フラワー・パワー」と呼ばれた歴史的瞬間とは
- イスラエルメディアが自国の攻撃に異議を…パレスチナで民衆が殺されるほど、ハマスはより強大になる…イスラエルが即刻戦争をやめるべき理由
この記事に関連するニュース
-
ロシアがなんだかんだでしぶとさ保つ最大の武器 それは陸軍でも海軍でも、はたまた核兵器でもない
東洋経済オンライン / 2025年2月10日 15時0分
-
ロシアーウクライナ戦争が起こった歴史的な必然 「東欧を制する者が世界を制する」100年前の格言
東洋経済オンライン / 2025年2月5日 15時30分
-
だから習近平政権は海洋進出に執着している…「東シナ海も南シナ海もインド洋も欲しい」中国の本当の野望
プレジデントオンライン / 2025年2月5日 8時15分
-
ロシアの広い国土が「弱さ」の裏返しと言える根拠 西側と政治的に隔てられていても繋がっている
東洋経済オンライン / 2025年1月31日 18時0分
-
トランプ大統領は本当に日本から米軍を引き上げるのか…「遠い国の戦争」に首を突っ込む米国の真の狙い
プレジデントオンライン / 2025年1月24日 8時15分
ランキング
-
1「めっちゃうま!」セブンで買える、SNSで話題のスイーツ3選。贅沢気分に浸れる美味しさ。
東京バーゲンマニア / 2025年2月10日 18時3分
-
2「ドラマの衣装合わせで下着を脱がされ…」芸能界にあふれるひどすぎるハラスメント被害の実態
プレジデントオンライン / 2025年2月10日 7時15分
-
3西成「家賃2万7千円」ほぼ廃墟ハウスに住んだ結果 住人はほぼベトナム人、そこで見た驚きの光景
東洋経済オンライン / 2025年2月10日 8時30分
-
4海自の巨艦「いずも」本格的に空母化へ “改修中の姿”を捉えた画像が公開 かなり大がかりな工事に
乗りものニュース / 2025年2月10日 11時42分
-
5夫が「手のひらサイズの◯◯」を300万円で購入…結婚後に知ってしまった夫の“別の顔”
女子SPA! / 2025年2月10日 8時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください