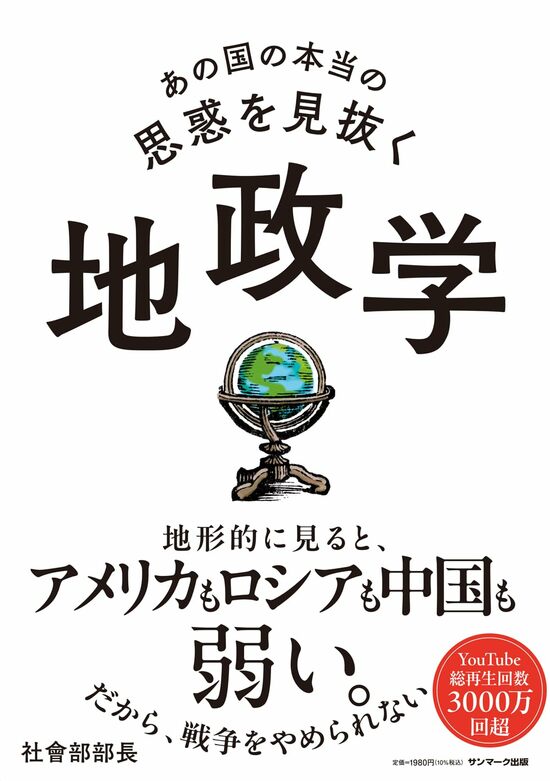第二次大戦後、アインシュタインも提案していた「世界から戦争をなくすただひとつの解決策」とは?
集英社オンライン / 2025年2月12日 7時0分
なぜ今もなお世界で戦争が起きるのか。この問いを理解するためには、「暴力を管理する権限」を持つ「警察」の不在という、国際社会の根本的な特徴を理解する必要がある。地政学動画で平均150万回再生を記録する社會部部長が、不変の地政学の法則を解説した『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
【画像】つい最近の日本でも、1位の企業に対抗するために2位以下の企業が協力して…
「世界の警察」は存在しない
世界からなぜ戦争がなくならないのか。この疑問にはさまざまな答えがあるでしょう。例えば、国と国との間に利害の対立があるから、宗教や文化の違いで争いが起こるから、歴史的な憎しみが続いているから、あるいは人は本質的に愚かだから、といった哲学的な理由まで考えられます。
しかし、ここでは少し視点を変えて考えてみましょう。なぜ、戦争が起きたときに誰も強制的に止めることができないのでしょうか? ここで鍵となるのは、国内社会と国際社会における、暴力への対応の違いです。
まず、日本国内での場合を考えてみましょう。日本国内で誰かが暴力を振るったら、すぐに警察がやってきて、その人を捕まえます。日本には「暴力を振るってはいけない」という法律が存在し、問題を話し合いで解決するよう人々は強制されます。
そして、もしこの法律を破る人がいれば、警察が力ずくで制止します。つまり、国内社会では警察が「暴力を管理する権限」を持っており、これのために警察以外の人による暴力を防ぐことができるのです。
では、これが国際社会ではどうでしょうか。もしある国が別の国から突然攻撃を仕掛けられたとしても、110番通報をして、警察が止めに来てくれることはありません。なぜなら、そもそも「世界の警察」なるものは存在しないからです。
例えば、2014年にロシアがウクライナのクリミア半島に侵攻したとき、ウクライナはなす術もなくクリミア半島を奪われてしまいました。欧米諸国はロシアを強く非難しましたが、ウクライナまで駆けつけて助けることはありませんでした。
軍隊は絶対になくならない
一応、「戦争を起こしてはいけない」という国際法は存在します。しかし、それをすべての国に強制する機関が、世界には存在しないのです。だからこそ、一部の国は「戦争を起こしても罰せられないだろう」と考え、問題を暴力で解決しようとします。
よって、世界から戦争をなくす究極的な解決策は、世界全体を1つの国にまとめ、単一の警察を作ることです。言い換えれば、「世界政府」を樹立し、世界全体をある国の「国内」にしてしまうことなのです。
世界政府ができれば、「この地球上で暴力を振るってはいけない」という法律を制定し、「世界警察」が違反者を取り締まることができます。実際に、アインシュタインは第二次世界大戦後に同様の提案を行いました。
「私が世界政府を擁護するのは、今まで人間が遭遇した最も恐るべき危険を除去する方法が他にはあり得ないからである。人類の全体的破滅を避けようという目標は、他のいかなる目標よりも優位でなければならない」(アインシュタイン『国際連合総会へ』より)
世界政府が無理ならどうするか
しかし、現実的に「世界の警察」が存在しない以上、国家は他の国から攻撃されたときには自分たちの手で自国を守らなくてはなりません。こうして、各国は「強い国」になろうとします。
少し想像してみましょう。もし日本に警察がいなかったら、あなたはどうするでしょうか? 暴力を振るわれても、誰も助けに来てくれません。泥棒に家財を盗まれても、誰も取り返してくれません。
このような状況下では、最悪の場合、あなたは生きていけません。究極的には、殺人すら誰も止めてくれないからです。そこで、あなたが自らを守るために取る方法が、今より強くなることです。例えば、武器を手に入れたり、家の防犯を強化したりすれば、暴力や泥棒から身を守れるでしょう。
ところが、ここで問題が生じます。もし隣の家の人が自分よりももっと強力な武器を持っていたら、どう感じるでしょうか? おそらくあなたは、不安になるでしょう。もし隣人の攻撃に遭えば、自らを守り切れないからです。
1つの国が強くなりすぎないように
そこであなたは、「隣人に負けないように、もっと強くならなければ」と考えて、より強力な武器を手に入れようと努力します。しかし、今度はあなたの行動を見た隣人も同様に「もっと強くならなければ」と感じます。こうしてあなたと隣人はどんどん強くなっていきます。
この競争が続くうちに、お互いに「これ以上の力は必要ない」と感じるときが来るかもしれません。それは、どちらも相手と同じくらい強くなり、相手が攻撃しようとしても自分も反撃できるくらいの力を持っていると認識するからです。
こうして両者が同じくらいの力を持ち、どちらかが攻撃してもおそらく失敗する、「力の均衡状態」が成立します。こうなれば、お互いに攻撃を仕掛けても意味がない状態が確立されます。
国家間でも同じような関係が成立します。人間や動物と同じく、国家は「生き残り」を至上目標とします。国際社会には警察がいないので、各国は強くなって他の国から自らの生存を守らなければなりません。しかし、周りの国々もそれに対抗して強くなり、力を均衡させようとします。この力が均衡した状態を「勢力均衡」と呼びます。
ここでいう「勢力」とは、ある国が他国に対して自らの意思を押し通す能力、要するに「国の強さ」を表します。一口に「国の強さ」といっても、完璧に測ることはできません。経済力や軍事力は良い指標ですが、それだけで勢力は決まりません。
例えば、日本は経済力でロシアを上回っていますが、ロシアより強いかというと、そうでもありません。ロシアは領土、人口、軍事力、その他多くの側面で日本を上回っているからです。とはいっても、世界には「強い国」と「弱い国」が確かに存在します。アメリカは明らかに強い国ですし、ニカラグアは明らかに弱い国です。勢力はこうした国の大体の強さを表します。
勢力均衡を全世界規模で保つために大事なのは、1つの国が強くなりすぎないようにすることです。1つの国が他の国よりも圧倒的な勢力を得ると、その国は他のすべての国を征服できるようになってしまいます。
世界征服を防ぐには
例えば、全部で4つの国がある世界で考えてみましょう。A国は10の勢力、B国、C国、D国はそれぞれ2、3、2の勢力を持つとします。すると、B国、C国、D国の勢力をすべて足し合わせても7しかなく、A国(10)に対する勢力は均衡しません。
こうなると、3か国がどれだけ力を合わせて対抗してもA国の攻撃を防げないので、世界はいずれA国によって征服されてしまいます。
A国のように圧倒的に強く、他のすべての国を支配する勢力を持つ国を「覇権国」と呼びます。覇権国の成立を防ぐことは「国際政治の鉄則」であり、古代から現代までどんな地域でも重視される普遍的な原則です。
古代ギリシャの歴史家ポリュビオスも、「我々は、単一の国家がその明白な権利についてさえ争うことを誰もが恐れるほど圧倒的な力を持つようになることに決して貢献してはならない」と述べました。
では、覇権国の成立を国際社会はどのように防ぐのでしょうか? その方法は、「潜在覇権国」を封じ込めることです。潜在覇権国とは、将来的に覇権国になるかもしれないほど強い国です。前の例に戻ると、仮にA国が6の勢力を持っていれば潜在覇権国と見なされます。B国、C国、D国の勢力7でまだ対抗できるものの、そのまま強くなり続ければいずれ覇権国になるからです。
国際社会では、他の国々が協力して潜在覇権国の勢力を抑え込もうとします。こうした潜在覇権国を抑えるための集まりを「対抗連合」と呼びます。諸国は手を組んで、潜在覇権国が覇権国になる前にその勢力を止めようとするのです。
どんな社会でも、潜在覇権国を対抗連合が抑える現象は起こります。例えば、戦国時代の織田信長に対する武田・上杉・毛利の反信長連合。この場合、織田信長は日本を統一する可能性が最も高い「潜在覇権国」で、武田・上杉・毛利はそれを阻止する対抗連合です。
中国の春秋戦国時代にも、強大な秦に対して韓・魏・趙・燕・楚・斉の6か国が連携する動きが見られました。第一次・第二次世界大戦においてドイツを封じ込めたイギリス・フランス・ロシア(ソ連)の連合、その後の冷戦でソ連を封じ込めた西側陣営、また、近年の中国に対抗するための台湾・日本・アメリカ・フィリピンの連携も勢力均衡策の1つです。
あるいは、ビジネスにおいてある業界の1位の企業に対抗するために2位と3位の企業が協力する動きも勢力均衡の一種です。このように、勢力均衡は人間社会において平和を維持するための普遍的な原則です。
写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「ロシアの軍隊と人民を支持」金正恩氏北朝鮮軍創立記念演説で
デイリーNKジャパン / 2025年2月10日 11時0分
-
アメリカは“世界最強の国”なのに「対米包囲網」が敷かれないのはなぜか…じつは中国やロシアほどは他国に恐れられていない本当の理由
集英社オンライン / 2025年2月10日 7時0分
-
ロシアーウクライナ戦争が起こった歴史的な必然 「東欧を制する者が世界を制する」100年前の格言
東洋経済オンライン / 2025年2月5日 15時30分
-
ロシアの広い国土が「弱さ」の裏返しと言える根拠 西側と政治的に隔てられていても繋がっている
東洋経済オンライン / 2025年1月31日 18時0分
-
トランプ大統領は本当に日本から米軍を引き上げるのか…「遠い国の戦争」に首を突っ込む米国の真の狙い
プレジデントオンライン / 2025年1月24日 8時15分
ランキング
-
1毎回洗うのは面倒…「羽織ったカーディガン」は何回目までセーフ? プロが解説、洗う頻度と注意点
まいどなニュース / 2025年2月11日 20時15分
-
2さっぽろ雪まつりが閉幕 232万人が来場
共同通信 / 2025年2月11日 22時37分
-
3トヨタ最新「ルーミー」に反響集まる! 「一気に昔の高級車っぽくなる」「レトロ感がたまらない」の声も! “高級感&渋さ”アップの「昭和感サイコー」な専用パーツとは?
くるまのニュース / 2025年2月11日 6時10分
-
4アウトドアブランドの「サコッシュ」おすすめ4選 1000円台から買える! コスパ抜群のミニサコッシュやノースフェイスのモデルなど【2025年2月版】
Fav-Log by ITmedia / 2025年2月12日 8時15分
-
5Q. 「睡眠時間が短いと短命になる」って本当ですか?
オールアバウト / 2025年2月11日 20時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください