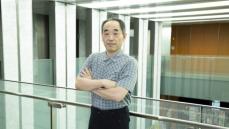“朝日新聞も私も「傲慢罪」という罪に問われているのだ――”
こんな印象的な書き出しから始まるノンフィクション『朝日新聞政治部』(講談社)が注目を集めている。早くも累計5刷・4万8千部を突破し、「2022年 Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」へのノミネートも発表された。
政治取材では「騙される方が悪い」!? 記者の仕事の実態とは
集英社オンライン / 2022年9月13日 11時1分
“朝日新聞も私も「傲慢罪」という罪に問われているのだ――”こんな印象的な書き出しから始まるノンフィクション『朝日新聞政治部』(講談社)が注目を集めている。早くも累計5刷・4万8千部を突破し、「2022年 Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」へのノミネートも発表された。同書のテーマの一つが「政治記者」という仕事についてだ。鮫島氏がかつて所属していた「政治部」とはどのような組織なのか? そして記者の仕事の実態とは? 注目のインタビュー、中編をお届けする。
同書のテーマの一つが「政治記者」という仕事についてだ。鮫島氏がかつて所属していた「政治部」とはどのような組織なのか? そして記者の仕事の実態とは? 注目のインタビュー、中編をお届けする。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
新聞記者が権力を批判できなくなる構造
――前編では朝日新聞社内の「社会部と政治部の派閥抗争」にも話が及びました。『朝日新聞政治部』では、新人記者はまず地方支局に配属されて、その後実績に応じてドラフトにかけられ所属先が決まるという話も書かれています。それでは政治部と社会部では、取材手法がまったく違うのでしょうか。
鮫島 うーん、まったく違うとも言えないかな。例えば政治部の官邸記者クラブと、社会部の司法記者クラブはある意味そっくりですよ。司法記者クラブは東京地検特捜部にベッタリで、政治部の官邸クラブは官房長官なんかにベッタリでしょう。
新聞社のダメなところは、記者が「遠くを批判する」んですよ。つまり社会部は捜査当局と組んで、見たこともない政治家を叩く。本来、自分たちが権力監視をすべき担当の警察や検察とは癒着しているんです。そして政治部は政治家と癒着して、単なる代弁者になってしまっている。
経済部では、一番のエースは財務省担当になります。だから経済部は財務省の味方。政治部は首相官邸の味方。社会部は警察や検察の味方。科学医療部は医師会や医者の味方。
こんなの反権力でもなんでもありませんよ。むしろ権力への加担でしょう。本来の記者や権力監視というのは、自分が監視している対象を激しく追及するのが仕事です。究極的には、記者は読者の味方なんだから。たとえどんな報復を受けようとも、自分が担当している持ち場の人をちゃんと監視して批判すべきです。
しかし現実には、みんなが取材先に食い込んで、べったり一心同体化して批判できなくなってしまっているので、自分とは直接関わりのない「遠く」の対象を標的にして批判した気になっている。この悪しき文化は昔から変わっていません。
――どうしてそんなおかしなことになってしまうのでしょうか?
鮫島 新聞記者は新人時代に全員、警察回りから入るから、そのDNAを引きずるんですよ。警察回りの実績で「こいつは無能、記者失格」というバッテンを人事評価でつけられたら、その後もずっとそのまま。警察回りで成功できるかどうかによって新聞記者人生が決まってくる面があります。
その警察回りの取材方法ですが、「夜討ち朝駆け」と言われるように、早朝から晩までとにかく警察官の自宅に足を運んで、未発表の捜査情報を聞き出すというものです。ここでは警察官にいかにペコペコしてすり寄り、気に入られてネタの「お零れ」をもらえるかどうかがカギを握ります。
他社を出し抜いて警察官の懐に飛び込み、どこも入手できていない「特ダネ」をもらえれば「優秀な新聞記者」の仲間入りです。もうこの段階から権力追及じゃなくなっていますよね。
そういう経験を積むもんだから、実は新聞記者というのは「他社に抜かれたら(=自分が入手できていない情報を先に出されたら)どうしよう」「ネタ元(情報源)に嫌われて各社の輪から仲間外れにされたらどうしよう」という心配ばかりで日々を生きるようになります。「今日は自分だけ外されて、各社で官房長官に会っていたらどうしよう」とかね。これでは権力側に主導権を取られてしまうのも仕方がない。
昔は国家権力の内部でも権力が分散していました。自民党でいうと、経世会や宏池会、清和会といった複数の派閥同士が激しく戦い、権力が分散していたから、互いに牽制し合う形で緊張関係が保たれていた。それぞれの派閥には担当記者が癒着していたんだけど、記者同士も互いに叩き合っていたから、なんとか批判が機能しているように見えただけの話です。
最近では第二次安倍政権以降、首相官邸一強になってしまったので、全員が首相官邸に頭が上がらなくなり、誰も批判できなくなってしまった。権力が一極集中したから批判が機能しなくなったというだけで、もともと新聞ジャーナリズムのあり方には欠陥があったんです。
――大手新聞社などによる記者クラブがもはや既得権益化しており、多くの問題を孕んでいることもしばしば指摘されています。
鮫島 記者クラブも本来は、情報を隠す当局に対して複数社が団結して当たることができるという、一種の団体行動を可能にするところに存在意義がありました。しかし、いまでは完全に当局側が情報コントロールをするための道具になり下がっています。
記者クラブは所属外の、例えば優秀なフリージャーナリストたちを締め出しています。それだけではありません。もう一つ重要なのは、司法クラブならば「ある新聞社の司法担当以外の記者を弾くことができる」という点です。
つまり朝日新聞だと、「社会部の司法担当以外の、他の朝日新聞記者を弾く」という重要な要素があるんです。事情は政治部でも同じで、政治部の担当記者以外は弾く。
結局のところ、自分にペコペコする担当のヤツだけにしか取材をさせないという情報コントロールの手先になっているんですよ。そして所属する記者たちはそんな閉鎖性の中に安住している。いまの記者クラブはどう見ても弊害の方が多すぎます。一刻も早く解体すべきだと僕は思います。
政治記者の鉄の掟 「騙されるヤツが悪い!」
――取材先に食い込んで情報を得る「アクセスジャーナリズム」という手法自体に限界があるのでしょうか?
鮫島 僕は決してアクセスジャーナリズムの全てが悪いとは思っていません。これも大事な手法のひとつです。大事なんだけど、極めて難しい。能力が無い人がやると、取材先に利用されて終わるだけですから。利用されたり中途半端になったりするぐらいならやらない方が良いんですよ。例えば記者会見だけに絞ってガンガン攻めるのも一つのやり方です。
僕は本当に能力がある人ならばアクセスジャーナリズムをやるべきだと考えています。なぜか。政治報道に関して言えば、政治家は状況が変われば言うこともコロコロ変わるんです。だから、その時その時でどういうことを言ったか、という記録を取っておくことが非常に大切になってきます。発言の変遷を見ることで、後から分析・検証ができるから。
つまり、別に政治家の取材って情報を教えてもらうためにやるんじゃないんです。その政治家を常にチェックするためにやると思っていた方が良いんですよ。それをみんな、勘違いしている気がします。政治家が言うことなんて8割は嘘ですから。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
――もとから「政治家は嘘をつくのが当たり前」と考えて取材をするんですね。
鮫島 そもそも、記者だったら「政治家が俺なんかに真実を喋るわけないじゃん!」と思わないといけないでしょう。でも、迂闊な政治記者ほど勘違いして、「●●さんがご飯をご馳走してくれた!」とか、「SNSで繋がってくれた」とか有頂天になって、認められたと大喜びするんです。
政治家が自分なんかとSNSをやっている暇なんてあるわけがない、単に情報操作しようと思って自分を利用しているだけだと、冷静に考えればわかりそうなものだよね。でも、人間なかなかそうは思えない。
政治取材の現場では、政治家の思惑もすべてわかったうえで、情報を取るのではなくて相手がその時に何を言ったかを見るため、つまり「嘘をつかせる」ために取材するようなことがあります。嘘からわかることもあるからです。わざわざ嘘をつくということは、何かを隠そうとしているわけだから。
そういう結構込み入った、相当レベルの高い駆け引きが必要なので、明確に向き不向きのある業界です。たとえどんなにピュアで誠実で立派な記者であったとしても、この世界では「騙された方が悪い」んですよ。嘘を見抜く力や洞察力が無いと、特に政治の世界でアクセスジャーナリズムに関わるのは難しいね。
――政治報道というのは、ある種の職人芸・達人芸の世界ですね。
鮫島 まさしく職人だと思いますよ。もちろん、非常に限られた世界の中での達人みたいなものに過ぎないから、別に偉いとかそういうことではないんだけど。
政治家と対等に渡り合うためには、自分の見方に自信を持って相手のことを客観視できないとダメです。政治家は偉い人だ、なんて思って見上げているとすぐに利用されて騙されちゃうから。すり寄ろうとしているうちは絶対に騙されますよ。政治家は基本的に人たらしですからね。人当たりも良いし、本当に魅力的な人が多いから、普通に近づいたら簡単にやられます。
記者にとっての「天国」をつくろう!
――そんな従来型のアクセスジャーナリズムから一線を画して、縦割りや担当範囲、ルーティン取材をなくし、調査報道(独自調査によって問題を発掘・報道していく手法)に特化した「特別報道部」をつくったという話も『朝日新聞政治部』には書かれています。これはかなり革新的だったのでしょうか。
鮫島 斬新な試みだったと思います。「週刊文春」の元記者だった松田史朗さんのアイデアがとても参考になりました。もともと、記者の仕事を息苦しくつまらないものにさせている要素を全部取り除いて、記者にとっての理想の職場をつくろうと思ってできた部署だったからね。幸い、当時は社内的にそれなりに力があったから実現できたわけだけど。
さっきも説明したように、記者は常に担当範囲が決まっていて、常に仲間外れを恐れているセコイ仕事になってしまっているんですよ。それはおかしいでしょう。別に、他社がすべて書いているネタを独自判断であえて載せなくても良いわけですから。
持ち場とノルマがあるために他社に「抜かれる」恐怖に怯えるんだったら、そもそも持ち場やノルマをなくしてしまえばいい。年功序列も会議も、そういう新聞記者の仕事を面白くなくさせているものを全部やめて、記者にとっての理想郷をつくろうと思ったんですよ。
ルールは「大スクープしか狙わない」という、ただそれだけ。外れがあっても良いと思っているんですよ。中途半端なものを集めてもしょうがないから。一個、特大ホームランが出ればそれだけで十分だと思って。
1年間で成果を上げられずに1本も原稿を書かなくても悪い評価はつけないし、元の部署に絶対に人事で戻す、一切心配するなと約束しました。上司からの仕事の発注もないし、会議もない。
あと二つ重要なのは、キャップとデスク。企画発案者がキャップ(チームリーダー)になれる。この部署ではチームをつくらないので、年功序列も関係ない。たとえ1年目でもキャップになれる。
仲間については、欲しければ発案した人間が自分で口説いて募るという風にしました。先輩でも後輩でも関係なく、一緒にやろうよと。誰も乗ってきてくれなければ、たぶんそのネタが面白くないんだろうということで(笑)。
そうするとそのうち、自然発生的にチームができるんだよね。「この話、面白そうだから協力しよう」といって、個々の記者が自発的にテーマを選んで取り組むようになってくれた。
そして、これは絶対にやった方が良いと思って僕がこだわったのが、記者がデスクを選べる制度。普通、デスク(上司)って一方的に決められちゃうでしょう。「お前はこのデスクの班」って。僕はその制度が大嫌いだった。だから完全自由競争制にして、デスクを記者が自由に選べるようにしました。ただしデスクの側にも拒否権があって、お互いの希望が一致しなければならないということで。
デスクは僕も含めて4人いるから、4人に拒否されたらそもそもネタが面白くないんだろうと。でも、良いネタで一生懸命口説けば、1人くらい関心を持つはずだということでね。
……ということでやってみたら、もうみんな働く働く!
――「減点法」や「強制」という発想をなくしてしまったんですね。
鮫島 最初は戸惑う記者も多かったですよ。記者って、基本的に発注されたことをそつなくこなす天才ですから。普通、新聞記者はみんな記者クラブに所属していて、朝起きたら記者クラブに行って発表を取材したり、あるいは担当の政治家とか役人がいるから、朝回りで行く場所が決まっているんです。
でも、特別報道部ではいっさいのノルマもない。朝起きて毎日が自由で、何をしても良い。「会議もないから、別に会社に来なくていいよ。家で寝ていてもいいから」って僕は言いましたからね(笑)。
――究極、寝ていてもいい(笑)
鮫島 映画を観に行ってもいい。ネタはどこに転がっているかわからない。なんならパチンコに行っても良いよ、何やっても良いよ~って言ったら、もう最初の1か月や2か月ぐらいは不安で仕方がなくて、何をしていいかわからない、ノイローゼになりそうだっていう人がいっぱいいました。
それは記者の仕事が「与えられた課題をこなす」ことばかりになっちゃっているから。10年も20年もそういう仕事をしてきているからですよ。いま新聞が面白くない原因もここにあると思っています。起きたことを傍観的に書くことばかりやっているから、自分はこれを伝えたいという情熱が無いんだよね。だからどこかつまらないんだと思う。
夢の「特別報道部」はなぜ廃止されたのか
――実際に、特別報道部は福島第一原発作業員の「被曝隠し」報道、そして「手抜き除染」報道(いずれも2012年)など、華々しい成果を挙げていきます。読者の期待にも応えられていたと思います。
鮫島 自分たちの関心に基づいて取材を進め、「火のないところに煙を立てる」ようなスクープをつかんでいく。まさに調査報道の醍醐味だね。あの頃は本当に楽しかったですよ。
――しかし鮫島さんの退社後、朝日新聞社では2021年春に特別報道部は廃止されてしまいます。
鮫島 まず前提として、調査報道には2パターンあることを整理しておきましょう。社会部をはじめ、どの新聞社も昔から取り組んでいる調査報道というのは「当局一体型調査報道」というもので、警察や検察、国税といったところからネタをもらって報道するやり方です。
その背後には捜査当局など、情報を流す側の思惑があります。例えば、国税が自分で摘発するだけだと弱いとか、マスコミが世論を喚起してから動いた方が良いというパターンだね。新聞社も独自取材を付け加えるけど、しょせんは利用されているだけなんですよ。
こういう要素を覆すためにつくられたのが特別報道部だったんです。記者が主体的にテーマを決めて、誰も知らないネタに向かっていき、隠された事実を明るみに出す。これがもう一つの調査報道のパターンだね。
もともと、新聞社では当局依存型ではない調査報道というのはほとんど存在しませんでした。社会部は警察を、政治部は首相官邸を、というように、それぞれの部局が担当を決めて張りついて、というやり方が普通だから。主体的にテーマを決める調査報道というのは、実は新聞社にはそんなに根付いていなかった。
それでも、ときどき天才的な記者がいて、個人の能力でやり遂げてしまうことはあったんだけど、あくまでそれは個人芸だったんですよ。
――当局依存型ではない調査報道はお金も時間も、そして根気も要りそうです。
鮫島 フリーのジャーナリストで調査報道を続けておられる方がいますけど、本当に頭が下がりますよ。僕も組織を辞めたら調査報道だけはできないと思った。個人でやるにはあまりにも割に合わないから。本当は組織ジャーナリズムが担うべき最後の仕事だと思うんだけどね。
――現状の新聞では、調査報道に特化した成果を期待するのはやはりもう難しいのでしょうか。
鮫島 特に朝日新聞を見ていると、もうそういう活力が無いですね。「吉田調書事件」がきっかけになって、いまの朝日新聞社では、ちょっとでも問題を起こしそうなことはやめてくれという「リスク回避」の空気が蔓延しています。抗議を受けて失敗したら大変なことになるから、リスクを背負って危険な調査報道をやろうという意欲はありません。むしろ、ややこしいネタを持ってくるな、損をするだけだ、という感じじゃないかな。残念なことですけどね。
――調査報道の継続が難しくなってしまった新聞には未来があるのでしょうか。次回は、新聞や政治報道のこれから、そして“SAMEJIMA TIMES”の新たな試みについてもお話を伺えればと思います。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
(文責:集英社新書編集部/撮影:野崎慧嗣)
関連書籍
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
喧嘩の弱い、遊びを知らない「優等生」の話など誰も聞きたがらない…新聞・テレビの「正論」が皆つまらない理由
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分
-
どんなクソつまらない仕事もマシになる…新聞記者が「8時間立っているだけ」の仕事を面白くした方法
プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分
-
かつて野中広務が田原総一朗に渡そうとした裏金の額とは?「いいお茶を渡したい」喫茶店で渡された紙袋の中には100万円の封筒がひとつ、ふたつ…
集英社オンライン / 2024年6月26日 8時0分
-
新田哲史 東京都知事選・大情報戦を斬る! 魅了した石原慎太郎知事…失われた「政治とメディアの真剣勝負」 都庁番記者は外注のテレビ局 都政関係者に舐められる悪循環
zakzak by夕刊フジ / 2024年6月26日 6時30分
-
なぜ「政治とカネ」を追求されても岸田政権は倒れないのか…「マスコミの傲慢」を生んだジャーナリストの功罪
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 8時15分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
31年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分
-
4湿気が多いこれからの季節に役立ちそう…警視庁が紹介する「跡が残らないヘアゴムの結び方」
まいどなニュース / 2024年6月30日 20時30分
-
5若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください