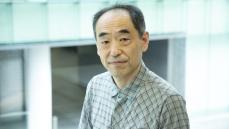“朝日新聞も私も「傲慢罪」という罪に問われているのだ――”
こんな印象的な書き出しから始まるノンフィクション『朝日新聞政治部』(講談社)が注目を集めている。早くも累計5刷・4万8千部を突破し、「2022年 Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」へのノミネートも発表された。
選挙報道はもっと面白くできる! “SAMEJIMA TIMES”の挑戦
集英社オンライン / 2022年9月13日 11時1分
“朝日新聞も私も「傲慢罪」という罪に問われているのだ――”こんな印象的な書き出しから始まるノンフィクション『朝日新聞政治部』(講談社)が注目を集めている。早くも累計5刷・4万8千部を突破し、「2022年 Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」へのノミネートも発表された。同書を上梓した鮫島浩氏は新聞をはじめ、現在のメディア状況や政治報道をどう見ているのか。そしてこれからの活動の展望とは? 注目のインタビュー、後編をお届けする。
同書を上梓した鮫島浩氏は新聞をはじめ、現在のメディア状況や政治報道をどう見ているのか。そしてこれからの活動の展望とは? 注目のインタビュー、後編をお届けする。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
新聞社は一度滅びた方がいい
――率直に伺います。これからの新聞が何らかの形で魅力化を図ったり、方針転換を試みたりすることで生き残っていくのは難しいと思いますか?
鮫島 紙媒体に関して言えば、もう無理でしょう。大抵の方が感じていると思いますが、日々のニュースを伝える媒体として、紙という手段ではネットにはどうやっても勝てません。
まず、スピードでは絶対に無理。紙の新聞ではどんなに頑張っても、前日に起こった出来事を翌日に報じることしかできない。
さらに内容、深さの点でも無理なんですよ。ネットだとグラフが表示できたり、映像が流せたりするけど、紙だとそれもできない。つまり、早さも深さも幅広さも劣る。関連情報に飛ぶこともできない。これではもう、「ニュースを伝える」という機能ではネットに負けるしかないんです。
いま新聞だけを読んで世の中全部を知る人なんていないですよね。ちなみに私、辞めて1年が経ちましたが、朝日新聞は読んでいません(笑)。でも何も困らない。いまでは色んな情報に接しながら自分の頭で考えていますね。インターネット上には情報がタダで存在しているから、情報収集能力があれば困ることはありません。
それなのに、いまだに新聞は「新聞さえ読めば文学から人生からスポーツから芸能まで、全世界のことがすべてわかる」というつくりをしています。結果、どれも中途半端なんですよ。そんなものに商品価値がありますか?
紙媒体の良いところは何度も読み返してもらえるとか、読んで感動したらしばらく飾っておいてもらえるとかいった点にあります。本だと「だいたい何ページのあの場面」といった分量的な感覚も記憶に残りやすい。そういう物体ならではの効果があるので、本はある種の高級品として残ると思うんですよ。
でも、それは本だからこその話。デジタル情報と違って思いを込めたり、自分で色々と書き込みをしたりして、読んだ跡が刻まれる。そういう形で個々の人にとって「大事な一冊」というのは残ると思うけど、日々のニュースはそんなことあり得ないですよね。
――新聞社の中で蓄積されている取材のノウハウや裏取りの技術などは、ネット時代でも重要なスキルだと思うのですが。
鮫島 僕もそう思います。新聞という媒体はいずれ滅びると思うけど、ジャーナリズムは滅びないでしょう。何らかの形では残っていかないといけないし、恐らく残るはずです。
いまのところ、少なくとも日本社会ではジャーナリズムのかなり多くの部分を新聞が担っているのは事実です。その取材のノウハウや経験、蓄積にしても、悪い部分も含めて、新聞社が一番持っている。
個々の新聞社や記者が持っているノウハウをオープンにして、社会に共有して、ジャーナリズムを新しい形で発展させていこうと動いているならば、まだ頑張って欲しいと思います。でも、いまの新聞社はジャーナリズムをなんとか再建しようとか、弱ってきてしまったジャーナリズムをこれからもう一度強くしようというところに力を入れてはいません。
むしろ、もはやビジネス的に終わっている新聞媒体を含めた「新聞社経営」をなんとか盛り返すために、必死で喘いでいる状態です。結果的に、財産である取材ノウハウを痛めつけ、記者の活動や自由を奪い、管理・統制を強めながら、なんとか新聞社経営を維持して「延命」を図ろうとしているという最悪の状況なんですよ。
自分の生き残りばかり考えて、首を絞めているくらいなら、もう新聞社が日本社会に存在する意味は無い。むしろ害悪です。いっそのこと早く潰れてしまって、新聞社という枠組みの中で自由を奪われて苦しんでいる人が野に放たれてしまった方が良いんじゃないですか。
それぞれの記者は生活が大変になるかもしれないけど、一度そこまで追い込まれてしまった方が、日本のジャーナリズムは再活性化して一挙に元気になる可能性があると思います。
いまは正直、ネットメディアの方が頑張っているけど、やっぱり質という点で見れば新聞記者の方が情報や経験を持っています。でも、彼らは新聞社という枠組みに縛られていて自由に書けない。本当にもったいないんですよ!
時代はYoutube、ライバルは中田敦彦!
――鮫島さんは朝日新聞社に所属していた頃から個人での情報発信を積極的に行い、いまでは“SAMEJIMA TIMES”というウェブサイトを運営されていますね。
鮫島 高齢者層は別として、もう「NHKが言っているから」「朝日新聞が言っているから」という信用はだいぶ落ちてきています。発信者の顔が見えないと信用しづらくなっている。参考資料として複数の意見を比較しながらものを考えよう、という人も増えてきているし、この流れはますます強まってくると思います。
だから、結局は誰が責任を負うかという時にも、「朝日新聞が責任を負います」「NHKが責任を負います」という時代はもう終わりつつあって。「私が責任を負います」「私が説明します」という風に言わないと、みんな信用してくれないんですよね。
これは良いことだと思います。インターネット革命のおかげで情報も双方向になった。それに対して新聞やテレビというのは一方的に「これを読め」「これを観ろ」と押し付けていく旧時代の媒体です。もうそんな時代は終わっていて、誰もが発信できる環境になったので、テレビ・新聞は明らかに負けているんですよね。
僕もウェブサイトを運営しながら、最近はYoutubeに一番力を入れています。目標となるライバルは読売新聞や朝日新聞じゃなくて、中田敦彦だと思っていて。彼のチャンネル登録者数は朝日新聞の購読者よりも多いですから。
――もう新聞社はライバルではないと(笑)。
鮫島 いま僕のチャンネル登録者数が2万人ぐらいで、「中田敦彦のYoutube大学」は500万人近くだから、もうボロ負けなんだけど(笑)。まあ目標はあくまでも大きく、というね。
でも本当は文章を書くのが一番好きなので、動画も出しながら書いた記事の発信と両方やっていきたいなと思っています。
――SAMEJIMA TIMESはどういう読者が多いのでしょうか。
鮫島 結構色々ですね。僕の専門が政治報道だから、記事は政治がメインですけど、マスコミの裏話なんかも定期的に載せています。嬉しいのは、意外と海外の日本人が多いんですよ。ヨーロッパやアメリカ在住の読者が増えています。
海外で暮らす方は日本の情報を知りたがっている。でも、日本のマスコミ報道を見ても何が起こっているのか全然わからない。それで調べてSAMEJIMA TIMESにたどり着いてくれるらしいですね。
新聞記者の時は読者との直接のやり取りはほとんどなかったけど、SAMEJIMA TIMESには寄付をくれる方もいるし、意見を遠慮せずにガンガン言ってくれる人も多い。読者とのやり取りが普段からかなりあるんですよ。私も迷っている時は皆さんの意見を聞きながら考えを変えることも多いですね。
これこそが本当の双方向性だなと思っています。だから、忙しくても読者の意見だけは必ず自分で見るようにしています。新聞では全くできていなかったことですよね。朝日新聞社に電話したら「お客様コールセンター」に繋がって、その部署の人が電話で聞いて終わりですから。
それじゃやっぱりダメですよ。やっぱり書き手が自分で読者の声を聞かなきゃ。本当は編集局長がお客様コールセンターで応対しろよ、って話なんですよ。僕はいまそれを自分でやっていて、楽しいですよ。その代わり、朝日新聞時代よりも忙しいけどね。休みも無いし、ブラック企業になっているわけだけど(笑)。
自分が正しいと信じていることであれば、堂々とやっていけば良いわけで。信念を貫いていけば、批判する人もいるけど、応援してくれる読者もいっぱいいます。応援してくれる読者にちゃんと自分の信念をブレずに示し続けていれば、その人たちは離れないでしょうから。
それは日頃からやり取りをしていて信頼関係があるからこそ。それがある限りはあまり怖いものが無いので、楽しいんですよ。これが本当のジャーナリズムだと思います。
安倍元首相暗殺事件が真に問いかけること
――7月に行われた参議院議員選挙についてもSAMEJIMA TIMESでは積極的に発信されていました。
鮫島 参院選はもともと自民党が勝つと言われていたけど、安倍元首相の暗殺事件は驚きましたよね。
――投票日2日前の7月8日、奈良市で応援演説を行っていた安倍晋三元首相が銃撃され、命を落とすという事件がありました。
鮫島 僕がこの事件の余波で心配していることがあります。安倍さんのシンパが彼の功績を称えて、国葬をはじめ、神格化・英雄視するという動きに出ているでしょう。対してアンチは統一教会と自民党の話を突くばっかりになってしまっている。
確かに、統一教会と自民党の問題も大事ですよ。カルト宗教の社会的問題も重要なテーマだし、自民党が統一教会にどんな影響を受けてきたかを暴くのも大切。だけど、もうひとつ絶対に忘れちゃいけない論点がある。残念ながら、そこが完全に見落とされている気がしてなりません。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
――その論点とは何でしょうか?
鮫島 それは現在の日本社会を覆う格差社会と貧困の問題です。
貧乏人育ちだからよくわかります。貧しい人や苦しい人にとって、イデオロギー的に右も左もありません。もう30年間も不況が続いて、ただただ苦しいだけだから。
僕も母子家庭で育ったけど、それでも僕の世代は奨学金も軽くもらえたし、アルバイトもいっぱいあったんですよ。どん底から這い上がったやつもいっぱいいる。いま思えばまだ楽だった。
でも、安倍さんを銃撃した山上徹也容疑者の世代はロストジェネレーションで、かなり厳しい家庭環境だったのに、いくら頑張っても這い上がれない格差の固定化みたいな状況になってしまった。そうなると絶望しかないんだよね。
本当はどんな親のもとに生まれようが、どんなにおかしな家だろうが、親は親で子は子だから。たとえどんな親であっても子に責任はないから、どんな環境でも子どもは堂々と生きていける社会にするというのが、本来は政治の一番の役割ですよ。
そこに思いが至らずに、「安倍さんは素晴らしい、かわいそうだ」「いや、統一教会はひどい、自民党との関係を追及せよ!」という二極化した論争が起こっている。そうじゃなくて、僕は現状の貧困・格差固定社会こそが問題の本質だと思うんですよ。一回落ちると這い上がれない歪んだ社会。この社会的要因にメスを入れて取り除かない限り、また同様のことが繰り返されるかもしれないという悪い予感があります。
山上容疑者みたいな追い込まれてしまった苦しい人は、恐らく日本にはいっぱいいます。そういう人は怨念を抱いていますからね。「なんで俺だけ割が合わないんだ」って思っているはずですよ。
大学時代、僕でさえ思ったことがありますから。うちは母子家庭で貧乏だったので、家賃が月に1万円ぐらいの下宿に入ったら、部屋にはトイレも水道も無くって。京都の冬はかなり厳しいのに、外で歯を磨くようなところで1年過ごしたからね。
それに比べて友達はみんな家賃6万円とか7万円のお風呂付きワンルームマンションみたいな物件に住んでいて。なんなんだこの格差は、あまりにも理不尽で割に合わないな、って驚きましたよ。幸い、当時はアルバイトがいくらでもあったから、必死に働いて引っ越すことができたけど。
いまでは東大・京大に通う学生の親の平均年収が高くなって、ある程度のお金持ちじゃないと東大・京大には行けなくなっているでしょう。階層格差が固定した時代なんですよ。そういうことを考えると、やっぱり格差問題・貧困問題こそが本当は参議院選挙の最大の焦点であるべきだった。実際に貧困を背景とした大事件が起きてしまった。
でも、ほとんど誰もそこに目を向けようとしていない。安倍元首相暗殺事件がこのまま「単なる山上容疑者の個人的な恨みによる犯行」で片づけられてしまうと、ちょっと怖いね。
――メディアの分析もピントがずれているのでしょうか。
鮫島 メディアの人間たちも「上級国民」だからね。メディアは「右か左か」ばかりで考えるからダメなんです。「上下」で考えないと。貧乏人は右にも左にもなります。正直、イデオロギーなんてどっちでも良い。ただ辛いから。そんなの考える余裕もないから。とりあえず恨みを募らせているんですよ。
だから貧困をまず問題にして解決しないといけない。でもメディアの人間たちは本気で弱い人の立場に立つことができていない。自分たちが恵まれた環境にあるからだと思うんだよね。
れいわ新撰組と山本太郎を支持する理由
――メディアに限らず、「格差と貧困」の問題に目を向ける政党や政治家は少ない気がします。
鮫島 立憲民主党なんかもエリートの集団だからね。立憲民主党の人気が無いのは、エリートだと思われているからですよ。しょせん体制側の「エスタブリッシュメント」だろうと。
でも、本当は苦しい立場にある国民に寄り添うのが野党の役目でしょう。左右対決をやっているうちは楽なんですよ。憲法が云々とかね。確かに憲法の議論も大事だけど、普通の人はそんなに興味が無いからさ。もっと自分の暮らしを何とかしてよと思っているはずです。
いま自民党と野党の大半が繰り広げているのは、ただの空中戦に過ぎません。単なるエスタブリッシュメント同士の、右と左のプロレスみたいなものです。
そんなことより、生まれながらにしてこんなに差があるのっておかしいでしょと。ただ生活していくだけなのに、こんなにお金がかかっちゃって生きていけない。本当に追い込まれてしまっている。日々そういう矛盾を感じて生きている人たちが、エスタブリッシュメント同士の左右イデオロギーの喧嘩を見せられたってシラケるのは当然で。これじゃあ、いつまで経っても投票率50%のままですよ。
経済が落ち込んだのに社会保障が整備されていないから、不幸な人はどんどん不幸になる。一方で、恵まれた環境に生まれた人はそれに思いが至らない。そしてそういう人たちが政治家になり官僚になり記者になっていく。最悪だよね。
どんな家に生まれたって堂々と生きていける。そういう社会を実現することこそが本来は政治の役目のはずなのに。
――その観点で見ると、れいわ新撰組は目線が他と違うと感じました。「消費税廃止」というあまりにも大胆な公約を掲げていることでも注目を集めています。
鮫島 党首の山本太郎がすごくしっかりしていますよね。象徴的なのが、舩後靖彦さんや木村英子さん、天畠大輔さんを候補者に立てたことです。色々と文句を言う人もいるけど、僕は立派だと思っています。あれも一つのメッセージであり、シンボルなんだよね。まさしく「誰一人見捨てない」という理念を形にして見せているわけですよ。
どんな人も見捨てないというのは、言うのは簡単だけど実際には大変です。それを正々堂々と掲げて実行に移すのは素晴らしいと思いますよ。僕はずっと政治記者をやってきたけど、そんな政党はちょっと記憶にありません。
いまのような暗い時代には、「どんなことがあっても安心していこう」「あなたのことは絶対に見捨てないよ」というメッセージこそ、政治が最も出すべきものでしょう。この最も大事なメッセージを、一般の人に響く言葉できちんと表現できているのはれいわ新撰組です。
まだまだ未熟な政党です。僕から見るとわかっていないところも多いなあと感じるし、弱い点は沢山あるんだけれども、熱意よし、意気込みよしと思っていて。一般の人たちの立場に寄り添い、従来の政治を変えようとしている。異質な政治家・政党が出てきたなと感じていますし、野党の中では「化ける」可能性は山本太郎が一番高い気がします。
ボランティアとか、エネルギーがすごいですよ。利権も無いのに、あんなに熱量のあるボランティア団体は見たことがない。
政治報道はもっと面白くできる!
――SAMEJIMA TIMESではれいわ新撰組支持を明確にしたうえで発信をされています。従来の新聞報道とはまったく違うスタンスですね。
鮫島 アメリカで言えば、例えば「ニューヨーク・タイムズ」紙は民主党支持を鮮明にして政治報道を行っています。欧米ではメディアが選挙前に支持政党を表明するのはそんなに珍しいことではありません。むしろ日本が異常なんです。
なぜ日本のメディアは「客観・中立」を旗印にしてきたのか。ただ単に文句を言われたりトラブルに巻き込まれたりしたくないという、ことなかれ主義でしかありません。そもそも「客観・中立」という看板自体が嘘にまみれています。「客観」なんてあるわけがないでしょう。何を取材して取り上げるか選択した時点で、すでに主観が入りこんでいるんだから。
わざわざ嘘をついて防波堤をつくるのは、争いごとや面倒に巻き込まれないようにしているだけです。そういう嘘つき選挙報道にずっと加担しきたことに、内部の人間として忸怩たる思いがあったんですよ。それでいて投票率が上がらないって嘆くけど、そりゃ選挙報道がつまらなければ上がらないのは当然であって。
なんでつまらないのかといえば、傍観的・解説的にものを言うからです。野球観戦の時に、野球に興味が無い人にいきなり客観・中立的に解説をしたって面白くもなんともないでしょう。例えば巨人・阪神戦を観ながら、「1球目、インサイドのシュートで体を起こしました。2球目は外角のスライダーで泳がせて三塁ゴロに……」なんていくら言っても、野球を知らない人からすると「うーん……なんなんだ?」としか思わない。
いまの選挙報道ではそういうことをやっているわけですよ。それなのに「政治に興味を持ちなさい」「若者が選挙に行かない」って、行くわけないじゃん。
――確かに、政治報道は「面白くない」というイメージがある気がします……。
鮫島 じゃあどうすれば面白くなるか。野球なら贔屓の球団とか選手ができて初めて応援に熱が入るんですよ。「巨人頑張れ」「阪神頑張れ」ってね。サッカーのワールドカップだって自分の国を応援するから興奮するわけでしょう。
政治も同じで、まずは贔屓の政治家とか政党ができたら興味を持つはずです。「山本太郎、ステキ!」とか。きっかけはかっこいいとかかわいいとか何でも構わないんですよ。応援し出して初めて、「なんでこの人、こういうことを言っているのかな」「この政策ってどういう意味かな」と興味が出てくる。好きな人がいるからこそ学ぼうと思うわけで。
まずは報じる側が立ち位置を鮮明にして、「俺はれいわを応援するぞ!」と発信する。「ジャーナリストなのに肩入れしやがって」と言われることもあるでしょう。それでも構いません。「山本太郎を応援します!」って言うだけでなんとなくちょっと面白いじゃん。なんでこの人、こんなことを言っているんだろう。なんでれいわ新撰組を支持するのか。気になりますよね。
それで興味を持ってくれた人はれいわのことを勉強し出すし、場合によっては共感してビラを配り出すかもしれない。そういう風にして初めて興味を持って、選挙に参加してくれるようになる。
家でテレビを観ているよりは、甲子園のスタンドに行って黄色いメガホンを振っていた方が面白いに決まっています。同じように、家でただ選挙報道を見ているよりは、街頭で一緒にビラを配ったりする方がきっと面白いはずです。
だから7月の参議院議員選挙では、実験も兼ねて自らの立ち位置を鮮明にして、「俺はれいわを応援します! みなさんも一緒に応援しましょう」と呼びかけてみました。理由を聞いて賛同してくれる人は一緒に応援してくれても良いし、おかしいと思う人は他の政党を支持してもらっても良い。その方が選挙を考えるにあたって材料提供としての意味があると思ったから。
――選挙報道としては挑戦的な試みですね。従来のマスメディアでは難しいかもしれません。
鮫島 新聞やテレビは腰が引けて絶対にできないでしょう。SAMEJIMA TIMESは個人運営の超・弱小メディアなので、大メディアが絶対に追いつけないことをやらなきゃいけませんから(笑)。
でも、ここにたぶんこれからのヒントがあるんだと思います。書き手のスタンスがはっきりしていた方がむしろフェアだと思いますし。
最近もれいわ新撰組とは関係のない、自民党や立憲民主党に関する記事をいくつも公開しているけど、読む人は「鮫島はれいわを支持している」とわかってくれていて良いんですよ。自分としてはちゃんとデータと論理に基づいて、説得力をもって書いたつもりだから。「こいつはこういう立場から見ているんだ」とわかる方が、読む側からしても安心でしょう。
別に僕の記事だけを読んで判断する必要はありません。あくまでも考える材料のひとつとして見てもらえれば本望です。
賛否の声はたくさん届いています。皆さんの評価をいただいたうえで、SAMEJIMA TIMESが一石を投じる形になって、政治報道のあり方をめぐる議論が広がっていき、新しいジャーナリズムの形を再建するための材料になれば良いなと考えています。

ジャーナリスト・鮫島浩氏
(文責:集英社新書編集部/撮影:野崎慧嗣)
関連書籍
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【逆説の日本史】最近世間を騒がせた二つのトピックス「高野連の発表」「大東亜戦争の呼称」について考察しよう
NEWSポストセブン / 2024年6月24日 16時15分
-
自民・田村憲久氏 党内からの岸田首相退陣論に「政策論争はいいが、けなし合いは…言うなら直接本人に」
スポニチアネックス / 2024年6月23日 15時2分
-
〈郵政民営化の恨み?〉「絶対に政治をやってもらっては困る人がいる…それは小池百合子」元自民・小林興起氏が都知事選立候補見送りで田母神俊雄氏を支援。田母神氏は「国民は騙されているんです」と経済政策をアピール
集英社オンライン / 2024年6月18日 8時0分
-
なぜ「政治とカネ」を追求されても岸田政権は倒れないのか…「マスコミの傲慢」を生んだジャーナリストの功罪
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 8時15分
-
立憲・岡田克也幹事長 衆院解散見送り報道にも警戒緩めず「ゼロとは言えない」
東スポWEB / 2024年6月4日 19時30分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
31年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分
-
4湿気が多いこれからの季節に役立ちそう…警視庁が紹介する「跡が残らないヘアゴムの結び方」
まいどなニュース / 2024年6月30日 20時30分
-
5若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください