民間保険は本当に必要?病気やケガに備えて保険制度の確認を
トウシル / 2025年2月4日 7時30分
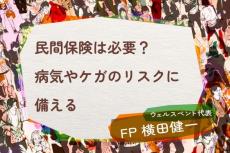
民間保険は本当に必要?病気やケガに備えて保険制度の確認を
人生にはさまざまなリスクがありますが、比較的身近なものとして病気やケガがあります。風邪をひく、つまずいて転ぶといった軽度のものもあれば、骨折やがんのように入院や手術が必要になるものまであります。
今回は、こういった病気やケガのリスクに対してどのように備えればよいのか、基本的な考え方についてご説明します。
「病気やケガで働けなくなるリスクにどう備える?新しく保険に入る前に確認を」では病気やケガによって働けなくなる・障害となるリスクについてご説明しましたが、もう少し幅広く病気やケガ全般への備えです。
日本は国民皆保険!基本的には公的医療保険で十分
日本は国民皆保険ですから、原則として誰もが健康保険証を持っています。2024年12月からはマイナンバーカードを使ったマイナ保険証に切り替えが進んでいますが、保険証は国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合といった公的医療保険制度に加入している証です。
公的医療保険制度の体系

自営業者、会社員、公務員など働き方によって加入する制度は異なりますが、誰もがいずれかの公的医療保険制度に加入しています。そして、75歳になると全員が後期高齢者医療制度に移る形になります。
現在加入している公的医療保険からどのような給付が受けられるのか、ご存じでしょうか。多くの人は「病院に行ったら3割負担で済む」ことは知っていても、これ以外にどういった給付があるのか、しっかり理解できている人は少ないのではないかと思います。
次の表は公的医療保険からの主な給付、その上乗せとなる職場の保障、自助努力して加入する民間の医療保険などについて整理したものです。
病気やケガのリスクへの備え

「病院に行ったら3割負担で済む」というのは「療養の給付」と呼ばれるものです。他にもいろいろありますが、ここではぜひとも知っておいていただきたい「高額療養費」についてご説明します。
高額療養費は病気やケガなどで治療費が高額になった場合に、その人の収入水準に応じて自己負担額が一定金額までに抑えられる仕組みです。具体例で考えてみましょう。
何らかの病気やケガで治療費が1カ月で100万円かかったとしましょう。一般的には3割負担ですから30万円となるわけですが、公的医療保険では高額療養費が支給されるため、一般的な年収(年収370万~770万円程度)の方の場合、次の図のように、実際の自己負担額は8万7,430円となります。
高額療養費の給付例(年収370万~770万円程度の場合)

実際には窓口でいったん3割に相当する30万円を支払い、その後自己負担限度額である8万7,430円を超過した21万2,570円が還付される形となります(ただし、マイナ保険証を利用していれば、窓口で自己負担限度額の8万7,430円を支払うのみとなります)。
この自己負担限度額は年収区分に応じて定められており、次の表のようになっています。
高額療養費制度(69歳以下の方の自己負担限度額)

高額療養費制度のおかげで、いわゆる保険適用の治療を受けている限りは自己負担額が低めに抑えられるのです。また、過去一年間のうち4カ月以上にわたり高額療養費の支給を受けた場合には、4カ月目以降は自己負担限度額がさらに低くなる、多数該当という仕組みもあります。
長期にわたり高額な治療費が発生したとしても、公的医療保険制度では自己負担額が低くなるよう配慮されているのです。
入院の実態:平均日数と診療費は?
病気やケガで入院などした場合に備えて民間の医療保険に加入している人も多いと思いますが、実際に入院した場合どのくらいの期間で、どのくらい費用がかかっているのでしょうか。
次の表は主に中小企業に勤める現役世代が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)と、75歳以上の後期高齢者医療制度について、疾病分類別に平均入院日数と診療費を調べたものです。

現役世代の協会(一般)の方で平均入院日数が最も長期になるのは「精神及び行動の障害」で22.60日、診療費が最も高額になるのは「循環器系の疾患」で約97万円です。一方、後期高齢者の場合でも、平均入院日数が最も長期になるのは「精神及び行動の障害」で27.94日、診療費が最も高額になるのは「循環器系の疾患」で約71万円です(特殊目的用コードを除く)。
これらの診療費は10割相当の金額ですから原則として3割負担、さらに高額療養費が適用されますので、実際の自己負担額はさらに低くなるのです。
治療費以外の部分は自己負担に
最後に、高額療養費制度を含む公的医療保険は病気やケガなどで治療費が発生したときには強い味方となってくれますが、留意しておいていただきたい点もあります。
それは、負担が減るのはあくまで治療費についてで、治療費以外の部分については自己負担になるということです。例えば、入院中に個室を希望した場合の差額ベッド代、入院中の食事代の自己負担額、パジャマのレンタル代などは自己負担となります。
また、現在自己負担限度額を引き上げる方向での議論がなされていることも認識しておいた方がようでしょう。
このような留意点があるとはいえ、公的医療保険制度の保険料は会社員の方であれば毎月のお給料から天引きで納付、国民健康保険の方もご自身で納付し、必ず加入しているものです。保険料を支払う代わりに、どういった給付が受けられるのか、基本的な内容についてはしっかり理解しておくことが大切です。
関連記事:病気やケガで働けなくなるリスクにどう備える?新しく保険に入る前に確認を
(横田 健一)
この記事に関連するニュース
-
高額療養費負担「8万円→13万円」へ…荻原博子「これからはじまる"現役世代いじめ"に備えるにはこれしかない」
プレジデントオンライン / 2025年1月27日 10時15分
-
「マイナ保険証」をまだ利用していません。マイナ保険証を利用するとなにかお得になりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月26日 9時20分
-
南海トラフ地震で家が燃えても「火災保険」は適用されない…元国税局職員「これだけは加入すべき2つの保険」【2024下半期BEST5】
プレジデントオンライン / 2025年1月20日 8時15分
-
年収が280万円の場合、民間の医療保険より国の制度を利用するべき?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月16日 8時40分
-
入院前、医療費は「保険診療だし高くても8万円くらい」と思っていたら、想像の「2倍」近く請求されて驚愕! いったいなぜ? 自己負担額を下げる方法はないの?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月7日 3時0分
ランキング
-
1電力大手、7社減益=燃料費減の効果一転―24年4~12月期
時事通信 / 2025年2月3日 20時10分
-
2トイレの前で待ち伏せする男性社員、その狙いは…フジ騒動を発端に「#私が退職した本当の理由」セクハラ告発がSNSに殺到
集英社オンライン / 2025年2月3日 20時2分
-
3給与受け取りなどで「みずほポイント」…若年層の開拓へ今春から、「楽天ポイント」に交換も可能
読売新聞 / 2025年2月3日 21時14分
-
4スシロー「鶴瓶氏を削除」が完全に見誤ったワケ 企業は「CM取り下げ」をどこで判断すべき?
東洋経済オンライン / 2025年2月3日 17時35分
-
5スーパーの「値引きシール」貼られるタイミングは? AIが判断する店も…
日テレNEWS NNN / 2025年2月3日 22時16分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









