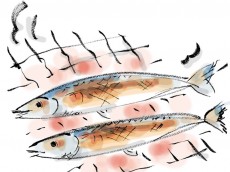サンマの美味しさの秘密は”煙”にあった!?
ウェザーニュース / 2018年9月26日 11時45分

日本人にとって、秋の味覚の代表格といえばサンマ。価格も手頃で江戸時代から庶民の食卓にのぼっていました。
近年、サンマの漁獲量の減少が続いていましたが、今年は9月後半には、水揚げが上向く見通し(水産庁・2018年長期漁海況予報)だと言われています。
発酵学者で食文化論の泰斗、小泉武夫東京農業大学名誉教授に、なぜサンマが美味しいのか、その理由について伺いました。
Q.サンマを語る上で外せないお話とは?
「『目黒のサンマ』という有名な落語です。話の筋はさておいて、なぜ殿様があのようにまでサンマに恋い焦がれたのかについて話しましょう。それが焼きたてのサンマの匂いと味です」
Q.お殿様が目黒まで遠出した際に、家来が弁当を忘れてしまったんですね?
「腹をすかせているところに嗅いだことのない旨そうな匂いが漂ってきたんですね。カンカンと炭火のおこった七輪の上の網わたしに、丸々とした生のサンマをのせると、『ジュージュープップッ』と鳴きながら、まず表面が焼ける。
だが表面だけがはやく焼けるようでは焦げついてしまうので、中までうまく火が通るようにしなければならない。そこは炭火のよいところで、火に適当な加減を加えれば、十分にうまくいきます」
Q.煙の匂いには意味があった?

煙が味を増幅させるワケは…
「殿様を最初に喜ばせた煙の匂いは、魚の表面の皮やその皮下層に重なっている脂肪が焼けて、炭化する時のもので、多数の化合物が複雑に加熱反応しあって生じたものです。
サンマには、30%近いタンパク質と、7~8%もの脂肪があるから、これが炭火で焙(あぶ)られると、脂肪が溶けだし、これが炭火に落ちて燻(いぶ)られる。その煙の匂いには、魚の生臭みの成分(トリメチルアミン、エチラミンなど)をはじめ、加熱反応で生じたカルボニル化合物や、脂肪とタンパク質が炭化の際に生じたフェノール化合物などがあって、それらが特有の匂いを発するのです」
Q.焼くからこそ生まれる味なんですね?
「『焼く』と『煮る』とでは、加熱するという共通の調理法でありながら、まったくの大違いで、サンマを湯で煮ただけでは、目黒には遠く足元にも及ばない。焼くことによって容易に目黒に至るわけです。
煮ることはせいぜい100℃以下で進む加熱であるのに対して、焼くとなると、渡し金の上でさえ200~300℃という高温。火の表面では、1000℃という灼熱の状態になります。魚から出る匂いや味が、煮ると焼くとで異なるのは当然なのです」
Q.サンマは焼きたてに限る?
「お殿様だけでなく、焼いた魚から出る匂いは、魚好きの日本人を魅了してしまいますが、焼かれてうまい魚は多くの場合、日本の近海もので、脂肪ののった魚。キンキン(キチジ)、サンマ、鰯(いわし)、ホッケ、鰊(にしん)などはその代表格で、目黒組の優等生。
殿様が『サンマは目黒に限る』といったのは、実は、お城に帰ってきて食べた憧れのサンマが、お毒見を経て冷たくなり、まずかったためです。目黒の村で食して実にうまかったのは、焼きたてのアツアツだったからで、熱いうちに食べると舌にうま味がのこり、魚本来の生臭みを燻しの匂いが隠してくれる。やはり、サンマは焼きたてに限るというわけです」
この記事に関連するニュース
-
レーザーVS稲妻、どっちが破壊力が強いか はじけ飛ぶ水晶、爆発するスイカ、前代未聞の“7番勝負”が「すごかった」
ねとらぼ / 2024年12月23日 21時0分
-
「上のアジ」と「下のアジ」、どちらが新鮮か分かりますか?プロに聞く「新鮮でおいしい魚」の見分け方
日刊SPA! / 2024年12月23日 15時53分
-
「簡単で時短で最高です!」 1週間分のヘルシーな作り置き “パッと作れる”レシピの連続に「助かってます」と感謝の声
ねとらぼ / 2024年12月22日 8時15分
-
初心者でも簡単!手羽先の【焼く】レシピ3選~グリルやオーブン、フライパンで失敗しない
Woman.excite / 2024年12月7日 6時0分
-
本当に使える? ネットでバズったライフハック“古いパンを焼き立てに復活させる技”を実践→興味深い結果に【海外】
ねとらぼ / 2024年12月1日 8時20分
ランキング
-
1JALと三菱UFJ銀がサイバー攻撃被害…システム障害で警視庁が通信記録解析へ
読売新聞 / 2024年12月26日 22時50分
-
2政治資金問題へのけじめ…自民党が「赤い羽根募金」に7億円超を寄付へ、党費などを原資に拠出
読売新聞 / 2024年12月26日 20時38分
-
3「証拠捏造」認定せず…静岡県警「事実や証言得られず」、最高検「時系列とも矛盾」と批判
読売新聞 / 2024年12月26日 23時42分
-
4JALサイバー攻撃 75便に欠航や遅れ 最大4時間の遅れも
毎日新聞 / 2024年12月26日 19時38分
-
5不要不急の119番を1400回、偽計業務妨害容疑で男逮捕…救急要請に計22回出動も
読売新聞 / 2024年12月27日 7時27分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください