「1本の鉄橋」がヒトラーの寿命を縮めた…ナチス・ドイツが西部戦線で犯した「致命的なミス」
プレジデントオンライン / 2024年2月2日 7時15分
■ナチス・ドイツの最後の防壁となった「ライン川」
レーマーゲンは、まことに小さく閑雅(かんが)な町で、駅から十分も歩けば中心部を通り抜けてライン川に至り、箱庭細工のように見える東岸のありさまを一望できる。かつて、そこにはルーデンドルフ橋が架かっており、両岸を結ぶ通路となっていたのだが、今日でも、そのなごり、橋塔が博物館となっており、昔を偲ぶよすがとなっている。

だが、八十年近く前、この風光明媚な町は最前線になろうとしていた。ノルマンディに上陸し、激闘を繰り返しながらフランスやオランダ、ベルギーを横断してきた連合国の遠征軍が、ついにドイツ本土への進攻を開始したのである。
これを迎え撃つドイツ軍は前年、一九四四年十二月に発動されたアルデンヌ攻勢に失敗し、戦略・作戦レベルの抵抗力を失ったも同然であった。彼らにできるのは、消耗・疲弊しきった既存部隊と、泥縄(どろなわ)式に編成された「国民突撃隊(フォルクスシュトゥルム)」で薄い防衛線を張るか、拠点防御を実行する一方、ごく少数の、戦力を残していた予備部隊で、機会をつかんでは局所的な反撃を加えることぐらいだったのだ。
ゆえに、西部戦線のドイツ軍は、最後の防壁──ライン川に希望を託すほかなかった。スイスの山中に源流を発し、独仏国境地帯からオランダを通って北海に流れ込む、全長一千二百余キロの大河だ。
その流域も今や戦場になりつつあるが、そこに架かる大小さまざまな橋をすべて爆破してしまえば、「父なるライン」は連合軍のドイツ進撃を阻む巨大な水濠と化す。ドイツの川の王者を防衛線として、それを死守すれば、第三帝国の延命も夢ではなく、その間に政治的な解決を可能とするような状況の変化も生じるやもしれぬ。
■渡河の可否が戦争の勝敗を決める
一方、攻める連合軍からすれば、さような事態の生起は、なんとしても許すわけにいかなかった。ドイツ軍アルデンヌ攻勢によって惹起された「バルジの戦い」(一九四四年十二月~四五年一月)の勝利により、連合軍は勢いづき、ほとんど全戦線にわたって進撃しつつある。かかる衝力(モーメンタム)を失うことなくドイツ本国に突入し、戦争の勝敗を決するには、迅速なライン渡河(とか)が必要不可欠なのであった。
こうした情勢下、連合国遠征軍最高司令官ドワイト・D・アイゼンハワー米陸軍元帥(一九四四年十二月二十日に戦時進級)も、従来の方針とは裏腹に、ライン渡河の重点を定めることを余儀なくされた。
これまでアイゼンハワーは、どこか一正面に戦力を集中するのではなく、戦線のほとんどすべてで圧力をかけて、不均等な攻勢を行なった場合に生じるであろう齟齬(そご)を回避しつつ進撃するという「広正面戦略」を採用していた。
これは「狭正面戦略」、すなわち、限られた正面に持てるリソースを注ぎ込み、いわゆる一点突破の全面展開をはかるべきだとした英第二一軍集団司令官バーナード・ロー・モントゴメリー英陸軍元帥の主張(それには、当然、自分の担当正面にあらゆる戦力を集中せよとの議論も含まれていた)と真っ向から対立するもので、しばしばあつれきの種となっていたのである。
■米遠征軍最高司令官の機転
だが、さしものアイゼンハワーといえども、大河ラインを渡るにあたって、リソースを分散することはできなかった。連合軍戦線の北部に位置している英第二一軍集団を主攻部隊と定め、その戦域に砲兵・工兵部隊や上陸用舟艇、大量の物資を投入、一大渡河攻勢「掠奪(プランダー)」作戦を実行させることにしたのだ。しかも、この攻撃は、ライン川東岸を確保するための空挺(くうてい)作戦「大学代表チーム(ヴァーシティ)」によって支援される。

こうしてラインを渡河した英第二一軍集団は、ドイツ西部のルール工業地帯へ突進、これを占領して、第三帝国の継戦能力に致命的な一撃を与える。最終的な参加兵力は百万以上にのぼり、ノルマンディ上陸に匹敵する規模となる作戦であった。
その際、アイゼンハワーは、のちに重要な意味を持つことになる指示を出していた。万一にでも、ライン川に架かっている無傷の橋を見つけたら、それを最大限に活用し、対岸に橋頭を築くべしと補足していたのだ。
おそらく、彼自身、かような幸運はあり得ないと思いつつ、念のために述べておいたのであろうけれども、戦神(マルス)は、ある米軍部隊にとびきりのつきを与えていた。その部隊こそ、第一二軍集団指揮下にあった、米第一軍第三軍団に所属する第九機甲師団のB「戦闘団(コンバット・コマンド)」だった。
■ヒトラーの厳命、乱れる指揮系統…ドイツ軍が撤退を繰り返した理由
このように経験を積み、戦力も充実したアメリカ軍に対し、一九四五年の西部戦線にあったドイツ軍は無惨なありさまとなっていた。アルデンヌ攻勢に失敗し、後退する過程で多数の将兵や装備を失った上に、その補充はままならない。
さらに、総統アドルフ・ヒトラーが、最後の一兵までライン川西岸を死守せよ、東岸への退却はまかりならんと厳命したことも、ドイツ軍の潰滅を早めることになった。
加えて、戦場がドイツ本土に移るにつれ、指揮の混乱も生じた。本国の軍事組織は、補充軍(エアザッツヘーア)司令官、すなわち、ハインリヒ・ヒムラー親衛隊全国長官の管轄となるから、野戦軍の指揮官たちが容喙(ようかい)することはできない。
ところが、ドイツ軍の戦線が後退し、補充軍麾下の新編・補充部隊が戦闘に参加せざるを得ない状況が生起したにもかかわらず、それらは野戦軍とは別の指揮系統で動き、有効に使用できないといった事態が多発したのである。

このような失敗の結果、当然のことながら、西部戦線のドイツ軍は退却につぐ退却を強いられた。もはや頼みの綱となるのはライン川のみ。ただし、ライン川を天然の防壁とするためには、そこに架かる橋梁(きょうりょう)をすべて爆破しなければならない。
ドイツ軍はときに、肉迫してくる米軍部隊の眼前で爆薬に点火するといった、きわどい作業もこなしつつ、つぎつぎとライン川の橋を落としていく。そう、レーマーゲンのルーデンドルフ橋も、同様に爆破されるはずだった――。
■爆破を先送りにしたドイツ軍将校
一九四五年三月七日、レーマーゲン地区守備隊長ヴィルヘルム・ブラートゲ大尉は困惑していた。この日、レーマーゲンの南北に米軍が進んできたと知った彼は、ただちにルーデンドルフ橋を爆破しようとしていた。
しかし、前夜、レーマーゲン地区に対する指揮権を継承したヨハン・シェラー少佐が待ったをかける。シェラー少佐は、上級組織であり、この正面を担当している第六七軍団司令部の副官だったが、派遣幕僚としてブラートゲを指揮するためにやってきたのだ。少佐は、可能なかぎり多くの将兵と装備をライン川東岸に撤退させることを望んでおり、そのため、橋の破壊をなるべく先延ばしにしたいと考えていたのである。
だが、敵は目前に迫っている。ブラートゲは、直接橋の爆破に当たる工兵中隊長カール・フリーゼンハーン大尉とともに、この新任の上官を説得しようと試みたものの、シェラーは、爆破の準備を万全にしておくようにと言ったのみで、その実行は自分の指示を待てと命じたのだ。
こうしたやり取りで時間が空費されるうちに、午後三時、ルーデンドルフ橋付近で最初の銃声が響いた。米第九機甲師団B戦闘団から抽出・編合された「エンジェマン任務部隊(タスクフォース)」が、ライン川に突進してきたのである。
これに対するドイツ軍の対応は、ぶざまなものだった。爆破の許可を求めるブラートゲと、ぎりぎりまで待てと主張するシェラーの押し問答の結果、午後三時二十分になって、ようやく爆薬点火となったが──不発となる。おそらく、砲撃で点火用の電気回路が切断されていたのであろう。

■柔軟性を失ったドイツ軍、臨機応変な行動ができた米軍
むろんアメリカ軍が、この千載一遇のチャンスを無駄にするはずがない。エンジェマン任務部隊に配されていた第二七機甲歩兵大隊A中隊の長、カール・ティンマーマン少尉は、ルーデンドルフ橋の奪取を命じられ、戦車の支援を受けながら、これをなしとげた。
ドイツ軍が持ち前の柔軟性を失い、硬直した対応しかできなかった隙(すき)を衝(つ)いて、計画性偏重のきらいがあったアメリカ軍が、臨機応変の行動によって成功を収めたのである。
第九機甲師団B戦闘団が敵中を長駆進撃、ルーデンドルフ橋を急襲・奪取したことにより、ライン川という障害に通路が開かれることになった。ドイツ語にHusarenstreichという単語がある。「大胆不敵な一挙」という意味だが、直訳すれば「軽騎兵の一撃(フザーレンシュトライヒ)」になる。
ルーデンドルフ橋の爆破に失敗したドイツ軍にしてみれば、まさに、いずこからともなく現れた華麗な軍服の軽騎兵に、またたく間に斬り倒された思いであったろう。

■橋頭堡の確保と拡大
奪取されたルーデンドルフ橋には、ただちに米軍工兵隊と橋梁部隊が派遣され、修理と補強にとりかかった。占領の翌日、三月八日の朝にはもう、増援された米第七八歩兵師団の先陣が橋を渡る。
第七八歩兵師団に続いて、第七九と第九九の両歩兵師団もライン川東岸に進んだ。これらは効率的な橋頭堡(ほ)の拡大と前進をはかるため、一時的に第九機甲師団B戦闘団の指揮下に入った。
一時は、橋板に開いた穴に戦車がはまり込み、車輛が通行不能となることもあったが、アメリカ軍は組織の優越を見せつけるかのように、新手(あらて)の部隊を東へと着実に送り込んでいく。橋頭堡を見下ろす位置にあり、脅威となっていたドイツ軍陣地も掃討された。
むろん、こうした重点変更は、アイゼンハワー連合国遠征軍最高司令官の承認を得ていた。レーマーゲンでライン渡河に成功したとの報告を受けたアイゼンハワーは、降伏したケルン市方面の占領に当たる予定だった五個師団を、そちらにまわすと決定していたのだ。
また、アメリカ軍は、予想外の地点に開かれたドイツ本国への門に、空の傘をさしかけることも忘れなかった。
ドイツ側からみれば、ルーデンドルフ橋を破壊するか、使用不能におとしいれなければ、西部戦線が決壊するのは明白であったから、たとえ満身創痍(そうい)ともいうべき状態にあったとしても、使用可能な航空部隊のすべてを投じて、反撃に出てくることは必至だったからだ。
■「最強の駆逐戦車」で挽回しようとしたけれど…
アメリカ軍が万全の邀撃(ようげき)態勢をととのえたのは無駄ではなかった。三月八日から九日にかけてのドイツ軍の反撃は微弱なものでしかなかったけれど、十日になって、最新鋭の駆逐戦車「猟虎(ヤークトティーガー)」や「猟豹(ヤークトパンター)」を装備した中隊を含む装甲部隊に支援された独第六七軍団が、本格的に橋頭堡に圧力をかけてきたのである。とはいえ、この軍団の戦力はそれまでの退却戦闘で減衰(げんすい)していたから、さほどの成果は上げられなかった。

■典型的な責任転嫁…4人の将校が即日銃殺刑に
一九四五年三月九日、ヒトラーは「西方移動軍事裁判所」(第二次世界大戦末期に設置された、戦線後背部を巡回し、即決で裁きを下す機関)に命じ、ルーデンドルフ橋失陥(しっかん)に責任があるとされた将校五名を軍法会議にかけさせた。
彼らは「怯懦(きょうだ)」と「軍人服務義務違反」で死刑を宣告され、うち四名は即刻銃殺された。そのなかには、ヨハン・シェラー少佐も含まれていた。
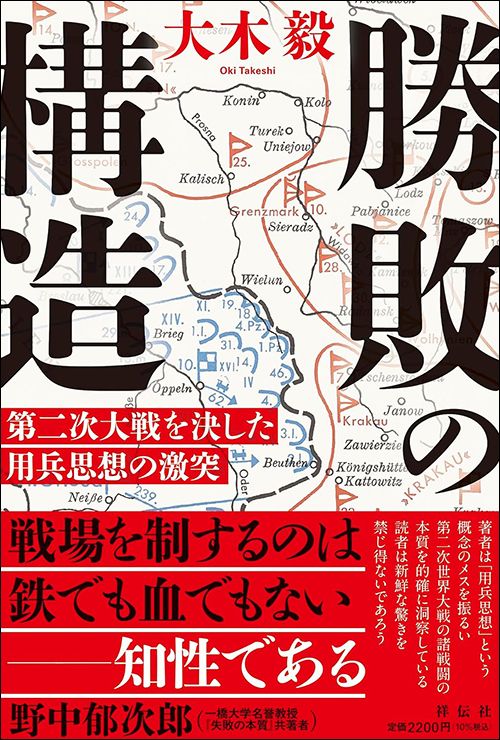
典型的な「生け贄の羊(スケープゴート)」への責任転嫁であったけれども、反面、こうした不法は、ドイツ軍にとってレーマーゲンの敗北がいかに致命的かつ衝撃的であったかを明示しているともいえよう。
このアメリカ軍の成功は、一見僥倖(ぎょうこう)のたまものであるかにみえるが、もちろんそうではない。マネジメント重視で育てられた米軍将校のなかにも、臨機応変の指揮という要素は残されており、それが予想外の勝利をもたらしたのである。
レーマーゲンの第九機甲師団B戦闘団は、米軍のドクトリンとは裏腹に、詭動(マヌーヴァー)の重要性を証明したのであった。
----------
現代史家
1961年、東京生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学。DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生としてボン大学に留学。千葉大学その他の非常勤講師、防衛省防衛研究所講師、国立昭和館運営専門委員等を経て、著述業。『独ソ戦』(岩波新書)で新書大賞2020大賞を受賞。主な著書に『「砂漠の狐」ロンメル』(角川新書)、『ドイツ軍事史』(作品社)、訳書に『「砂漠の狐」回想録』『マンシュタイン元帥自伝』(以上、作品社)など多数。
----------
(現代史家 大木 毅)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
山下裕貴 目覚めよ日本 「日本との局地戦」想定した計画策定に備えよ 中国の台湾侵攻シミュレーション 常設の統合部隊を置くことが必要では
zakzak by夕刊フジ / 2024年4月27日 15時0分
-
『機動戦士ガンダム』本当に「戦いは数」なのか 現実とは異なる「宇宙世紀の戦場」
マグミクス / 2024年4月19日 6時25分
-
赤狩りと恐怖の均衡について(上)「核のない世界」を諦めない その3
Japan In-depth / 2024年4月18日 20時41分
-
アイゼンハワーかく語りき 「核のない世界」を諦めない その2
Japan In-depth / 2024年4月16日 17時0分
-
「日中戦争」と「大阪万博」は残念なほど似ている…日本人が「ぐだぐだ」「ダラダラ」を止められない根本原因
プレジデントオンライン / 2024年4月4日 7時15分
ランキング
-
1映画「もののけ姫」の映えスポットで撮影した女性の投稿に大反響! 「言われなくても生きそう」「無敵感がすごい」
よろず~ニュース / 2024年5月2日 15時0分
-
2iPhoneに「侵害されたパスワード」という通知が来ました。パスワードが漏洩してしまったのでしょうか?
オールアバウト / 2024年5月2日 21時25分
-
3枯れたミントを畑に捨てたら…3年後に「地獄絵図」、 繁殖力に地主も後悔「土の総入れ替えしかない」
まいどなニュース / 2024年5月3日 7時10分
-
4制服と体操服でやりがちなNG洗濯! 体操服を洗濯する時、ファスナーは閉める? 開ける?
オールアバウト / 2024年5月2日 21時15分
-
5固形コンソメを簡単に「粉状」にする方法 味の素公式が教える裏ワザが目からウロコ
Sirabee / 2024年4月30日 5時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










