なぜ「世界最古の高層ビル」はシカゴにあるのか…129年前の14階建てビルがいまでも使われている理由
プレジデントオンライン / 2024年5月22日 7時15分
■企業城下町としてのプルマン工業都市
さて、当時の米国でニューヨークに次ぐセカンドシティとして繁栄したのはシカゴです。ミシガン湖畔から運河で大西洋とつながっているシカゴには商品先物取引所が置かれ、全米の農産物が集まりました。
そのシカゴでは、第一次産業革命時のヨーロッパと同様、都市環境の悪化が進みます。そのため、フランスのゴダン共住労働共同体と似たような(しかしはるかに規模の大きい)試みも行なわれました。1880年代にシカゴ郊外で開発された「プルマン工業都市」です。これは、鉄道車両の製造を行なっていたプルマン社の「企業城下町」のようなものでした。
ゴダン共住労働共同体は1700人程度が暮らすコミュニティでしたが、プルマン工業都市は6000社もの従業員と家族が暮らす住宅を用意した文字どおりの「都市」です。従業員が働く工場があるのはもちろん、市場、教会、図書館、娯楽施設なども提供されました。1893年のシカゴ万博ではこの街が観光名所となり、1896年には「世界でもっとも完璧な都市」として国際的に表彰されています。
ただし1890年代の金融恐慌後には、従業員の待遇をめぐってストライキやボイコットなどの労働運動が発生。企業がそこで暮らす人々の生き方を決めることへの反発も生じました。1898年には、イリノイ州の最高裁判所が「企業に都市を造営する権利はない」として、会社のビジネスに不要な不動産を売却するよう命じます。そのためプルマンの社宅は、1909年までに売り払われました。
■次々と高層ビルを生んだ「シカゴ派」
プルマン工業都市はシカゴ郊外での試みでしたが、シカゴそのものは、この頃から米国建築文化の中心地として注目される街となっていきました。
ひとつのきっかけとなったのは、1871年10月に起きたシカゴ大火。
残念な出来事ではありますが、大きな火災を契機に都市が新しくなることはよくあります。たとえば東京の銀座煉瓦街は、1872年(明治5年)に起きた銀座大火の後、燃えにくい都市になるべくつくられたものでした(それも関東大震災で焼失してしまいましたが)。その前年に大火を経験したシカゴも、耐火構造の建物につくり替えられていきました。
また、経済発展によって人口が増え、オフィス需要も高まってくると、かぎりある地面により多くの空間をつくるために、高層ビルが必要になります。郊外につくられたプルマン工業都市はいわば「横」への展開ですが、こちらは「上」に伸ばしていく。
それまでニューヨークではせいぜい5階建てのビルしかありませんでしたが、シカゴでは10階以上の高層オフィスビルが次々と建てられました。鉄骨構造やエレベーターの進歩によって、技術的にもそれが可能になっていたわけです。
■鉄骨、エレベーター、頑丈な外壁…
この本でも見てきたとおり、ギリシャ・ローマ以来、西洋建築の主役は神殿、教会、宮殿、博物館、図書館といった公共的な建物でした。
しかしシカゴの高層建築は、オフィスビルが主役。それ以来、今日にいたるまで高層オフィスビルは建築家にとって重要なテーマのひとつとなっています。その意味で、商業都市シカゴは西洋建築史にひとつの新しい潮流を生んだといえるのではないでしょうか。そこで活躍した建築家たちは「シカゴ派」とも呼ばれています。
そんなシカゴの高層オフィスビルの中でもよく知られているのが、この時代の米国を代表する建築家のひとりであるダニエル・バーナム(1846~1912)が手がけた「リライアンス・ビル」(1895年完成)です。バーナムは、1893年のシカゴ万博でも総指揮者を務めました。
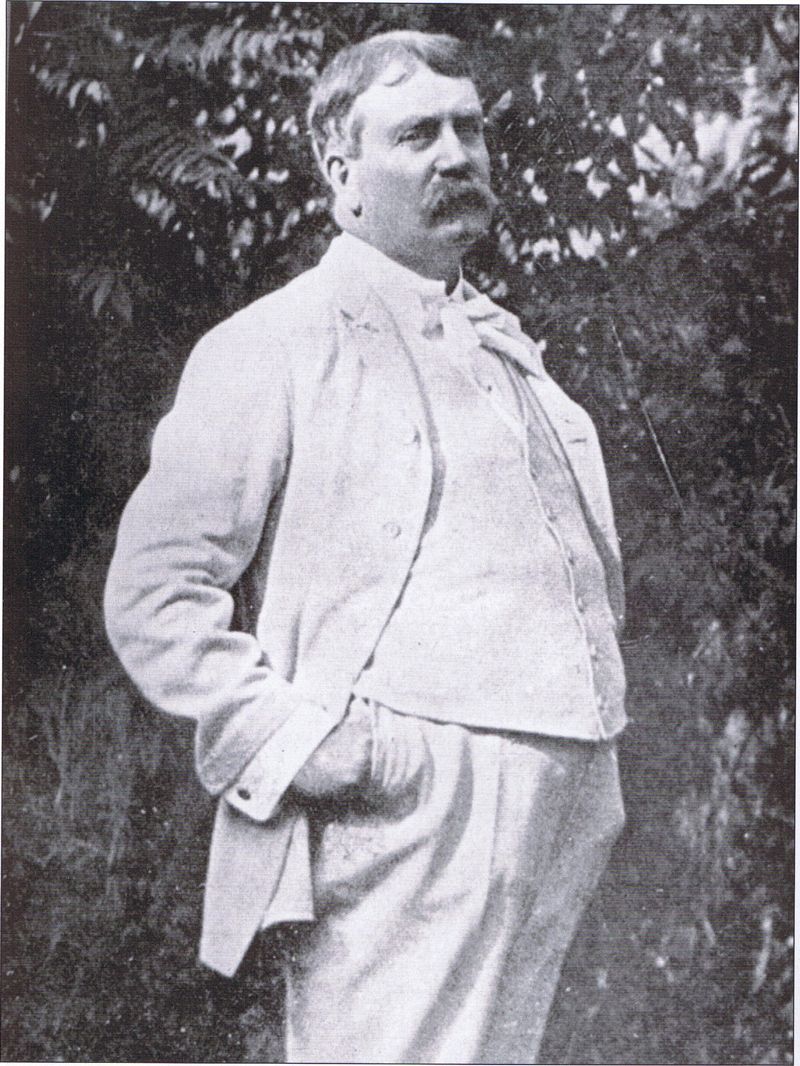
リライアンス・ビルは14階建て。鉄骨の芯を上から下までジャングルジムのように張り巡らせた構造になっています。広く取られた窓を含めて、外壁構造が薄いのも従来のビルとの大きな違い。高層ビルは風圧に耐える頑健さが必要ですが、さまざまな技術の進歩によって、軽い外壁でもそれが可能になりました。

建物の表面に特徴的なデコボコをつくっている出窓は、すべて開くわけではありません。大きな窓ははめ殺し(フィックス窓)で、その両側にある細い窓だけ空気を入れ換えるために開閉できます。採光と換気の機能を持つこのような窓のスタイルは、のちに「シカゴ・ウィンドウ」と呼ばれるようになりました。
■ルイス・サリヴァンの多様な作品
バーナムのリライアンス・ビルは広いガラス窓が軽やかな印象を与えますが、その数年前には、重厚なロマネスク建築風の高層ビルが建てられています。ルイス・サリヴァン(1856~1924)の設計によって1889年に完成した「オーディトリアム・ビル」です。こちらもシカゴを代表するビルのひとつとなりました。

サリヴァンは10代後半のうちからフィラデルフィアやシカゴの建築事務所で働き、パリのエコール・デ・ボザールにも留学。ボザールでは、ミケランジェロをはじめとするルネサンス建築の影響を受けたようです。
彼の代表作であるオーディトリアム・ビルは、外観はまさにロマネスク建築のように分厚い石を組み上げているように見えますが、もちろん、その中は鉄骨。下から上まで大きく3分割したデザインが特徴的です。重厚な基壇の上に、ギリシャ神殿風の長い柱が伸び、やわらかいアーチが最上部を支えている。たいへん美しい新古典主義の名作だと思います。

ただ、サリヴァンは必ずしも新古典主義の全面的な支持者だったとはいえません。そのためにバーナムと対立もしています。
というのも、バーナムが指揮したシカゴ万博は、会場が「ホワイト・シティ」と呼ばれるほど、ヨーロッパ風の宮殿など白一色の古風な建物が並びました(ちなみに日本館は、京都府宇治市にある平等院鳳凰堂のミニチュア版でした)。
サリヴァンもこの万博には関わっていましたが、新古典主義が前面に押し出されたことについて「この国の建築を50年遅らせた」とバーナムを強く批判したといわれています。
■ヨーロッパの伝統文化に対する憧れがあった
しかし高層ビルの設計を発注する実業界の人々には、ヨーロッパの伝統文化に対する憧れのようなものが根強くあったのでしょう。オーディトリアム・ビルも、そういうニーズに応えて設計されたのかもしれません。
実際、サリヴァンはオーディトリアム・ビルとはずいぶん印象の異なるビルも設計しました。「カーソン・ピリー・スコット・ストア」という百貨店がそれです。装飾がほとんどなく、ジャングルジムのような構造がそのまま見えるあたりは、かなり近代的な感覚です。
このビルの特徴のひとつは、道路の交差点に面した角の部分がカーブを描いていること。バーナムのリライアンス・ビルやサリヴァンのオーディトリアム・ビルもそうですが、オフィスビルは玄関のある側が「正面」です。でもカーソン・ピリー・スコット・ストアは商業ビルなので、人通りのある道の両方からお客さんを集めたい。だから角にカーブをつけて、そこを玄関にしているわけです。
サリヴァンの作品には、ほかにも有名なものがいくつかあります。たとえば、1891年に完成した「ウェインライト・ビル」と、1895年に完成した「ギャランティ・トラスト・ビル」。どちらも基壇、ボディ、飛び出した屋根という似たような構造ですが、この2つは、ある意味で対照的な個性を持っていると思います。
■ビルに表れる建築家の個性が面白い
ウェインライト・ビルは、4つの角を太い柱が支えていることで、水平性よりも「上」へ向かう垂直性が強調されています。屋根は分厚く、全体的に力強い。僕には、このビルが「男性的」なものに感じられます。
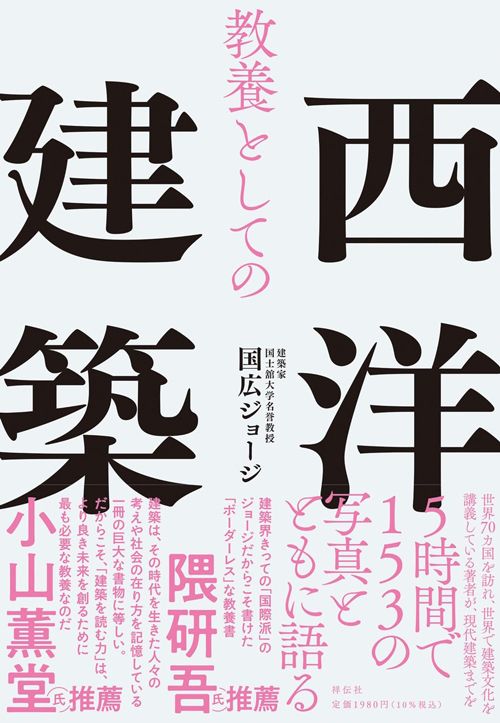
一方のギャランティ・トラスト・ビルに、そのような強さはありません。角の柱が細く、全体に編み物のようなやわらかさがあります。そのため、どちらかというと女性的なイメージ。男女の性質を一面的に決めつけてはいけませんが、古代建築の円柱にも、男性的なドリア式と女性的なイオニア式がありました。
同じ建築家が、このように個性の異なる作品を手がけていることが、僕にはとても面白く感じられます。こうやって、「建築を読む」という鑑賞方法をゲーム感覚でやることで、建築に対する親しみや楽しみが増えるのではないでしょうか。
ところで、サリヴァンのカーソン・ピリー・スコット・ストアは、まったく装飾がないわけではありません。2階から上は、のちのモダニズムにも通じる機能性重視のデザインですが、通りを行き交う人々が目にする1階には花模様などの装飾が施されました。これは、1890年代から20世紀初頭にかけて流行した「アール・ヌーヴォー」という様式を取り入れたものです。
----------
建築家、国士舘大学名誉教授
1951年東京生まれの日系三世。三菱財閥本家で創設者岩崎彌太郎の玄孫。カリフォルニア大学バークレー校卒業。ハーバード大学Graduate School of Design修了。その後、サンフランシスコ、ロサンゼルスの設計事務所で修行した後、1982年にロサンゼルスにて、George Kunihiro Architectを設立。1998年に国士舘大学工学部助教授、2003年同教授、22年名誉教授に。2023年には、建築界の最上部組織てある国際建築家連合(UIA)においてアジア地区を代表する評議員に選出される。任期は2026年まで。京都美術工芸大学客員教授、清華大学客員教授(北京)、一級建築士事務所ティーライフ環境ラボ取締役会長、アメリカ建築家協会フェロー(FAIA)、日本建築家協会フェロー(FJIA)、国際建築家連合(UIA)評議員。専門は建築意匠論、アジアにおける近代文化遺産および現代建築の研究。近年の研究は「過疎化とコミュニティ再生」、「廃棄物0有機資源化」など。著書に『教養としての西洋建築』(祥伝社)がある。
----------
(建築家、国士舘大学名誉教授 国広 ジョージ)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「ざま見やがれ」強気な建築家・前川國男の驚く偉業 コンペに落ちた若手が「巨匠」と呼ばれるまで
東洋経済オンライン / 2024年5月30日 15時0分
-
木造は石造より命が長い?プロが語る建築の本質 東洋の「木の文化」と西洋の「石の文化」の違い
東洋経済オンライン / 2024年5月23日 16時30分
-
なぜニューヨークに「世界一の高層ビル」が次々と建ったのか…マンハッタンが現在の姿になった歴史的経緯
プレジデントオンライン / 2024年5月23日 7時15分
-
1889年に高さ300mで世界一に…エッフェル塔を実現した「錬鉄」と「水圧式エレベーター」という最先端技術
プレジデントオンライン / 2024年5月21日 7時15分
-
世界の建築にも影響、日本発「メタボリズム」の正体 西洋建築と日本の歴史を通して見えてくるもの
東洋経済オンライン / 2024年5月16日 18時0分
ランキング
-
1引きこもり女性が出会った“ゴミ箱状態の家”で暮らす男性の「まさかの正体」
日刊SPA! / 2024年6月3日 8時52分
-
2テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】
オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分
-
3ハーバード大「ヒトは180歳まで生きられる」…逆に言うとそこまで死ねない人間がすべき老化を防ぐ5つの習慣
プレジデントオンライン / 2024年6月3日 16時15分
-
4「腹八分目は健康にいい」説、実際どうなの? 内科医に聞いて分かった“真偽”
オトナンサー / 2024年6月3日 9時10分
-
5「辞めるなら120万円払え」と脅された人も…退職代行業者モームリが出合った“ヤバい会社”
日刊SPA! / 2024年6月2日 8時54分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











