話題の文芸評論家・三宅香帆が“最恐ホラー”「自選作品集 わたしの人形は良い人形」を読む
文春オンライン / 2025年2月5日 6時0分
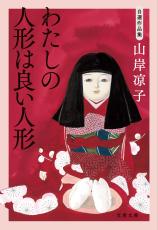
『自選作品集 わたしの人形は良い人形』(山岸凉子 著)
ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で知られる話題の文芸評論家、三宅香帆さんは「山岸凉子先生は、私にとって神様です!」と熱く語ります。
「花の24年組」と呼ばれた少女漫画界のレジェンドのひとりである山岸さんの代表作としては、バレエ漫画『アラベスク』『テレプシコーラ/舞姫』や、厩戸王子(聖徳太子)を描いた『日出処の天子』が挙げられますが、ホラー漫画家としても絶大な支持を受けています。
なかでも“最恐”の呼び声の高い「わたしの人形は良い人形」と、「千引きの石」「化野の…」「八百比丘尼」の全4作が、『 自選作品集 わたしの人形は良い人形 』として文春文庫から刊行されました。1980年代に発表されたこれらの作品は、その後40年にわたって繰り返し読み返され、読み継がれてきた伝説の短篇作品です。
三宅さんが、今なお時代の最先端を走り続ける山岸ホラーの恐怖の源を読み解いていきます。
◆ ◆ ◆
無念が噴き出す亀裂を鎮める作家
人間の感情を軽視すると、碌なことが起きない。
山岸凉子先生の作品を読むたび私はそれを知る。感情、情念、欲望、思慕。人間の想いは強く濃く重く、時を超えて残る。私たちは他人の感情も自分の感情も無視してはいけない。それはとても重いものであるからだ。短編長編エッセイ問わず、山岸作品を読むたび私はそんなことを思う。それが歴史漫画であってもバレエ漫画であってもホラー漫画であっても、同じことを思うのだ。……だが私は頭が悪いので、すぐそのことを忘れてしまうのだ。感情なんて、無視すればいつか消えるものだと思ってしまう。
だって感情は、形として目に見えない。少しくらい心にしこりの残る出来事があったとしても、忘れたらなかったことになる気がしてしまう。何せ、日々は忙しない。ひとつひとつ他人や自分の感情に気を配っていては、仕事は進まないし時代に乗り遅れてしまう。ついそう考えてしまう。
しかし大人になってみるとよくわかるのだが、実は、感情は消えない。案外それは残る。他人の感情も、自分の感情も、忘れたと思ったら案外残っているものだ。
誰かにないがしろにされたこと。誰かに搾取されたこと。誰かに傷つけられたこと。人間はずっと覚えているし執着する。感情はなかったことにはならない。現実で痛い目を見てそれを知るたび、私は山岸作品を読み返す。そして「ああ、ずっと前に山岸凉子先生が教えてくれていたじゃないか」と苦笑するのだ。
普通に生きている人間が転げ落ちてくる
山岸作品は手を替え品を替え、「想いに似たもの」を描く。たとえばそれは少女を手にかけ続けようとする人形である(「わたしの人形は良い人形」)。あるいは突然空襲にあってしまった人々の聴こえない叫び(「千引きの石」)。あるいは亡くなってしまったことを自覚できない人の言葉(「化野の…」)。そして自分を律そうとせずにただ受け身で生きている人間にいつのまにか付け入って搾取してしまう人魚たち(「八百比丘尼」)。本書に収録されたどの作品においても、想い――普段の生活でどこかなかったことにしたくなる、見て見ぬふりをしたくなる、言葉にならない情念が、この世ならぬものの形をとって私たちの目に触れている。
人形も、幽霊も、人魚も、どれも私たちの日常にふと入り込んだ亀裂のようなものだ(ちなみにこの亀裂という比喩は『日出処の天子』を読んだ方はどの場面から来たものかわかっていただけるように思う。あれこそ強い想いが形になった最たる描写だと思うのだ)。読者は一度山岸作品に触れると、世界にたしかに存在する「亀裂」に気づかざるを得ない。私たちの日常はこんなにも、誰かの感情を抑圧して成り立っているのか、と。
そして恐ろしいことに、その忘れられた情念は、亀裂の底でおとなしくしているだけではない。本書に描かれている通り、時として、亀裂の割れ目の底から出てくるのだ。その時を彼らは待っている。今か今かと、普通に生きている人間が転げ落ちてくるのを、待っているのだ。
山岸作品が「幽霊」の正体を教えてくれた
昔、「どうして物語に出てくる幽霊は、人間を呪い、そして死者の世界に連れて行こうとするのだろう?」と不思議に思ったことがある。幽霊は幽霊、人間は人間、違う世界に生きているということでいいじゃないか、と幼心にホラー漫画を読んで考えたのだ。しかし十代も半ばを過ぎ、母が本棚に並べていた山岸作品を読んではじめて、その答えを知った。幽霊とは、人間が忘れようとしている(だが実は忘れられていない)情念たちが、ふと人間の目に見える形をとったものなのである。山岸作品を読むとそれがよくわかる。抑圧した感情は、「忘れるな」と叫ぶ。「なかったことになんてさせない」と。だから幽霊は人間を自分たちの世界に連れて行こうとする。自分だけが忘れられるなんて、そんなことはさせない、と彼らは叫んでいるのだ。
無念、という日本語がある。くやしくてどうにもならないという感情だ。山岸作品を読むと、幽霊とは結局「無念」が姿を変えたものなのだとよくわかる。形にならなかった、情念。突然亡くなってしまったり、戦争でいきなり傷つけられてしまったりすると、自分の生き延びたかった世界にはもういられないのに、それでも念だけが残り、形には残らない。体は消える。しかし念は消えない。だから幽霊の体がうまれる。
そこには理屈や因果は関係がない。「八百比丘尼」の人魚にとって、ふらふらついてくる人間を、たぶらかして栄養とすることに理由なんてない。誰でもいいのだ。誰かでなくてはいけない理屈なんてない。「化野の…」や「千引きの石」に登場する、この世にいない人々の魂もまた、きっと因果を超えている。科学と資本主義が浸透しきって、理屈と理論に覆われた現代社会であっても、どうしようもないのは感情なのだ。人間の感情とは、現代の最大の隘路なのかもしれない。
こんな恐ろしい話、ほかにない
そして本書に収録された「わたしの人形は良い人形」。こんなに恐ろしい話、ほかにない。なぜこの物語が恐ろしいのか。それはこの話が、どうしようもないからだ。――あるひとりの少女が、不憫な事故で亡くなった。そして人形を副葬品として棺に入れなかった。そんなの、どうしようもない、ありふれた出来事だ。しかしどうしようもないからこそ、想いはどこにも行き場がないまま残る。だから道連れにする少女を、無念の塊である魂は探し続ける。
彼女たちの魂は、「ただの“思い” 執着心でしかない」と評される。そうなのだ。執着が生まれてしまった因果については、どうしようもなかったのだ。だから怖い。対策できない。対策してもどうにもならないことがこの世にはあるのだと思い知らされる。
世界の亀裂の底へ落ちていかないように
きっとこの先も、人間はどうしようもなく、無念な魂を生み出し続ける。社会が発達しても、人間が賢くなっても、変わらない。そのたび、あらゆる無念に、私たちは祈りをささげるほかない。どうか鎮まってください、と。人形に対し陽くんが「あの世へ送ってやるんだ」と説いたり、「千引きの石」で榊が怨霊に桃を投げつけたりすることは、忘れられた感情への供養なのである。
無念が生み出される因果は、どうしようもない。しかしどうしようもないからこそ、私たちは感情を軽視しすぎないほうがいいのだ、きっと。抑圧した感情が噴出し、大地に亀裂が生まれてしまったとき、私たちは山岸作品を思い出したほうがいい。
『アラベスク』でも『日出処の天子』でも『舞姫 テレプシコーラ』でも描かれていたことだが――弱さを受け入れ、ときに揺らぐ感情を無視しないことの価値を、私は山岸作品を読むたび、知る。
山岸凉子作品とは、今を急ぐ私たちが世界の亀裂の底へ転げ落ちていかないように留めてくれている存在なのではないか。そんなふうにも思う。
作中で繰り返し描かれる、無念な他者の想いを鎮める姿。それこそが私が山岸凉子という作家からもっとも強く受け取った祈り、なのである。
(文芸評論家)
(三宅 香帆/文春文庫)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【漫画】教室に水筒を忘れた女子生徒 取りに戻り、再び廊下に出ると…衝撃のラストに「怖かった」<作者インタビュー>
オトナンサー / 2025年2月1日 19時10分
-
実在の心霊スポットをめぐる韓国ホラー『ヌルボムガーデン』監督インタビュー 「どんな一面が隠されているのか、想像を膨らませた」[ホラー通信]
ガジェット通信 / 2025年1月24日 21時0分
-
野村萬斎が演出・出演! 漫画『日出処の天子』能 狂言化&今夏上演
クランクイン! / 2025年1月24日 8時0分
-
「劇場版モノノ怪」第二章の主題歌もアイナ・ジ・エンドが続投 本編映像を使用したアニメMV公開
映画.com / 2025年1月22日 22時0分
-
【インタビュー】“死者が帰ってくる”ドラマを描く『アンデッド/愛しき者の不在』 監督がこだわった不穏さとリアリズム[ホラー通信]
ガジェット通信 / 2025年1月17日 20時0分
ランキング
-
1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車
週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分
-
2「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分
-
3「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧
共同通信 / 2025年2月5日 10時26分
-
4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分
-
5「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態
まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









