親から相続した不動産、名義変更しないとどうなる?「行政罰」だけではない5つの“大問題”【司法書士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 12時0分
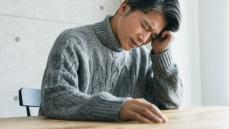
(※写真はイメージです/PIXTA)
2024年4月より不動産相続時のルールが変わり、「相続登記」が義務化されました。不動産を相続した人は、必ず3年以内に「相続不動産の名義変更(=相続登記)」を行う必要があり、正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料(=行政罰の一種)の適用対象となります。申請期限には余裕があるものの、手続きを急ぐに越したことはありません。不動産が故人名義のままだと、過料以前にさまざまな問題が生じるからです。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。
相続登記をしないでいると、どうなる?
これまで相続登記はさまざまな理由から放置されてきました。手続きにはお金(登録免許税など)がかかるから。相続不動産の価値と手続きのコスト(時間や費用)が見合わないから。専門家に依頼するのはお金がかかるし、かといって自力で進めるには複雑で面倒だから。放置状態でも特に困っていると感じないからなど。
そんななか設けられた過料は、多くの人にとって「相続登記を行う動機」となる一方で、「自分の場合、申請コストのほうが高くつく」「過料10万円を払ってでも放置したほうが安い」と考える人もいるでしょう。どちらの場合にも知っておいてほしいことがあります。
まず、過料を支払っても相続登記の義務は免除されません。また過料ばかりが取り沙汰されていますが、相続登記しないリスクやデメリットはそれだけではないのです。本稿では、相続登記を放置した相続人に待ち受ける5つの危機を解説します。
(1)相続不動産を売却できない
相続登記をしなければ相続不動産を売却することはできません。売却するには、売買の関係者(司法書士、仲介業者、買主など)に対して、自分がその不動産の現在の所有者であることを証明しなければなりません。
相続登記をしなければ登記上の名義人は故人のままですから、「自分が所有者である」とは主張できず、売却に進めません。
登記は不動産の履歴書とも言われていて、どういった経緯をたどって現在の所有者へ権利が承継されてきたかを正確に記載する必要があります。仮に相続登記をしないで買主の名義に登記されると、あたかも亡くなった人が売買したかのような記載になってしまいます。登記は中間省略ができませんので、被相続人から相続人、そして買主へと、名義が移った経緯をきちんと登記簿に記載する必要があるのです。
(2)相続関係の複雑化
2つめは相続関係の複雑化です。相続登記を行うには、原則として遺産分割協議をまとめたうえで、関係者たちの戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を法務局に提出しなければなりません。放置している間に相続人の誰かが亡くなれば新たな相続が発生し、関係者が増えます。何代にもわたり放置すれば相続が繰り返され、関係者が誰なのかを特定するのもひと苦労です。また相続人どうしの関係性も希薄になりますから、連絡が取れない、話し合いに応じてもらえないなど遺産分割協議のハードルも高くなります。相続登記がいよいよ進まないという事態にもなりかねません。
(3)認知症などで遺産分割協議が困難化
3つめは、放置しているうちに相続人が認知症を発症するなどして、遺産分割協議が難しくなるリスクです。
65歳以上の4人に1人が認知症を発症すると言われる今、相続人の誰かが発症しても不思議ではありません。
認知症や精神的障がいなどにより、その法律行為(契約や手続きなど)が自分にとって有利か不利かなど内容を判断する能力が十分ではない場合、その人には、本人の利益を考えながら代わりに法律行為を行う成年後見人等(判断能力の程度によって成年後見人・保佐人・補助人の3類型があります)をつける必要があります。成年後見人等は家庭裁判所が選任します。
相続人の誰かが認知症を発症した場合も同様で、その人に成年後見人等をつけなければ遺産分割協議を行えなくなることがあります。また、選任までの手続きが大変なだけでなく、遺産分割の内容に制限が生じるという点にも留意が必要です。成年後見人等は成年被後見人となった相続人本人の利益を守るため、原則として法定相続分(民法が定める相続の割合)の遺産を確保しなければならないからです。そういった意味でも遺産分割協議が困難化するリスクがあると言えます。
(4)他の相続人の債権者から差し押さえられるリスク
4つめは他の相続人の債権者から差し押さえられるリスクです。共同相続人のうちの1人に借金や税金の滞納があった場合、債権者は、借金のある相続人の法定相続分を差し押さえることが可能です。登記簿上は被相続人の名義になっていますが、債権者は相続人の意思とは無関係に(法定相続分の割合に限りますが)相続人名義へ相続登記することが可能です。このように相続人に代わって相続登記することを「代位登記」といいます。つまり、相続登記をしていない状態であっても債権者が代位登記をして、借金をしている相続人の共有持分を差し押さえることができるのです。
このように、相続人のなかに借金をしている人がいる場合、その相続分を債権者に差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。特定の相続人の共有持分が差し押さえられてしまうと、遺産分割が思うように進まなくなってしまったり、手続きが一向に進まなくなったりする可能性が出てきます。遺産分割協議のうえ借金のある相続人がその不動産を取得しないことになっても、すでに差し押さえられた相続分に関しては、借金をしている相続人がきちんと返済するか、場合によっては他の相続人が立て替えて返済するなどしない限りは、売却等を行う場合に差し支えることにもなりますし、借金が返済されない状態が続くと最悪、債権者から強制競売の申立がなされることにもなりかねません。
(5)他の相続人が勝手に売却するリスク
最後は、相続人の1人が自分の相続分を売却するリスクです。あまり知られていませんが、実は法定相続分の割合であれば、相続人のうちの1人からの申請で、相続人全員の共有名義で登記したうえで、自分の相続分のみを共有持分として売却することが可能です。
共有持分とは、同じ不動産を共有しあう人たちがその共有不動産に対して持っている「それぞれの所有権の割合」のことです。共有不動産を丸ごと売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみであれば独断で売却できます。
共有不動産を活用するには他の共有者の合意を得なければならず、使い勝手がいいとは言えません。そのため、共有持分のみを売却しようとしても買手がつかないことも珍しくないのですが、世の中には特殊な業者がいるのです(インターネットのほか、地下鉄や電車内などでも、たまに「共有持分、買い取ります」というような広告が出ています。機会があればチェックしてみてください)。
共有持分が売却されることによって、他の相続人と買取業者がいわば「共同相続状態」に陥ると、大変なことになってしまいます。例えば共有持分を売却されたのが自宅不動産だった場合、その家に買取業者と一緒に住むわけにはいきません。実はこういった買取業者は、最初から共有持分を安く買い取って共有物の分割請求をすることを狙っています。
この請求がされると、自宅を売却して現金に換えてから分配するのか、他の相続人が業者に売った分を買い戻すのか、業者に自宅を買い取ってもらうのかなどの検討が必要になります。話し合いで決着がつかなければ、買取業者は裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起します。買取業者はここまで見込んで共有持分の買取をしていますので、一般の方だと一筋縄では行かなくなってしまいます。
相続手続きに「放置して大丈夫なもの」はありません。相続登記にしても、放置したところで手続きにかかるコスト(登録免許税など)から一時的に逃れられるくらいで、ペナルティが科されても申請義務はなくなりません。また、放置するほど相続人が増えたり誰かが認知症を発症したりといったリスクも増大していきます。
相続登記を先延ばしにするメリットはない
以上、本稿では相続登記を放置するリスクやデメリットを紹介しました。登録免許税を節約するつもりがより大きな損失を生むことになってしまっては本末転倒でしょう。やはり、放置するメリットはないのです。期限内であってもできる限り早く手続きすることをおすすめします。
佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所 所長
この記事に関連するニュース
-
父が亡くなり、自分が「実家の土地」を相続! 先日兄から「相続登記は済ませたか」と聞かれましたが、司法書士に頼むと10万円もかかるし、期限もないなら放っておいて大丈夫ですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月23日 5時0分
-
「実家だけは、同居している長男家族に遺したい」…不仲の長女を抱える〈77歳・父〉の相続対策【行政書士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月22日 12時15分
-
親の遺産を「一部だけ」相続することはできる?「相続放棄」の仕組みを紹介
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月18日 5時0分
-
昨年末に親が亡くなりましたが「相続登記」していません。令和6年から「義務化」されたと聞きますが、放置するとどうなりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 5時0分
-
どうすんのこれ…亡夫が母親から相続した土地は原野商法で購入した那須の山林60坪…残された63歳女性が〈昭和の負の遺産〉を前に呆然としたワケ【相続の専門家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月9日 10時15分
ランキング
-
1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車
週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分
-
2「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分
-
3「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧
共同通信 / 2025年2月5日 10時26分
-
4部屋を整理していたら、使っていない「クレジットカード」を3枚発見…!すぐに解約したほうがいい?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月5日 4時30分
-
5「23歳と29歳の時、突然クビに」2社を不当解雇で訴えた男性。総額4700万円の和解金を勝ち取れたワケ
日刊SPA! / 2025年2月5日 8時53分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください









