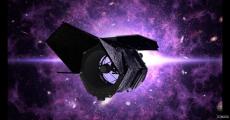JAXA、日本が提供したNASAのNGR宇宙望遠鏡用光学装置が性能を達成と発表
マイナビニュース / 2024年5月27日 21時58分
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は5月24日、NASAが2027年ごろまでの打上げを目指して開発中の超大型次世代宇宙望遠鏡「ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡」(NGRST)に対し、JAXAなどは系外惑星観測を行う上でのキー技術である「コロナグラフ装置」(CGI)への光学素子の提供などを行っており、今回同装置の最終試験において、求められる性能が達成されたことをNASAが確認したと発表した。
同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) NGRSTプロジェクトの山田亨教授/リーダー、同・住貴宏主任研究者(PI)(大阪大学教授兼任)、東京大学/アストロバイオロジーセンターの田村元秀教授、北海道大学・村上尚史講師、オプトクラフト、光学技研、三共光学工業、夏目光学らの共同チームによるもの。
"ハッブル宇宙望遠鏡(HST)の母"と呼ばれ、NASA初の主任天文研究者であり、女性として最初に幹部職に就いた天文学者の名を冠したNGRSTは、主鏡の直径こそHSTと同じ2.4mだが、「広視野観測装置」(WFI)を搭載しており、一度に観測可能な視野はHSTの約200倍にもなる。同望遠鏡ではそれを活かし、(1)約100億光年先の宇宙まで、数億個の銀河の分布や数千個の超新星爆発の光度変化を観測し、宇宙膨張の歴史とその中での銀河の分布構造の形成と進化の歴史を正確に測定して精密な宇宙論研究を行う、(2)重力マイクロレンズ法を用いて天の川銀河内の系外惑星を新たに数千個見つけ出し、太陽~地球間の距離(約1億5000万km)を越えるような、主星から離れた冷たい惑星までを観測して系外惑星の軌道分布の全貌を解明する、(3)さまざまな分野での広視野を活かした近赤外線波長での天文学研究を実施するという、3点の科学成果の創出が目指されている。
そしてもう1つの大きな目的が、JAXAが光学素子を提供したCGIを活用した、明るい主星のすぐそばにある地球と同程度の小型で暗い惑星を直接観測するという、「高コントラスト観測」の技術実証を行うことだ。CGIは、明るい主星の光を隠すことで、そこからわずかしか離れていないずっと暗い系外惑星を観測するための装置。系外惑星を直接観測できれば、惑星の色や詳しい波長スペクトルとその時間変化などから惑星大気や表面についての情報が得られる(特に地球類似惑星では、生命の兆候の発見も期待される)。
-

-
- 1
- 2
-

この記事に関連するニュース
-
宇宙の“化学”を明らかにする遠赤外領域望遠鏡「SALTUS」を欧米研究者合同チームが提案
sorae.jp / 2024年6月17日 16時46分
-
JAXA、超大質量ブラックホール同士が合体直前の可能性がある銀河を分析
マイナビニュース / 2024年6月17日 13時20分
-
ESAユークリッド宇宙望遠鏡が撮影した「かじき座銀河群」の銀河たち
sorae.jp / 2024年6月12日 20時59分
-
ESAユークリッド宇宙望遠鏡が撮影した“オリオン座”の反射星雲「M78」
sorae.jp / 2024年6月1日 21時11分
-
ESAユークリッド宇宙望遠鏡が撮影した“くじゃく座”の渦巻銀河「NGC 6744」
sorae.jp / 2024年5月28日 20時48分
ランキング
-
1約20万円でも「Xiaomi 14 Ultra」が想定以上の反響だった理由 ミッドレンジは“企業努力”で価格を維持
ITmedia Mobile / 2024年6月17日 11時49分
-
2楽天モバイル、700万回線を突破 - 2カ月半で50万回線増加
マイナビニュース / 2024年6月17日 15時55分
-
3今売れている「ミニコンポ・セットコンポ」おすすめ3選&ランキング ハイレゾ音源に対応したセパレート型をピックアップ【2024年6月版】
Fav-Log by ITmedia / 2024年6月17日 6時10分
-
4Teams Roomsに新機能、AutopilotとAutologinが一般提供
マイナビニュース / 2024年6月17日 9時44分
-
5サイバーエージェント、社員一人ひとりに独自の生成AIを提供‐2.4万時間削減へ
マイナビニュース / 2024年6月17日 13時4分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください