話がつまらない人に共通する3つの"ない"
プレジデントオンライン / 2019年3月15日 9時15分
※本稿は、下地寛也『プレゼンの語彙力』(KADOKAWA)を再編集したものです。
■話の途中で聴衆をドキッとさせているか?
話のつまらない人、いますよね。本人は真面目に話したりプレゼンをしているのに、どうしてもだんだん眠くなったり、集中が途絶えて他のことを考え始めてしまったり……。
私も昔はその「話のつまらない人」でした。なにせ、人と話すのが苦手だからという理由で、デザイナー職を志望してコクヨに入社したほどだったのです。オフィスの設計者になりましたが、案の定、顧客対応が下手すぎて上司や営業に怒られる日々。「会社辞めたい……」と思いながら働いていたものです。
それが今では、プレゼンで「YES」を引き出すための言い回しのコツをまとめた本を出すようになりました。それは20年にわたり、「眠くなるプレゼン」と「引き込まれるプレゼン」を自分なりに研究しつづけた結果です。
ここではその中から「話のつまらない人の共通点」に焦点をあて、3つのポイントをご紹介しましょう。
■つまらない話には「緩急」がない
ポイント1。つまらない話には、緩急がありません。だから眠くなります。
たとえば、「それって本当に正しいの?」と世の中の常識に疑問を投げかけられると、人はドキッとします。突然「あなたがいつも面倒だと嘆いているその仕事って、本当に必要なんでしょうか?」なんて言われたら、思わず考えてしまいますよね。
「たしかに深く考えていなかったけれど、言われてみれば本当にこれで良かったんだっけ?」と思考がグルグル回り始めます。
一般的に当たり前だと言われている物事にツッコミを入れる。これは、相手の眠気を吹き飛ばすのに大きな効果を発揮します。つまりは「常識を疑う」ということです。
しかし、「常識を疑え」と言われても、何が常識かを意識するのは難しいものですが、やってみればいくらでも例があるはずです。
毎日、何気なく歯を磨き、電車に乗って、上司に挨拶をして、パソコンのメールをチェックし、お客様のオフィスを訪問する――。そんな無意識の行動のどこかに、疑問を投げかけるわけです。
「そのメールって本当に意味があることなんでしょうか?」
「それがお客様との最適な関係なんでしょうか?」
この人はなんてモノゴトを深く考えているんだろう、と聞き手は思います。そして「自分は深く考えずに日常を過ごしている。何が本当の答えなのかな?」とその先の話を聞きたくなるでしょう。
■つまらない話には「数字」がない
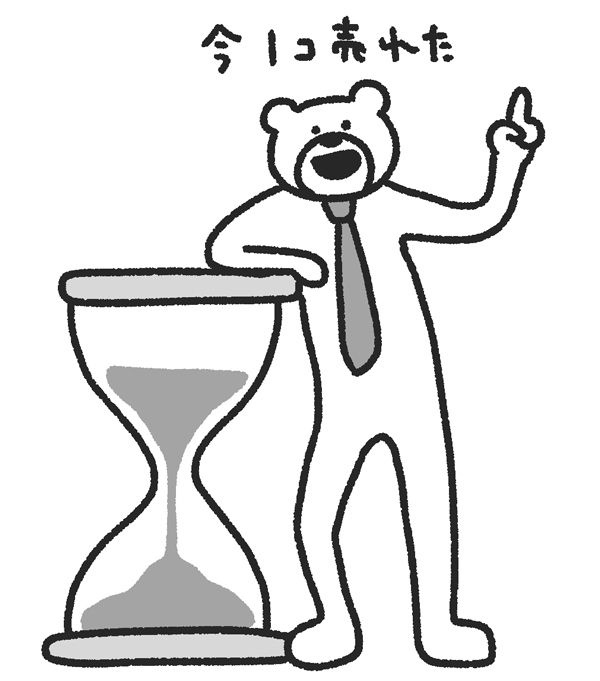
ポイント2。つまらない話には数字が出てこない。だからぼやけています。
説得力を増すために数字を使うのは、常套テクニックです。たとえば、「たくさん売れてます」「かなり安いです」と言われるより、「10秒に1個売れています」「他社より3割安いです」と数字を使って具体的に言われるほうが、聞き手はずっとクリアに理解できます。
さらに、プレゼンをするビジネスパーソンにとっては別のメリットもあります。数字を使えば、イメージがズレることがありません。誰にとっても10秒は10秒ですし、2000個は2000個でしょう。
■ただし大すぎる数字には要注意
ただ、数字があまりにも大きいと聞き手がイメージできなくなりますので注意が必要です。「新規格では20000Mbpsの超高速な通信速度を実現するんです」と言われても、普通はピンと来ません。
なので、比較対象と比べて数字を言うようにしましょう。たとえば「旧規格が200Mbpsだったので、新規格はその約100倍の速度です」と言えば、詳しくない人でもその速さ、革新性をイメージできるでしょう。
他にも、「1日2000個できる商品が、毎日3時には売り切れます」「私は80キロだった体重を、これを使って2カ月で68キロまで落とせました」などなど、数字を入れることで切れ味が増す事例はたくさんあります。
ちょっと調べたり計算したりして、話に数字を入れてみてください。
■つまらない話には「事例」がない
ポイント3。つまらない話には、事例がありません。だから退屈なのです。
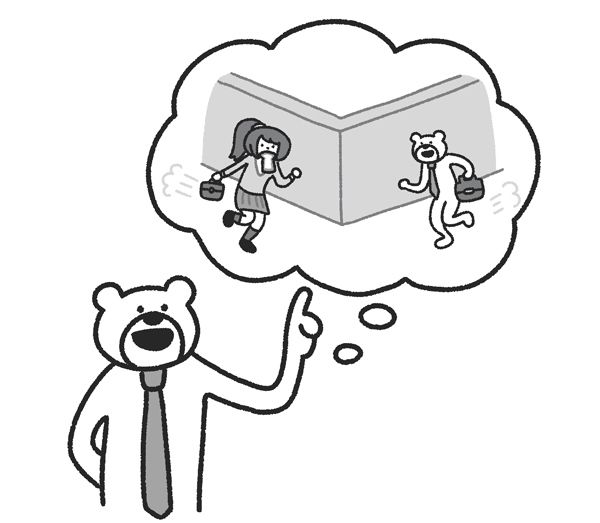
人との会話はもちろん、プレゼンにもライブ感は重要です。今日あった出来事を盛り込むと、聴衆の興味を引くと同時に、「プレゼン力が高い!」というイメージを与えられます。
ただ、どんな話をするかは考慮が必要です。単なる雑談にならないよう、入れ込むエピソードはプレゼンにつながる内容にしましょう。単なる雑談になってしまうと、一気に「出た、脱線……あと何分延びるんだ?」と思われてしまいます。
だから、「お金」の話であれば「お金」のエピソード、「イライラ解消グッズ」の話であれば「駅で怒っている人」のエピソードを入れるのです。
■「今日あった出来事」を入れ込むリアリティ
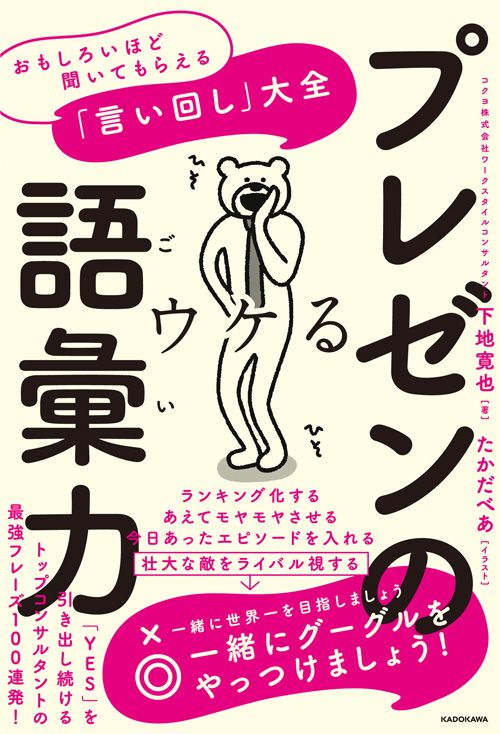
たとえば子供向けのスマホアプリの話であれば、駅で見かけた親子のエピソードは使えます。「今日、困った親子を見まして、子供は商店街をドンドン進んでいくのですが、母親はスマホで電話していて子供に注意を払っていない。しばらくすると……」みたいな感じです。
そして、「泣きじゃくる子供を抱っこしたお母さんが子供に謝る姿をみてホッとしました。よくあることだと思いますが、今日プレゼンしたいスマホアプリも……」と本筋に戻します。
「今朝、幼稚園の前で子供を叱っているお母さんが急に……」とか「今日、ランチタイムに店員さんにこんなことを言われました」などと話し始めたら、「お、何があったんだ?」と気になりますよね。
すぐに本題に入る単刀直入さも有効なスキルですが、あわせてこの「今日あった出来事を盛り込んだリアルさ、ライブ感」というスキルもぜひ、身に付けていただきたいと思います。
----------
コクヨ株式会社ワークスタイルコンサルタント
1969年、神戸市生まれ。2008年から[コクヨの研修]スキルパークを主宰。未来の働き方を研究するワークスタイル研究所の所長、ファニチャー事業部の企画・販促・提案を統括する提案マーケティング部の部長などを経て、現在は経営管理本部にて、コクヨグループの働き方改革や風土改革に取り組んでいる。
----------
(コクヨ経営管理本部シニアエキスパート 下地 寛也 イラストレーション=たかだべあ)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「ただいまご紹介にあずかりました」は絶対ダメ…スピーチの達人が勧める"とっておきの語り出し"
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分
-
ゲームやYouTubeを取り上げてはいけない…「頭のいい子」を育てるために親が子に繰り返すべきフレーズ
プレジデントオンライン / 2024年5月26日 10時15分
-
5歳までは「夜8時までに就寝」が鉄則…帰宅後30分で寝かしつけを始める小児科医の子育てルール
プレジデントオンライン / 2024年5月25日 10時15分
-
テレビ東京「何を隠そう…ソレが!」(2)新たな雑学スター誕生に注目
スポニチアネックス / 2024年5月21日 7時3分
-
ちょっとした会話でウケる人・ウケない人の違い 雑談でうっかり「そもそも論」していませんか?
東洋経済オンライン / 2024年5月4日 10時0分
ランキング
-
1サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分
-
2「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点
東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分
-
3秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ
読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分
-
4食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰
時事通信 / 2024年6月1日 13時55分
-
5「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










