なぜ頭の悪い人のプレゼンには「難しそうな言葉」がたびたび出てくるのか
プレジデントオンライン / 2021年8月18日 9時15分
※本稿は、小西利行『プレゼン思考』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
■「ムズカシクする人はアホ。カンタンにする人が天才」
プレゼンの基本とは何でしょう?
それは人の心を動かすことです。そして、そのためには難しいことをカンタンにして話したり、相手が興味を持つように話すことが必要です。
思いが相手に届き、共感されるプレゼンができれば、ビジネスも人生もうまくいきます。そのプレゼンの核にあるのが、「人の心を動かす」というシンプルな目的なのです。
僕は、プレゼンが苦手だった若い頃、その目的を意識するだけで、相手が共感する提案ができるようになりました。そして、そのときに生まれた僕の指針が、「伝える」より「伝わる」。
自分は伝えたから後は知らない、という責任逃れをやめ、相手にしっかりと伝わるまで諦めずに提案をする、という意識改革が、すべてを変えたのです。
ちなみにその頃から、僕は、「ムズカシクする人はアホ。カンタンにする人が天才」だと思うようになりました。世の中には難しい言葉や難解なロジックを使って「頭が良いように見せる」人もいますが、本当は、難しいことを誰もがわかるカンタンな内容にするほうが、頭の良いことだし、数百倍は困難だと思います。
■たくさんの人を幸せにするために
でも、僕はその困難なほうへ向かうようにしたのです。なぜなら、そうすることで、たくさんの人に買ってもらい、たくさんの人に愛してもらい、そしてたくさんの人を幸せにすることができるからです。

商品や思いをより多くの人に共感してもらうためには、まず、より多くの人に伝わることが大切です。そして、そのためにはカンタンであることが必須です。だから僕は、難しい話をカンタンにして、誰もが共感できることを目指すのです。
難解なことの面白さや、不可解なことの楽しさもわかったうえで、それでも、できるだけカンタンに、わかりやすく、興味がわくように書き換える。それが僕のやり方であり、本書のベースになっている考え方です。
ちなみに、僕が徹底してそこにこだわるのは、それこそが、プレゼンの本質だと思っているからです。僕がプレゼンで目指すのは、提案内容が相手に深く伝わり、その人たちが「自分ごと」として考えるきっかけとなり、さらに周りの人に話したくなること。
そのためには、カンタンでわかりやすいことが必須というわけです。そしてその意識は、これからの時代にとても大切なことだと思うのです。
■「話し手」ではなく「聞き手」の立場で話す
僕は、「プレゼンが苦手なんです」という人から、相談されることがよくあります。学生から経営者まで、いろんな人がいろんな立場で「プレゼンがうまくなりたい」とやって来ます。そんなとき、僕はまず、「聞き手になって話してください」と言うことにしています。
なぜならそれが、最高のプレゼンへの最初のステップであり、それだけでも十分に、プレゼンがうまくなるからです。
「どう話せばスムーズに理解できるか?」「何を話せば興味を持てるか」といったことを、相手側の立場に立って考え直してみるだけで、自分のプレゼンの中身を客観視でき、「これじゃわからない」「興味が湧かない」「長く話しすぎ」などの気づきが生まれ、プレゼンがわかりやすくなります。
言い換えると「相手の立場に立って」考え、つくり、話すということ。ただそれを意識するだけでも、プレゼンががらりと変わります。実際に、それを部下にアドバイスするだけで、すごくわかりやすく面白いプレゼンになったことが何度もありました。
「答えは相手の中にある」は、僕の口癖のひとつですが、長い経験から見ても、それは真実だと思います。どんなときも、届けるのは「自分の思い」なのですが、相手の立場に立てば、思いの届け方に「答え」があるとわかるのです。
僕の大好きな落語家である立川志の春さんも「お客様がどう思っているかで、話す内容も、話し方も変える。そうすることで、相手がもっと面白がってくださるんです」と話されていました。相手の立場に立つことは、芸を極める答えでもあるのでしょう。
ちなみに演劇には「我見(がけん)」と「離見(りけん)」という言葉があり、その中でも、客席側からの視点を指す「離見」が大切だと教えられるそうです。いずれも、相手の中に答えがあるということだと思います。
これはもちろんプレゼンでも同じこと。大切なのは「離見」です。相手の立場に立って自分のプレゼンを見るスキルをモノにすれば、最高のプレゼンに一歩近づけます。
もちろん「相手の立場で考えるのが大切だなんて知ってるよ」という人も多いと思います。そんなに珍しい考えではありませんし、「お客さま発想」のようなキーワードも多くの会社のスローガンとして掲げられています。なのになぜ、本稿の最初にこの話をしているか?
それは、この「相手の立場に立つ」ということこそが、企画やプレゼンでもっとも大切なことであり、ほぼすべての企業や人ができていないことだからです。
■「相手のために」話すのは、間違い
相手の立場に立とうというと、よく「相手のために話せば良いのですね?」と返す人がいますが、それは大きな間違いです。「相手のためにすること」と「相手が望んでいること」は同じではありません。
相手のために考えても、結局は自分たちが考えた、自分たちがやりたいことを押し付けることになりがちです。
2020年の春には、コロナ禍で窮地に追い込まれた飲食店を救うために金銭的な支援をする活動が多くありましたが、実際に飲食店のシェフに聞くと、「気持ちはうれしいけれど、施しだとプライドが傷つく。プロとして美味しいものを提供して対価をもらいたい」と話していました。
「助けたい! だから相手のためにお金を寄付します」というのは、ある意味「出し手の論理」です。でも、相手の立場に立てば、しっかりと美味しい料理を食べてもらい、納得して対価をもらいたいという本音が発見できます。そうすれば違うアイデアも生み出せるわけです。
人は、プレゼンでも、会議でも、後輩へのアドバイスでも、子どもへのしつけでも、さらにはプロポーズですら、「相手のために」と思いながら、ついつい自分のエゴを出してしまいます。
「自分の思いを必死で伝えれば、それを相手も受け止めてくれるし、相手のためにもなる」と自分に都合よく解釈してしまうのです。相手側にすればそんなエゴに付き合うのも嫌なので、ニコニコしながら軽くあしらったりもするでしょう。
付き合って間もない恋人のように、相手を理解しようとしているなら別ですが、普段の会話で一方がエゴを押し付けると、「まあ適当に聞いておこう」で終わるのが現実。
これがプレゼンとなると、お金のやり取りや仕事上の責任が発生するので、相手のエゴなど聞くはずもなく、「自分や会社に都合良いこと以外は、すべて突っぱねよう」という壁が生まれ、意思疎通がさらに難しくなります。
普通の話し合いでも難しいのですから、プレゼンでは、内容のほとんどが「うまく伝わらない」と考えたほうが良いでしょう。
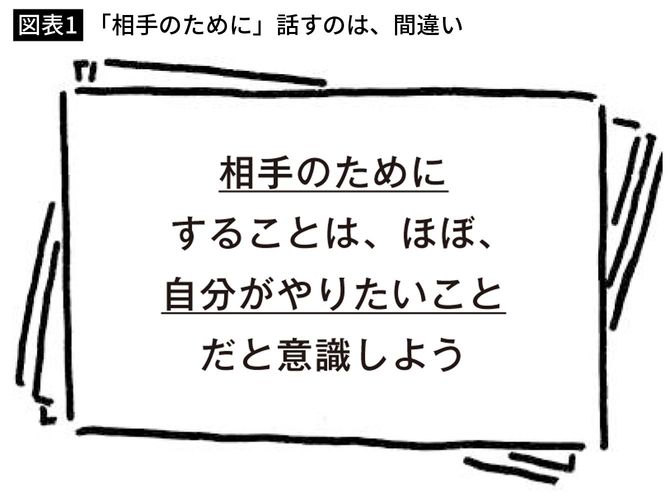
僕は、すべてのプレゼンが、いわば「不相思不相愛」から始まると思っています。そして興味がないことを興味があることへ逆転するのがプレゼンの本質だとも思っています。だからこそ、自分から歩み寄り、相手に伝わるように努力すべきなのです。
「いやいや、相手も歩み寄るべきだ」という人もいると思いますが、プレゼンの成功を相手任せにしないためにも、まずはあなたから行動すべきだと思います。
■そもそも相手は聞いていないという前提
相手に歩み寄るためには、「相手は聞いていない」という前提から考え始めることが大切です。残念ながら、「プレゼンを聞いてもらえている」と思うのは幻想です。
たとえ出席者全員がうなずいていても、本当にあなたの話を聞いているとは限りません。興味のない話だと思ったらうなずきながらスルーするでしょうし、「今日の夜ご飯、何食べようかな?」と別のことを考えている人もいるでしょう。
リモート会議では、画面に向かって相槌(あいづち)を打ちながら、違うメールに返信しているなんてザラ。それらはもちろん聞いていないのと同じことです。聞いていなければ共感もされず、もちろん合意もされません。
だから大切なのは、聞いていない人に聞いてもらうことです。なんだか禅問答のようですが、つまり、「相手は聞いていない」というスタンスを持って、聞いてもらうにはどうするかを考えることが「伝わるプレゼン」の第一歩になるのです。
プレゼンは相手があるものです。だから「プレゼンは水ものだ」と言う人もいます。でもその考えは絶対に間違いだと僕は思います。相手が決めることであっても「絶対に成功させる」という思いこそが、あなたのプレゼンを変えます。
「聞いてもらえる」という姿勢は、プレゼンの成否を相手に委ねています。逆に、聞いてもらえないという前提で「絶対聞きたくなるプレゼンにする」という発想は、プレゼンの成否をあなた側に引き寄せるのです。
■聞きたくなるように変換する努力を
では聞く気がない相手が、聞くようになるにはどうすればいいか?
その答えは簡単です。「相手が聞きたくなるように、話せばいい」のです。
「なあんだ、本当に簡単ですね!」と思った人は……あまりいませんよね? そうです。理屈は簡単ですが、かなり難しいことです。そもそも相手が聞きたくなることが何なのかわからないし、本当に相手のために提案するなら、相手の耳が痛くなることも話さなきゃならない。
それをすべて「相手が聞きたくなるように」するなんて、本当に難問だと思います。でも、そうした難問があることを理解することからすべては始まります。
そして、相手が聞きたいことも聞きたくないことも、聞きたくなるように変換する努力を始めれば、誰にとってもカンタンで聞きやすく、納得できるプレゼンができます。それだけでも、あなたの提案は通り始め、ビジネスは飛躍的に成功へと進み始めるでしょう。
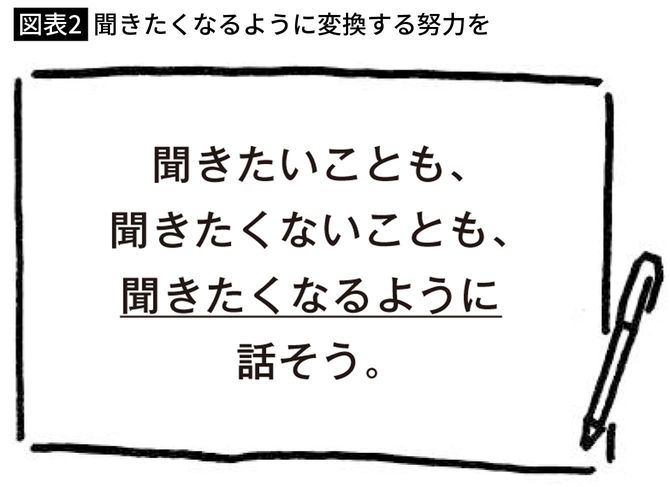
----------
POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター
1968年、京都府生まれ。大阪大学卒業後、博報堂を経て2006年に独立。CM制作、商品開発から、街づくりや国の戦略構築も行う。手掛けた広告は「伊右衛門」「ザ・プレミアム・モルツ」を含め1000本以上。2017年に「プレミアムフライデー」を発案。2021年には「GOOD EAT COMPANY」にてブランディング&クリエイティブディレクションを担当。同社CXOにも就任。著書に『伝わっているか?』(宣伝会議)、『すごいメモ。』(かんき出版)がある。
----------
(POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター 小西 利行)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「どっちのネックレスがいいと思う?」仕事がデキる人がプライベートの会話でも実践している一流の返答テク
プレジデントオンライン / 2024年5月28日 7時15分
-
部下に「君の気持ちはよくわかる」は絶対NG…共感でも傾聴でもない、部下の本音を見抜ける上司がしていること
プレジデントオンライン / 2024年5月25日 17時15分
-
沈黙を埋めるために当たり障りのない話題を振るのは絶対ダメ…心理カウンセラーが「沈黙を全く恐れない」理由
プレジデントオンライン / 2024年5月24日 15時15分
-
「悩みごとに感想を言う」は絶対ダメ…「子どもが不登校で」と打ち明けてくれた人に返す寄り添いフレーズ
プレジデントオンライン / 2024年5月20日 15時15分
-
会った瞬間に相手の長所を7つ見つけられるか…「話していて気分がいい人」がしている「積極的傾聴」3要素
プレジデントオンライン / 2024年5月17日 15時15分
ランキング
-
1バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?
日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分
-
2中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明
時事通信 / 2024年6月15日 16時44分
-
3「南高梅」が全国で記録的不作、価格は例年の3〜4倍に…「こんなことは初めて」
読売新聞 / 2024年6月15日 12時4分
-
4投資の神様「ウォーレン・バフェット」の功罪。他の投資家と何が違ったのか【プロの投資家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月15日 8時15分
-
5リニア工事で井戸などの水位低下、JR東海の対応策を静岡県が了承
読売新聞 / 2024年6月15日 18時22分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












