「若者向けの政策ができないのは、若者が投票に行かないからだ」そんな政治家を絶対に信じてはいけない
プレジデントオンライン / 2022年3月26日 10時15分
※本稿は、西田亮介『17歳からの民主主義とメディアの授業 ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。
■高齢者層を優遇する政策は多数行われている
【先生】「手厚くない」かどうか厳密に立証することは難しいですが、年長世代を優遇する政策が行なわれているということは明確です。
年金の給付水準に関して、物価が下がるデフレ下においては年金の給付水準も下げないと釣りあいません。
物価は下がっているのに給付額が変わらないなら、実質的には年金の給付水準=価値が高いことになりますよね。日本は「失われた30年」などと呼ばれる超低経済成長社会で、長いデフレ状態です。
少子高齢化等で負担と給付のバランスも崩れています。そこで年金支給額の抑制のためにマクロ経済スライドという考え方を2004年に小泉政権が導入しました。ただ、給付引き下げを行なうと高齢者からの反対があるということで実施が2015年度まで遅れました。結果、年金財政に影響を与えたということが知られています。高齢者優遇の例です。ただし、いくつかの研究では医療費の伸びは高齢化だけでは説明できず、医薬品価格など、他の要因にも目を向けるべきという指摘もなされています。
また、70歳以上の高齢者の医療費負担は長く無料でしたがいまは1割で、2022年から2割になります(年収制限あり)。これも高齢者優遇と言えるかもしれません。
若者の投票率が低いことが直接の原因かどうかはさておき、ボリュームが多くて、投票率が高い、つまり政治的影響力の大きな高齢者を優遇するような政策が多数行なわれています。
■若者や子育て世代は「数」で明らかに不利
ここでちょっと考えてみていただきたいんですけど、団塊世代(1947~1949年生まれ)の出生数は厚生労働省の統計によると806万人です。その子どもにあたる団塊ジュニア世代(1971~1974年生まれ)が各年、出生数200万人を上回るぐらいでした。
最近はどうかというとご承知のとおり100万人を大きく割り込んで、出生数80万人台になりました。
いまの20歳代の場合、120万人を割るか割らないかくらいですね。
さて、選挙に直接影響を与えるのは投票率ではなくて、投票数です。
投票率も高いほうがいいのかもしれませんが、政治家にとってみればやっぱり何票取れたかということが重要です。そう考えてみると若い世代の場合、絶対的に数が足りないんですよ。
政治家は「若者や子育て世代は投票しないから、あなたたち向けの政策ができない」などと無茶苦茶なことを言っています。若者と政治に関する政治家のインタビューで、よく見かける論調です。
でも、若い人たちはもともと人口が少ないわけですから、年長世代と同じような政治的影響力を持つことはできません。
だから若者や子育て世代が投票しないから政策を手厚くできないなどという政治家や政党を信頼するな、そういう人たちに投票するな、とぼくはいつも思っています。
■投票率が下がると、一般の人たちの声が反映されにくくなる
投票数についてお話ししましたが、では、「投票率が高いほうがいいのか、低いほうがいいのか」と言ったときに、低いとどうなるのでしょうか。
投票率が低くなると、一般の人たちの関心や声よりも、いつも投票する人たち、政治に対して強い利益関係がある人たちの声が反映されやすくなります。利益団体、業界団体や、政治を強く支持しているような宗教団体ですね。これは要するに創価学会のことです。
経済団体もそうです。日本で最大の利益団体である日本経済団体連合会、通称経団連は社として加盟し、経済同友会には経営者が個人で加盟します。とくに経団連は政策評価を行ない、政治献金や票の取りまとめをします。医師会も同じです。
野党の側に目を向けてみれば労働組合や、そのナショナルセンターである日本労働組合総連合会(連合)があります。産業別労働組合は候補者を擁立し、国会に議員を送っています。業界団体や労働組合から出る政治家を「組織内候補」や「組織内議員」と言います。低投票率下においては、前にも少し述べましたが、そういう政治に関して強い関心を持っている人たちの声が当然議席に反映されやすくなります。

■天候と投票率の関係では「くもり」がちょうどいい
2000年代に森喜朗総理が「無党派層の有権者は寝ててくれればいい」というようなことを口走り、非難が集まりました。
自民党の評判が悪い中、選挙に一般有権者の声が反映されると政権党である自民党にとって不利だからです。だけれども投票日に寝ててくれれば、自民党のいつもの支持層が投票するので、有利になるという主旨です。たしかにそのとおりなのですが、正直すぎますね(笑)。
他にもたとえば天気や気温が投票率に影響することが知られています。天候が悪いとやっぱり投票率が下がる傾向にあります。
でも、天気がよくても外出してしまったりして投票率が伸びるわけでもありません。天候と投票率の関係で言えばくもりくらいがちょうどよいようです。
■メディアや報道も政治に影響を与えている
ぼくは印象やイメージの影響に関心を持っています。情報番組やワイドショー、SNSでの論調のようなものです。
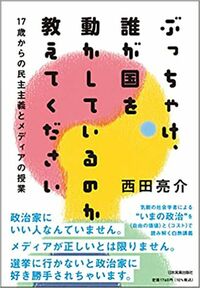
最近だとリアリティ・ショーの出演者がネットの誹謗(ひぼう)中傷を苦にして自殺した「テラスハウス」事件がありました。
人が亡くなると、日本の社会に大きなインパクトを与えますね。ネットの誹謗中傷対策が、政治の世界や外資系のプラットフォーム事業者も巻き込む形で一気に進みました。ネットの誹謗中傷は前から認知されていた問題です。
SNSや検索サイトを運営する外資系のプラットフォーム事業者は日本の規制や所轄官庁に対して日本的に言えば大変不誠実で、のらりくらりとしか対応しないのがつねですが、亡くなった方が出てしまったことで世論の関心が著しく高まったととらえたようです。他にも働き方改革を巡る問題でも、電通の若い女性社員が亡くなる事件がきっかけになって、労働環境改善とか、ワークライフバランスということが強く言われるようになりました。
なので、政治を動かすのは必ずしも投票率には限らないというわけです。
ワイドショーや視聴率が高い情報番組で繰り返し取り上げられるなど、そういったことも政策や政治に影響を与えます。「劇場型政治」などと呼ばれています。
また、世論の反応や受け止められ方を分析して、コミュニケーション戦略を設計する専門家のことを「スピンドクター」などと呼びます。
----------
東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 准教授
1983年、京都生まれ。専門は社会学。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励II)、独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、立命館大学大学院特別招聘准教授などを経て現職。著書に『メディアと自民党』(角川新書、2016年度社会情報学会優秀文献賞)、『なぜ政治はわかりにくいのか:社会と民主主義をとらえなおす』(春秋社)、『情報武装する政治』(KADOKAWA)、『ネット選挙 解禁がもたらす日本社会の変容』(東洋経済新報社)などがある。
----------
(東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 准教授 西田 亮介)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
鹿児島県知事選 告示まで2週間余り 塩田氏先行 米丸氏・樋之口氏追う
MBC南日本放送 / 2024年6月4日 19時43分
-
公的年金は「100年安心」からどんどんかけ離れていく…政府がNISAで「貯蓄から投資へ」を後押しする残念な理由
プレジデントオンライン / 2024年5月28日 17時15分
-
ブラマヨ吉田 0歳児選挙権反対の泉房穂氏に柔軟性訴え「誰しもが泉さんのようにパワフルでは…」
スポニチアネックス / 2024年5月28日 16時15分
-
4人に1人が65歳超え…“超高速高齢化”日本を待ち受ける、2040年、まさかの光景【経済のプロがシミュレート】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月25日 8時15分
-
社会保障拡充に協力的な財界と反発する労働組合 子育て支援金をめぐる日本の摩訶不思議な現象
東洋経済オンライン / 2024年5月20日 8時0分
ランキング
-
1岩田明子 さくらリポート 都知事選「小池氏VS蓮舫氏」は「保守VS左派」の構図 国政にも影響の〝首都決戦〟気がかりな「つばさの党」幹部の出馬表明
zakzak by夕刊フジ / 2024年6月5日 6時30分
-
2「車を蹴られてへこんだ」停車中のタクシーのドアを蹴って…通りすがりに悪態か、酒に酔った自称25歳の男「何もやっていない。意味がわからない」
北海道放送 / 2024年6月5日 8時59分
-
3花壇へ水やり中の女性が通りすがりの女に果物ナイフで背中刺される 女を逮捕 2人に面識なし 滋賀・彦根市
MBSニュース / 2024年6月5日 7時20分
-
4万博ポスター、交野市が撤去…市長「府の強権的な手法に対する抗議として指示」
読売新聞 / 2024年6月5日 8時46分
-
5出生率、過去最低1.20=8年連続低下、東京は初の1割れ―人口減少幅は最大・厚労省
時事通信 / 2024年6月5日 14時21分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












