開発担当者が「私自身がこれを買いたい」と断言できないとダメ…アイリスオーヤマが家電で成功できた理由
プレジデントオンライン / 2023年6月28日 13時15分
※本稿は、村松進『アイリスオーヤマ 強さを生み出す5つの力』(日本経済新聞出版)の一部を再編集したものです。
■なぜアイリスは年間1000点も商品を出せるのか
日用品から家電、食料品まで幅広く手掛けるアイリスオーヤマは1年間に約1000アイテムの新商品を発売する。アイリスオーヤマが独自性の高い多くの新商品を素早く発売できる背景にあるのが、毎週月曜に開く新商品開発会議(プレゼン会議)だ。
どんな企業でも会議は開いている。しかし大山健太郎会長は「一般的な会社は月次会議で経営の方針を決める。当社は社長や幹部が集まって毎週1回、年間では約50回の会議を開いて現場担当者から商品開発のプレゼンテーションを聞く」と頻度の違いを強調する。
プレゼン会議で担当者が1つの商品の説明に費やす時間は約5分間で、大山晃弘社長がゴーサインを出せば会社としての開発方針が決まる。
そして「当社が速いのは開発スピードではない。ジャッジ(判断)スピードだ。プレゼン会議は社長の考えを社内に浸透させる場でもある」と大山会長は言う。「1人の社員が50回の会議に10年出れば、合計で500回だ。この会議自体が情報を共有する機会になっており、他社がまねしようとしても簡単なことではない」と強調する。
■プレゼン会議で社長が話していること
アイリスオーヤマのプレゼン会議で、大山晃弘社長と担当者は一体どんな会話をしているのか。日本経済新聞社のコンテンツ配信「NIKKEI LIVE」で実際の会議を取材したことがある。それは、こんな内容だった。
小型家電事業部の社員が、大山社長をはじめとする幹部が扇状に広がって座る会議室の中心部に立つ。そして新商品の開発に向けて練ってきたアイデアのプレゼンテーションを始める。
ある製品の市場規模や価格動向などを説明する社員に大山社長は「結構な値段だよ」と語りかけ、価格へ注意を払うことを促す。
「そうですね。私も想定よりは、ちょっと高いなという感覚はありました」と答える社員に、大山社長はしばらく沈黙した後で「ちょっと高いんじゃない?」と聞き返す。その後で「そうね、デザインで売るんだな」とつぶやいた。
ここからが経営トップとしての判断だ。「デザインで売るんならデザインが無いと、なんとも言えんな」と述べたうえで「何を作るのかということが、明確じゃないじゃん」と課題を指摘する。「もうちょっとさ、明確にしようや。ブレてるよ。これ、ただデザインや見た目がいいだけじゃん。欲しいと思う人が、ちょっとそれじゃ少ないんじゃない?」と疑問を投げかけた。
■「売りたい」ではなく「自分が使いたい」
別の社員が「分かりました。デザインとあわせてもう少し具体的に掘り下げて、また提案させていただきます」と引き取ろうとしたところで、大山社長は「いや、たぶん分かってないと思うよ」と言い切る。
そして「何をお客さんに提案するのかっていうところを、もう少し事業部で考えないと、いかんわ。コンセプトがまだ定まってないよ」と続ける。社員が「もう一度、考え直します」と答えると大山社長は「商品としてはやりますが、コンセプトはもっと練り直してください」と条件付きの承認で締めくくった。
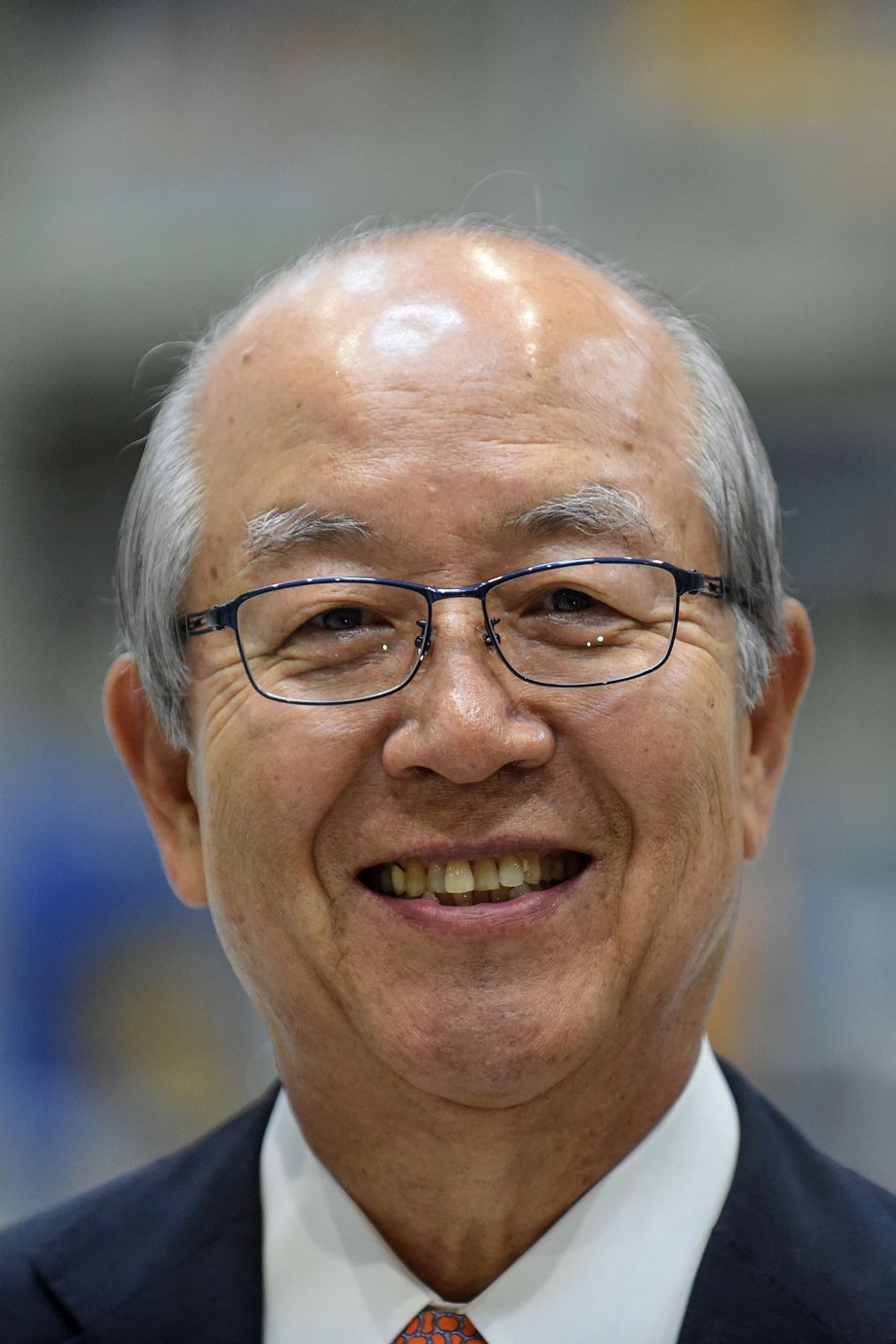
会議後に大山社長は社員とのやり取りについて「今回はちょっと厳しい話をしたが、顧客イメージが、ちょっとぼんやりしていた。さらに、どちらかと言うと『売りたい』という意識が強かった。使ったらどういう便利な機能があるのかを語り『自分が使いたい』という気持ちを持っていないように感じた」と背景を説明した。
そして条件付きの承認としたことについて「担当者が『この商品は、こんなことができます』という開発目線だった。『こういうことができるから、この商品を私は買いたいです。だから作りたいです』という目線が無かったことが気になった。突っ込んだ議論をすると、まだまだ弱いなと感じた」と理由を明かした。
■社長が直接「駄目出し」する効果
会議で指摘を受けた社員は「口では消費者目線と言っていたが、そうなれていなかった。他社の競合品などを見て、スペックや価格に目が行ってしまっていた。もう一歩踏み込んだ消費者目線の提案ができていれば通ったのではないかと思う」と反省していた。
社長が社員に直接「駄目出し」をすることで、経営陣と同じような意識を持てるように人材を育てることがアイリスの流儀だ。
社員の立場で考えれば、社長をはじめとする多くの幹部の前で自身のアイデアをプレゼンすることは大きなプレッシャーだ。しかも同僚が見ている前で厳しい指摘を受ければショックも受ける。それでも「合格」するまで、あきらめずに再提案することが自身の成長にもつながる。
■アイリスオーヤマ社員が自宅でする「使い倒し」とは
アイリスオーヤマは失敗を恐れず、それを糧として新たな手を組織全体で次々に打ち続ける。そして他社が犯した「失敗」も、自社の力にしてしまう。その典型例が他社製品の「使い倒し」だ。
開発担当者が会議で自身のアイデアを通すには、生活者に「なるほど」と思わせるデザインや機能などを示すことが欠かせない。そのために技術者たちは自身がユーザーとなり、生活者の立場で同業他社の製品を徹底的に使ってみる。その行為を使い倒しと呼んでいる。
■パナソニックとアイリスの決定的な違い
2017年の夏、アイリスの商品開発の秘訣(ひけつ)を探るため、各地の拠点を取材した。最初に向かったのは大阪市にあるアイリスの家電開発拠点「大阪R&Dセンター」だ。社員証をかざさなければドアが開かないフロアには、多くの試作機が他社製品とともに並んでいた。その近くでは技術者たちが開発中の商品の動作確認や、他社製品との性能比較に追われていた。
担当者の多くは他社からの転職者たちだった。当時のデザインセンターマネージャーは、かつてパナソニック(現パナソニックホールディングス)で洗濯機や炊飯器、テレビなどのデザインを担当していた経験を持つ。「パナソニックのデザイン部門と比べれば、うちの人数は100分の1ぐらい。そして仕事の進め方は正反対だ」と語った。
マネージャーはアイリスに入社した直後の時期に、社長だった大山健太郎氏から意外な言葉で叱責(しっせき)を受けたことがある。「そんな数字より、おまえ自身はどう思うんや」というセリフだ。
少量の油で揚げ物ができる調理器の開発会議で自分が考案したデザインの長所を示すため、他社製品と比べた市場調査の結果を示したときのことだった。
「パナソニックでは複数の部署と連携して市場調査などのデータを過不足なく集め、様々な会議を確実に通す提案書を書けるのが優秀な人材だった」と振り返る。
一方で、アイリスは許可を得る手順が極端に少ない。毎週月曜に宮城県の主力生産拠点で開くプレゼン会議で計画が了承されれば、それで決まりだ。
■他社製品の不満を100個挙げる
プレゼン会議では担当者が大山健太郎氏から、必ずといっていいほど投げかけられる言葉があるとマネージャーは明かした。「その商品、どこが『なるほど』や」だ。「その質問に確実に答えるため、我々は他社の製品を使い倒す」と技術者としての日常を語った。
アイリスの技術者たちは他社製品を自宅で実際に使ってみて、不満や文句につながる「マイナスポイント」を見つけることに余念がない。家電製品ならば稼働している際の騒音が大きい、操作ボタンの配置が悪くて扱いづらい、本体が重すぎて1人では持ち運べないといった基本的な特徴が挙げられる。
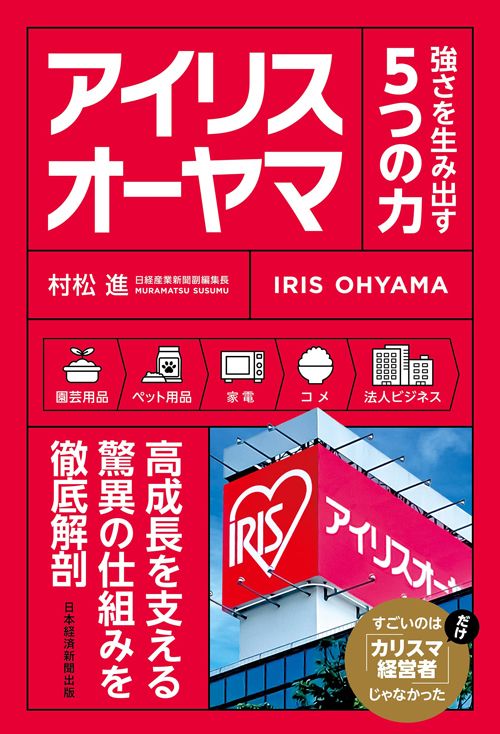
これらに加えて「緩衝用の発泡スチロールが引っかかって段ボール箱から取り出しにくい」といった何気ない内容まで、開発担当者が実際に使ってみて感じた全ての不満や「失敗」が対象となっていた。「開発チームで最大100個は不満を挙げる」とマネージャーは実態を明らかにした。
そして100個の不満や失敗のうち、自社の技術で解決できるものを選び抜いて新商品に反映させる。技術者が他社製品の不満を解消し、プレゼン会議で「誰よりも私自身がこの新商品を買いたい」とトップを説得できたとき、プロジェクトにゴーサインが出る。そんな体験談を語っていた。
こんな過程を経て消費者から「なるほど」の声を引き出した商品は強い。2016年10月下旬に発売したヨーグルトメーカーはセ氏25度から65度まで1度刻みで温度を設定できる機能を持たせて、甘酒や納豆も自宅で作れるようにした。当初の年間販売目標は4万台だったが、販売開始から9カ月で10万台以上を売るという予想を超える実績を残していた。
----------
日経産業新聞 副編集長
1971年和歌山県生まれ。94年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、日本経済新聞社に入社。東京本社や大阪本社、甲府支局、仙台支局で一貫して企業報道を担当し、ヘルスケア分野の取材経験が長い。2014年に企業報道部次長、20年から現職。
----------
(日経産業新聞 副編集長 村松 進)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
最大22.8日間(※1)の高い保冷力を実現した「HUGEL 真空断熱クーラーボックス60L」発売
Digital PR Platform / 2024年5月22日 12時49分
-
防災・減災や産業振興などで連携 宮城県石巻市と包括連携協定を締結
PR TIMES / 2024年5月17日 15時45分
-
最大51%オフ! アイリスオーヤマ家電が安い「アイリス祭」が開催中
マイナビニュース / 2024年5月14日 17時53分
-
アイリス祭2024 5月14日よりオンライン開催 アウトレット商品(※1)が最大51%OFF
PR TIMES / 2024年5月13日 13時15分
-
アイリス祭2024 5月14日よりオンライン開催 アウトレット商品(※1)が最大51%OFF
Digital PR Platform / 2024年5月13日 11時12分
ランキング
-
1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点
東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分
-
225年末まで減産延長=油価下支えへ―OPECプラス
時事通信 / 2024年6月2日 23時29分
-
3PIAAからヘッド&フォグ用LEDバルブ 6000K「超高輝度」シリーズ・5製品が登場
レスポンス / 2024年6月2日 10時30分
-
4なけなしの貯金と「年金月14万円」で暮らす70代女性、冷房代が払えず「“タダで涼める”スーパーへ避難生活」が続くも…「店長のひと言」で人生が一変したワケ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月29日 9時0分
-
5万博「経済効果」は2.9兆円? 国と民間、大阪府市で異なる予測の数字なぜ
産経ニュース / 2024年6月2日 18時43分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










