アメリカ人も「EVシフトと脱炭素は拙速だった」と気付いた…豊田章男会長の「4年前の予言」に注目が集まるワケ
プレジデントオンライン / 2024年5月24日 9時15分
■「EVシフトだけで脱炭素は実現できない」
電気自動車(EV)の販売に急ブレーキがかかっている。各国は「EVシフト」目標を掲げていたが、一般消費者への普及の壁である「キャズム」を乗り越えることが困難で、新車EV販売の楽観的な目標達成は現実的ではないとの見方が支持を増やしている。代わりに、トヨタ自動車の豊田章男会長による「自動車市場でEVは最大3割のシェアにとどまる」という予想が現実味を帯びてきている。
加えて注目されているのが、豊田氏が2020年12月に日本自動車工業会のオンライン懇談会で発した次の言葉だ。
「乗用車400万台すべてをEV化すると電力が10~15%不足するが、これは原発でプラス10基、火力発電であればプラス20基に相当する」
「その投資コストは、約14~37兆円にも上る」
豊田氏の主張は、要するに「EVシフトだけで脱炭素は実現できない」というものだ。同時に、「再エネの普及には想像をはるかに超える経済的・社会的コストが発生する」とも指摘している。
■再生可能エネルギーの有効性が疑問視されている
この豊田氏の分析は、何も日本に限った話ではない。たとえば、米国や欧州では風力・太陽光などの再生可能エネルギーへのシフトが進められており、巨額の政府補助金が支出されている。
にもかかわらず、多くの再エネプロジェクトは高コスト体質を露呈している。
特に米国では、再生可能エネルギーの一部プロジェクトが不採算で打ち切りになったり、電気料金の高騰を招いている。そのため、「EVシフトがすぐには起こらないのと同様、再エネの急速な普及も非現実的」と疑問視され始めている。
本稿では、再エネ発電先進州であるカリフォルニアをはじめ、北東部諸州において再エネプロジェクトが頓挫している実態を紹介するとともに、再エネの是非が11月の大統領選挙において争点化している現状を伝える。
■カリフォルニア州の電気料金が高騰している理由
米国電力研究所(EPRI)が4月に発表したEV白書では、「EVが普及すると、そのスケール効果により電気料金が下がる」とされている。
米国でもっともEVシフトが進んでいるのはカリフォルニア州だ。カリフォルニア州の新車販売に占めるEVの割合は約25%。EVシフトの失速により前年比では減少しているが、それでも顕著に高い数字だ。
だが、カリフォルニア州の電気代は下がっておらず、むしろ激しい上昇を見せている。
2008年を基準とすると、2023年現在のカリフォルニア州の電気料金は、15.1%も値上がりしている。同じ期間に全米平均の電気料金が4.7%上昇したのに対し、カリフォルニア州の電気料金はなんと3倍以上もの値上がり率だ。
一方で、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、達成が困難な同州のEV普及目標のテコ入れを図るため、州内のガロン当たりのガソリン価格を2025年から毎年約50セント(80円)継続して値上げすることを計画中だ。
経済的事情からEVを購入できない人や、利便性の面からガソリン車やハイブリッド車を選ぶ人にとっては「懲罰的」な値上げとなる。
■再エネが普及するほど電気料金が上がる
カリフォルニア州は全米で最も再エネ発電が進む場所だ。
米国においては発電のおよそ60%が化石燃料、19%が原子力、21%が再エネというミックスとなっている(米エネルギー情報局調べ)。
一方、カリフォルニア州では、再エネの割合が2022年現在で32%と3分の1近くに達している。
再エネ推進派の主張によれば、再エネは安価で効率的な発電方法とされる。そのため、再エネが普及すればするほど電気代は下がるはずだが、そうなっていない。
電気代の高騰により、カリフォルニア州の電気契約者のうち約340万人もの人が、電気料金を滞納している。その総負債額は22億ドル(約3427億円)にも上るという。

■再エネのための負担は重くなる一方
民主党系のシンクタンクであるアメリカ進歩センターは、再生可能エネルギーは「無尽蔵で石油や天然ガスよりも経済合理性があり、エネルギーコストを下げる」とうたっている。
だが、再エネは想定よりはるかにコストが高くつく可能性があり、再エネを推進すればするほど、電気料金が高くなるのではと、米国の有権者は疑問を持ち始めている。
火力発電所が次々に閉鎖される中、風力や太陽光は発電量が不安定であり、それを補うバックアップ電源の建設にも莫大なコストが必要だ。
電気代の値下げが実現しないどころか、再エネ開発のための税負担や電気料金負担は重くなる一方だ。
■「バイデノミクス」への不満が高まっている
バイデン政権は再エネ推進を柱とする経済政策「バイデノミクス」に巨額の補助金を投じている。
だが、その巨額の投資そのものがインフレを加速させており、「バイデンフレーション」とさえ呼ばれている。
しかも再エネに投資しても電気料金は安くならず、むしろ高騰の要因にさえなっている。
バイデン大統領が就任した2021年1月以降の食品と電気料金を除いた物価上昇率は18%ほどにとどまるのに対し、電気代は27%も上昇していると、米エネルギー情報局(EIA)が報告している。
再エネへの投資も、元はといえば米国民が納めた税金だ。また、インフレによって生活が苦しくなるのも米国民自身である。
そのため、米国の有権者の間には、「バイデノミクス」への不満が高まっている。
バイデン大統領の経済運営に関しては、英紙フィナンシャル・タイムズが米国で5月に実施した世論調査において、58%が「満足していない」と回答。4月の55%から3ポイント増加し、支持率の低下が浮き彫りとなっている。

■民間企業の撤退が始まっている
いま米国では再エネ開発プロジェクトが中断するケースが増えている。
デンマーク企業のオーステッドはニュージャージー州沖で洋上風力発電の設備建設を手掛けていたが、予期せぬインフレによる経費増や、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げによる金利負担の膨張により、事業継続が困難になった。
同社は2023年6月に、州政府から特別に税額控除による還付金を受けたが、その後も基礎工事・電力ケーブル敷設・維持管理コストの高騰が止まらず、採算のメドが立たなかったため、合計で1.1ギガワットという2つの事業を2023年10月に中断した。
バイデン政権は2030年までに、1000万世帯分の電力に相当する合計30ギガワットの洋上風力発電能力を実現させる計画だった。だが、オーステッド、ノルウェーのエクイノール、英BP、スペインのイベルドローラなどの大手民間企業が、2023年末までに軒並み手を引いている。彼らが手を引いたのは、ニュージャージー州、ニューヨーク州やコネチカット州など合計12ギガワット以上もの大プロジェクトだ。
相次ぐ洋上風力発電事業からの撤退をかつての名作映画になぞらえて「風と共に去りぬ」というシャレまで作られている。

■それでも再エネ推進は続く
バイデン政権が2030年までに30ギガワットの発電能力獲得を目指す洋上風力発電は、カリフォルニア沖で計画中の分も含めて、その半分でも実現すれば御の字だと、ブルームバーグは伝えている。
こうした逆風にもかかわらず、ホワイトハウスは「洋上風力発電5カ年計画」を策定し、新たに10ギガワット分のプロジェクトを立ち上げようとしている。
さらに、バイデン大統領は「気候変動の緊急事態」を宣言し、大統領令で化石燃料の開発を大幅に制限する一方、議会承認の必要がない巨額の補助金を再エネ開発に投入することを検討中だと、ブルームバーグが4月17日に報じた。
ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事など北東部沿岸の民主党州の知事らは、洋上風力発電事業の入札条件を緩和し、完工時期に厳格にこだわらないほか、インフレに合わせてプロジェクト経費を入札額より15%ほど多く州に請求できるようにする再交渉で、洋上風力発電企業を呼び戻そうとしている。
■トランプ氏が「再エネ見直し」を宣言
こうした「バイデノミクス」への不満が高まる中、再エネ推進策の是非が大統領選の行方にも影響を及ぼしている。
トランプ前大統領は共和党の大統領候補に指名されることが確実視されているが、東海岸ニュージャージー州で5月11日に開催された支持者集会で、「洋上風力発電プロジェクトを標的とした大統領令を発布する」と宣言した。
具体的な内容は明らかにしなかったが、大統領令によって洋上風力発電の影響を改めて調査し、新規プロジェクトの許可を停止する可能性があると、ロイター通信は伝えている。
■「バイデン大統領がインフレをもたらしている」トランプ氏の攻撃
トランプ氏がニュージャージー州で宣言したことには理由がある。ニュージャージー州は米東部沿岸に位置し、民主党が強い州として知られている。
同州の家庭用電気料金は2023年に最大6.9%値上げされている。それに加えて、6月にはさらに最大8.6%も引き上げられる予定だ。
その結果、同州の家庭用電力はさらに20%を超える値上げがあり得ると予想されている。
トランプ前大統領とつながりが深い共和党系のシンクタンクであるヘリテージ財団の試算では、人口がおよそ930万人のニュージャージー州において、マーフィー知事が提唱する「完全再エネシフト」で合計11ギガワットの洋上風力発電能力を獲得するには、州民1人当たり8000ドル(約125万円)、総額で740億ドル(約11兆5346億円)の負担が必要だ。インフレ調整後には、さらに高額となる。
ニュージャージー州住民の洋上風力発電への支持率は、2019年9月の80%から、2023年9月には50%まで低下した。逆に、反対は15%から33%へ増加している。
トランプ氏の「再エネ見直し宣言」は、こうした状況を踏まえたものである。
「バイデン大統領は、採算の取れない再エネ推進で、『光熱費インフレ』をもたらし、コストの負担を住民に押し付けている」「バイデン大統領は生活に必須の電気代を高騰させ、貧しい人のお金を収奪している」と攻撃しているわけだ。
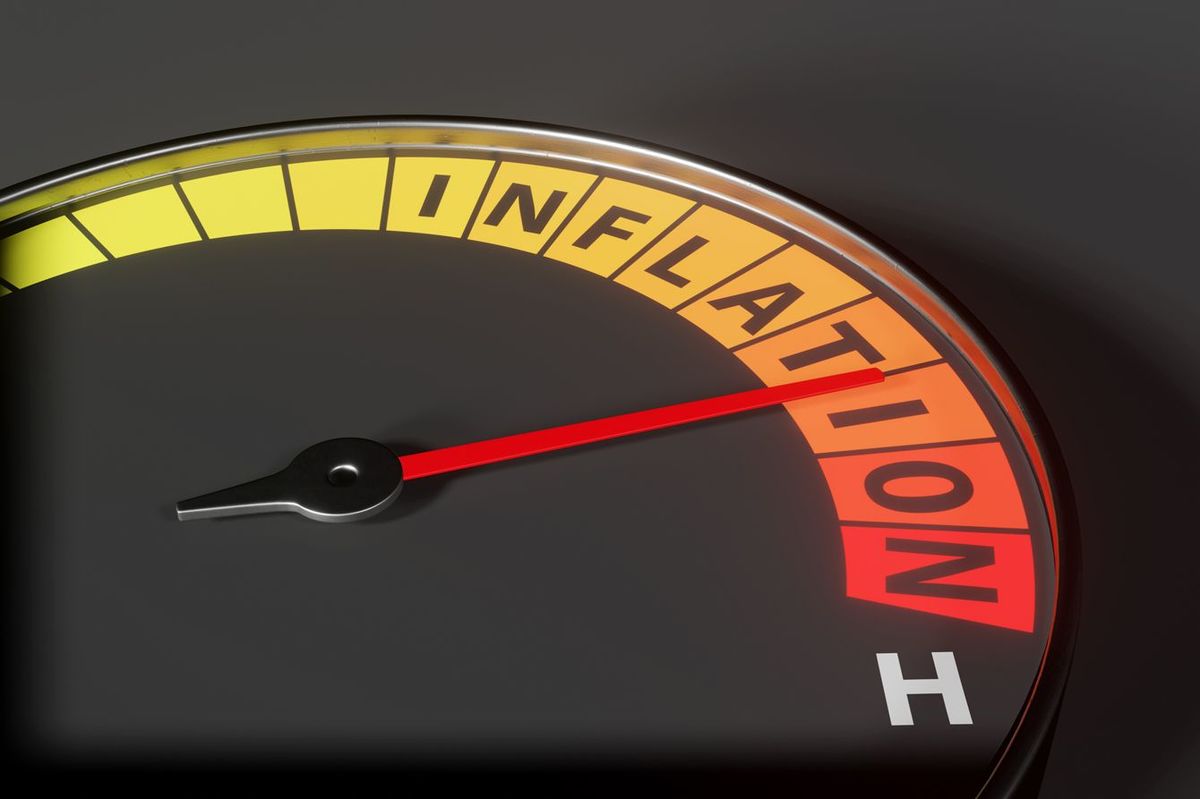
■EVは「捕らぬ狸の皮算用」
経済合理性や生活上の利便性を度外視し、現実離れした条件・前提に基づく需要見通しのもと、EVという未成熟技術を強引に推進しようとしても、まさに「捕らぬ狸の皮算用」だった。
一方、目標の大幅な下方修正を迫られている再エネもまた、EVとよく似た面があるのではないか。
■再エネ推進が「破滅的な結果をもたらす」予想も
事実、米環境保護庁(EPA)が2023年11月に開催した電力供給信頼性会議において、電力業界関係者から「EPAが2030年から実施する予定の化石燃料による発電の制限は現実的ではない」「電力網の信頼性が損なわれ、破滅的な結果をもたらす」「規制導入までの時間が短すぎる」などの反対意見が噴出したという。
こうした再エネやEVにまつわる一連の動きを見るにつけ、冒頭に紹介した豊田章男氏の冷静な分析の凄さが際立つ。2020年12月の段階で、「EVだけでは脱炭素にならない」「再エネは想像をはるかに超える経済的・社会的コストをもたらす」と、その問題点を正確に看破していたのだから。

「クリーンエネルギーへのシフトはもはや止められない」(国際エネルギー機関、IEA)といったメディアで喧伝される「バラ色の将来予測」は、現実に即した冷徹な再計算で見直されるべきではないだろうか。
----------
在米ジャーナリスト
米NBCニュースの東京総局、読売新聞の英字新聞部、日経国際ニュースセンターなどで金融・経済報道の基礎を学ぶ。米国の経済を広く深く分析した記事を『現代ビジネス』『新潮社フォーサイト』『JBpress』『ビジネス+IT』『週刊エコノミスト』『ダイヤモンド・チェーンストア』などさまざまなメディアに寄稿している。noteでも記事を執筆中。
----------
(在米ジャーナリスト 岩田 太郎)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
RE100が失望示す、韓国に「世界市場を失いかねない」と警告=韓国ネット「この国は30年後退」
Record China / 2024年6月13日 6時0分
-
米アマゾン、スペインのAI・クラウド基盤強化に157億ユーロ投資へ(スペイン、米国)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月3日 0時50分
-
韓国政府、再生可能エネルギー普及拡大および供給網強化戦略を発表(韓国)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月22日 15時40分
-
米財務省、IRAに基づく国産部材ボーナスクレジットに関するガイダンスを発表(米国)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月20日 16時50分
-
米エネルギー省、浮体式洋上風力のコスト削減などに向けた取り組みの進捗を発表(米国)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月20日 10時50分
ランキング
-
1バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分
-
2爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分
-
3「戦力の集中」運用に背いたゆえのミッドウェー敗戦 空母4隻と2隻に分けたことがそもそもの敗因
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 9時0分
-
4お金の問題は「お金がないこと」ではない…収入が低くても「一生お金に困らない人」が絶対に欠かさないこと
プレジデントオンライン / 2024年6月16日 10時15分
-
5「役職定年」を廃止する日本企業が増えた理由 タイプ別で変わってくる新潮流への適応方法
東洋経済オンライン / 2024年6月13日 7時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












