「血圧が高い患者に降圧剤を出す」は大間違い…和田秀樹「薬物療法メインの医師が大量生産される根本原因」
プレジデントオンライン / 2024年8月29日 15時15分
※本稿は、和田秀樹『「精神医療」崩壊 メンタルの不調が心療内科・精神科で良くならない理由』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
■大学の精神科の講義は薬一辺倒の内容
入学試験の段階で、人間性やコミュニケーション能力の高さが問われる一方、入学後の6年間の講義で“心の医療”やコミュニケーション能力を養う講義が1つもないことも、医学部教育の大きな問題です。
医学部の学生は6年間の在学中にすべての診療科の講義を受けます。精神科の講義は半年間で13~15回ありますが、人間の心の問題に触れることができる数少ないチャンスです。
私が医学生の時代(1980年代初め)には、精神療法の大家とされる憧れの教授が、各地の医学部に何人もいました。
薬で治らない心の病を診療できる精神科医を育てようという志の高い教授も結構いて、カウンセリングのやり方から、傾聴の仕方、共感の仕方などを、その時々の心の医療のトレンドを取り入れながら、みっちり教えてもらえました。
そのうえで、ついでに薬物療法も習うという感じでした。
ところが、今の大学の精神科の講義は薬の話がほとんどです。ちゃんとした精神療法を行っている教授がほとんどいないため、カウンセリングなどを学ぶ機会は皆無に等しい。教授選の弊害によって、薬一辺倒の内容になってしまっています。
■医療全体がどんどん冷たくなっている
精神科に限らず、今の医学部の教授たちは薬物療法中心で、心の医療なんかいらないと思っている人たちばかりです。こういう人たちに教育を受けるので、精神科医だけでなく、すべての医学部卒業生も心の医療や患者さんの話を聞くことを軽視しがちです。
薬の話と論文の書き方ばかり聞かされて医者になった人たちは、精神療法を自学自習で身につけるしかありません。
ところが、「精神療法なんて意味がない」と考える精神科医も多いのです。精神療法を身につけたところで、大学の医局では腕を発揮する場面がほとんどないばかりか、教授への道が閉ざされてしまうからです。
そんな精神科医が開業したら、患者さんの話をろくに聞かず、ただ薬を出すだけのクリニックになる可能性が高いでしょう。
実際、精神科医なのに診療中パソコン(電子カルテ)画面しか見ていない医者も多く、医療全体がどんどん冷たくなっています。医療訴訟が増えたり、モンスターペイシェントと呼ばれる患者さんが増えたりしているのは、そういうところにも理由がある気がします。

入試面接を行うことで、人の気持ちがわかる、人の話を聞ける人を優先して医学部へ入学させているはずなのに、真逆の医者が合格しやすく、そのため現場でも真逆の医者が増えているわけです。
■心の診療を学ぶ機会がないと、医療全体の質が下がる
心の問題がわからないと、内科や外科の医者も検査数値がすべてとなって、正常範囲から少しでも外れていると、躊躇なく薬を出すような医者になってしまいます。
確かに、血圧値が正常値から外れている人に降圧剤を出せば、血圧値は下がります。でも、その効果は一時的ですから、降圧剤を一生飲み続けることになりかねません。
他方、初診のときに患者さんの話に少しでも耳を傾けたら、「この人の血圧が高いのは、ストレスが多いせいではないだろうか」と気づくことも多々あるわけです。
すると、よほど血圧値が高くない限り、まずカウンセリング的な対応をしてストレスを減らしてあげて、なるべく薬を使わないでいいようにしようという発想が生まれます。
最初は降圧剤でのコントロールが必要であったとしても、ストレスを減らすためのアドバイスを同時に行えば、ストレスの軽減とともに薬物療法は必要なくなります。
医者というのは、そうした見立てができないといけない。検査数値だけでは見えないものがあります。最近はストレスが多いと血糖値が上がることもわかっています。
つまり、医学部の精神科の教授がほぼすべて薬物療法家で占められていることは、日本の医療全体の質を下げてしまうことにもつながるのです。
■女性や多浪生の入試の点数が操作されていた
入試面接は、受験生の年齢差別・性差別の温床にもなってきました。
2018年に、文部科学省の局長が自分の役職を利用して、東京医科大学に子どもを裏口入学させていたことが発覚した事件のことは、ご記憶の方も多いでしょう。
このとき、文科省が全国の大学医学部を対象に調査したところ、およそ10の大学で特定の受験生を優遇する不正が見つかり、女性や多浪生の点数が大学側によって操作されている事実も明らかになりました。
つまり、女性であることや年齢が高いことを理由に、本人が知らないうちに不合格にされていたケースが複数の大学で確認されたということです。
じつはこの事件が発覚する10年以上前に、群馬大学医学部の入試面接で、50代の女性が年齢差別によって不合格にされたとして裁判を起こしたことがありました。
この女性は親の介護を終えたあと、2年間必死に勉強して群馬大学医学部を受験し、ペーパーテストでは合格者の平均点を10点以上も上回っていたにもかかわらず不合格となりました。
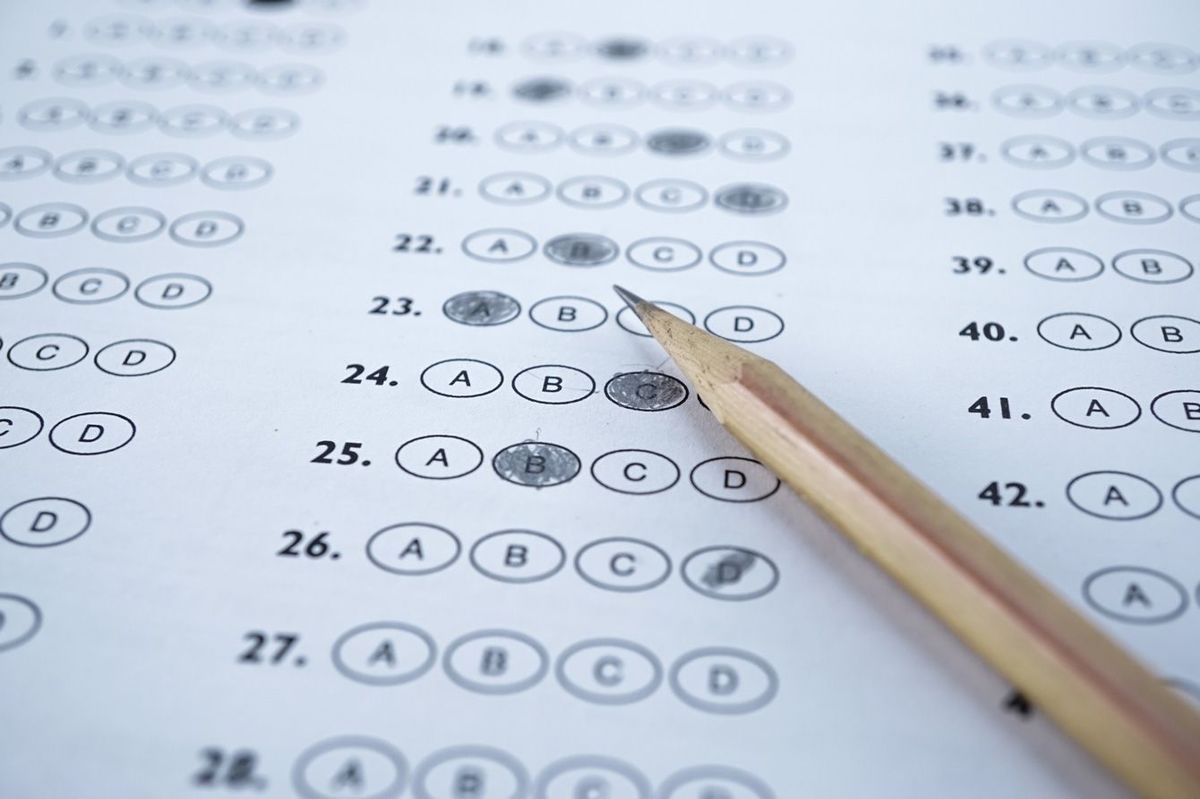
女性は納得がいかず、大学に対して面接のチェック項目や点数化について情報開示を求めたものの、大学側は拒否。「総合的に判断した」という回答とともに、年齢が関係していることを女性にほのめかしたといいます。
■群馬大学の年齢差別の背景に研究至上主義
裁判の結果、前橋地裁は「年齢により差別されたことが明白とは認められない」と原告の請求を棄却(松丸伸一郎裁判長)。年齢差別を容認するような判例が作られてしまいました。
このときに文科省が動いていれば、大学の対応や裁判の結果は違っていたことでしょう。そうすれば、50代の女性が救われたのはもとより、前述した東京医科大学の事件が起こるまでの間に、入試面接で女性や多浪生が不当に落とされることも防げたはずです。
群馬大学の年齢差別は、その歳で医者になっても研究できないという研究至上主義が背景にあったとされます。
我々医者の間でも群馬大学の研究重視、臨床軽視は有名で、60年以上も精神科の教授は生物学的精神医学の人間(ロボトミーの臺弘(うてなひろし)教授も含む)が選ばれています。
2015年に群馬大学で同一執刀医による30人の手術死が明らかになりますが、私は群馬大学医学部の体質と深く関係していると考えています。
いずれにしても、前出の文科省幹部の事件発覚は、医者を目指す女性や多浪生にとって福音となりました。
しかし、果たして現在の入試面接で、年齢差別・性差別が一掃されているかといえば、それはどうかわかりません。医学部のキャンパスで車イスに乗っている学生をほとんど見かけないことも、私はずっと不思議に思っています。
■真に問われるべきは、面接官の教授たちの人間性
欧米の名門大学でも、入試面接は行われています。しかし、日本と異なるのは、原則として教授は面接にタッチしないところです。教授が面接を行うと、自分に忖度するような人間を選んでしまいがちなので、大学事務局に専門の面接官を置いています。
つまり、教授だからといって無条件に信用し、すべてを任せるようなことはしないのです。一方で、反抗的な学生であっても、優秀な人材であれば躊躇なく合格させます。
これに対して日本では、教授の意向を絶対視する傾向があり、教授は大学の中で強い権限をもっています。入試面接はもとより、教授を選ぶのも教授の集まりである「教授会」です。
しかも、教授に一度なったら、よほどの不祥事を起こさない限り、定年までその地位が保障されます。
だから通常、医局には教授のイエスマンしかいません。
日本では、医学部を卒業して医師国家試験に合格すると、基本的に出身大学の医局へ研修医として入ります。
その後、「助教→講師→准教授」というプロセスを経て、教授選に勝つと教授に選ばれます。そうしたヒエラルキーの途中で医局の教授に嫌われたら、もはや出世の道は途絶えます。
欧米の一流大学であれば、学生に人気があったり、研究費を集められたり、画期的な研究を行っていたりする人がいると、「ディーン」と呼ばれる教授のスカウトのような役職の人が目をつけてヘッドハンティングします。
絶えず外部から優秀な人材を入れることで、学内を活性化し、進歩させていこうと考えているのです。
■心の問題がわかる医者を育てるべき
日本の大学のように、閉鎖的な“教授ムラ”ですべてが決定されるような環境では、医療崩壊が起こっても致し方ない気がします。精神科の教授が、ずっと薬物療法中心の医者で占められているのは、その象徴といえるでしょう。
問われるべきは、19歳、20歳の若い受験生の「人間性」ではなく、その判定を行っている面接官の教授たちの人間性でしょう。
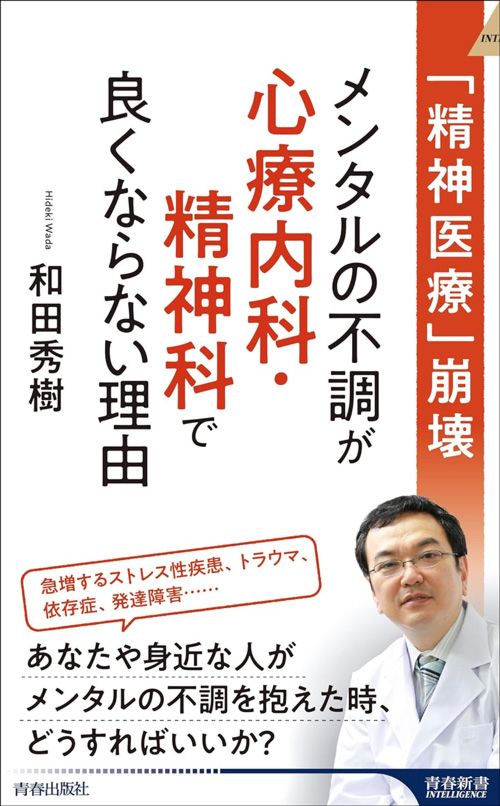
大学は教育機関なのだから、その入り口で「人間性」をあいまいな基準で判定するより、入学後の6年間で人間性を鍛えて、心の問題がわかる医者を育てるべきだと、私は思っています。患者さんに対するコミュニケーションの取り方なども、医学部に入ってから教育すればよいのです。
そして、どうしても面接をやりたいなら、入試のときではなく、国家試験のときに行えばいいと私は常々提案しています。医学部に入るのは、臨床医だけでなく、研究者もいていいからです。
そうすれば、国家試験の合格率を上げるために、大学側は医学部の授業で心の診療、すなわち精神療法的な教育を取り入れざるを得なくなります。
これは大学にとっても、医学生にとっても、患者さんにとっても、必ずや良い結果をもたらすでしょう。精神医療崩壊を食い止めるきっかけにもなります。
----------
精神科医
1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」
----------
(精神科医 和田 秀樹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
どんなにヤバい医者でも一生医者でいられる…それでも医師免許を「更新制」にしてはいけないワケ
プレジデントオンライン / 2025年1月11日 18時15分
-
高齢者を「薬漬け」にするよりずっと効果的…長野県が「お金がかからない長寿県」になった意外な理由
プレジデントオンライン / 2025年1月10日 18時15分
-
医学部入試でなぜ「面接」が必須なのか…医師・和田秀樹が告発「邪魔な人間を徹底排除する医療界の闇」
プレジデントオンライン / 2025年1月9日 18時15分
-
どんな"勝ち組"でも威張れるのは65歳まで…和田秀樹が高齢者専門の病院で見た「孤独な老後を送る人」の特徴【2024下半期BEST5】
プレジデントオンライン / 2025年1月5日 7時15分
-
おやつをやめずに食生活を改善できる?...和田秀樹医師に聞く「老けない」最強の食事法
ニューズウィーク日本版 / 2024年12月19日 15時5分
ランキング
-
1芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか
東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分
-
2急増する大手黒字企業リストラのシビアな背景…2024年「早期・希望退職」1万人超え、前年比3倍に
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分
-
3賞味期限「2年前」のゼリーを販売か…… 人気スーパーが謝罪「深くお詫び」 回収に協力呼びかけ
ねとらぼ / 2025年1月15日 7時30分
-
4「室内寒暖差がつらい…」その要因と対策が明らかに! - 三菱電機が紹介
マイナビニュース / 2025年1月14日 16時10分
-
5靴下真っ黒で徘徊…87歳老母が冷凍庫に隠していた「うなぎパック50個」の賞味期限を知った50代娘の切なさ
プレジデントオンライン / 2025年1月15日 10時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










