母親はベランダからわが子を突き落とした…「子どもをうまく愛せない親」が子育てに絶望する知られざる理由
プレジデントオンライン / 2024年12月16日 18時15分
※本稿は、橋本和明『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
■発達障害児の虐待リスクは非常に高い
発達障害という概念が登場してからせいぜい20〜30年といったところであろうか。まだまだ歴史の浅いところもあるが、それでも発達障害の概念が急速に社会に広がり、それについての理解や支援が普及してきている。
虐待との関係で言うと、発達障害のある子どもが虐待を受けてしまうリスクは高いと言われ、それについての研究も数多く出ている。2000年に実施されたサリバンとクヌートソンの調査では、障害のある子への虐待発生率は31.0%と、障害のない子の虐待発生率に比べて、実に3.4倍の高さであったと報告している。
また、細川徹と本間博彰の研究では、障害児の中でも、身体障害よりも発達障害の方が虐待を招きやすいと指摘している。さらに、杉山登志郎の研究では、虐待症例の中に、広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)が全体の25%、注意欠陥(欠如)多動性障害が20%で、何らかの発達障害の診断が可能な子どもは実に55%に達するとも報告している。
最近の研究報告も含めて考えると、子どもに発達障害があることにより、親から虐待を受けるリスクが高くなることはこれらのことから明らかである。では、なぜ発達障害のある子どもの子育てにおいては虐待のリスクが高まってしまうのだろうか。定型発達の子どもを育てることと、発達障害のある子どもを育てることに、それほどまでに大きな違いが果たしてあるのだろうか。
さらに言えば、仮に子どもに障害があった場合においても、その障害が身体障害であるのと発達障害であるのとに虐待リスクの違いがあるのはどう考えればいいのだろうか。
■なぜ虐待リスクが高まってしまうのか
このような話の展開をすると、発達障害のある子どもは必ず親からの不適切な養育を招くといった誤解につながりやすいので、あえて釘くぎを刺して言いたいのは、発達障害児=被虐待児では決してない、ということである。
実際に、多くの親が発達障害のあるわが子を非常に適切に養育され、驚くほど上手に子どもとかかわっておられるのを目の当たりにする。その苦労や工夫は本当に見ていて脱帽する限りである。発達障害があるからと言って、それが虐待に必ずしも結びつくわけではないということを確認しておきたい。
ただ、統計上言えることとして、定型発達の子どもよりも、さまざまな障害のある子どもの方が親から虐待を受けるリスクが高いということになる。では、なぜ発達障害のある子どもが虐待と結びつきやすくなるのかを検討していきたい。
まず挙げられる虐待のリスクに関連する要因の一つは、親子の間で愛着の形成がしにくいことである。特に、自閉スペクトラム症児や注意欠如多動症児の場合にはそれがしばしば見られやすい。そもそも愛着とは何かを説明しておかねばならないが、愛着と愛情とは少し意味合いが違う。
■親への「愛着」はどのように形成されるのか
愛着というのは、困ったときや不安なとき、恐ろしいときなど、子どもは信頼できる大人(主には養育者)に近づき、触ってきたり、抱きついてきたりするという行動を指す。
英語で愛着はアタッチメント(attachment)と言うが、まさに「近づいてきてタッチする」という意味になる。日本語では「ひっつく」「くっつく」「なつく」といったニュアンスの方が表現としてはぴったりくる。つまり、いずれも「つく」という感覚が愛着には伴うのであり、それが本来の持っている意味合いである。

子どもが生まれたときは誰とも関係を持たないが、養育者(ほとんどの場合は親となるので、以下は親と記述する)の献身的な世話によって、子どもと親との間に関係性が生まれてくる。このもっとも基本となるのが愛着の形成なのである(近年の研究では、子どもは母親の胎内にいるときから母親の声が聞き分けられるとの報告もあり、出産前から子どもは母親との関係を持っているとも理解してよいかもしれない)。
では、その愛着がどのようにして形成されるのかをもう少し詳しく述べたい。まず生まれてきた赤ちゃんは空腹や気持ちが悪いとき、あるいは眠たいときなどのように不快や痛み、違和感があると泣くという行為をする。
その際、泣いている赤ちゃんの前に親が顔や姿を現し、声かけをしたり、おっぱいをあげたり、オムツを替えたり、抱っこするなどして不快や痛み、違和感を取り除く。このようなことを何度も何度も繰り返す中で、赤ちゃんは不快や痛み、違和感があると親が目の前に現れてそれを取り除いてくれることを身をもって学習する。
■大人は自分にとっての「安全な避難場所」
その赤ちゃんが少し成長し、ハイハイや歩き始めるようになると、親のところから少し離れたところまでひとりで向かう。
しかし、目の前にふと親がいないことを知り、不安や恐怖などを感じると、親を振り返り、親のもとに戻ってきて触ってきたり、ひっついてきたり、抱っこを求めたりする。これがまさに愛着に基づく行動で、その子どもにとっては将来の人間関係を築く土台となる。
つまり、愛着を示す大人が自分を守ってくれるという安全な避難場所となり、次にはその大人との関係が安心基地となって、そこから離れていろんな世界を積極的に探索し、子どもに自律性を与え、自分への自信さえも得るのである。

いずれにせよ、子どもにとってはこの愛着をいかに形成させるかがその後の発達には重要と言える。しかし、発達障害のある子どもの場合はどうかと言うと、定型発達の子どもよりも愛着形成が遅れたり、うまく形成しにくかったりする面が見られる。特に、自閉スペクトラム症児や注意欠如多動症児の場合は、しばしばそれが見受けられる。
例えば、自閉スペクトラム症の子どもの中には、自分の名前を呼ばれても呼んだ人の方を振り向かなかったり、話をしている相手と視線が合わずアイコンタクトが取りにくかったりする子がいる。
そのため、親はわが子とコミュニケーションを図ろうとするものの、思うようにコミュニケーションが成立しない。そうなると、子どもに対してなかなか共感がわきにくく、ひいては子どもを愛(いと)おしく思いにくいという事態にまで発展してしまうことがある。
■親子間の信頼関係が深まりにくい傾向になる
子どもの名前を呼び、その子がこちらを振り向いて、ニコッと笑顔で応答してくれると、それだけでも親は子どもとの関係性を確認でき、心底「かわいいねぇ」と思えてくるものであるが、自閉スペクトラム症の場合はなかなかそうはいかないこともある。
注意欠如多動症の子どもにおいては、自分の興味のあることや関心のあることに刺激を受けやすいため、じっとしていられなかったり相手の話を聞けなかったりすることもある。少しひとり歩きができるようになると、今まで寝て見ていた光景とは違い、周囲が興味や関心のあることだらけで、そちらにまっしぐらに突き進んでしまう。
そうなると、先ほどの愛着で説明したときのように、後ろを振り返り親のことを確認したり、不安になって親のもとに戻ってきたりという行動にはつながりにくい。また、親が子どもと話をしようと思っても、子どもの方はすぐに注意がそれて、親の言わんとすることを中途半端に理解し、満足のいくコミュニケーションとなりにくい。
親自身も子育てに不全感を抱き、子どもとの関係も満足の得られるものとはなりにくくなってしまう。
■「丸太ん棒を抱いているようだった」
また、発達障害の人の中には感覚の独特さを持っていることもしばしば見受けられる。その一つに感覚の過敏さが挙げられ、触られたり抱っこされたりすることをとても嫌がる子もいる。通常なら、優しくなでられたり触られたりするのが心地よいものであるが、その子にとってはそれが不快にしか感じられない。
そうなると、愛着の原点であるひっつく、くっつく、なつくといった「つく」という行為が安心感、安全感とはならずに、不快感や嫌悪感となってしまう。自閉スペクトラム症の子どもを持つ親がわが子を抱いても、「いつも丸太ん棒を抱いているようだった」と感想を述べられたりすることがあるが、まさにこのことなのである。
つまり、その子どもにとっては抱かれることが気持ちのよいものではなく、逆に身をこわばらせてしまい、親の方に身を預けない行動となる。本来なら愛着が形成される頃になると、子どもは親を安全で安心な基地とするため、首がすわる頃から1歳になるまでの間に親の方に身を預け、自ら抱かれやすくするものである。
しかし、それがうまくいかず、先の丸太ん棒のような状態になってしまう。こうなってしまうと、親側としてはわが子が自分に身を預けてくれない物足りなさや抱いても機嫌を取り戻してくれないもどかしさ、逆に泣くのがますます激しくなってしまうために育てにくさやかかわりにくささえも感じてしまう。
■「他の子に比べてどうして…」という不安
発達障害のある子どもが親から虐待を受けるリスクとなるもう一つの要因は、定型発達の子どもと比べて、発達スピードが緩やかであることが挙げられる。
そのため、親はわが子の発達が他の子どもよりも遅れていると焦りや苛立ちを感じやすくなってしまう。それがだんだんエスカレートしていくと、そのことが気になって仕方なくなり、ゆとりを持った子育てがしにくくなっていく。
具体的なことで言えば、わが子に言葉がなかなか出てこなかったり、トイレット・トレーニングが円滑にいかずにいつまでもオムツをさせていたりするなどがある。そんなときに親として考えやすいことは、「他の子に比べてどうしてうちの子だけは……」と感じたり、「このまま発達が止まって、将来どんなふうになるのだろうか」と不安になったり、こうした状況が続けば悲愴感や絶望感さえも抱いてしまう。

子どもが言葉を習得する背景には、親が指さしをしたモノ(仮に、指を指した先に自動車があれば、その自動車)に子どもが視線を向け、そして、親が子どもに対して発した言葉(この場合であれば、“ブゥーブゥー”という自動車を表す言葉)があるという共同注視(Joint Attention)が成立していなくてはならない。
通常なら、生後3カ月頃になると、親の視線を子どもも追うようになり、生後5〜6カ月頃になると子どもは自分が発する声で親の注意を引こうとし、生後9〜10カ月にもなると子どもは自分で指さし行動ができるようになる。このような発達をする中で、親の意図を汲み理解できるようになってくる。
■どんなに注意しても手応えを感じにくい
しかし、自閉スペクトラム症の子どもの中には、親の視線を追わないし、ましてや親が指さしたモノに視線を持っていかないため、仮に親が発した言葉(この場合であれば、“ブゥーブゥー”)が何を指すのかわからず、言葉が覚えられなくなってしまう。
そうなると、親としては、子どもにどのように言葉を覚えさせればよいのか手応(てごた)えが得にくくなり、いつまでも一語文が出てこないわが子の言葉の遅さに途方に暮れてしまう。また言葉の習得だけに限らず、さまざまなところで発達の遅れを感じさせられることもある。
例えば、注意欠如多動症の子どもの場合であれば、何度教えても同じ失敗を繰り返してしまう。学習したことが身につかないと言ってしまえばそれまでであるが、それはそもそも持っている注意がそれてしまうという特性の影響も大きい。それゆえに、「水は出しっぱなしにしてはいけません」と何度親が言っても、手を洗った後にいつも蛇口を閉めずに次のことをしてしまう、といったことになる。

そして、こんなことが一つや二つではなく、生活全般にあちこち起こってくると、親としてもたまったものではない。
■発達速度が緩やかなことで、愛情を持てない場合も
生活訓練をしてもそれが身につかないという問題は、発達の中でも親を苦しめる大きな要因となる。
確かに、発達障害のある子どもは定型発達の子どもに比べて、発達のスピードは緩やかであるかもしれないが、発達をしないわけではない。発達障害の特性のゆえに、先にも取り上げたように親が指さしたモノに視線を向けなかったり、注意がそれて蛇口を閉めるという行動まで結びつかなかったりするが、特性が相当に重くない限り、年齢とともにできるようになってくる。
それらの学習の仕方が定型発達の場合と少し違うために、そのスピードは緩やかなものとなりはするが、それができないわけではない。しかし、親としては、「同じ年齢の他の子どもはもうとっくにそれができているのに、わが子はできない」とそこだけを過剰に意識してしまうため、育児のストレスを高めてしまう。
筆者が行った犯罪心理鑑定の事例の一つで、母親(被告人)がわが子を殺害した事件があった。
その子どもは4歳になっても一語文(例えば、“チョコレート”)しか話さず、二語文(例えば、“チョコレートほしい”)が言えなかった。1歳のときから、名前を呼んでも振り返らず、目と目が合うことも少なく、この子の姉の様子とは少し違うと感じていた。
■孤立に追い込まれた母親が起こした悲劇
言葉だけではなく、トイレット・トレーニングはもとより、歯磨きや衣服の着脱も時間と手間がかかり、「姉の場合はこれぐらいの年齢のときにはここまでできていたのに……」と発達の遅れが母親としては気になって仕方なかった。
年齢が大きくなるほどに他の同年齢の子どもとの成長の開きを感じ取り、さまざまな発達支援センターや教育相談機関に行き、発達検査なども受けさせた。しかし、まだ子どもの年齢も幼かったこともあり、どこに行っても発達障害とまでの確定診断はされず、「しばらく様子を見ましょう」と言われるだけだった。
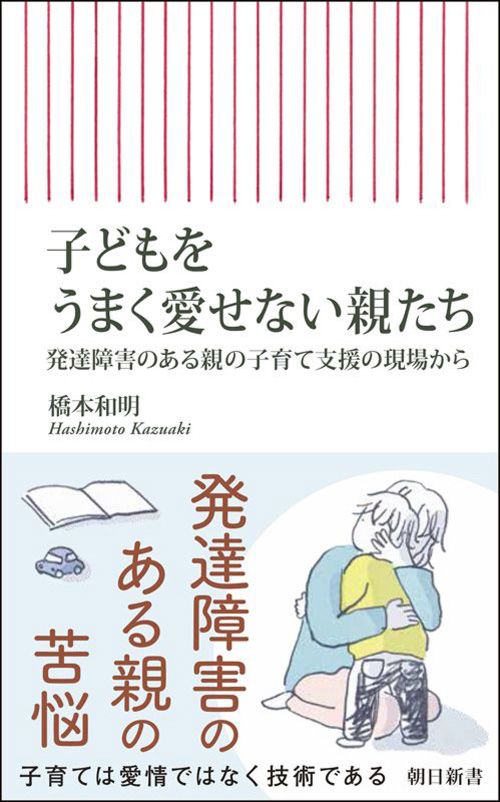
家庭においても、毎日子どもの様子を父親に報告するも、父親は「そんなに気にする必要はない」「思い込みすぎ」とさほど母親の話を熱心に聞いてくれるわけではなかったので、ますます母親は家の中でも孤立していった。
母親の育児ストレスが限界に達し、最終的にはベランダからわが子を突き落とすという虐待行為に及んでしまったのである。
この母親は決してわが子に対して憎くて虐待したわけではない。逆に、わが子のことが心配でたまらず、発達が停滞していることや将来のことを悲観的に考え、このままではわが子がかわいそうでならないと思い込んで殺害に至ったのであった。
そこに、家族の支えや周囲のフォロー、専門機関の支援がもう少しあればこのような事態にならずに済んだかもしれないと残念でならない。
----------
国際医療福祉大学教授
1959年、大阪府生まれ。名古屋大学教育学部卒。武庫川女子大学大学院臨床教育研究科修士課程修了。専門は非行臨床や犯罪心理学、児童虐待。大学を卒業後、家庭裁判所調査官として勤務。花園大学社会福祉学部教授を経て現職。児童虐待に関する事件の犯罪心理鑑定や児童相談所のスーパーバイザーを行う。現在、内閣府こども家庭庁審議会児童虐待防止対策部会委員。公認心理師試験研修センター実務基礎研修検討委員。日本子ども虐待防止学会理事。日本犯罪心理学会常任理事。主な著書に、『虐待と非行臨床』(単著、創元社)、『非行臨床の技術-実践としての面接、ケース理解、報告』(単著、金剛出版)、『子育て支援ガイドブック-「逆境を乗り越える」子育て技術』(編著、金剛出版)、『犯罪心理鑑定の技術』(編著、金剛出版)、『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新書)などがある。
----------
(国際医療福祉大学教授 橋本 和明)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
お姉ちゃんでしょ!…幼稚園で先生を無視、友だちとのケンカが増えた娘。やがてもとの活発で優しい子に戻った「母の対応」【医師が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月3日 15時15分
-
石落としばかりでひとりの世界にいた子のことばを伸ばす本自閉症専用3ヶ月 おしゃべり上達メソッド電子書籍無料配布開始
PR TIMES / 2025年1月31日 13時40分
-
くり返す精神疾患の原因になる「親との愛着関係」 大人になってから克服するには?
PHPオンライン衆知 / 2025年1月28日 11時50分
-
周囲に気を遣いすぎてしまう...生きづらさの根本にある「幼少期の親子関係」
PHPオンライン衆知 / 2025年1月23日 12時0分
-
精神安定剤をお菓子のようにポリポリ…「児童虐待」の裏側にあった父親の精神疾患。障害のある親に対する子育て支援の実態
集英社オンライン / 2025年1月11日 13時0分
ランキング
-
1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車
週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分
-
2「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分
-
3「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧
共同通信 / 2025年2月5日 10時26分
-
4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分
-
5「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態
まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










