「息子(10)を殴る→顔写真を撮影→腫れた顔を見て夫婦で笑う」無邪気に虐待を続ける父親(45)の"歪んだ常識"
プレジデントオンライン / 2024年12月20日 18時15分
※本稿は、橋本和明『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
■わが子を“特別扱い”しなければ子育てはできないが…
認知バイアスの一つとして、自己メタ認知能力が備わっていないと社会では適応が難しくなり、それが子育てにおいても顕著に現れる。
これから取り上げたいことは、自分に対する認知ではなく、まさに子どもそのものへの認知バイアスについてである。確かに、いろいろな子育ての光景を見ると、親がわが子を主観を交えずに、実に客観的に捉えているというのは少ないかもしれない。
「色眼鏡で見る」という言葉があるように、よその子とは区別してわが子を特別扱いしたり、親としての思い入れや大きな期待を寄せたりするのもわからなくもない。ある意味ではそれがなければむしろ子育てはできないし、いわば当然のことかもしれない。しかし、それがあまりにも度を越してしまうと、そこには不適切なかかわりや養育の問題が発生してしまう。
たとえて言うならば、多少の色つきのレンズで見るのはやむをえないことだが、見る対象の姿が変わって映ったり、景色そのものが変わったりするほどの極端な度付きサングラスをかけるとなると、世界が大きく違って見えてしまうのである。
■虐待などのトラブルを起こしかねない「共感性の欠如」
まず子どもへの共感性の欠如を挙げたい。この共感性は、親が子どもの立場に立っていろんなことを感じたり考えたりすることができる、子どもの気持ちを理解できる、ということである。筆者がこれまでかかわったケースなどを振り返ると、思っていた以上にこの共感性が乏しい親が多い。
一般的に、われわれは子どもが生まれたら自然に子どもへの愛情が湧き出てくる、子どもとかかわっていく中で子どもも親の気持ちを理解していくようになり、互いの関係が親密になっていく、と言われる。しかし、妊娠や出産はしたものの、皆目愛情が湧かず、生まれてきた赤ちゃんは物体、しかも生ゴミでしかないという捉え方しかできない人も実際にはいる。
そんな親を冷血な人間、残虐な人格の持ち主などと批判するのは簡単であるが、よくよく見ていくと、情の問題というよりもそこに認知のあり方の問題が横たわっていることに意外と気がついていないことがある。

■ボロボロになったわが子の写真を見て笑う夫婦
【事例①:子どもの顔面を殴り、写真を撮影して部屋に貼った40代の父親】
Xさんは45歳の自営業を営む父親で、妻と10歳の男児、7歳の女児の4人暮らしであった。元来、Xさんは力で相手をねじ伏せ、言うことを聞かせようといった強引なところがあり、夫婦関係でも妻に暴力を振るうなどのDVもこれまで何度かあった。
ただ、2人の子どもにはそれなりの愛情をかけ、やや自分本位のやり方ではあったものの、休日は公園や遊園地に連れて行くなどもしていた。そのため、子どもも父親を嫌っていたわけではなく、親密に感じているところも見られた。
ただ、上の男児が小学校の高学年となると、しだいに自己主張が強くなって親の言うことに反発し、親に隠れて陰で自分のしたいことをする行動が出てきた。そのたびに母親とともにXさんは男児を厳しく叱りつけるのであった。
あるとき、Xさんは怒りにまかせて男児の顔面を数発殴って、もう二度と同じことを繰り返さないようにと、殴られて腫れている息子の顔面を写真に撮り、それを見せしめのように部屋に貼った。Xさんは自分が暴力を振るったことを棚に上げ、反省など微塵(みじん)もないことはもとより、殴られてボロボロになったわが子の顔があまりにもおかしいと、時々夫婦でその写真を見て笑いの材料にしていたのであった。
この話を聞いた人はなんて悲惨な状況だと思うに違いない。
■辛そうな顔ではなく“変顔”だと認識していた
また、殴られた上に、顔が腫れて変形している写真を常に部屋に貼られ、両親の笑いの材料にされている男児のことを思うと不憫(ふびん)でならないと思うだろう。息子にとってみれば、こんな仕打ちを親からされ、情けないを通り越して地獄にいるような気持ちであったとも想像できる。
ただ、Xさん自身はわが子が同じ失敗をしないようにと親心としてのしつけを行ったまでの認識で、手を上げたことはさすがにやりすぎたと考えてはいるが、それも一時的でしかなかった。

それより、その後の写真を貼ったり、それを笑いの材料にしたりしていたことは、皆目悪いと思っていないのであった。Xさんからすると、その息子の顔の写真は普段から家庭内でよく遊びでしている“変顔”の一つでしかなかったのである。
このようなことが生じるのは、親がどこに認知を向けるかという問題と密接に関係している。同じ息子の顔写真であったとしても、「殴られたあとの辛そうな顔」と見るのか、「おもしろい変顔」と見るのかでそこが大きく違う。
親の注意が子どものどこに向けられているかとともに、そこに子どもへの共感性がどれだけ作用しているかである。そこには息子の辛くて悔しい気持ちをくみ取るといった親の共感性のある・なしが問われる。
■子どもの能力を高く評価しすぎてしまう事例も…
子どものどの部分に親の注意を向けるかという点で言えば、子どもの持っている能力に対しての親の認知バイアスが問題になることもしばしばある。
実際の子どもの能力と親が認知する子どもの能力の間に開きがあることで、近年、「教育ネグレクト」や「教育虐待」などと叫ばれている事象などが出現してしまう。この子どもの能力への認知バイアスとして、親が実際以上に子どもの能力が高いと認知し、結果子どもに負担を強いるものがある。
【事例②:娘をオリンピック選手しようとして虐待通告された20代の母親】
Yさんは27歳で、夫と別れたために現在は5歳になる娘と2人暮らしをしている。
Yさんは幼い頃から新体操のクラブに入り、高校や大学のときにはさまざまな大会で賞をもらうなどの成績を収めた経験があった。その後、結婚して自身は新体操から離れて、特にそのことにこだわりも未練もなかったのであるが、娘を出産して状況が変わった。
娘が生後7、8カ月になる頃、Yさんが娘のオムツを交換していると、娘は気持ちよかったのか、両脚を大きく伸ばした。それをYさんが見ていて、娘の脚を手で触ったところ、思いのほか脚力があると感じた。後になって振り返って話したところによると、Yさんはこのときに娘の脚力は並大抵のものでないと思い、将来はオリンピック選手にさせようと決意したようである。
■小さな期待が異常な訓練に結びついてしまった
それから娘が少し歩き出し、そして走ったり物につかまったりもできるようになってくるとYさんの猛特訓が徐々に加速していった。3歳になって幼稚園に入る頃には公園にある鉄棒で娘に何度も逆上がりをさせたり、鉄棒の上を何度も歩行させたりもした。訓練が朝早くから始まることもあれば、逆に夜遅くになることもあり、近所の人が何人もそれを目撃していた。

そして、娘が5歳になったとき、それを見かねた住人が児童相談所に虐待通告したのであった。
このYさんは他の親と同様、子どもを愛し、期待をかけていたのは間違いない。それが決して悪いわけではなく、「オリンピック選手にさせたい」という思いもそれ自体は外からとやかく言われることでもない。
ただ、どこにボタンの掛け違いが生まれたかというと、娘の能力に対しての親の認知にあまりにもバイアスがかかり、そのことが過剰な訓練となってしまったところである。まだ生後7、8カ月という月齢で、果たして将来はオリンピック選手となれるかどうかなどと判断できるのだろうか?
仮にできたとしても、3歳という年齢からこのような訓練が妥当だろうかと考えさせられる。このYさんの事例と似たものとして、子どもがまだ幼いにもかかわらず、親は「もう何でもできる」と認知し、できもしないことを無理矢理押しつけたりして問題となってしまうこともある。
もっともわかりやすい例として、「ひとりでお留守番ができる」と考え、まだ3歳の子どもを家にひとり残して、長時間不在にするといった事例などは典型である。このようなケースにおいても、親は実際の年齢以上に子どもが発達していると思い込み、無理な課題を押しつけてしまう。
■衰弱しきった娘のSOSに気が付かず…
認知のあり方が子どもに大きな危機を招く要因の一つに、親が子どもに差し迫っている危機を察知できずにいる「危険察知能力の欠如」と、もう一つはすでに危険な状態に陥っているにもかかわらず、それが慢性化してしまい、危険という認識が麻痺してしまう「認知感覚麻痺」がある。
【事例③:子どもの衰弱に気づかず、白目で痙攣するまで放置した20代の母親】
βさんは夫との離婚後、2歳の女児を引き取り母子2人で生活をする26歳の母親である。
女児は2歳まで順調に発育をして、体重や身長なども問題はなかった。ところがインフルエンザをこじらせ、脱水状態となったその頃から、摂取する食事の量もかなり減り、体重は増えるどころか減少が続いた。わが子の変貌ぶりは誰の目にも明らかなはずなのに、一番身近にいるβさんは「少し痩せたかなぁ」程度の認識しか持たなかった。
その後も女児の回復の兆(きざ)しがなく、今までであれば大きな声でこちらにSOSを訴えるかのように泣いていたものがだんだん声も小さくなり、βさんに聞こえるか聞こえないかのか細い泣き声となっていた。
■訓練によって認知そのものを改善する必要がある
通常であれば、子どもの衰弱の様子を親が気づくはずであるのに、βさんは子どもの泣き声が小さくなっていくとますますそれをキャッチすることができなくなり、死という危険がもう身近に迫っているなんて予想もしなかった。
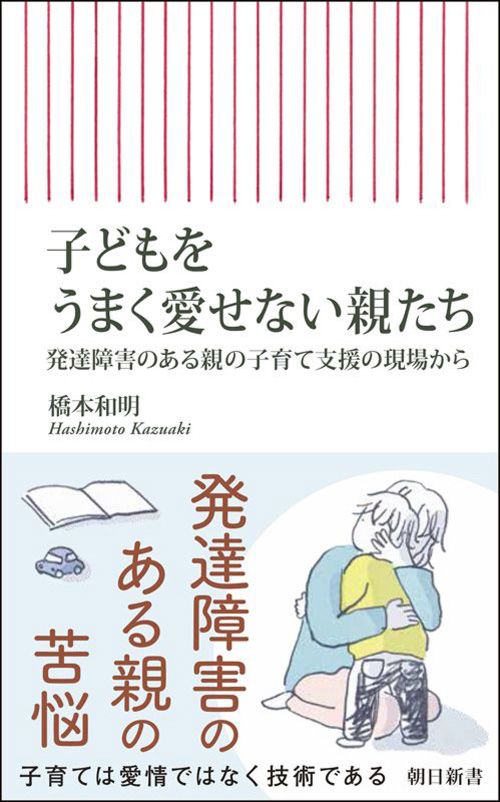
幸い女児が白目をむいてひきつけを起こしている場面を目撃し、βさんは初めて女児の異変に危機感を持ち、119番に連絡して一命を取り留めた。このとき、医師から「なぜここまで放置していたのか」と厳しく言われたという。
βは、あえて子どもを放置し危険な目に遭わせようなどとは思っていなかったはずである。しかし現実には命にかかわる重大事態の直前にまで至っていたのは、他ならぬ親の危険察知能力の乏しさゆえだと言わざるをえない。
こんな認知になるなんて考えられない、頭で考えたらわかりそうなものだ、と思うかもしれないが、認知というのはそんなことではなかなかうまくいかない。、認知の訓練を積まねばなかなか改善されず、また自分の認知の不足を補うための子育て技術を手に入れることが重要なのである。
----------
国際医療福祉大学教授
1959年、大阪府生まれ。名古屋大学教育学部卒。武庫川女子大学大学院臨床教育研究科修士課程修了。専門は非行臨床や犯罪心理学、児童虐待。大学を卒業後、家庭裁判所調査官として勤務。花園大学社会福祉学部教授を経て現職。児童虐待に関する事件の犯罪心理鑑定や児童相談所のスーパーバイザーを行う。現在、内閣府こども家庭庁審議会児童虐待防止対策部会委員。公認心理師試験研修センター実務基礎研修検討委員。日本子ども虐待防止学会理事。日本犯罪心理学会常任理事。主な著書に、『虐待と非行臨床』(単著、創元社)、『非行臨床の技術-実践としての面接、ケース理解、報告』(単著、金剛出版)、『子育て支援ガイドブック-「逆境を乗り越える」子育て技術』(編著、金剛出版)、『犯罪心理鑑定の技術』(編著、金剛出版)、『子どもをうまく愛せない親たち 発達障害のある親の子育て支援の現場から』(朝日新書)などがある。
----------
(国際医療福祉大学教授 橋本 和明)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
なぜ暴力的な犯罪を起こすのは女より男が多いのか…進化の過程だけでは説明できない「攻撃的になる理由」
プレジデントオンライン / 2025年2月3日 18時15分
-
なぜ男の子が赤いランドセルを選ぶのを許せないのか…心理学者が分析「無意識に子の性差を作り出す親の言動」
プレジデントオンライン / 2025年2月2日 18時15分
-
「妹にネコ缶を食べさせ」「80歳の認知症の母親を半監禁と暴行」…訪問介護者が見た壮絶な家族虐待のリアル
集英社オンライン / 2025年1月11日 13時0分
-
精神安定剤をお菓子のようにポリポリ…「児童虐待」の裏側にあった父親の精神疾患。障害のある親に対する子育て支援の実態
集英社オンライン / 2025年1月11日 13時0分
-
「開けた瞬間…ニオイと見た目に衝撃」炊飯器で水に浸した米を腐らせた70代認知症母が洗濯機も使えなくなった
プレジデントオンライン / 2025年1月11日 10時15分
ランキング
-
1「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分
-
224年10~12月期「中古パソコン」の平均販売価格、7四半期ぶり高水準…“中古スマホ価格は低迷”の理由
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時15分
-
3「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態
まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分
-
4「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素 埼玉県八潮の事故はまったく他人事ではない
東洋経済オンライン / 2025年2月4日 8時0分
-
5函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










