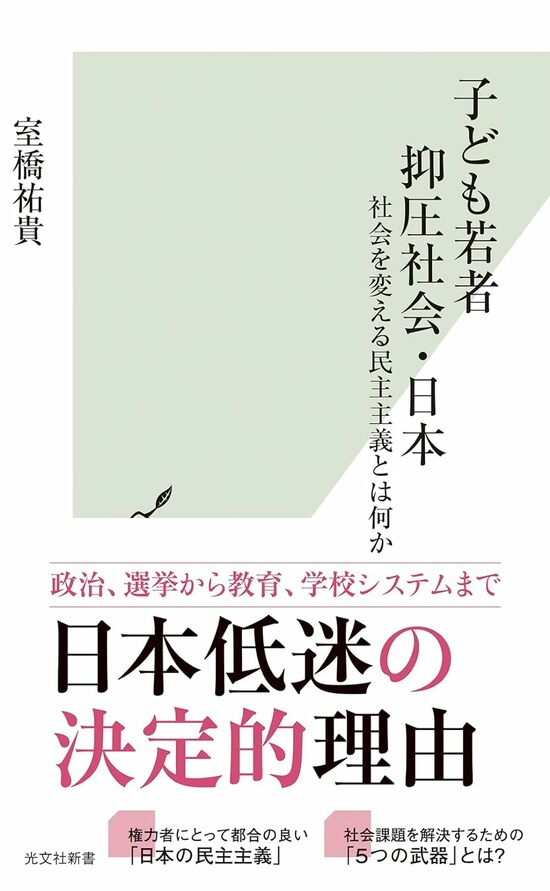子どもの自殺が2022、2023年ともに500人を超えるも学校は硬直的。生徒の自己肯定感は低く、学力、運動能力、年齢でラベリングされ、序列化される現実
集英社オンライン / 2024年5月27日 8時0分
〈なぜ日本からブラック校則はなくならないのか…校則は憲法より上位の存在、その校則の権限は校長に絶対的に委ねられている現状〉から続く
2022年の厚生労働省の統計によると、子どもの自殺者数が過去最多となった。2023年にも500人を超えたままであるが、その原因は何なのだろうか。
【画像】全国でも極めて自殺率の低い「自殺〝最〟希少地域」とは
本記事では書籍『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』より一部を抜粋・再構成し、極めて自殺率が低いとされる徳島県の海部町(現海陽町)の特徴を深掘りする。子どもを自殺させないための自殺予防因子とは?
自殺の少ない町の予防因子とは
子どもの自殺は、2022年に500人を超えて過去最多となった。なぜここまで自殺する子どもが増えているのだろうか。通常、増加要因を分析していくのが一般的だが、これまでそれによって成果が出ていないことから、今回は逆に、自殺の「少ない」地域の特徴を見ていきたい。
そこに自殺の予防手段を見出すことができるのではないかという思いからだ。
岡檀・一橋大学経済研究所客員教授が書いた『生き心地の良い町』では、全国でも極めて自殺率の低い「自殺〝最〟希少地域」である、徳島県南部の太平洋沿いにある小さな町、海部町(現海陽町)を徹底的にフィールド調査し、5つの自殺予防因子をまとめている。
自殺予防因子その一
──いろんな人がいてもよい、いろんな人がいた方がよい(多様性を尊重する)
海部町では、赤い羽根募金を募っても「何に使われるかわからないものに金は出さない」と一蹴されたり、高齢者を地域の老人クラブに勧誘しても「俺はいい」と断られたりと、周辺地域の中で募金額や加入率が最も低いという。
しかし、それを咎める人もおらず、それぞれが自由に選択して、生きている。ともすると、こうした田舎町では、同調圧力が強く、勝手な行動を取ると浮いてしまう。しかし海部町では、そうした空気が一切ないという。
特別支援学級の設置についても、近隣地域の中で海部町のみが異を唱えており、設置に反対する理由として町会議員はこう説明する。
「他の生徒たちとの間に多少の違いがあるからといって、その子を押し出して別枠の中に囲いこむ行為に賛成できないだけだ。世の中は多様な個性を持つ人たちでできている。一つのクラスの中に、いろんな個性があった方がよいではないか」
また住民へのアンケートでは、「あなたは一般的に人を信用できますか」という質問に対し、「信用できる」と答える人の割合が他の町より高く、「相手が見知らぬ人である場合はどうですか、信用できますか」という質問に対しても、信用度はほとんど下がらなかった。
つまり、相手が身内であるかよそ者であるかによって大きく態度を変えない、排他的傾向がより小さなコミュニティであると解釈できる。
自殺予防因子その二
──人物本位主義をつらぬく(地位や学歴、家柄を重視しない)
こうした地方の小さい町であれば、年功序列などの文化がより根強く残っていそうであるが、海部町では地位や学歴・家柄に囚われず、能力があると見れば新しく町に引っ越してきた新参者をリーダーに抜擢するなど大胆な人事がよく行われるという。
実際、教育長に商工会議所に勤務していた41歳の、教育界での経験は皆無という男性が抜擢されたりと、民間人を公立学校の校長に採用するという都市圏でも比較的新しい取り組みは、ここでは約30年前から行われてきた。町の相互扶助組織でも、年長者が変に威張ることはなく、年少者であっても妥当だと思われた意見は即採用される。
自殺予防因子その三
──どうせ自分なんて、と考えない(自己効力感が強く、主体的に社会活動に関わる)
日本財団の調査結果(図表1-3、20ページ)が示したように、日本では、「自分の行動で、国や社会を変えられると思う」という感覚(政治的有効性感覚)が、他の先進国の若者と比べて非常に乏しい(26.9%が「変えられると思う」と回答)。だが、この町は異なる。
「自分のような者に政府を動かす力はない」と思いますか、という質問に対し、「そのような力なんてない」と感じている人の比率は、海部町で26.3%(つまり73.7%が動かす力があると回答)であったのに対し、自殺多発地域であるA町では51.2%と2倍近く離れていた。
実際、海部町では主体的に政治に参画する人が多いという。自分たちが暮らす世界を自分たちの手によって良くしようという基本姿勢があり、行政に対する注文も多い。ただし、「お上頼み」とは一線を画しており、畏れの対象とは見ていない。首長選挙も盛んで、地方の小規模な町には珍しく、海部町には長期政権の歴史がない。
自殺予防因子その四
──「病」は市に出せ(すぐに助けを求める)
海部町の人がいう「病」とは、たんなる病気のみならず、家庭内のトラブルや事業の不振、生きていく上でのあらゆる問題を意味している。そして「市」というのはマーケット、公開の場を指す。
体調がおかしいと思ったらとにかく早めに開示せよ、そうすれば、この薬が効くだの、あの医者が良いだのと、周囲が何かしら対処法を教えてくれる。まずはそのような意味合いだという。
同時にこの言葉には、やせ我慢すること、虚勢を張ることへの戒めがこめられている。悩みやトラブルを隠して耐えるよりも、思いきってさらけ出せば、妙案を授けてくれる人がいるかもしれないし、援助の手が差し伸べられるかもしれない。だから、取り返しのつかない事態に至る前に周囲に相談せよ、という教えなのである。
自殺予防因子その五
──ゆるやかにつながる
海部町は物理的密集度が極めて高く、住民同士の接触頻度は高い。一方、隣人間の付き合いは、基本放任主義で、必要があれば過不足なく援助するというような、どちらかといえば淡白なコミュニケーションが多いという。
近所との付き合い方は「立ち話程度」「あいさつ程度」と回答する人たちが8割を超えていて、「緊密(日常的に生活面で協力)」だと回答する人たちは16%程度だった。一方で、自殺で亡くなる人の多い地域は「緊密」と回答する人が約4割だった。
また人間関係が固定しておらず、他の地域の相互扶助組織が事実上の強制加入制であるのに対し、海部町は任意加入で、入退会に際し個人の自由が尊重されている。自分一人が入会しないからといって、そのことを理由にコミュニティ内で排除されたり、不利益を被ることもない。複数のネットワークが存在し、ちょっとした逃げ道や風通しをよくする仕掛けが多く存在する。
これらの特徴と今の日本の学校を照らすと、明らかに真逆であることがよくわかる。コミュニティは画一的で、硬直的。互いに競争しているために、すぐに助けを求める雰囲気はなく、自己肯定感は低い。頭の良さや外見、運動能力、年齢、性別など、「記号」でラベリングされ、序列化される。海部町の事例を踏まえると、いかに自殺予防因子が足りないかがよくわかる。
日本教育の大きな岐路となった「1969年」
若者の政治参加の低迷、「ブラック校則」や「部活動強制加入」を考えるにあたって、「1969年」ほど重要な年はない。「1969年」は、戦後目指してきた日本の民主化教育を諦め、管理教育へと大きくシフトした象徴的な年だからである。
その最大の象徴が、主権者教育に関心のある人々の間では有名な、「1969年通達」である。
昭和44年(1969年)、文部省は「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(昭和44年10月31日文部省初等中等教育局長通知)という通知を出し、高校生の政治活動を「教育上望ましくない」とし、政治教育も慎重に行うべきだとした。
「放課後、休日等に学校外で行なわれる生徒の政治的活動は、……学校が教育上の観点から望ましくないとして生徒を指導することは当然である」
「現実の具体的な政治的事象は、取り扱い上慎重を期さなければならない性格のものであるので、必要がある場合には、校長を中心に学校としての指導方針を確立すること」
通知の背景にあったのは、東西冷戦の激化、60年安保闘争の激化、学園紛争の激化である。
また、「部活動強制加入」につながる「必修クラブ」が導入されたのも1969年である。1969年、1970年改訂の学習指導要領において、任意の自由研究の一環として導入された「クラブ活動」が必修化され、1999年の見直しまで「必修クラブ」は続いた。
「クラブは、学年や学級の所属を離れて共通の興味や関心をもつ生徒をもって組織することをたてまえとし、全生徒が文化的、体育的または生産的な活動を行なうこと」(文部省1969年中学校学習指導要領)
そして部活動との代替措置が取られ、いまなお部活動の実質的必修化は色濃く残っている。
一方、戦後日本は「民主化」を目指し、「民主主義」教育を積極的に行おうとしていた。「クラブ活動」が導入された1951年学習指導要領では、特別教育活動は生徒自身の手で計画・組織・実行・評価されるもので、それを通じて民主的生活の方法を学び、公民としての資質を高めることができるものとされた。つまり、「特別教育活動」は、民主主義の原理と生活の方法を学ぶ活動として位置付けられていた。
「クラブ活動は当然生徒の団体意識を高め、やがてはそれが社会意識となり、よい公民としての資質を養うことになる。また、秩序を維持し、責任を遂行し、自己の権利を主張し、いっそう進歩的な社会をつくる能力を養うこともできる」
「生徒は強制されてはいけない。生徒がクラブ活動の中心である。したがって、クラブ組織については、生徒評議会の会議でじゅうぶん討議され、審議されるべきである。教師は指導者となって働いてもよいが、生徒の意見を重んじなければならない」(文部省1951年中学校学習指導要領)
「生徒は強制されてはいけない」「自己の権利を主張し」と、クラブ活動はあくまで、民主主義社会の形成者を育成するための取り組みだったのである。だからこそ、生徒自身の意思を尊重することを重視していたのであり、強制していては「民主化」教育につながらないと考えた。
「クラブ活動に全校生徒が参加できることは望ましいことであるが、生徒の自発的な参加によってそのような結果が生れるように指導することがたいせつである」(文部省1958年中学校学習指導要領)
しかしそうした精神は今となっては失われた。その転機となったのが、上述の1969年から始まるクラブの「必修化」である。
写真/shutterstock
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
中学部活の“ヒップホップ禁止令”が呼んだ波紋。「些細な問題すら当事者間で解決できない」社会が示すもの
日刊SPA! / 2024年6月14日 8時53分
-
中国で校内暴力といじめが横行、殺人も発生し中央政府が改めて対策指示
Record China / 2024年6月2日 8時20分
-
ブラック校則のルーツ!? 校内暴力全盛期の“ツッパリ・ヤンキーブーム”から「制服」の今をひもとく
オールアバウト / 2024年5月30日 21時50分
-
部活動の強制加入、高校野球の強制応援が続く日本の教育現場…岩手県の中学校は、2020年度で6割の学校が「強制加入」
集英社オンライン / 2024年5月28日 8時0分
-
なぜ日本からブラック校則はなくならないのか…校則は憲法より上位の存在、その校則の権限は校長に絶対的に委ねられている現状
集英社オンライン / 2024年5月26日 19時0分
ランキング
-
1「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ
プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分
-
2"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?
マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分
-
3自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖
NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分
-
4ジェネリック医薬品ごとの増産能力や在庫などメーカーが公表へ…厚労省、安定供給狙い
読売新聞 / 2024年6月16日 22時21分
-
5トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?
くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください