インターネットの情報に癒やされ読書から遠ざかる現代人は「“ノイズ”を受け入れる余裕がない」/『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』書評
日刊SPA! / 2024年5月28日 8時50分
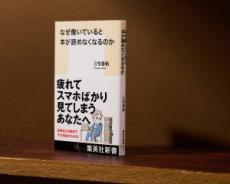
三宅香帆・著『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)
世の中には読んだほうがいい本がたくさんある。もちろん読まなくていい本だってたくさんある。でもその数の多さに選びきれず、もしくは目に留めず、心の糧を取りこぼしてしまうのはあまりにもったいない。そこで当欄では、書店で働く現場の人々が今おすすめの新刊を毎週紹介する。本を読まなくても死にはしない。でも本を読んで生きるのは悪くない。ここが人と本との出会いの場になりますように。
書店員という仕事柄、「月に何冊本を読んでいるんですか」と訊かれることがある。大抵「あまり多く読めるほうではなくて……。10冊くらいですかね」と答えているのだが、噓である。そんなに読んでいたのは大学生の頃くらいで、最近は好きな文芸誌を毎月3冊程度といったところだ。本当に本が読めなくなってしまった。泥だらけのカーペットを洗浄するショート動画なら、いつまでも観ていられるのに。
噓をつく必要などまったくないのだが、書店員の割にそれだけかと思われるのが怖くて、山積みのプルーフを横目に動画を見続けている。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』というタイトルの通り、本書は「どうすれば労働と文化的な生活を両立させられるのか?」という、社会人なら誰もが一度は直面する難問に挑んだ1冊だ。前述の通り、どうやっても学生時代のように本が読めなくなってしまった私は、それは単純に時間がないからでしょう、と思いつつ読み始めたのだが、どうやらそれだけが理由ではないらしい。
著者は文芸評論家の三宅香帆。「本が読めなかったから、会社をやめました」という前書きの通り、生粋の本好きである。著者自身も直面したタイトルの問いを探るため、本書では明治以降から現在の日本における労働と読書の変移について、さまざまな文献にあたりながら丁寧に紐解いていく。果たして、本が読めないのは現代人特有の悩みなのだろうか?
明治時代に始まった読書という習慣は、大正時代になると、本から教養を得ようとしたエリート層を中心に浸透していった。ちょうどその頃、労働者階級でも富裕層でもない中間の、いわゆる「サラリーマン」という概念も広まりつつあった。
昭和に入り、1950年代には、源氏鶏太のサラリーマン小説が爆発的に流行し、主人公に共感しやすい娯楽小説は多くの支持を得る。つまり、その頃になると読書はインテリ階級に限られたものではなくなったと言える。
1970〜1980年代になると、会社では「自己啓発」という概念が重要視されていく。大卒=エリートというイメージが薄まってきたこの時代は、自らの階級ではなく、コミュニケーション能力や自己の努力次第で出世するチャンスを得られるようになった。読書や教養は、学歴がなくても一発逆転を狙えるツールとしてさらに広まった。
しかし1990年代になると、日本の労働環境は一変する。バブルが弾けたのだ。不景気に伴って書籍の売れ高も減少したが、一方で自己啓発書の市場は伸びていたというから驚きだ。それは、他人や社会というコントロールできないものは捨て、コントロール可能な自己の変革によって人生を変えるしかない、と思う人々が増えたという証左である。
「他者」という、変えようがない存在は脅威になりうる。自分にどのような影響を及ぼすかわからない、そんな存在を著者は「ノイズ」と呼ぶ。そして、この「ノイズ」という概念が、タイトルを紐解く重要なキーワードとなる。
-

-
- 1
- 2
-

この記事に関連するニュース
-
ミラノ風ドリア「480円→290円」で売上数3倍…創業者が「サイゼリヤの料理は、まずくて高い」と語る深い理由
プレジデントオンライン / 2024年7月4日 8時15分
-
「なぜか読書ができない」社会人必読の一冊 ― 20代~30代が今読んでいるビジネス書ベスト3【2024/6】
マイナビニュース / 2024年7月1日 17時0分
-
『N』は今まで自分が書いてきた中で一番の、究極の「体験型」小説かもしれません『N』道尾秀介
集英社オンライン / 2024年6月30日 10時0分
-
【夏限定新カバー登場!】杉井光『世界でいちばん透きとおった物語』(新潮文庫nex)、完全描き下ろしイラストの季節限定ダブルカバー特別仕様で発売中!
PR TIMES / 2024年6月26日 14時15分
-
「全身全霊で働くっておかしくないですか?」会社員が読書できるゆとりを持つためには――大事なのは、真面目に働く「フリをする」技術【三宅香帆×佐川恭一対談 後編】
集英社オンライン / 2024年6月22日 11時0分
ランキング
-
1「知らないとヤバい…免許返すべき?」 道路にある「謎の斜線ゾーン」通って良い? どんな意味ある? 元警察官が解説
くるまのニュース / 2024年7月5日 9時10分
-
2スーパーでまとめ買いしたお肉→「そのまま冷凍庫」はNG!?理由に「知らんかった」ネット驚愕 ニチレイフーズオススメの方法は
まいどなニュース / 2024年7月3日 12時8分
-
3【早期発見のために】乳がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、胃がん、食道がん…“予兆”の可能性がある「体からの警告」
NEWSポストセブン / 2024年7月5日 16時15分
-
479%がパスタは家で作って食べる!最も好きなパスタソース1位はバリエーションが豊富
よろず~ニュース / 2024年7月5日 11時40分
-
5寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください












