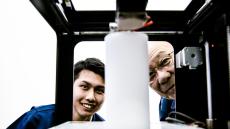不確実性を恐れる日本企業に伝えたい解決の近道 「フワフワ」した話もビジネスには重要だ!
東洋経済オンライン / 2024年1月9日 16時0分
前例のないアイデアに対して否定的になる日本企業は多いですが、それでは良質な「問いかけ」によるイノベーションは生まれません。あるアイデアが「本当に可能なのか?」と考えるとき、会議室での議論の前に、完璧でなくていいから「とりあえず」作ってみればいいのです。ビジネスデザインを専門に手掛ける野々村健一氏が解説します。
※本稿は野々村健一氏の新著『問いかけが仕事を創る』から一部抜粋・再構成したものです。
日本企業は「曖昧なこと」が苦手
「不確実な状況を楽しむ」「曖昧であることを楽しむ」──誤解を恐れずに言うと、これは日本企業が最も苦手とするところの1つだと思います。
「落としどころはどこなの?」「前例はあるの?」「なんでうまくいくと言えるかがわからない」など、さまざまな言い方がありますが、要は先行きが不確実な状況を「悪いこと」として糾弾することが頻繁にありますよね。
もちろん、そういうことを言いたくなるには理由がありますし、場合によってはこれを突き詰めないといけないこともあります。
例えば日本が大量生産競争に追いつこうとしていた時代、製造業でやらなければいけなかったことは、この不確実性といえるような「振れ幅」をできるだけ小さくし、品質を上げるということでした。これに関して日本は見事に世界一になったと言えます。ただ、そこから生まれるものは、あまり創造的な問いかけとは言えません。
一方で、イノベーションに取り組んでいったり、問いかけることを頻繁に繰り返していくと、多くの曖昧さや不確実性と意図的に向き合っていくことになります。これは、私たちが数十年ほど正しいと思ってきた仕事の基本動作とはかなり異なります。
私が紹介している「問いかけ」も、ほとんどが唯一解のあるものではありませんし、オープンエンディッド(「AかBか」ではない、オープンな問い)なものがいいと言っているくらいですが、人によってはそれを“曖昧”と捉える可能性があります。
でも、それでいいのです、ここでいう問いかけは「問い詰め」ではありません。人間の想像力は余白があるからこそ発揮されるものなのです。
「フワフワした話」を恐れすぎていないか
多くの組織は不確実性を極度に恐れていることは先ほど述べましたが、この状況がさらに進行してしまうと、明確な“病状”が現れます。
例えばその1つは、「フワフワ恐怖症」です。「なんかフワフワしたロジックなんだよね」「なんだかフワッとしててすみません」──実はこうした言い方がされるのは、日本だけではありません。欧米でもこうしたことを“Fluffy”などと表現しています。
この記事に関連するニュース
-
柳澤大輔氏がiUの教授に就任 2025年度からプロジェクトを推進
PR TIMES / 2024年5月24日 12時45分
-
グッドパッチ、グロービス経営大学院と新科目「デジタル・プロトタイピング」を共同開発
PR TIMES / 2024年5月8日 14時45分
-
アップルやアマゾンでも「失敗する」共通の特徴 プロジェクト自体は最終目的ではなく達成する手段
東洋経済オンライン / 2024年5月7日 18時0分
-
MIMIGURI 池田めぐみと安斎勇樹の共著『チームレジリエンス:困難と不確実性に強いチームのつくり方』が本日5月7日(火)からAmazonにて先行予約開始!
PR TIMES / 2024年5月7日 15時45分
-
指示待ちならまだマシ…「指示通りにすらできない新人」を大量につくり出してしまう上司の2パターン
プレジデントオンライン / 2024年5月7日 9時15分
ランキング
-
1物流TOB合戦、佐川の「異次元の高値買収」で決着へ 株式市場は厳しい評価、問われる巨額買収の果実
東洋経済オンライン / 2024年6月3日 17時30分
-
2データ転用・独自解釈・書き換え…5社に広がった型式不正、揺らぐ自動車業界の信頼
読売新聞 / 2024年6月4日 0時1分
-
3中小の瓶飲料がピンチ 資材・原材料の値上げラッシュも価格転嫁しにくく板挟み 悲鳴を上げる業界団体の長
食品新聞 / 2024年6月4日 9時30分
-
4新紙幣発行まで1か月 ATM・券売機の交換は…“タンス預金”に変化も?
日テレNEWS NNN / 2024年6月3日 21時17分
-
5「ライドシェア」全面解禁の議論、Uber社CEOが懸念“時間かかるほど状況は悪化する”
日テレNEWS NNN / 2024年6月3日 22時24分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください