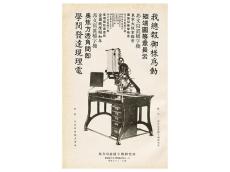写植機誕生物語 〈石井茂吉と森澤信夫〉 第44回 【茂吉】文字と文字盤(1) 酷評
マイナビニュース / 2024年6月25日 12時0分
フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
○この文字では使えない
海軍水路部での写真植字機導入が順調に進み、2台目の機械の注文が入って安堵したのと入れ替わるように、1929年 (昭和4) 秋から1930年 (昭和5) 春までかけて写真植字機が納入された共同印刷、秀英舎、凸版印刷、日清印刷、精版印刷の5大印刷会社から、機械を実際に扱ってみたうえで「邦文写真植字機はまだ実用には不十分である」という厳しい指摘が入った。ようやく実用機が世に出たとおもっていたのに「まだ使えない」と言われてしまったのである。
その理由は、つぎのようなものだった。
一、文字の字体が活字明朝と違っており、かつ字体そのものが洗練されていないから、印刷した時に力が足りない。また、文字の太さにムラがある。――これは字母の不完全さによるものであった。
一、印字したものを見ると、一行の中に文字が左右にハミ出しているものが目立つ。――文字盤に配置した文字の位置が正確でないためと、文字盤を固定するラックのピッチが正確でないためであった。
一、ふり仮名印字ができない。――普通の仮名をレンズによって縮小して、ルビの位置だけ右へ送りを与えて印字すればできることであったが、このような面倒なことは実用上不可能に近かった。
[注1]
また、大阪の精版印刷でこの邦文写植機を実際に扱った中田祐夫 (後の中田印刷社長、日本印刷学会長) が後年述懐したところによると、「レンズによる文字の大小の変化が10種類では不足」と感じたという。
〈その時の機械は一枚文字盤方式で、取りはずしに大変不便であった。レンズは六本しかなく、その上機械の安定性も悪く、シャッターが動かないこともしばしばで、動いても露出時間にムラがあり、何回も分解して調べたことがあった。また、電圧調整ができなかったから、傍にあった製版カメラに影響されて、ひどい濃淡のムラが出てしまい、二カ月くらいいろいろいじくってみたが、とうとう使いものにならず、親爺 (当時の精版印刷の社長) も大変なものを買い込んだものだと思った〉[注2]
この記事に関連するニュース
-
TOPPANホールディングス 印刷博物館 P&Pギャラリーで「欧文活字の銀河」展開催
PR TIMES / 2024年6月28日 11時45分
-
モリサワ 「SOPTECとうほく2024」に出展【7/11-12・仙台】
PR TIMES / 2024年6月17日 16時15分
-
登録抹消された「ガンダム」のその後 グレート合体を各陣営がトライアルしたワケは?
マグミクス / 2024年6月12日 6時25分
-
写植機誕生物語 〈石井茂吉と森澤信夫〉 第43回 【茂吉と信夫】海軍水路部からの注文
マイナビニュース / 2024年6月11日 12時0分
-
天下一レンズキット「EOS R7+RF-S 18-150mm」がレース流し撮りもスナップも万能過ぎ!
ASCII.jp / 2024年6月8日 15時0分
ランキング
-
1柴犬が必死でくわえようとするのはまさかの“一生無理”なヤツ 子どものような戦いに「激可愛すぎて永遠にリピート」
ねとらぼ / 2024年6月30日 7時0分
-
2iPhoneでも使うべし!Google系便利アプリ5選|iPhoneでGoogle
&GP / 2024年6月29日 22時0分
-
3別人級メイクの達人がすっぴんからパーティーメイクすると…… 驚きの大変貌に「めちゃめちゃビジュがいい!」「これはまさしく詐欺」
ねとらぼ / 2024年6月29日 19時30分
-
4オックスフォード大学ご訪問の天皇陛下、“ネクタイの柄”に注目集まる
ねとらぼ / 2024年6月29日 15時9分
-
5華やかな“Copilot+ PC”売り場、でも「それ、Arm版Windowsですよね?」 “分かっている人があえて選ぶPC”が一般層に猛プッシュされている不安
ITmedia PC USER / 2024年6月26日 12時25分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください