蚊取り線香が「渦巻き型」になった理由を説明できるか…世界初の「蚊取り線香」を生み出した"ある農家"の軌跡
プレジデントオンライン / 2022年4月15日 10時15分
※本稿は、田宮寛之『何があっても潰れない会社 100年続く企業の法則』(SB新書)の一部を再編集したものです。
■もともとはミカンなどを栽培する農家だった
大日本除虫菊株式会社(以下、大日本除虫菊)。この社名から、日本に暮らす人なら誰もが知る製品が瞬時に思い浮かぶ人は、あまり多くはないだろう。
その製品とは、通称「金鳥の蚊取り線香(正式名称は「金鳥の渦巻」)」である。
「金鳥の夏 日本の夏」という、よく知られるキャッチコピーは実に半世紀余りにわたり使用されてきた。このひと言を聞くと、多くの人が「今年も夏がやってきたんだな」と感じる、これはもはや一製品の宣伝を超えた「日本の夏の風物詩」といってもいいだろう。
その他、「かとりマット」「キンチョール」「虫コナーズ」「ゴン」──蚊取り線香のみならず、大日本除虫菊は日本人に長年親しまれてきた数々の殺虫剤、防虫剤を世に送り出してきた。137年もの歴史を持つ老舗企業であり、今なお業界をリードし続けているトップ日用品メーカーだが、その出自は意外なところにある。
大日本除虫菊の前身は、1885年(明治18)、和歌山県有田郡(現在の有田市)で創業された上山商店だ。商店といっても商材は物品ではない。上山家の家業は、すでに300年以上も続いていた上山柑橘園、つまりミカンなどを栽培する農家だった。
■蚊取り線香開発のきっかけは、ミカンの輸出業
当時、明治政府は輸出を奨励していた。近代化にかかるコストを補うには、輸出で外貨を稼ぎ出すしかない。すでに日本は生糸の輸出国として欧米に知られていたが、他にも欧米に売れそうなものがあれば何でも輸出せよ、という気運が高まっていた。
こうして海外に広く門戸が開かれた時代に、上山家の四男である英一郎が、上山柑橘園のミカンを輸出しようと設立したのが上山商店である。大日本除虫菊のスタートは、ミカンの輸出業だったのだ。
上山商店初代社長となった英一郎は、ここから不思議な縁に導かれるようにして、蚊取り線香の開発に至る。
上山商店の設立と同年、アメリカ・サンフランシスコで植物会社を経営するH・E・アモアという人物が来日した。慶應義塾に学んだ英一郎は、恩師・福澤諭吉にアモアを紹介され、実家の上山柑橘園を案内した。そしてアモアの帰り際には上山柑橘園のミカンに、竹や棕櫚(しゅろ)、葉蘭、秋菊など日本特有の植物の苗を添えて渡したという。
アモアと知り合ったことがアメリカの販路開拓・拡大につながれば、という考えが英一郎にあったことは想像に難くない。もとより上山商店のミカン輸出業は順調に滑り出していたようだが、一方、アモアとの縁はまったく別の果実を英一郎にもたらした。
■「除虫菊を日本で初めて実用化し、普及させた人物」
後日、アメリカに帰国したアモアから返礼品として、さまざまな植物の種が送られてきた。
「この植物を栽培して巨万の富を得た人が多い」との注意書きが添えてある「ビューハク」と表示された袋の中にキク科の多年草の種があった。
それこそが「除虫菊」、上山商店をミカン輸出業から蚊取り線香をはじめとする日用品メーカーへと変えたきっかけであり、現在の社名のもとになった運命の植物、除虫菊である。

ただし英一郎は、「除虫菊と出会った最初の日本人」ではない。公的な記録によると、英一郎が除虫菊を手にする前に内務省衛生局所有の植物園で実験的に栽培されており、殺虫効果も認められていた。にもかかわらず普及しなかったのは、栽培の奨励に当たり種を配布していた地方役人の理解不足や、新しいものを忌避しがちな農家の狭量が原因だったようだ。
こうした背景もあるなかで、英一郎は「除虫菊を日本で初めて実用化し、普及させた人物」になっていく。また、英一郎と除虫菊の出会いは、それまで日本に存在しなかった「殺虫剤工業」の始まりでもあった。1886年(明治19)のことである。
■除虫菊は貧しい農家を救い、日本を貿易国に押し上げる植物だ
英一郎は、まず自分で除虫菊を育ててみることにした。花を製粉して既存のノミ駆除剤と比べてみたところ、殺虫効果にまったく遜色はなかった。そこで除虫菊を栽培する農家を増やすための全国行脚を始める。しかし、その道のりは決して平坦ではなかった。
まず直面したのは、先に国家事業としての除虫菊栽培が頓挫した理由と同様、新しいものを忌避しがちな農家からの懐疑的な目である。農家には保守的な人々も多く、たいていは除虫菊の栽培をすすめる英一郎を「得体の知れない人物」と見なして門前払いした。
それでも英一郎が諦めなかったのは、福澤諭吉の薫陶を受けたことで「貿易立国こそが日本の生き筋である」と固く信じていたからだ。除虫菊を輸出品へと育てることで貿易立国に関与したいと考えたからこそ、除虫菊普及のために西へ東へと飛び回った。
しかも、除虫菊は痩せた土地でも育つ。これならば荒れ地を持て余している農家の食い扶持になる。除虫菊は日本を貿易国へと押し上げる輸出品の1つになると同時に、貧しい農家の救済策となる可能性を秘めた、まさに一石二鳥の植物だったわけだ。
■地道な普及活動の結果、種の注文が殺到するように
また、先述のとおり、明治期の日本では一気に海外との行き来が増大した。盛んな交易は日本の近代化のために必要不可欠だったが、それには疫病や外来害虫という代償もつきものだった。外国種の柑橘類の苗と一緒に日本に「輸入」され、大きな被害をもたらしたカイガラムシなどは、その代表格である。
ミカン農園を家業とする英一郎にとって、害虫はのっぴきならない問題だった。貿易立国という国家ビジョンを差し引いたとしても、除虫菊は自身の農園のため、そして日本全国の農家のために絶対に実用化し、普及させたいものだったのだ。
全国行脚を続ける他、英一郎は博覧会などにも積極的に除虫菊を出品した。こうした地道な努力が、徐々に先進的な農家の目にとまるようになっていく。英一郎は、除虫菊を栽培してみたいという声がかかれば種を分け与え、もっと詳しく知りたいという問い合わせが入れば迷わず自ら現地に飛んでいった。
1892年(明治25)には、除虫菊の有用性と共に英一郎の普及活動を紹介する記事を大阪朝日新聞が掲載し、他のマスコミの注目も集めたことで、全国から種の注文が殺到したという。
■「風が吹いただけで飛び散る」当初の使い勝手は良くなかった
ここから、除虫菊はどのように「蚊取り線香」になったのか。その背景にある大日本除虫菊の企業スピリットはいかなるもので、どのように現在に受け継がれているのか。
当初は、除虫菊の花を挽いた粉末をおがくずなどと混ぜ合わせ、火鉢や香炉の灰の上に円状に撒き、その末端に火をつけるという用法だった。これは煙で蚊を除ける「蚊遣り火」という従来の手法に除虫菊を用いたものだが、少し風が起こっただけで灰が飛び散るうえに大量の煙が発生してしまう。決して使い勝手は良くなかった。
高い殺虫効果がある除虫菊を、もっと使いやすい日用品にするにはどうしたらいいのか。除虫菊という新しい植物に出会った英一郎が、あの「蚊取り線香」に辿り着いた出発点は、こうした発想だった。
最初のきっかけは、除虫菊の普及行脚で訪れた東京の宿で仏壇線香屋の息子と出会ったことである。その人物と話すうちに、英一郎は、線香の原料に除虫菊の粉末を練り込んではどうかと着想した。

■1890年に世界初「棒状の蚊取り線香」が誕生した
こうして1890年(明治23)に完成したのが、いまだかつて世界に存在しなかった革新的殺虫剤、除虫菊を練り込んだ棒状の蚊取り線香である。赤と青のベースカラーに、商品名の「金鳥香」「キンチョウコウ」、鶏のトレードマークを配したパッケージ。どんな人にもひと目で「金鳥の蚊取り線香」とわかるデザインの原型は、このときに誕生したものだ。
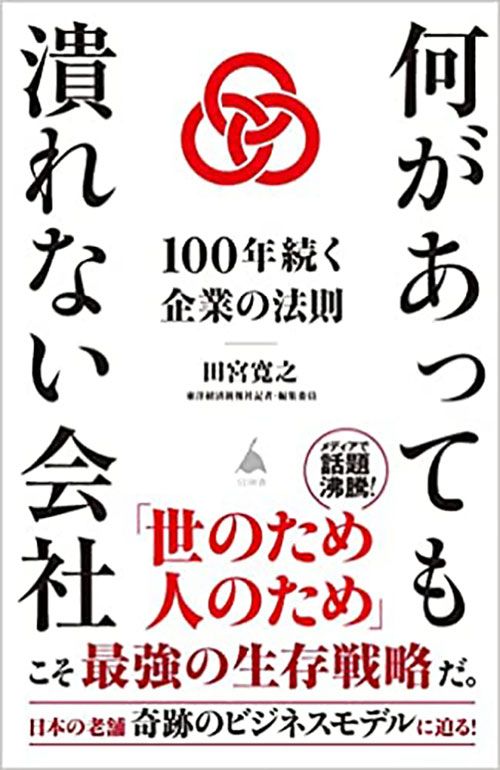
ここで初めて現れた鶏のマークは、英一郎が信条としていた中国故事「鶏口となるも牛後となるなかれ(大きな集団の末端に甘んじるよりも、小さな集団の頭になれ)」からきているという。小さな集団どころか、日本には存在すらしなかった殺虫剤工業という新しい業界を創出した身として、最先端を走っていくのだ、という気概を込めたものである。
ただし、きわめて画期的な商品ではあったものの、棒状の蚊取り線香には、いくつか決定的な難点があった。
まず、細すぎるために折れやすい。仏壇や墓に供えるだけの線香ならば細くても問題ないが、殺虫剤という日用品となると、どこへ持ち歩いても、どこで焚いても折れずに効果を発揮する頑丈さが求められた。
また、煙の発生量が少ないため、1本ではせっかくの効果が十分に発揮されない。また、燃焼時間が40分と短く、一晩中効果を得るためには何本も取り替えなくてはいけない。苦肉の策として3本を同時に焚ける専用台を付属品としていたが、ある程度の煙の量は確保できても燃焼時間の問題は解消されない。
■「渦巻き型」になったのは、燃焼時間を長くするため
より効率的に、より長時間にわたり殺虫効果を持続できるよう、改良を加える必要があった。かといって単に長くすればいいという話でもない。40分の燃焼時間を数時間にするには4倍、5倍の長さにする必要がある。棒状ではいっそう折れやすくなるだろうし、折れなかったとしても使用する際の取り扱いが不便すぎる。
思案に暮れる英一郎に、「線香を渦巻き型にしてはどうか」というアイデアを提案したのは妻・ゆきだった。そこから渦巻き型の蚊取り線香を量産するための試行錯誤が重ねられ、ついに私たちがよく知る「金鳥の渦巻」が発売される。実に渦巻き型の着想から7年後、1902年(明治35)のことである。
渦巻き型になった蚊取り線香の燃焼時間は約6時間、つまり寝る前に点火すれば、朝まで蚊を除けることができる。これならばもっと売れると英一郎が確信したとおり、蚊取り線香は徐々に売上を伸ばしていった。
こうしてミカンよりも除虫菊を多く扱うようになった上山商店は、1919年(大正8)、株式会社化に伴い大日本除虫粉株式会社、1935年(昭和10)には現在の社名である大日本除虫菊株式会社に社名変更した。
----------
経済ジャーナリスト
東洋経済新報社編集局編集委員、明治大学講師(学部間共通総合講座)、拓殖大学客員教授(商学部・政経学部)。東京都出身。明治大学経営学部卒業後、日本経済新聞グループのラジオたんぱ(現・ラジオ日経)、米国ウィスコンシン州ワパン高校教員を経て1993年東洋経済新報社に入社。企業情報部や金融証券部、名古屋支社で記者として活動した後、『週刊東洋経済』編集部デスクとなる。2007年、株式雑誌の『オール投資』編集長に就任。2009年、就職・採用・人事などの情報を配信する「東洋経済HRオンライン」を立ち上げて編集長となる。これまで取材してきた業界は自動車、生保、損保、証券、食品、住宅、百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、外食、化学など。『週刊東洋経済』デスク時代は特集面を担当し、マクロ経済からミクロ経済まで様々な題材を取り上げた。2014年に「就職四季報プラスワン」編集長を兼務。2016年から現職。
----------
(経済ジャーナリスト 田宮 寛之)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
明治大学植物工場基盤技術研究センターが 扶桑化学工業・大和ハウス工業との共同研究実績を公開
PR TIMES / 2024年5月17日 14時0分
-
オレンジ高騰の一方… 国産ミカンも“カメムシ”が原因で不足の可能性 西日本中心に大量発生のカメムシ「吸われると実がだめになる」
CBCテレビ / 2024年5月13日 18時57分
-
王子HD、「薬用植物の王様」に注力する切実な事情 甘草の大規模栽培で「脱・製紙企業」目指す
東洋経済オンライン / 2024年5月4日 9時0分
-
【今、ご当地コスメが面白い】 歯みがきを瞑想時間に変える傑作や 大人気の福岡とろ~り「生せっけん」
CREA WEB / 2024年5月3日 7時0分
-
ミカン農家がドローン学校、園地で散布訓練 かんきつ栽培で普及促進、負担軽減を後押し
共同通信 / 2024年4月18日 8時3分
ランキング
-
1キャベツ高騰 1玉1000円!? スーパーからキャベツ消えた、春キャベツ一体どこへ?【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月16日 21時20分
-
2クルマの価格はまだまだ上がる? 下がる要素がとても少ないワケ
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 6時5分
-
3インドネシアで3億円過大計上か トヨタ系部品メーカー
共同通信 / 2024年5月16日 22時32分
-
4《告発スクープ》周富徳さんの弟・周富輝氏の中華料理店で長年にわたる食品偽装が発覚、元従業員が明かした調理場の実態
NEWSポストセブン / 2024年5月17日 11時15分
-
5EVが売れると自転車が爆発する...EV大国の中国で次々に明らかになる落とし穴
ニューズウィーク日本版 / 2024年5月17日 12時5分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










