「孫の名前、言える?」は絶対にダメ…むしろ親の認知症を加速させてしまう"NGな家族の声かけ"の中身
プレジデントオンライン / 2024年12月27日 18時15分
※本稿は、川内潤『親の介護の「やってはいけない」』(青春新書インテリジェンス)の一部を再編集したものです。
■記憶力を試すような声かけは逆効果
多くの家族は、認知症の親の徘徊がはじまると、家に閉じ込めて外に出られないようにしてしまいます。
たとえば、玄関を開けるとチリンと音が鳴るようにベルをつけたり、家族が片時も目を離さないよう交代で、まさに“見張り”ます。でも、私の今までの経験から言っても、それは逆効果だと言わざるを得ません。
本人を混乱させてしまいますから、家族が目を離した隙に、ふらっと出て行ってしまう可能性が高まるんです。「徘徊するからといって外に出さないのは、本人の混乱を生んで、よりトラブルを増やしてしまうのでやめましょう」と書いてある記事を読んだことがありますが、私もその通りだと思います。
徘徊は心配かもしれませんが、GPSをつけているのですから、家のなかに閉じ込めず、外に出てもらってはどうでしょう?
現在は「地域の高齢者見守りネットワーク」というものがあって、そこに事前に登録するのも1つの方法です。ただ、徘徊が頻繁(ひんぱん)になってきたら、そのときは施設に入ってもらうことを検討したほうがいいと思います。
また、家族は認知症の進行を少しでも遅らせたくて、「お父さん、夕ご飯に何を食べたか、覚えてる?」「孫の名前、言える?」「お父さん、今いくつ?」などと、できなくなっていくことを主体に聞いてしまいます。でも、親のためと思っているこうした声かけが、実はいちばんよくありません。忘れていくことを知ることで、逆に本人にストレスがかかり、混乱させてしまいます。
つまり、家族が認知症予防だと思ってやっていることが、認知症を悪化させているわけです。恐ろしいことですよね。
■「認知症=怒りっぽくなる」と言われているが…
お父さんの記憶がどんどん失われていくのを目の前にすれば、こんなふうに声をかけるのは仕方のないことです。こう書いている私でも、実際に自分の親を前にしたら、同じことをしてしまうでしょう。それが家族の心理だと思います。だったら、目にしないほうがいいのです。
認知症を患うと怒りっぽくなると、よく言われます。脳の構造上、たしかにそれはあるのですが、本人と家族の会話を聞いていると、「怒りっぽいのではなくて、怒らせているんじゃないか?」と思うことがよくあります。
「お父さん、何やってるの⁉ 立ち上がらないでって言ったじゃない」
なんて言われたら、認知症じゃなくたって、「娘のクセに、なんだっ!」って声を荒らげて言い返したくなりますよね。デイサービスで働いていた頃、「家に帰ると、娘にキャンキャン文句を言われるから、ここに泊めてくれないか?」と懇願されたことがあります。
介護施設にいらっしゃることで認知症の症状が落ち着いた、というケースもごまんと見てきました。認知症の方のケアには、専門的な知識や対応が必要です。そのトレーニングを受けていない家族が行動を制限したり、まずい声かけをしたりしてしまうと、症状が悪化する原因になりかねません。
そのうえ、深夜の見守りは肉体的な負担も大きく、共倒れになってしまう危険性もあります。徘徊が頻繁になってきたら、子どもが頑張らず専門家に委ねることが、結果的に親の安全を守ることにつながると思います。

■どれだけ頑張って介護をしても不安は解消されない
家族で介護するのはもう限界だ。施設に入ってもらうしかない──こんな話をよく耳にしますが、よくよく考えてみると、おかしくないですか?
なぜ、家族は「もう限界だ」と悲鳴を上げるまで、親の介護を頑張ってしまったのでしょうか。「人間、年をとったらみんなこうなってしまうんだから、仕方がないよね」と思って頑張らなければ、「もう限界だ」とはならなかったはずです。
限界を感じるまで介護に関わってしまったのは、もしかしたら自分の不安を解消したかったからではないですか。つまり、「親のため」と言いながら、結局は「自分のため」の介護になっていたのではありませんか。
でも、子どもがどんなに頑張って介護しても、安心感が得られることはありません。むしろ、不安はどんどん強くなります。親が老いて、いろいろなことが次々とできなくなっていく姿を近くで見ていて、不安がやわらぐ人はいないでしょう。
そして、不安が強くなっていけば、「お母さんを介護しているせいで、私の年収、いくら下がったと思っているの⁉」「お父さんより先に、こっちが倒れそうだわ」などと、言わなくてもいいことを言ってしまいます。
そのあと、「なんてことを言ってしまったんだろう」とすごく後悔するんです。
■一緒にいて辛くなるのなら、距離を取ったほうがいい
もともと親をしっかりお世話してあげるような子どもです。親を傷つけるようなことを言ってしまったという罪悪感は、介護をやらないことの罪悪感の比ではありません。
介護の現場にいたとき、そういう場面をよく目にしましたが、皆さん本当につらそうでした。ですから、親のそばで介護をして、不安や罪悪感をなくそうとすること自体が、もはや違うのではないかと思います。
介護に対して、どれだけ自分たちが頑張って向き合ったとて、不安や罪悪感を拭うことは、決してできません。だとすれば、自分の心と体の健康を保ちながら、どう親を介護したらいいかを考えるべきなのではないでしょうか。
「親のそばにいる」ことで、言わなくてもいいことを口走ってしまい、強い罪悪感に苛(さいな)まれたりするくらいなら、逆に一緒にいないほうがいい。年とともに、どんどんいろいろなことができなくなっていく親をそばで見ていて不安が抑えきれず、つらく当たってしまうくらいなら、距離を取ったほうがいい、と私は思います。
■「自分の親を虐待する」というケースに発展するおそれも
どういうわけか、多くの子どもは、それまで親と離れて心地良く暮らしていたにもかかわらず、いざ介護となると、昭和のホームドラマのような家族を目指してしまいます。残された時間はそれほど多くはないと考え、たくさん休みを取って、あるいは同居を選択して、親となるべく時間を共有して懸命に支えようとします。
でも、先ほども触れた通り、それで不安が解消されるかというと、むしろ逆です。「うちの親は、これからどうなっていくんだろう」という不安が、どんどんどんどん強くなります。なぜなら、老いは誰にも止められないからです。
どんなに家族が懸命に支えたとしても、転びやすくなるし、記憶力も低下していくものなのです。私が、「親とはなるべく一緒にいないほうがいい」「距離を取ったほうがいい」と言うと、「冷たい」とか「ドライだ」と感じる方もいるようです。
でも、これは私が訪問入浴やデイサービスといった介護の現場をいくつか経験し、子どもが親を虐待するという痛ましい事例をたくさん見てきて辿り着いた結論です。
直接自分で介護しようとするから、介護離職を考えてしまうし、実際に介護した結果、共依存になったり、親を虐待したりしてしまうのです。

■子供が怒ってしまうのも無理はない
病院で、親の診察に付き添っている息子さん、娘さんの姿をよく見かけますが、何組かは必ずと言っていいほどケンカをしています。

「お父さん、名前呼ばれたの、聞こえてないの?」「お母さん、もっと早く立ち上がれないの?」などと怒鳴り散らしているんです。具合が悪いから、体が動かなくなっているから来ているのに、と見ていて悲しくなります。
でも、そんな思いまでして診察室に入ったかと思うと、3分くらいで出てくる。3分あるかないかの診察のために、子どもは会社を休んで、片道1時間も2時間もかけて、親を病院に連れて来ているんです。それで着いたと思ったら、さらに待ち時間が1時間も2時間もかかる。親に怒鳴り散らしていたとしても、責められないですよね。
「母親の都合で病院を予約してしまって、こっちの仕事の都合はお構いなし。だから、病院に連れて行くのが大変なんですよ」という息子さんや娘さんからの声もよく聞きます。でも、なぜ子どもが親を病院に連れて行かなければいけないのでしょうか。
都合が悪いなら、断ればいいだけの話です。できないなら仕方ない。無理なら、親は友だちに付き添ってもらうかもしれないし、看護師が付き添ってくれる民間サービスを利用することもできるだろうし、そもそも1人で通えないのであれば、訪問診療に切り替えてもいいはずですよね。
■意図的に「見ないようにする」のも一つの手
それを、無理してでも親に合わせて付き添ってしまうから、「うちの子は言うことを聞いてくれるから」と勝手に日程を決めて、「あんた、来れるんでしょ⁉」となってしまうわけです。
自分のキャリアを削って、時間とお金をかけて親の病院通いに付き添うのは、一見親孝行に思われるかもしれません。しかしそもそも、たった3分間診察してもらうだけのために病院に行く必要があるのでしょうか。
今日は都合が悪いから付き添えない、ではダメなのでしょうか。もしかしたら、病院に行くことが目的になってしまい、親の症状は少しも改善されていないかもしれませんよね。親の手元や足元が覚束なくなったとしても、「ご本人はなんとかやろうとしているのだから、あまり手を出しすぎるのはよくないですよ」。
私がそう言うと、「じゃあ、もっと我慢しろ、っていうことですか?」と返されるんですが、そうではないんです。親がうまく物が取れなかったり、こぼしそうになったりすれば、見ている子どもは手を差し伸べたくなって当然です。手を貸さずに見ていることはつらい。だから、やっぱりちょっと離れて“見ない”ようにするのが得策です。
そのうえで、自分以外の人にも親の通院や介護に協力してもらえるようなルートを確保するのも、立派な介護です。
■距離を取るからこそ、優しく接することができる
そう考えると、同居というのはやはり難しい。最近も、同居して親を介護している家族から、「自分の感情がコントロールできなくなってしまった」「これまでの親子関係が全部、引っくり返されてしまった」という相談を受けて、家を離れてもらったケースがいくつもありました。
「また、親が怒り出すんじゃないか」と怯(おび)えながら、来る日も来る日も親の介護をしていたとしたら、もはや正常な状態ではありません。面倒を見れば見るほど親は弱っていくし、環境が悪くなっていくのでしたら、同居している意味はないでしょう。
なかには金銭的な理由で同居を選ばれている方もいらっしゃいましたが、家賃を払うのと介護離職をした場合のダメージを比べてもらって、家を出ていただいたケースもあります。実際、「離れて、すごく気持ちが落ち着きました」と言う方がとても多いのです。
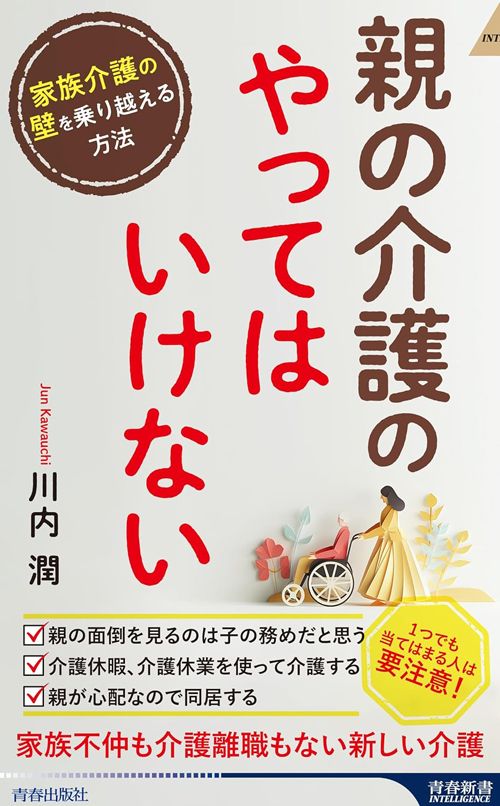
介護は育児とは異なり、時間の経過とともに支える側の負担はどんどん増えていきますから、だんだん家族の手には負えなくなってきます。でも、子ども夫婦が同居したりしていると、やはり介護のプロの手が入りづらいんです。
一方で、遠距離介護の方は、「自分たちはそばで面倒を見ることができないから」と、早めにケアマネジャーやヘルパーなどとつながって介護サービスを利用します。どちらがいいのでしょうか。
親から離れると、日本人特有の「親の介護は子の務め」という意識が薄まりますから、自分の気持ちに余裕が生まれます。そして、自身の生活が大事にできているからこそ、親にも優しく接することができるようになります。距離を取ることは、介護する家族にとっても、ケアされる本人にとっても大事なことなのです。
----------
NPO法人「となりのかいご」代表
社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士。1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業後、老人ホーム紹介事業、外資系コンサルティング企業勤務を経て、在宅・施設介護職員に。2008年に市民団体「となりのかいご」設立。2014年にNPO法人化し、代表理事に就任。厚生労働省「令和4~6年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業」委員なども兼務する。家族介護による介護離職、高齢者虐待をなくし、誰もが自然に家族の介護にかかわれる社会を実現すべく、日々奮闘中。著書に『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』(ポプラ社)、『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(日経BP)、『親の介護の「やってはいけない」』(青春新書インテリジェンス)などがある。
----------
(NPO法人「となりのかいご」代表 川内 潤)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
重度認知症の人から話を聞くと「家族の無視がつらい」と訴えた【認知症の人が考えていること、心の裡】#1
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月4日 9時26分
-
今日も「妖怪ばぁば」に遭遇…40代娘が認知症の老母に出現する5つの人格パターンの"最悪人格"に怯えるワケ
プレジデントオンライン / 2025年2月1日 10時16分
-
ユニクロとスーパーを目の敵にする意外な事情…老父が老老介護する認知症母から受ける「妄想攻撃の破壊力」
プレジデントオンライン / 2025年2月1日 10時15分
-
靴下真っ黒で徘徊…87歳老母が冷凍庫に隠していた「うなぎパック50個」の賞味期限を知った50代娘の切なさ
プレジデントオンライン / 2025年1月15日 10時15分
-
「なぜこんなにボッキボキに」左肋骨12本中9本が折れ3本にヒビ…"無敵の人"に変貌した老母を見守る娘の思い
プレジデントオンライン / 2025年1月11日 10時16分
ランキング
-
1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車
週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分
-
2部屋を整理していたら、使っていない「クレジットカード」を3枚発見…!すぐに解約したほうがいい?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月5日 4時30分
-
3「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分
-
4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは
日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分
-
5「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧
共同通信 / 2025年2月5日 10時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










