不景気でも注文が殺到する「新マーケット」
プレジデントオンライン / 2013年4月15日 14時15分
■潰れる会社と増収増益企業の違い
日本企業の苦戦が続いている。象徴的なのは家電メーカーの凋落だ。パナソニック、ソニー、シャープは過去最大の赤字を計上。3社とも創業以来最大のピンチを迎えている。半導体業界も冬の時代。12年2月にはエルピーダメモリが会社更生法を申請。ルネサスエレクトロニクスも、工場の閉鎖・売却、5000人強の人員削減を決めた。
日本企業が不振に陥った原因はさまざまだ。長引く円高は輸出産業を直撃し、雇用や社会保障に対する不安は個人消費に暗い影を落としている。
しかし、こういったマクロ要因が改善されないかぎり、日本企業の復活はないと考えるのは早計だ。じつは同じ市場環境下にいながらも、過去最高益を計上したり、増収増益を続けている企業は少なくない。逆風が吹きつける時代においても、やり方しだいで十分に成長は可能なのだ。
そこでアナリストたちに、いま注目の企業を選んでもらい、それらの会社が快進撃を続ける理由について解説をしてもらった。不利な市場環境でも利益を生み出す戦略やビジネスモデルとは、どのようなものなのだろうか。
■ヒマは金なり:「あまりお金をかけずに孤独を癒やしたい」人たち
既存市場の縮小が避けられないなら、消費者のニーズを掘り起こして新しい市場をつくればいい。まるでマリー・アントワネットの「パンがなければケーキを食べればいい」だが、実際にケーキを発掘した企業は業績を伸ばしている。
いま熱いのは、孤独な時間をまぎらわせるニーズだ。レオス・キャピタルワークス取締役・最高投資責任者の藤野英人氏は、現在の消費の動向を次のように分析する。
「いま業績を伸ばしているのは、デフレに耐えうる低価格と、孤独を埋めるためにお金を使う“孤独消費”という2つのスイッチのうちのどちらかを押した会社です。孤独消費は世界的な傾向ですが、日本は特に顕著。たとえば若者を中心にSNSが流行っているのも、誰かとつながることによって孤独が癒やされるからです」
デフレと孤独消費。この2つのスイッチを押して業績を伸ばしているのが、DVDレンタルを展開するゲオホールディングスだ。同社は2012年3月期の経常利益14%増、3期連続増収増益と好調だ。
「ゲオは娯楽の少ない郊外を中心に店舗を展開し、不定期に7泊8日50円のキャンペーンを行っています。仕事帰りにゲオで1枚借り、コンビニでビール1本買っても、200円ちょっと。この価格なら、賃金が高くない地方の若者も手軽に孤独をまぎらわせることができます。また40~50代の主婦層は韓流ドラマをまとめ借り。10枚借りても500円です。映像コンテンツは配信の時代だと言われますが、配信はまだ価格が高い。もっと利用しやすい料金にならないと、孤独消費の主役にはなれないでしょう」(藤野氏)
孤独消費では、ソーシャルゲームも見逃せない。ソーシャルゲームで伸びた会社といえばグリーやDeNAが代表格だが、カブ知恵代表取締役の藤井英敏氏が注目するのはカプコンだ。

「ゲームソフト業界はコンシューマ機の不振で苦戦を強いられていましたが、スマホの普及で息を吹き返した。なかでもいち早くソーシャルゲームに軸足を移したのがカプコンです。『バイオハザード』などの人気タイトルを持つ強みで、今後は日本やアメリカだけでなく、アジア地域のスマホ普及の波にも乗っていくはず」(藤井氏)
経済が成長する時代は「時は金なり」で、仕事や家事を効率化して時間を生み出してくれる製品やサービスに価値があった。しかし、いまは「ヒマは金なり」。仕事が増えない時代は、あり余る時間をお金をかけずに潰してくれるものにニーズがある。DVDレンタルやソーシャルゲームは、その典型といえるだろう。
■キレイ願望:機能重視で参入容易なスキンケア商品
シニア層にも、従来にはあまり見られなかったニーズが生まれている。年齢を重ねても美しくありたいという“キレイ願望”だ。前出の藤井氏は、シニア層には2つのキレイ願望があるという。

1つ目のキレイ願望は、40~50代女性の美魔女ブームだ。美魔女は年齢を感じさせないアラフォー以上の女性を指す言葉で、いまやコンテストが開催されるほどの社会現象になっている。
「ブームをうまく取り込んだのがロート製薬です。同社は12年3月で連結経常利益が過去最高益になるなど好調ですが、牽引役はかつて主力だった目薬ではなく、スキンケア商品。なかでも50代女性をターゲットにした『50の恵』はヒットを記録。中高年女性のキレイ市場は手堅いのでは」(藤井氏)
スキンケアなどの基礎化粧品は、メーキャップ系化粧品のようなにブランド力もあまり必要ない。今後もさまざまな会社に参入のチャンスがある。
●家の中のタブーを堂々とビジネスに
「2つ目は、汚物などの処理です。これまでは高齢者の、いわゆるシモのお世話はタブー視されているところがあって、家庭でお嫁さんが鼻をつまみながら世話をするか、公的な介護サービスを利用するかのどちらかしかありませんでした。そこを堂々とビジネスにしたのがユニ・チャームです。大人用の紙おむつを開発して、営業体制を強化。新しい市場をつくりました」
ユニ・チャームは、人口増加中の中国やタイ、インドネシアにいち早く幼児用紙おむつを展開。少子化が進む国内市場を尻目に、アジアの成長を取り込んで収益を伸ばしてきた企業という印象が強かった。
しかし、それは成功要因の1つにすぎない。頭打ちと見られていた国内市場では、幼児用から大人用へのシフトに成功。13年3月期には、大人用の国内売上高がはじめて幼児用を上回る見通しだ。
■増える園児と減る園児:補助金に絡めるかどうかが成否を左右する
幼児市場に特化したビジネスで業績を伸ばし続けている企業もある。保育事業を展開し、6期連続最高益のJPホールディングスだ。同社はもともとパチンコ店のワゴンサービスの会社だった。事業は順調に成長したが、出産後に仕事と両立できずに辞めていく女性が多く、社員が定着しなかった。そこで社内に託児所を設置。それをきっかけに既存の保育所の姿勢に疑問を持つようになり、子育て支援事業へと転換した。12年3月期の経常利益が前期比33%増で、6期連続の増益だ。前出の藤野氏は、同社の強みをこう分析する。
「いま自治体の間で、保育園の管理・運営を民間に任せようという動きが広がっています。その中で脚光を浴びているのがJPホールディングスです。給料の高いベテラン保育士を抱える公立保育園と違い、同社の保育士は若い人中心で、コストが低い。それと同時に保育士の教育やメンタルケアに力を入れているので、行政から厚い信頼を得ています。また社長の山口洋氏は自ら大学院に通って保育士の資格を取るなど、真摯な経営姿勢も評価されている。行政と連携が必要なビジネスでは、こうした安心感が大きな強みになります」(藤野氏)
同じ子育て事業でも異色のサービスを提供しているのが、過去最高の純利益を出した幼児活動研究会だ。同社は幼稚園に講師を派遣して、体育指導のプログラムを提供。体育指導に特化したサービスはオンリーワンだ。どうして子どもの数が減っているのに売り上げが伸びているのか。TIW代表取締役の藤根靖晃氏は、次のように解説する。
「待機児童が発生しているのは、主に0~1歳児。もう少し上の年齢の幼児が通う幼稚園では、少子化によって園児の取り合いが起きています。園児にきてもらうには、何らかの差別化が必要。そこで外部の体育指導サービスのニーズが高まっている」
ただ、体育指導が保護者に人気があるなら、同社が直接、体育教室を開いて幼児を集めてもいいはず。じつはそうしないところに、子育て支援事業が儲かる理由がある。
「幼稚園は経営者や園児の保護者に自治体から補助金が出ます。もし幼稚園を通さずに独自に教室を開くと、補助金の恩恵にあずかれず高コストになる可能性がある。幼児向け体育指導サービスは、公的な支援があるからこそ成り立つのです」(藤根氏)
補助金の存在が大きいのは、JPホールディングスの保育園事業も同じだ。子どもの数は減少しても、社会的要請の強いところには行政からお金が出て、商機が生まれる。共働き家庭の増加により、保育園は不足して待機児童が発生し、幼稚園は余って園児の取り合いが起きている。増える園児と減る園児。そこに新しいビジネスチャンスが生まれているのだ。
■中身よりコロモが大事:薬は衣で効き目が変わり、ハコで売り上げが変わる
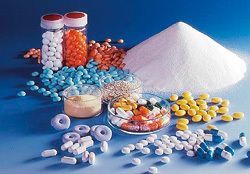
医療もこれからの成長が期待される分野だ。しかし、藤根氏は「薬そのものより、外側が面白い」と指摘する。
「私の注目はフロイント産業です。同社の主力は薬の造粒装置。とくにコーティングする機械は国内シェア7割以上を占めています。また薬の溶けやすさをコントロールするための添加剤も扱っています。12年2月期の経常利益は前期比60%増。今期も過去最高益更新の見通しです」
コーティングなど外側の部分は薬のおまけのようなもので、あまり儲けにならない気がする。しかし実は、中身よりコロモが大事らしい。薬の粒のうち、薬効成分はごく僅かで、大部分が添加剤の場合も多い。薬をきちんと働かせるためには、添加剤などで薬が溶けるスピードや吸収を調整する必要がある。そのノウハウがないと効き目が違ってくるのだ。
「フロイント産業は機械や添加剤とともに、製剤のノウハウを提供できる点に強みがあります。それを頼りにしているのがジェネリックの製薬会社です。ジェネリックメーカーは、薬効成分をつくれても、それを製剤化するノウハウに乏しい。そこで同社と組むために機械や添加剤を購入します。ジェネリックはこれからさらに伸びる分野。ジェネリックメーカーほぼすべてと取引がある同社も将来性は高い」(藤根氏)

同じ視点で藤野氏が評価するのは、12年3月期で13期連続増収となった朝日印刷だ。同社は薬の箱や能書きを印刷する会社。医薬品包装でナンバーワンだ。
「医薬品の包装は少量多品種で、なおかつ薬事法で厳しい規制があるため特殊な知識が必要です。そのため参入障壁が高く、かつて大手印刷会社も進出を断念したことがあります。一方、朝日印刷は富山で配置薬の印刷からスタートした老舗。ノウハウが蓄積され、メーカーにデザインを提案するくらいの企画力もある。医薬品包装界のトヨタのような会社です」(藤野氏)
医薬品のニーズが高まれば、コーティング装置や包装資材など外側のニーズも高まる。伸びる分野を見つけたら、その外側にビジネスチャンスを見出すのもいいだろう。
(ジャーナリスト 村上 敬 坂本道浩=撮影)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
目薬のロート製薬が6期連続で最高益 逆風の化粧品セクターで快走する理由
Finasee / 2024年5月16日 17時0分
-
当期純利益は前の期より73億2200万円増 山口フィナンシャルグループ2期連続の増収増益
KRY山口放送 / 2024年5月10日 18時46分
-
JR九州"3期連続"の増収増益 西九州新幹線の開業効果も 2023年度決算
RKB毎日放送 / 2024年5月9日 18時59分
-
伊藤忠食品、岡本社長「キャッチ・ザ・マーケット」 消費者起点で活性化を
食品新聞 / 2024年5月8日 10時36分
-
週刊スーパーマーケットニュース 2ケタ増収のベルク“椅子に座った接客”を実験
ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年4月22日 20時59分
ランキング
-
1庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか
東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分
-
2「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース
東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分
-
3「セブンプレミアム」売上高、累計15兆円を突破…節約志向でPBの存在感高まる
読売新聞 / 2024年5月18日 0時3分
-
4血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分
-
5住みたい街の特徴 3位「交通の便がいい」、2位「治安がいい」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 17時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










