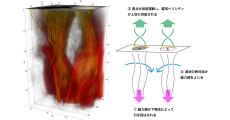「宇宙を作る」シミュレーション天文学への招待 第3回 シミュレーションが解き明かす太陽の謎 - 黒点とフレアのメカニズム
マイナビニュース / 2025年2月5日 7時1分
国立天文台(NAOJ)は1月24日、第30回「科学記者のための天文学レクチャー」として、「スーパーコンピュータが描く宇宙―アテルイIIからアテルイIIIへ―」を開催。これまで、研究者を対象に天文学の研究専用のスーパーコンピュータ(スパコン)としてシミュレーション天文学を支えてきた「アテルイII(ツー)」の業績と、2024年12月2日より、岩手県奥州市のNAOJ 水沢キャンパスにて本格運用を開始した後継機「アテルイIII(スリー)」の特徴や、同機で現在進められている最新の研究などが紹介された。
ここでは、その取材をもとに全4回のシリーズをお届けしており、第1回ではシミュレーション天文学について、第2回ではアテルイIIIの特徴について取り上げた。第3回と第4回は、シミュレーション天文学で具体的な研究内容を掘り下げる。
第3回は、太陽に関する研究を行っている宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所(ISAS) 太陽系科学研究系の鳥海森准教授による解説「数値シミュレーションと観測で迫る太陽黒点・太陽フレアの謎」をもとに、アテルイIIやアテルイIIIなどを用いたシミュレーションとその研究成果にフォーカスを当てていく。
○とても身近でも未だ謎の多い「太陽」
天文学では、さまざまな天体や天文現象などを観測して得られた情報をもとに、理論が構築されてきた。そしてその理論を用いて、天体の構造や天文現象に関する謎が紀元前より解明されてきた。つまり天文学は、観測と理論の両輪で発展してきたのである。そして今では観測能力は大きく向上し、134億光年彼方の初期銀河も観測できるほどだが、宇宙には光学的な観測が不可能なものも少なくない。例えば、太陽のような天体の内部を覗くこともその1つだ。
地球に最も近い恒星である太陽は、地球から光の速さで8分強の時間がかかる約1億5000万kmの距離にあり、太陽系の全質量のうちの約99.8%を占めている“太陽系の主”だ。そのほかの詳細は以下の通りだ。
○「太陽」の基本情報
赤道半径:約69万5700km(地球の約109倍)
質量:約1988𥝱(1.988×1027)トン(地球の約33万2946倍)
平均密度:約1.41g/cm3
表面重力:約274m/s2(約28G)
光度(明るさ):382垓8000京kW
絶対等級:4.82等級
スペクトル分類:G2V型(主系列星)
表面温度:約5500℃(一般的には約6000℃と説明される)
自転周期:(赤道付近)25日・(極付近)30日
主成分:水素…約71~73%、ヘリウム…約25~27%、そのほか(酸素・炭素・鉄など)…約2%
年齢:約46億年
この記事に関連するニュース
-
「宇宙を作る」シミュレーション天文学への招待 第2回 アテルイIIIの特性とその目指すサイエンスのゴールとは?
マイナビニュース / 2025年2月3日 7時1分
-
「宇宙を作る」シミュレーション天文学への招待 第1回 第3の天文学である「シミュレーション天文学」とは?
マイナビニュース / 2025年1月31日 7時1分
-
国立天文台の新天文学用スパコン「アテルイIII」始動! “理論の望遠鏡”で何が見える?
マイナビニュース / 2025年1月17日 19時57分
-
原始銀河は球状星団の先祖? - アルマ望遠鏡とJWSTが134億光年彼方に新発見
マイナビニュース / 2025年1月15日 17時45分
-
日欧の水星探査機「ベピ・コロンボ」が最後の水星スイングバイを実施 水星到着は2026年11月
sorae.jp / 2025年1月10日 22時5分
ランキング
-
1ゆたぼん、フジテレビ番組で“OA希望の発言”カットされ「許せへん」 スタッフ快諾も電波乗らず……「放送の仕方もヒドかった」「面白おかしく取り上げられて」
ねとらぼ / 2025年2月5日 17時0分
-
2現役の情シスが考える、KDDIのビジネスPC向け“月額費用なし”データ使い放題サービス「ConnectIN」の強み
ITmedia PC USER / 2025年2月4日 12時40分
-
3X、「コミュニティ」の投稿が誰にでも表示される仕様変更 ユーザー当惑「最悪のアプデ」
ITmedia NEWS / 2025年2月4日 19時13分
-
4「ASUS Zenbook SORA」が日本にフォーカスした理由 薄くて軽くて長時間駆動に現役大学生も夢中
ITmedia PC USER / 2025年2月5日 12時50分
-
5日産、ホンダとの統合撤回報道に「報道の事実も含めさまざまな議論進める」とコメント 方針は2月中旬めど
ITmedia NEWS / 2025年2月5日 19時0分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください