なぜ多くの知識人は「新しい生活様式」に飛びついたのか…東浩紀が「ChatGPT騒動も同じ」と断じるワケ
プレジデントオンライン / 2023年7月14日 9時15分
■リベラルと言われる言論人は無抵抗だった
――東さんは6月19日に『観光客の哲学 増補版』(ゲンロン)を出しました。2017年に毎日出版文化賞を受賞した既刊に新章2章2万字を追加されています。さらに今夏には姉妹編となる20万字の新著『訂正可能性の哲学』を刊行予定です。なにが執筆の動機になったのでしょうか。
【東】ここ数年、特に新型コロナとウクライナ戦争を通じて強く思ったことがあります。それは、人々はSNSなどでさまざまに理屈を並べても、何かあればすぐ一方向に流れされてしまうということです。そして知識人、言論人と呼ばれる人たちは、その大きな流れにほとんど抗うことができない。
例えば、リベラルを自認する言論人の多くはもともと生権力を批判していた。だからコロナが蔓延したときは政府による国境封鎖やロックダウンにみんな反対すると思っていました。しかし実際にはすぐ賛成した人が多かった。これはどういうことなのか、と。
■「学問って何のためにあるんだ?」
医学と権力が結びつくと怖いとこれまで政府を批判していた人たちが、「命を守るためにはしょうがない」と言いはじめる。これまで理論的に批判していた権力の在り方が現実に現れたのに、あっさり肯定したわけです。リベラルに限らず、人間とはなんて軽率なんだと思うことが次々に起こりました。
コロナ禍の最中は「感染症対策が前提の生活になる」「働き方や都市の在り方は大きく変わる」「新しい生活様式だ」「ニューノーマルだ」とさかんに言われました。当然ながら、人類は過去に何度もパンデミックを経験している。感染症によって人類の生活様式が変わるなら、とうの昔に変わっています。
人間は目の前の危機を過大評価し、過剰反応します。本来知識人はそういう流れに抗うためにいるはずですが、実際にはまったく抗うことができず、むしろ肯定する論理を作るようになる。そして知識人の意見にすがる人が流れをさらに大きくしていく……。自己否定みたいですが、「学問って何のためにあるんだ?」と疑問がわいてきました。
■人文書という世界の外側へ出たい
――増補版のカバーデザインは、哲学書や思想書とは思えないポップなものですね。

【東】ぼくは一貫して、思想書や人文書の読者を広げたいと考えてきました。1998年に最初の著書(『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』新潮社)を出して以来、四半世紀にわたって「人文書という狭い世界の外側へ出たい」と言いつづけてきました。特にここ数年は、その思いがより強くなりました。
例えば紀伊國屋じんぶん大賞の順位を見ても、最近は政治運動に関する本が評判がいいですね。ぼくの世代にとって、人文書を読むのは、むしろそういう政治から距離をとるというか、時代から少し離れてものを考えるためでした。
現在は状況がすっかり変わり、「私の苦しみをどう解決してくれるの?」「同じ苦しみを抱えている人いるの?」という訴えに寄り添う姿勢が人文書に求められている。それはそれでいいのですが、ぼくの本はそうじゃないので、困ったなと思っています。
正直にいうと、ぼくの読者がどこにいるか、いまはもうあまりわからないんです。読者なんていないのかもしれない。けれども、世の中の動きにすぐ対応するのではなく、少し離れた時間感覚で物事を考えるのが大事だと感じている人がいるとすれば、そんなひとに読んでもらいたいと思っています。
■谷崎潤一郎はなぜ、戦時中に『細雪』を書いたのか
――歴史上、知識人や言論人が世の中の流れに抗えたことはあるのでしょうか。
【東】抗えた試しはありません。ただ、抗えないまでも、時代の流れから距離をとった人たちはいます。
よく例に出るのが、谷崎潤一郎が第2次大戦中に『細雪』を「中央公論」に発表していたという話です。じつは同じ時期の「中央公論」には、京都学派による座談会「世界史的立場と日本」が掲載されていたりしたんですね。日本の戦争を支持する流れができて盛り上がる中、『細雪』は1943年に連載がはじまったのですが、軍の圧力で中断させられてしまう。
以前は、谷崎が『細雪』を書いたのは戦争へのある種の抵抗だったと聞いても、実はいまいちピンとこなかったんですね。でも最近、すごくわかるようになった。
戦争のような大きな流れの外に身を置くことはなかなか理解されませんし、平和ボケと言われます。それでも、距離をとる人間がいないとダメだと思うんですね。一方向の流れに抵抗するのでなく、興味のないふりをしてしれっと別のことをやりつづける距離感も大切なんだなと。
ぼくはよくシニカルで現実逃避だと言われますけど、そんなことを言ったら、どの時代も知識人はシニカルで現実逃避だと受け取られることをやってきたのだと思います。『細雪』然りです。実はそういう目線で書かれた本こそ、時代を超えて長く読まれるのではないでしょうか。

■「観光客的」とは「自分はわからない」と自覚すること
そもそも、抵抗すること自体にロマンチシズムを感じる人たちは、実は時代に流されやすい人だと思います。その意味では「ソクラテスは死刑になるまで抵抗したから偉い」と称賛する人はむしろ危険で、「ソクラテスってそういうへそ曲がりな奴だよな」と冷ややかに見つめる人のほうが流されないし、むしろソクラテス自身の態度に近い。
――時代と少し距離をとるスタンスが、本書に書かれている「観光客的」ということですね。
【東】観光客的であるために大切なのは、つねに「自分にはわからないことがある」と自覚しておくことです。
新型コロナでぼくがすごく困惑したのは、ネットに“自称専門家”が大量に出現したことです。よく知らないことを熱心に調べた結果、他人に罵詈(ばり)雑言を浴びせたり、挙げ句の果てには「ワクチンは危険だ」なんて変な方向へ走ってしまう。自分で考えるのは大事です。けれど自分の頭を過信するとQアノンのような陰謀論を信じてしまうことにもなる。
観光客的な距離感には「自分にはわからない」という諦めや謙虚さが必要です。自分はしょせんは事態を傍観するだけの観光客であって、当事者じゃないから本当のことはわからない、と距離をとる。

■中途半端なコミットメントしかありえないと認める
例えば、6月に施行されたLGBT理解増進法がある。「当事者は望んでいない」という人もいれば、「当事者にとってはまだ不十分」という人もいる。お互いに「あっちはニセモノの当事者だ」と言い合っているわけです。また、女性の権利の侵害だと訴える人々もいます。
もし自分自身が当事者なら、あるいは女性なら、ぼくもどちらかの仲間になれるかもしれない。でもそうじゃなければ「わからない」という距離感しかとれない。むろんぼくにも意見はありますし、個人的に尋ねられれば答えます。しかし、わかったフリをして、安易に正義を振りかざせる問題じゃないと思うんですよ。
この世界は複雑だから、全部にわたって知り、正しい判断を下すことはできない。ほとんどのことはわからない、という前提に立つべきです。ただ、だからといって、完全に無関心でもいられない。中途半端な関心、中途半端なコミットメントしかありえないと認め、個別の場面でできることを実践していくのが観光客的な態度です。

■ChatGPTに日本人がハマるのはなぜ?
――一方向の流れでいうと、今はChatGPTが大ブームです。開発したオープンAIのサム・アルトマンCEOは短期間に2度日本を訪れており、日本を重要な市場と位置付けていることがうかがえます。なぜ日本人はChatGPTが大好きなのでしょうか。
ChatGPTがなんで日本でブームになったのかは興味深い問題です。ちょっとはぐらかす答えかもしれませんが、ぼくはひとつには、日本人は「質問すれば何でも答えてくれる学校の先生みたいなもの」が時に好きだというのがあるのかなと思っています。
ときどき話すことなんですが、日本はとにかく初等教育の「学校」が社会の雛形になってしまっている。地域社会とか宗教とかが弱いから、それしか社会のモデルがない。そしてそのせいでいろいろ歪んでいる。
小学校だと、クラス内で問題が起こると、先生に言いつけたらすべて解決する。先生がだれが正しいか判断してくれるからです。ところが社会に出ると先生がいない。でも日本人は先生がいないと機能不全に陥るんですよ。だから、ネットでもトラブルが起こるとすぐ勤務先に「言いつけ」ちゃう。

■何でも適当にこなす超優秀なサラリーマンみたいなもの
仕事は手取り足取り教えてもらえて当然とか、誰でも平等かつ公平に扱われるべきだという発想も、すべてそういう小学校の教室モデルから来ているように思います。
現実の他人はそんなに親切じゃない。社会は不平等でえこひいきばかりです。確かに小学校では金持ちの子も貧乏人の子も同じ給食を食べるけど、それは小学校だからこそ作られている幻想ですよね。現実はそうなっていないのに、それが教えられないで大人になっている。困ったことだと思います。
――ChatGPTが多くの仕事を奪うと懸念する声も聞かれます。
【東】そうかもしれないけど、ぼくはあまり気にしてません。テック界隈では数年おきに似た議論が起こるので。
ChatGPTについては、「それっぽく答える人間」ぐらいの感覚で付き合えばいいのだと思っていいます。正しいことを教えてくれる全知全能な先生ではない。人間は会話するとき、多くの場合はほとんど考えずに答えてますよね。ChatGPTも同じです。基本的には適当に返答している。
だから無理難題を押しつけても、嘘とわからない程度の答えを返してくる。何でも適当にこなす超優秀なサラリーマンみたいなものです。そうと思って付き合えばそれなりに有能だしコストダウンにも繋がるけど、あまり真面目に考えてはいけない。
■AIは人間に近づけようとするほど厄介になっていく
あとぼくは、いま問題になっているAIのハルシネーション(幻覚、もっともらしいウソ)は原理的に改善されないと思っています。なぜかといえば、そもそも人間がもっともらしいウソをつくからです。AIを人間に近づけるというのは、そういう人間の厄介さも近づくということです。
AIを人間に近づけようとすればするほど人間の抱える厄介さに直面するということは、もっと強調されてよいと思います。人間を相手にする仕事は厄介なものです。怒るし、嘘をつくし、問い詰めたらキレるしで面倒くさい。そんな“うざい”人間から解放されるためにAIを開発しているのに、人間に近づけるのはその意味ではパラドックスです。
いいかえれば、これから問われるのは、むしろ人間とは何かという問題になると思っています。これからはAIがもっともらしい文章や美しい絵やすばらしい音楽を生成することになるでしょうが、それによって逆に、われわれにとって美とは何だったのか、真理とは何だったのか、信頼とは何だったのか、が問われてくる。どれだけ技術が進んでも、その謎は解けません。

■世の中のすべてが見えるのはいいことではない
――2017年に『ゲンロン0 観光客の哲学』が発売されて以降、世界各地で社会の分断が強く意識されるようになりました。これは近年の特徴なのでしょうか。
【東】社会の分断は昔からあったと思います。それが現在はSNSによって可視化されるようになったのでしょう。
可視化はいいことだとは限りません。そもそも、ぼくたちはいろんなことを「見ないふり」をしながら社会の秩序をつくっている。すべてを丸裸にすると、秩序自体を壊してしまう危険性があります。
たとえば衛生問題でいうと、もし家の至るところで雑菌が拡大され可視化されるようになったら、そこらじゅう雑菌だらけですよね。それがすべて見えたら、たぶん生活できません。
ところがSNSは、人々の心にうごめく雑菌を社会全体で可視化してしまう。例えば、政治家を信頼するといっても、政治家だって人間だから、プライベートではいろいろ問題がありうるわけです。でも、一種の幻想として「政治家的人格」を信じないと、とても信頼なんかできない。いまはその幻想が機能しなくなってしまったので、いろいろ難しくなってしまった。

■幻想を肯定することにもっと目を向けていい
――幻想ですか。
【東】「幻想とは何か」というテーマは、ウクライナ戦争が起きてからとくに考えるようになりました。多くの知識人は、現実を見せることが正義だと思っている。しかし実際には、あるていど幻想をつくらないと社会秩序は壊れるんです。家庭も企業も学校も、幻想によって成立しているわけです。すべての現実を赤裸々に出したら、ぼくたちはたぶん壊れてしまいます。
戦争と平和でいえば、確かに平和は幻想です。地政学的な条件、国家間の対立などを見ずにボーっとしているのが平和ですから。しかし「平和なんて幻想だ」と言って、ずっと戦争するわけにもいかない。平和という幻想には現実的な価値があるわけです。
幻想をつくるというと、「現実逃避だ」と言う人がいますが、幻想がないと社会は存在できません。幻想が現実を覆い隠しているというのは単純な考え方で、実際には、幻想があるから現実が維持されている。
知識人や言論人は、ただ現実を突きつけるだけが仕事ではない。政治にしても、学問にしても、実は幻想を供給する立場なのだと自覚することが必要なんだと考えるようになりました。知識人だけでなく、幻想の価値を認識し、幻想を肯定することに、みなもっと目を向けていいと思います。

■今後のテーマは「家族の哲学」
――今回の増補版では、第1部が「観光客の哲学」、第2部が「家族の哲学(導入)」となっています。家族の哲学は、今後のテーマということですね。
【東】それがまさに、この夏に続編として刊行される『訂正可能性の哲学』(ゲンロン)のひとつのテーマになっています。『観光客の哲学』では「家族の哲学(導入)」となっていますが、『訂正可能性の哲学』ではその「導入」が取れて、本格的に家族の哲学が展開されています。第一部のタイトルは「家族と訂正可能性」です。
なぜぼくが家族のテーマにこだわるかというと、ひとつにはリベラルの限界を超えたいという問題意識があります。リベラルは、家族という存在は閉鎖的なコミュニティだと考えます。その外に社会という開放的な空間があるのだから、閉鎖的な家族は壊してしまったほうがいい、たとえば教育や介護などもなるべく公共的なサービスへ移行するほうがいい、という意見もあります。
■哲学は「正義か悪か」を判断するだけではない
しかしぼくは、家族と公共を、閉じた家族と開かれた公共というかたちで対立させること自体が間違いだと考えてきました。家族と公共は対立しません。それは両方とも人間関係のネットワークを機能させるための幻想の名前にすぎず、その一つが「家族」と呼ばれているだけなんです。そういう議論をしているのが『訂正可能性の哲学』です。
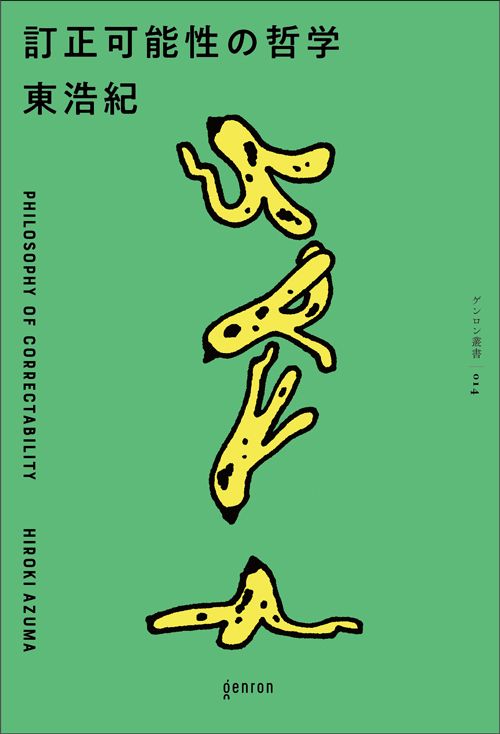
いずれにせよ、人間はひとりで生きることはできない。個人がみなバラバラに自由に生きていて、それでもすべての公共サービスが回るような国家像は考えることができないし、もしそういうものがあるとしたらそれは全体主義国家に近くなると思います。家族は幻想かもしれないけど、それには現実的な役割がある。
いまの「哲学」は、客観的な現実(エビデンス)を突きつけ、正義か悪かの判断を迫るような単純な議論ばかりになってしまいました。けれど、ぼくはそれとは異なった仕事をしていきたいと考えています。
----------
批評家・哲学者
1971年東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(学術博士)。株式会社ゲンロン創業者。同社発行『ゲンロン』編集長。専門は哲学、表象文化論、情報社会論。著書に『存在論的、郵便的』(1998年、第21回サントリー学芸賞 思想・歴史部門)、『動物化するポストモダン』(2001年)、『クォンタム・ファミリーズ』(2009年、第23回三島由紀夫賞)、『一般意志 2.0』(2011年)、『弱いつながり』(2014年、紀伊國屋じんぶん大賞2015「大賞」)、『ゲンロン0 観光客の哲学』(2017年、第71回毎日出版文化賞 人文・社会部門)、『哲学の誤配』(2020年)ほか多数。対談集に『新対話篇』(2020年)、 『観光客の哲学 増補版』(ゲンロン)がある。
----------
(批評家・哲学者 東 浩紀 構成=伊田欣司)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
イーロンによるツイッター買収最大の罪とは フランシス・フクヤマ「未来は絶望か希望か」
東洋経済オンライン / 2024年5月4日 21時30分
-
AIは欧米諸国の「知能劣化」を加速させるのか E・トッド「民主主義」の終わりとその先の希望
東洋経済オンライン / 2024年4月27日 21時0分
-
コルクの佐渡島庸平さん絶賛!東大卒・こじらせニートの哲学エッセイ 書籍『自分とか、ないから。 教養としての東洋哲学』4月23日発売
Digital PR Platform / 2024年4月16日 11時3分
-
AIを用いた対話型司書(検索)サービス「クジラ」4月15日リリース
PR TIMES / 2024年4月15日 14時45分
-
編集長・東浩紀 批評誌『ゲンロン 16』、4月10日発売開始
PR TIMES / 2024年4月8日 17時15分
ランキング
-
1ウインナーは切り込みNG?「ずっと間違ってた…」食品メーカーが“おいしさ損ねる三箇条”を伝授
ORICON NEWS / 2024年5月4日 17時30分
-
2コンビニは「前向き駐車」すべき? なぜ「バック駐車」は推奨されない? “納得の理由”と守らなかった際の「悪影響」とは
くるまのニュース / 2024年5月2日 17時10分
-
3なぜ「立体駐車場」ではタイヤが“キュルキュル”鳴る?「特殊な床」が原因なの!? 異音には「部品の劣化」の可能性も
くるまのニュース / 2024年5月4日 14時10分
-
4スターバックス、8日から“人気フラペチーノ”が復活 「絶対に買いに行く」と意気込む声が続出
Sirabee / 2024年5月3日 4時0分
-
5知られざる静岡が誇る蕎麦のチェーン店「そば処 鐘庵」で味わう絶品の桜エビの天ぷら蕎麦とは?
GOTRIP! / 2024年5月5日 6時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










