アメリカと中国が「全面核戦争」をするリスクはどれほどか…軍事分析のプロが指摘する中国軍の本当の実力
プレジデントオンライン / 2023年7月24日 15時15分
※本稿は、高橋杉雄『日本で軍事を語るということ 軍事分析入門』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
■人類の存続そのものが危ぶまれた米ソ冷戦
現代における戦争を考える上で、1つの基準点となるのが、冷戦期において想定されていた戦争である。米ソが激しく対立したこの時期、主要な戦場になると考えられていたのがヨーロッパであった。
東西に分断されていたドイツを主要な戦線として、米国を中心とするNATO軍と、ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍との全面軍事衝突が懸念されていたのである。NATO軍は通常戦力において量的劣勢にあり、その劣勢を補うために戦術核を戦場で早期に使用することが想定されていた。
米ソ双方とも、戦場で使うための戦術核に限らず、お互いの本土を攻撃するための戦略核も膨大な数を保有していたから、戦術核の使用は最終的に戦略核の使用にエスカレートし、米ソ双方による相手の本土への大規模な核攻撃が予測されており、その結果人類の存続それ自体が危うくなることが懸念されていた。
■全面核戦争が起きる可能性は消滅した?
冷戦期の大きな特徴は、ヨーロッパに限らず、米ソが関与するあらゆる紛争で核兵器が使われるリスクが内包されていたことである。地域紛争がひとたび米ソ対決の文脈に関連づけられてしまうと、そこに米ソが介入する可能性が生じる。そして米ソの直接介入は、人類を絶滅させうる全面核戦争へのエスカレーションの可能性を内包することと同義だったのである。
その意味で、冷戦期においては、あらゆる地域的な紛争要因がグローバルな全面核戦争のリスクとリンクしており、人類滅亡の引き金を引く可能性があったのである。
しかしながら、冷戦の終結は、こうした戦略上の図式を大きく変化させた。米ソの全面核戦争の脅威が事実上消滅したことで、地域的な紛争要因と全面核戦争の潜在的なリンクが切断された。
事実、1991年の湾岸戦争や1993-94年の第1次朝鮮半島核危機においても、それが人類の生存を脅かすようなグローバルな全面核戦争へとエスカレーションする可能性は存在しなかった。逆に言えば、米ソの相互核抑止の「影」が地域的な紛争要因を抑え込むことがなくなった。その意味で、冷戦終結後の紛争はグローバルな対立構造から切り離され、純然たる地域的なダイナミクスに基づいて発生するようになってきている。
■ロシアと中国の戦略的関心はどこにあるか
ただし、この点についてはもう少し考察が必要であろう。米国と中国、ロシアの関係悪化により、「大国間の競争」が復活したと考えられているからである。これは冷戦期のように、様々な地域的な紛争要因をグローバルな大国間の対立にリンクさせることはないであろうか。

この点でポイントになるのは、中国やロシアがどれくらいグローバルな安全保障に関与するか、である。冷戦期のソ連は、植民地独立の民族解放闘争を支援するという形で、ベトナム戦争をはじめとするいくつもの紛争にかかわっていた。その範囲はソ連周辺に留まらず、ヨーロッパどころかグローバルに広がっていた。そのため、同じようにグローバルな規模で共産主義を封じ込めようとする米国と世界中で対立し、その結果、それぞれの地域の紛争要因が米ソの全面核戦争とリンクする潜在的な危険性を持っていた。
一方、現在の中国は、核戦力および通常戦力の近代化を急激に進めているが、その戦略的な関心は台湾を中心とする東アジアに集中しており、それ以外の地域への安全保障上の関与は限定的である。一帯一路や太平洋島嶼部など、東アジア域外に影響力を広げようとしているが、軍事的なプレゼンスはきわめて小さい。ここから、台湾海峡有事が万一起こったとすれば、米中の核戦争へとエスカレートする危険はあるが、アジア以外の地域の紛争においてはそういったリスクはほとんどないと言える。
■中国の核戦力は2035年には3倍以上になる
そもそも2023年現在の中国の戦略核戦力の規模は400発程度とみられ、仮に米中の全面核戦争になったとしても冷戦期のソ連ほど大規模な核攻撃を行うことはできない。ただこの点については、2035年には1500発の弾頭を保有するようになるという見方もあり、将来的には、少なくともロシアと同規模の核攻撃を行う力を持つ可能性はある。
ロシアは、引き続き大規模な核戦力を保有しており、比喩的に言えば、人類を滅亡させる可能性のある核戦争が米国との間で発生するリスクは引き続き存在している。特に、2022年のロシアのウクライナ侵攻以降、ロシアがしばしば核恫喝を行っていることから、核戦争のリスクが極めて深刻に懸念されている状況でもある。ただし、それ以外の地域で、ロシアが核戦争のリスクを冒して米国と対立する判断を行うとは考えにくい。
■台湾とウクライナにおける核戦争リスク
以上から、台湾やウクライナといった、中露それぞれが戦略上極めて重視している地域を除けば、米国との全面核戦争へとエスカレートする可能性のある地域的な紛争要因は事実上存在しないと考えていいだろう。この例外を除けば、現在の戦争は、純然たる地域レベルのダイナミクスに基づいて展開すると考えられる。ここでは、その前提の上で、現代の戦争を4つのタイプに分類しておきたい。
最初に取り上げるのが、域外大国の軍事介入の形を取る戦争である。例えば1991年の湾岸戦争、2003年のイラク戦争、2015年のロシアのシリア介入などを挙げることができる。
こうした、域外大国の軍事介入という形を取る戦争の特徴は、介入する国がグローバルに兵力を展開させる能力を持っており、またそれを支える補給システムも持っているということである。
■アメリカが地球の裏側まで軍事介入できる理由
逆に言えば、そうした能力を持たない国は、他の地域の紛争に介入することができない。例えば米国にとって中東は地球の裏側に等しい場所にあるが、そこに戦車のような重装備や大量の武器弾薬を送り込むためには、大規模な海上・航空輸送能力が不可欠になる。また、自国領土から遠く離れたところでの作戦でも、有効な指揮統制が行えるC4ISRシステムが整備されていなければならない。
こうした作戦のことを米国では、「遠征作戦(expeditionary operation)」と呼ぶ。そもそも米国は米本土での軍事作戦はほとんど想定されないから、事実上すべての作戦が遠征作戦となる。そのため、それぞれの地域の指揮統制のために地域レベルの統合司令部を設置している。
例えば日本の位置するインド太平洋地域であれば、ホノルルに司令部があるインド太平洋軍、中東であればフロリダ州タンパに司令部のある中央軍、ヨーロッパであればドイツのシュトゥットガルトに司令部のある欧州軍である。そして、それらの地域レベルの統合軍を支援する機能別統合軍もある。遠征作戦の観点で重要なのは、部隊や補給物資の輸送に特化した輸送軍である。このように、米国は遠征作戦のために様々な準備を行っている。
■中国の侵攻にアメリカが介入する台湾有事
現在、この種の遠征作戦として想定されるシナリオの代表例が、台湾海峡有事である。もし中国が台湾に侵攻した場合には、米国が軍事介入を行って台湾を防衛しようとする可能性があり、現在こうした有事が発生する可能性が深刻に懸念されている。

中国は、米国の介入に備え、「接近阻止・領域拒否能力」と通称される戦力の整備を進めている。これは、弾道ミサイルや巡航ミサイル、あるいは潜水艦などからなり、台湾の支援のために域外から展開してくる米軍を、台湾に到着する前に物理的に阻止する能力である。
特に技術の発達による精密誘導兵器の拡散により、こうした能力の効果が増大してきており、遠征作戦の実行そのものが難しくなっていると考えられるようになった。そのため、米国では、あらかじめ一部の部隊を紛争が予想される地域に事前展開させておくことで、域外からの遠征作戦のリスクを減らそうとする「スタンドイン」といった作戦構想が考案されている(※1)。
(※1)U.S. Marine Corps, Department of Navy, “A Concept of Stand In Forces,” (December 2021),
■土地の支配を巡るロシア・ウクライナ戦争
第2に挙げられるのが、域外大国の直接的な軍事介入のない地域紛争である。例としては、2021年のナゴルノカラバフを巡るアゼルバイジャンとアルメニアの紛争、そして2022年に始まったロシア・ウクライナ戦争がある。
これはいずれもが、自国ないし隣国の土地の支配を巡る戦いとなっている。そのため、遠征作戦のように遠隔地に展開する必要がない。補給もまた、自国と地続きの道路や鉄道によって支えられる。
第1と第2の例として挙げたのは、正規軍同士の戦争であった。第3に挙げられるのが、内乱鎮圧作戦のような、正規軍対非正規軍の戦いである。イラク戦争やアフガニスタン戦争で、当初戦った現地政府を打倒したあとに米軍が展開した内乱鎮圧作戦がこれに当たる。
これらの戦争では、米軍はハイテク戦力を駆使して相手国の首都を短期間で制圧することができた。しかし、それで戦争は終わらず、それぞれの領域の中で反米勢力が抵抗活動を繰り広げた。この、首都制圧後の抵抗活動に対する米軍の戦いを、それぞれの戦争の「フェイズ2」と呼ぶことがある(「フェイズ1」は首都制圧まで)。
■正規軍がテロ組織や民兵と戦うのは難しい
第1に挙げた域外大国の軍事介入との違いは、正規軍対正規軍、すなわちクラウゼヴィッツ的な「三位一体戦争観」に基づく、社会の中で機能的に分化された軍隊同士の戦いに対し、一方は正規軍だがもう一方がテロ組織や民兵のような武装集団などの非正規軍である、という点である。
社会の中で機能的に分化していないこのような武装組織は、一般社会に潜伏しながら正規軍へのテロ的な攻撃を行う。そのため、戦いの図式が、〔軍〕対〔軍〕ではなく、〔軍〕対〔社会の一部〕となってしまう。そして、武装組織が一般市民に溶け込んで社会の中で活動すると、軍側としては探知―攻撃サイクルを実行することが難しくなる。
より正確には、一般市民と非正規軍とを区別し、非正規軍の戦闘員のみを選択的に攻撃するのが難しくなる。もし、一般市民を巻き添えにしたり、誤情報で攻撃したりすると、本来味方にすべき一般市民が敵に回る可能性がある。つまり、このタイプの戦争においては、正規軍側は、攻撃すればするほど敵が減らないどころか、敵を増やしていく可能性がある。
■イラク戦争・アフガニスタン戦争の結末
こうした戦いで重視されるのは、単なる物理力ではなく、一般市民の「心をつかむ」ことであった。一般市民を味方に付けることによって、非正規軍の戦闘員を社会から浮いた存在にして、一般市民から彼らの情報を得たり、一般市民の側から彼らを排除していくことで、非正規軍を弱体化させていくという考え方である。
これはイラク戦争のフェイズ2の中で「カウンターインサージェンシー」として米軍が実行し、特にブッシュ政権で行われた駐留兵力増派の時期に一時的に成功した。また、米軍は、アフガニスタン戦争のフェイズ2では、地上軍のプレゼンスを限定して、反政府の非正規軍をドローンや特殊部隊で選択的に攻撃する「カウンターテロ」作戦も行った。
しかし、いずれの方法も決定的な成果を上げられず、最終的に米軍はアフガニスタンから撤退し、イラクでも駐留兵力を削減することとなった。ベトナム戦争も同様の事例であり、それほどまでに正規軍が非正規軍に勝利することは実際には難しいのである。
■ユーゴ内戦では虐殺や性的暴行が頻発した
そして第4のモデルが、内戦である。これは冷戦後でも、ユーゴスラビア内戦であるとか、南スーダンなどで発生しているもので、国内の軍閥同士の戦いであったり、あるいは分離独立を求める勢力の中央政府に対する武力抗争という形を取ることがある。
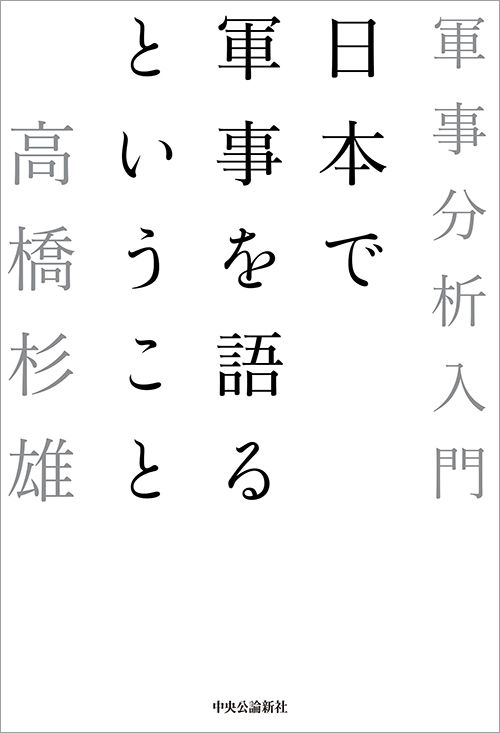
このタイプの戦争においては、クラウゼヴィッツ的な「三位一体戦争観」が成立しないことが多い。そもそも内戦を戦うような国内の武装組織は、正規軍対非正規軍のモデルにおける非正規軍のように、社会から機能的に分化された軍事力ではないことが多いからである。そうなると、ステートクラフトの1つの「道具」として軍事力が行使されるという前提そのものが成立しなくなる。
例えば、ユーゴスラビアという国家が分裂していくプロセスで、セルビア人勢力、クロアチア人勢力、ムスリム勢力が戦ったユーゴスラビア内戦においては、「民族浄化」と呼ばれる虐殺や性的暴行が頻発した。このように、民族的憎悪が戦いのベースとなってしまうと、政策の道具として軍事力を使うのではなく、破壊そのものが目的となってしまう。人種差別的な意識が影響した場合も同じようなことが起こるだろう。
■軍事力が政治の「道具」でなくなると…
アフリカにおける内戦を研究したバーダルとマローンは、アフリカにおいては「政治の延長」としての戦争ではなく、「経済の延長」としての戦争が存在していることを指摘した(※2)。
彼らが明らかにしたのは、戦争の継続によって可能となる経済活動(援助のピンハネや略奪など)を目的として戦争状態を継続する武装勢力が広く存在していることであった。政治の「道具」としての軍事力ではなくなってしまっているのである。
(※2)Mats Berdal and David M. Malone, Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars (Lynne Rienner Publishers, 2000).
----------
防衛研究所防衛政策研究室長
1972年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、ジョージワシントン大学コロンビアンスクール修士課程修了。1997年に防衛研究所に入所、現在、政策研究部防衛政策研究室長。国際安全保障論、現代軍事戦略論、日米関係論が専門。共著書に『新たなミサイル軍拡競争と日本の防衛』『「核の忘却」の終わり― 核兵器復権の時代』、編著書に『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』、著書に『現代戦略論』など。
----------
(防衛研究所防衛政策研究室長 高橋 杉雄)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「原爆が戦争止めた」は“神話”=根拠乏しい米国防長官見解―アジアの核拡散に歯止めを
Record China / 2024年5月14日 6時30分
-
アメリカからの武器援助を勘定に入れていない?プーチンの危険なハルキウ攻勢
ニューズウィーク日本版 / 2024年5月13日 18時55分
-
赤狩りと恐怖の均衡について(下)「核のない世界」を諦めない その5
Japan In-depth / 2024年5月1日 11時0分
-
国際情勢からの日本の憲法改正の必要性(上)抑止の否定は日本の滅亡へ
Japan In-depth / 2024年4月30日 20時16分
-
台湾有事に備え、態勢強化を進める日米。重視するのは「沖縄・先島諸島」 訓練強化、地元住民に募る不安
47NEWS / 2024年4月24日 10時0分
ランキング
-
1煮物だけじゃない!スーパーフード並みの栄養価「切り干し大根」の意外な食べ方
週刊女性PRIME / 2024年5月18日 8時0分
-
2キウイの皮を剥くのが面倒→皮ごと食べられます! 気になる毛の解決法も伝授、ゼスプリが明かすキウイの手軽な食べ方は?
まいどなニュース / 2024年5月18日 7時0分
-
3「ガラケーの使い方が分からない…」スマホ世代の新入社員が訪問先で“やらかした”大騒動
日刊SPA! / 2024年5月19日 15時54分
-
4軽自動車、20年で6割値上がり 初の平均160万円台が視野
共同通信 / 2024年5月18日 16時51分
-
5「バヤリースオレンジの瓶、製造中止」SNSで拡散 アサヒ飲料「そのような事実はない」と否定
ねとらぼ / 2024年5月18日 11時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










